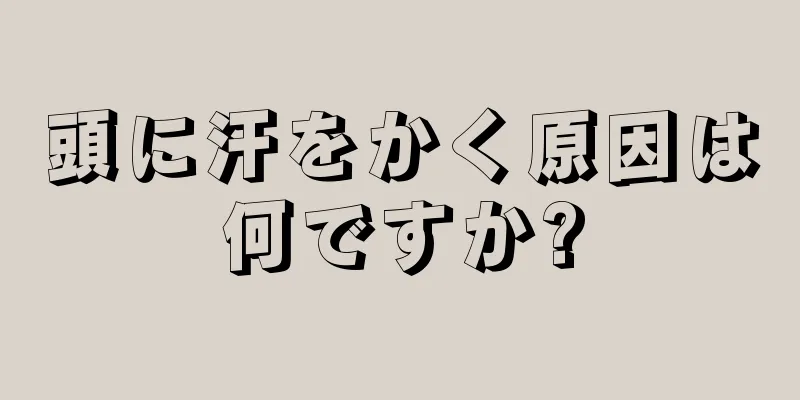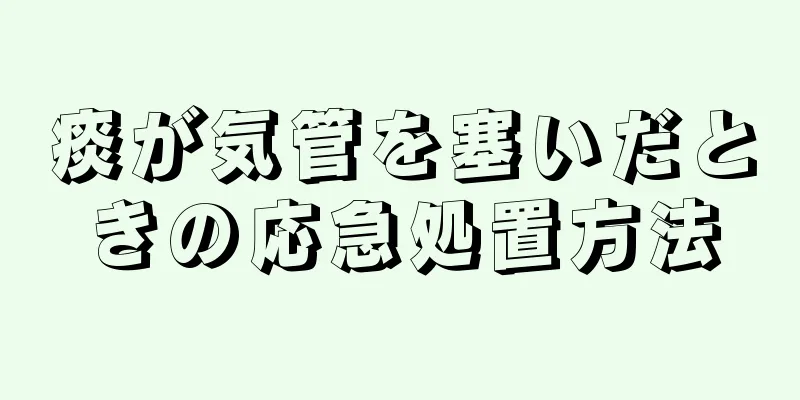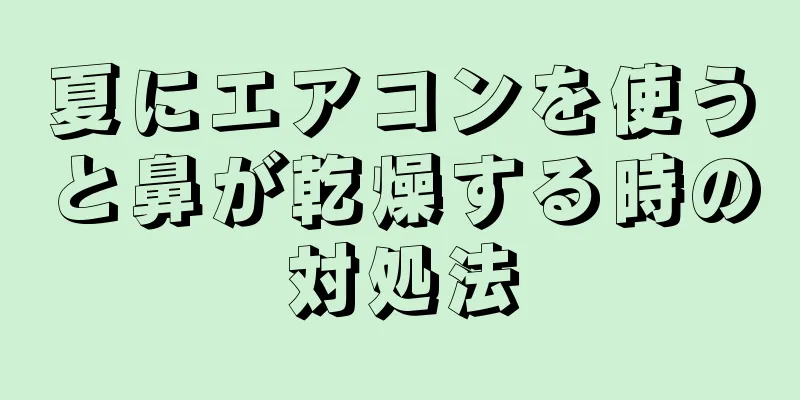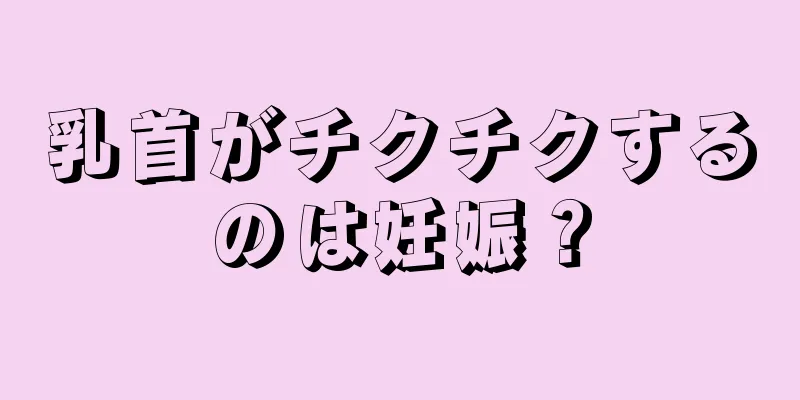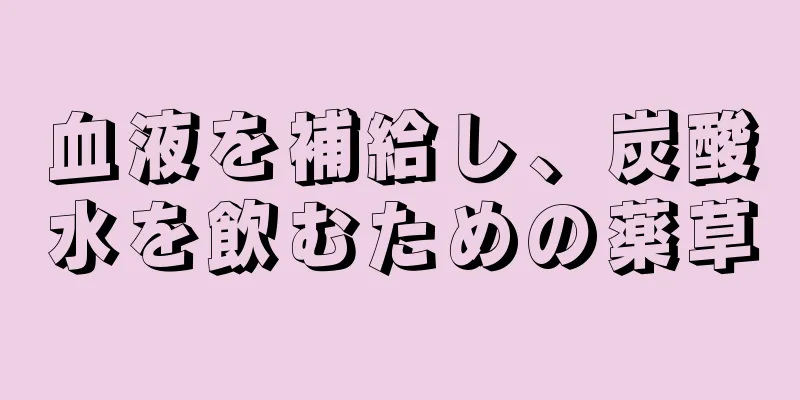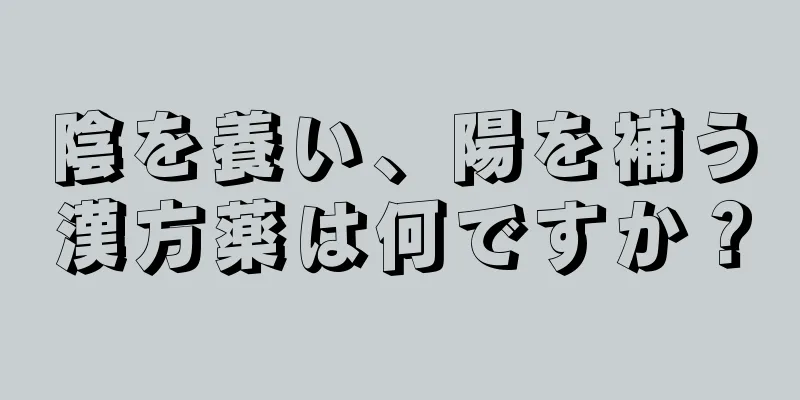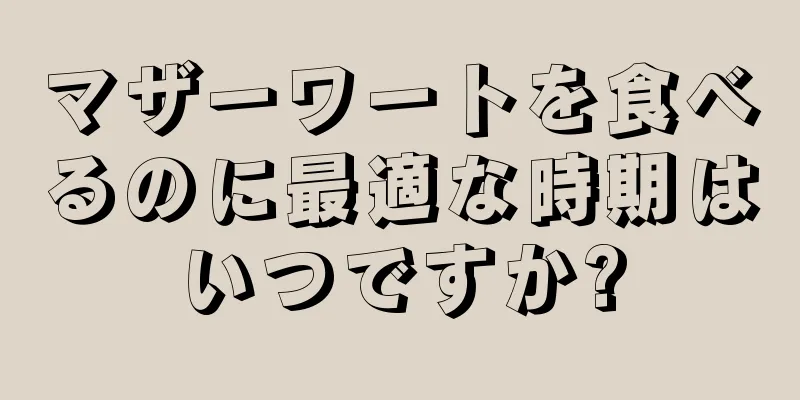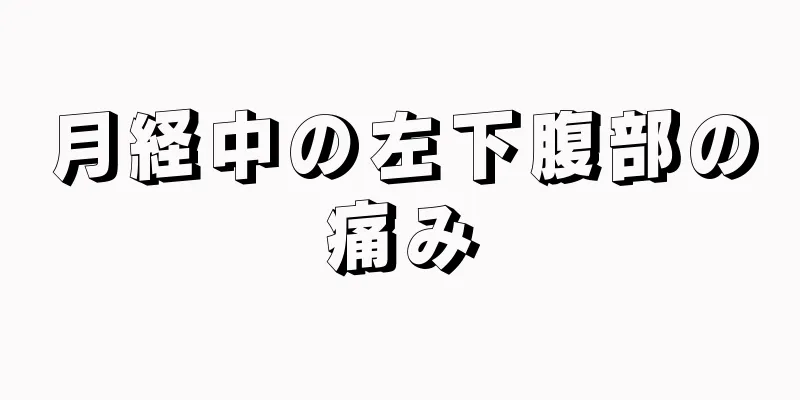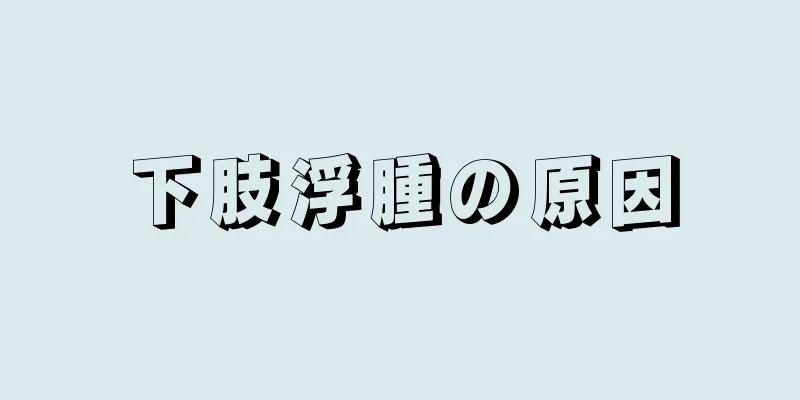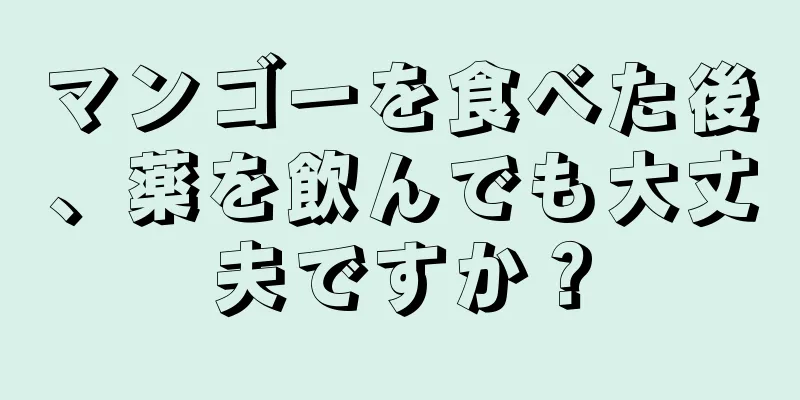溶血とは何か
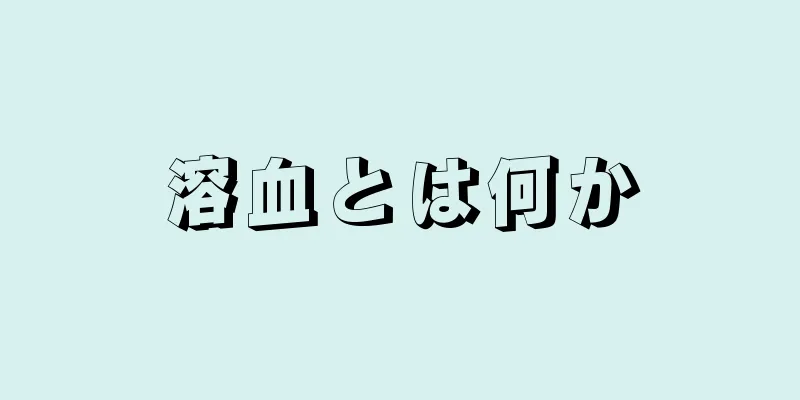
|
溶血性疾患は主に一部の新生児に発生します。これは主に母親と赤ちゃんの血液型の不適合が原因です。母親と胎児の間の抗原抗体反応により、胎児の赤血球の一部が破壊されます。いくつかの受動免疫疾患と相まって、赤ちゃんにさまざまな症状を引き起こす可能性があり、主に黄疸、肝脾腫、貧血として現れます。正常なプロセスも比較的緩やかです。 全身状態への影響は比較的小さいですが、重篤な疾患の進行は比較的速く、検査値が上昇または低下してビリルビン脳症や死亡につながることもあります。日常生活での予防も重要であり、そこで診断することができます。 1. 黄疸:赤血球の破壊によって分解されたビリルビンは黄色です。人体全体に分布し、体の組織を黄色に変色させます。皮膚と強膜(一般に白目と呼ばれる)は体の表面にあるため、黄色化が最も顕著であり、これが黄疸です。ほとんどの新生児は出生後に黄疸を呈しますが、黄疸が早すぎる場合や、進行が速すぎる場合、または血液中のビリルビン値が高すぎる場合は、溶血性疾患の可能性に注意する必要があります。溶血性疾患の乳児の黄疸は、通常、生後 24 時間以内または 2 日目に現れます。 2. 肝脾腫:軽症の場合、明らかな大きさの増加は見られません。重症の溶血性疾患では、胎児浮腫が発生し、肝臓と脾臓が明らかに肥大することがあります。この症状は、Rh 溶血性疾患でより一般的です。 3. 貧血の子供は、さまざまな程度の貧血を患っています。重症の場合は、心不全や全身の浮腫を引き起こす可能性があります。 4. ビリルビン脳症 血液中のビリルビン濃度が高すぎると、脳細胞が損傷し、溶血性疾患の最も重篤な合併症であるビリルビン脳症を引き起こします。これは通常、出産後 2 ~ 7 日で発生し、黄疸の悪化や、眠気、摂食障害、凝視、けいれんなどの神経症状として赤ちゃんに現れます。速やかに治療しないと、死亡したり、運動機能障害や知的障害などの後遺症につながる可能性があります。 5. 神経症状には、眠気、食事拒否、手足の脱力、それに続く痙攣などがあり、凝視、瞬き、手足の硬直や伸び、全身の後弓反張、時には叫び声として現れます。これは核黄疸またはビリルビン脳症と呼ばれ、血清ビリルビンが 20 mg/dl 以上になるとよく発生します。これは間接ビリルビンが脳組織に入り込み、脳細胞を損傷することによって起こります。 6. 発熱性溶血性疾患の子供は発熱することが多いです。発熱は、小児の溶血後の身体の反応である可能性があり、あるいはより重篤なビリルビン脳症である可能性もあります。発熱は必ずしも非常に高いとは限りませんが、後者が原因で発熱する場合は、状態がかなり深刻であることを意味します。 以上が溶血性疾患の治療です。日常生活の中では、タイムリーな診断と治療が必要です。同時に、新生児の治療も比較的重要です。一部の漢方薬と西洋薬は治療に使用できます。日常生活における新生児溶血性疾患は、あなたを怖がらせるものではありません。主に厳格な消毒と隔離、そして合理的な給餌と病状の観察です。 |
推薦する
神経性耳鳴りの治療方法
神経性耳鳴りは比較的よく見られる症状ですが、患者にとって非常に有害です。耳鳴りはしばしば人々に迷惑を...
性器イボと性器ヘルペスについて詳しくお話しましょう!
性器イボは、自分自身と相手の両方に危害を及ぼす可能性のある、非常に蔓延している性感染症です。しかし、...
伝統中国医学灸の知識
伝統中国医学は数千年にわたって受け継がれ、何世代にもわたる人々の知恵の結晶です。伝統中国医学の治療は...
静脈が詰まったらどうするか
静脈閉塞は人間にとって非常に有害です。例えば、足の静脈血栓症は最も一般的な病気で、下肢の腫れを引き起...
TCM は女性の内分泌疾患をどのように治療しますか?
女性の体内で内分泌障害が起こる原因はさまざまです。食事、睡眠、精神的ストレスなどが内分泌障害を引き起...
指のしびれの原因と治療法
指がしびれるという人もいます。深刻な病気ではありませんが、常に不快感があり、生活や仕事に一定の影響を...
心臓麻痺とは何ですか?それは3つの理由に関連している可能性があります
臨床実践においては、心臓麻痺があることがわかったらすぐに治療を受けるべきです。心臓麻痺の具体的な原因...
伝統的な中国医学は痛風をどのように治療するのか?昔の中国医学の医師はいくつかの食事療法を推奨している
痛風は中年の男性や閉経後の女性に多く発症する病気です。痛風発作が起こると、関節に赤み、腫れ、チクチク...
食べ物が胃ではなく胸に詰まっているようだ
食事をすると、必ずさまざまな問題が起こります。例えば、食事をしても食べ物が胃に入らず胸の中に詰まって...
脱出した内痔核の症状は何ですか?危険性は何ですか?
痔は肛門直腸医学において最も重要な部分であり、痔の発生率は肛門直腸疾患の中で第 1 位です。 「10...
痔の手術後に肉芽が成長した場合の対処法
痔の手術は痔の治療のために行われる手術です。痔を治療する最も直接的かつ迅速な方法ですが、手術後に適切...
授乳中に乳房に痛みがある場合の対処法
新生児の母親の多くは、共通の問題を抱えています。それは、赤ちゃんに授乳しているときに、特に母乳が十分...
新生児にビフィズス菌を摂取させるには?
ビフィズス菌は人間の腸に欠かせない菌であり、プロバイオティクスでもあります。プロバイオティクスを定期...
湿気や毒素を取り除くには、薬と食べ物のどちらが良いでしょうか?
突然食欲が減退し、舌苔が白くなったと感じたら、体内に湿気や毒素が溜まっていることを意味します。実は、...
唾液の役割
唾液は一般につばとして知られています。ご存知のとおり、無色無臭の液体です。私たちは毎日唾液を分泌して...