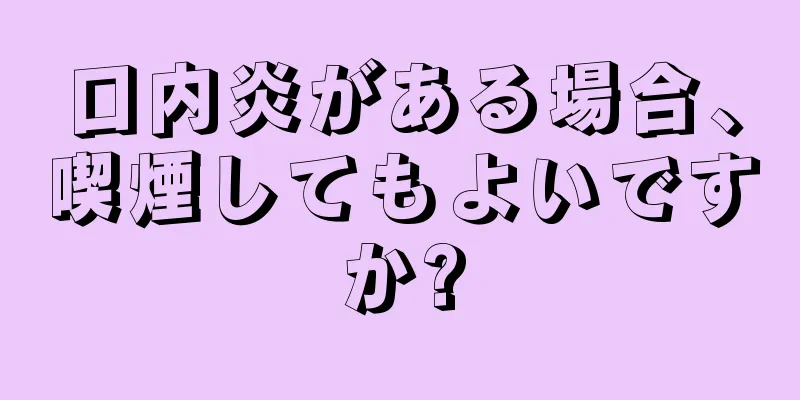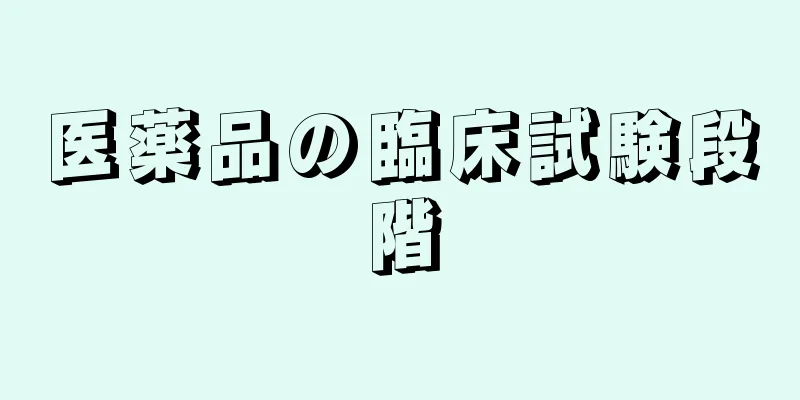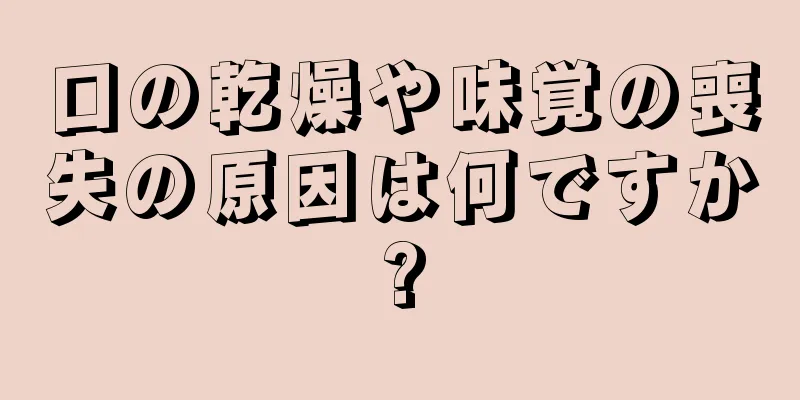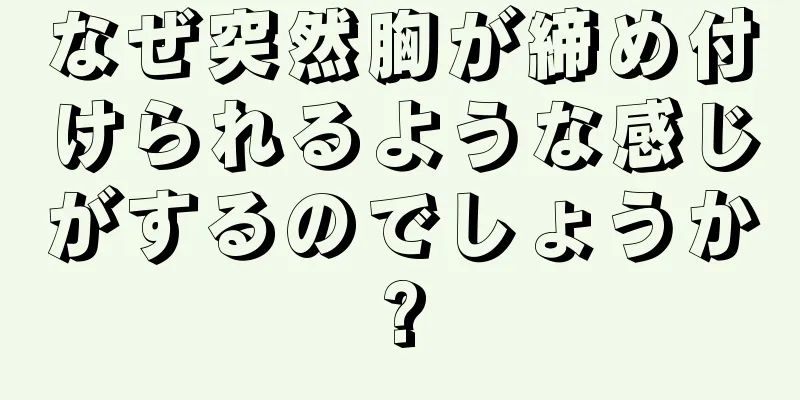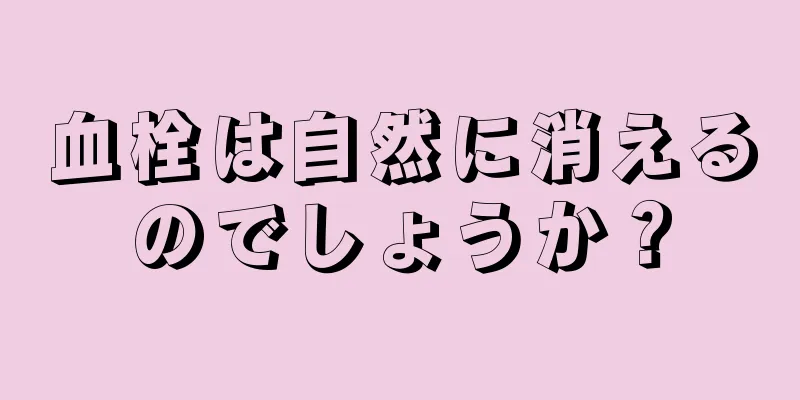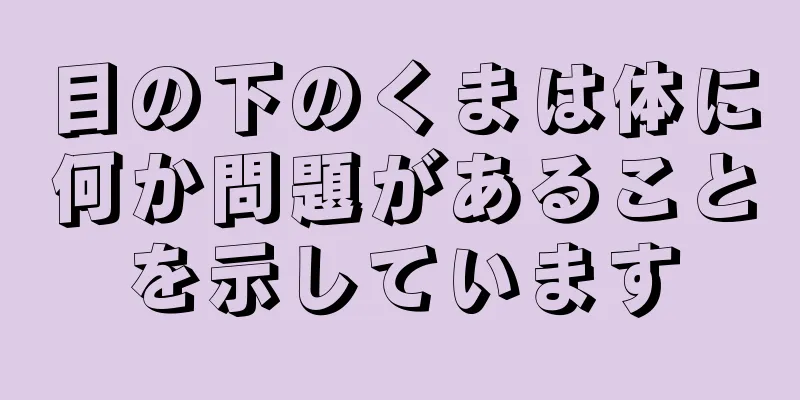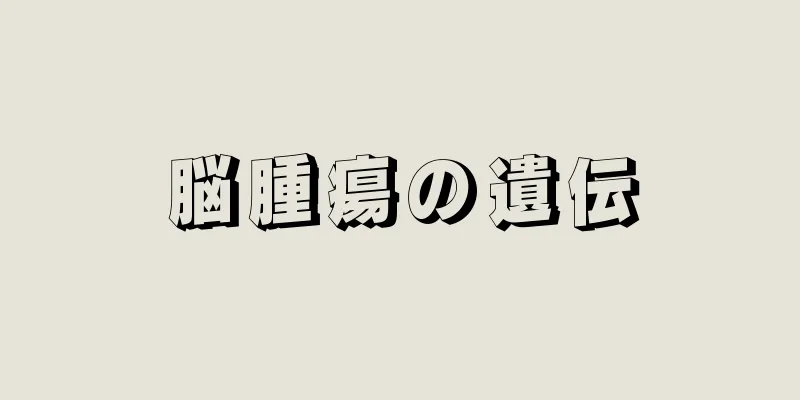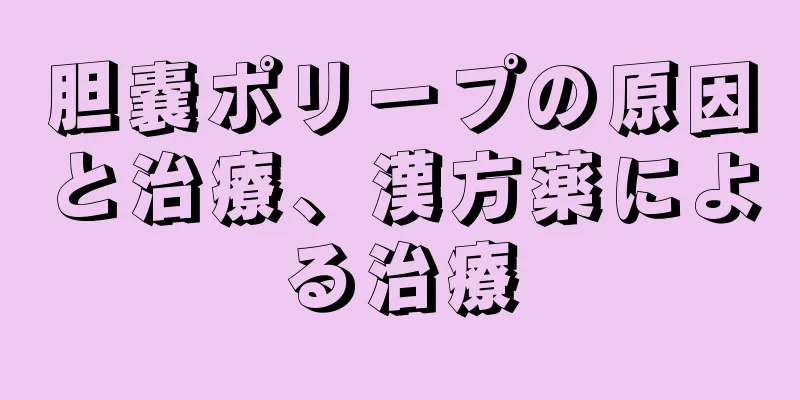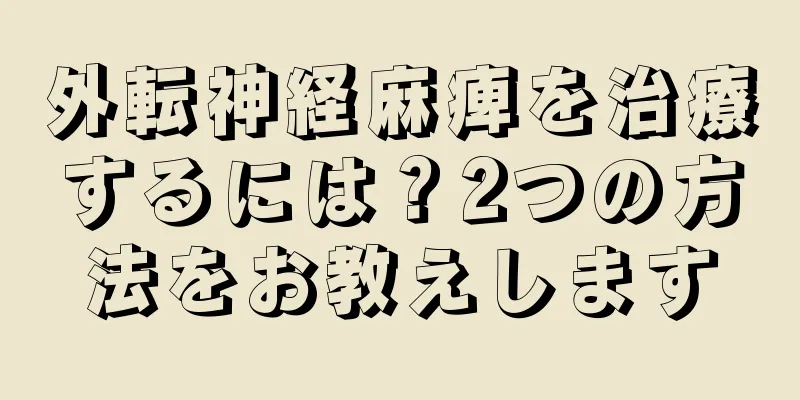男でも女でも、そんなに「淫ら」なことはできない
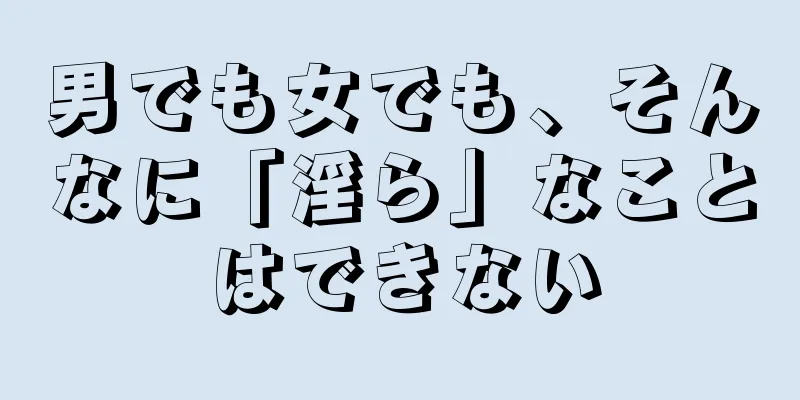
|
六邪とは、風、寒、暑、湿、乾、熱(火)という6つの外因性の病因の総称です。通常の状況では、これらは「六気」と呼ばれ、自然界の6つの異なる気候の変化であり、万物が成長するための条件であり、人体には無害です。気候の変化が異常な場合、六気が過剰または不足して発生したり、または気が不適切な時期に発生したり(春は暖かいのではなく寒い、秋は涼しいのではなく暑いなど)、気候の変化が急激すぎる場合(猛暑や極寒など)には、体内の陽気が不足して抵抗力が低下し、六気が病原因子となって体内に侵入し、病気を引き起こす可能性があります。この状況における6つの気は「六悪」と呼ばれます。 「色欲」とは、行き過ぎや没頭を意味します。六つの色欲は不健全なエネルギーであるため、「六悪」とも呼ばれます。 病気を引き起こす六邪の一般的な特徴は、季節の気候や生活環境と関係していることがほとんどです。例えば、春には風病が多く、夏には暑熱病が多く、長い夏と初秋には湿病が多く、晩秋には乾病が多く、冬には寒病が多くなります。さらに、湿地帯に長く住む人々は湿気に悩まされることが多く、高温環境で働く人々は乾燥、暑さ、火災に悩まされることが多い。六つの悪霊は、単独で人体に侵入して病気を引き起こすこともありますし、二体以上が同時に人体に侵入して病気を引き起こすこともあります。風邪、湿熱性下痢など。 病気の経過中、六邪は互いに影響し合うだけでなく、特定の条件下では互いに変化することもあります。たとえば、寒邪が体内に入ると熱邪に変化し、夏の暑さと湿気が長期間続くと乾燥に変化して陰を損傷する可能性があります。六邪は病気であり、皮膚表面から侵入したり、口や鼻から入ったり、あるいはその両方から同時に侵入したりして伝染することが多いため、「六邪」とも呼ばれています。 【ワンウィンド】 風は春の主風ですが、風が強すぎたり、時期外れだったりすると、季節を問わず人々を病気にする可能性があります。また、寒さ、湿気、乾燥、暑さ、暑気などの外邪は風に付着して人体に侵入することが多いです。風邪の性質と病因は次の通りです。 1. 風は陽邪であり、その性質は開いて排出することです。風邪は活動的で奔放であり、上昇、上方、外向の特性を持ち、陽邪である。また、人体の上部(頭や顔など)や皮膚表面に侵入しやすく、外因性の風邪によって皮膚や汗腺が開き、発汗や風を嫌うなどの症状が現れます。風は軽く、どこにでも届くため、風病の症状は体のあらゆる部分に現れる可能性があります。 2. 風邪の症状は頻繁に変化します。風邪は病気を引き起こし、発症や変化が急速で、病気の発生場所がさまよいます。例えば、蕁麻疹の発疹は移動性で現れたり消えたりしますが、リウマチの手足の関節や筋肉の痛みは移動性です。そのため、『蘇文:風論』では「風はよく動き、よく変化する」と言われています。 3. 風はすべての病気の根源です。風邪は六邪の主たる病因であり、寒邪、湿邪、乾邪、熱邪はいずれも風に付着して人体に侵入することが多く、つまり風邪は他の外因性の邪の先駆けとなって病気を引き起こすことが多いのです。 【二度目の風邪】 寒さは冬に主に感じられますが、他の季節にも見られます。外的な寒邪が皮膚表面を傷つけると「腸チフス」と呼ばれ、内臓に直接影響を及ぼすと「風邪」と呼ばれます。寒邪の性質と病因は次の通りです。 1. 寒さは陰の邪悪であり、陽のエネルギーに簡単にダメージを与えます。風邪は陰のエネルギーが過剰になったときに起こります。「陰が優勢になれば風邪になる」「陰が優勢になれば陽が病む」と言われています。陽気が寒邪により損傷され、温める機能と気を変える機能が失われると、寒邪が過剰になり、陽気が損傷する虚実混合症候群が現れます。寒邪が直接脾胃を侵すと、清水吐き、下痢、腹痛、温熱嗜好などの症状が現れます。 2. 冷えは停滞を引き起こします。人体の気、血、体液の循環は、すべて体内の陽気の温熱と促進に依存しています。陰寒邪が蔓延すると、陽気が損なわれ、経絡内の気血の循環が妨げられ、停滞して閉塞します。閉塞は痛みを引き起こすため、寒邪の害を受けたときに痛みがよく見られます。 3. 寒さは収縮を引き起こします。収縮と牽引は、人体への冷邪の侵入を指し、気の収縮を引き起こし、毛穴、経絡、腱、静脈が収縮して緊張します。冬に寒くなると、全身が丸まり、手足が痛いだけでなく、曲げ伸ばしが難しくなります。寒邪が皮膚表面に侵入し、毛穴や皮膚が塞がれ、衛陽が抑制されて排出できなくなるため、悪寒、発熱、発汗障害が生じることがあります。寒邪が血管に侵入し、血管が収縮するため、頭痛や体の痛み、脈がきつく締まるなどの症状が生じることがあります。 【3ヒート】 暑さは夏の主な空気です。夏の暑さは、明らかな季節性疾患を引き起こす可能性があり、主に夏至後から秋の始まりまでに発生します。夏バテの性質と病原性の特徴は次のとおりです。 1. 熱は陽邪であり、その性質は熱い。暑さは夏の熱い空気によって引き起こされます。暑さの影響を受けると、発熱、発汗、イライラ、冷たい飲み物への渇望、脈拍の速さなどの症状が現れることがよくあります。 2. 熱は上昇して拡散する性質があり、体液を損傷し、エネルギーを消費します。熱は陽邪であり、陽は上昇するため、熱邪は上昇して消散しやすい。人体に侵入すると、毛穴が開き、過度の発汗を引き起こす可能性があります。過度の発汗は体液にダメージを与えやすく、喉の渇きや飲水欲求を引き起こす可能性があります。多量の発汗は、体液とともに気も失わせ、気虚につながります。 3. 夏の暑さには湿気が伴うことが多いです。夏の気候は暑く、雨が多く、湿気が多く、熱と湿気が移動し、空気中の湿度が比較的高いため、熱邪が問題となり、湿気を伴うことが多く、熱と湿気の混合症候群を形成します。臨床症状としては、軽い発熱、喉の渇き、重苦しさ、疲労感、胸の圧迫感、吐き気、下痢、黄色く脂っぽい舌苔などがあります。 【四つの湿り気】 湿気は長い夏の主な気です。湿気は水と湿気の気なので、有形の邪気と呼ばれます。湿気の多い気候、水の中を歩くこと、湿地帯で長期間生活することなどにより、湿気が原因で病気になる可能性があるため、どの季節でも発生する可能性があります。湿気の性質と病原性は次のとおりです。 1. 水分は下方向に流れる傾向があります。湿気は水に似ており、水の性質は下に向かうため、湿気は下に向かう性質を持っています。そのため、人体の下半身は湿気の影響を受けやすく、病気になったり、下半身に浮腫、ただれ、下肢の関節や筋肉の痛み、あるいは尿の濁り、帯下、下痢、赤痢などの湿気の症状が主に現れたりしますが、これらのほとんどは湿気の影響と関係があります。 2. 湿っていて、重く、濁っている。湿気は重く、汚いという特徴があります。湿気が引き起こす病気は、多くの場合、身体の重さや不快感、そして汚れた不潔な分泌物や排泄物によって特徴付けられます。湿が外部に侵入すると、頭が重く、疲れやすく、手足が痛く、微熱が出ます。湿が経絡に停滞して関節に流れ込むと、関節が痛くて重く、動かしにくくなり、痛みが消えません。湿が下半身に流れ込むと、尿が濁って出にくくなり、便がゆるくなったり、便に血膿が混じったり、女性でもおりものがドロドロして魚臭くなります。 3. 濡れてベタベタする。湿気は粘着性と停滞性の特徴を持っています。一方では、人体に付着して解消が困難となり、病気の経過が長引くことがあります。一方、湿は臓器や経絡に留まり、気の流れを妨げて昇降できなくなり、胸腹部の膨張、排尿回数が少なく渋い、便が軟らかくて不快などの症状を引き起こします。長期間にわたる陽気の損傷、例えば湿気による陽気の損傷は、湿気過剰と陽虚の両方を伴う過不足の混合症候群を引き起こし、下痢、浮腫、乏尿などの症状を引き起こす可能性があります。 【五つの乾燥】 秋は乾燥が主な気候です。乾燥は温熱と涼しさの2つに分けられます。初秋はまだ暑く、温熱の乾燥を感じやすく、晩秋は涼しく、涼しい乾燥を感じやすくなります。温熱乾燥の病気の場合は熱の症状が顕著に現れ、冷熱乾燥の病気の場合は寒の症状が顕著に現れます。乾燥症の性質と病態的特徴は以下のとおりです。 1. 乾燥していて収斂性があり、体液にダメージを与えやすい。乾燥は乾燥を引き起こす病因であり、病気を引き起こすと、多くの場合、体液が損傷され、口や鼻の乾燥、喉の乾燥や渇き、目の乾燥、皮膚の乾燥やひび割れなど、一連の乾燥症状として現れます。 2. 乾燥は肺にダメージを与えやすくなります。肺は湿気を好み、乾燥を嫌う繊細な臓器です。乾燥は身体に害を及ぼす可能性があり、肺は口や鼻を通じて最もダメージを受ける可能性が高くなります。乾燥は特に肺陰を傷めやすく、鼻咽頭の乾燥のほか、痰の少ない乾いた咳、痰が粘ついて吐き出しにくい、痰に血が混じるなどの症状も現れることがあります。 6ヒート(火) 熱(火)病原体は、一般的に病気を引き起こす際に特定の季節パターンを持ちませんが、春と夏に多く見られます。火と熱は陽の過剰によって生じ、暖と熱と同じです。熱は暖かさが徐々に進行していくものであり、火は熱の極みです。熱(火)邪の性質と病因は次の通りです。 1. 熱は陽邪であり、その性質は炎症性です。火と熱は陽に属し、陽は乾燥して上向きなので、火と熱は人に害を及ぼす可能性があります。熱の症状に加えて、邪悪な火と熱は心を乱し、落ち着きのなさ、不眠、躁病、昏睡、せん妄などの症状を引き起こすこともあります。 2. 熱は気を消耗させ、体液を損傷しやすくなります。火熱の邪気は体内の陽気を消耗しやすく、体内の水分を強制的に流出させ、陰液を消耗させて体内の陰液不足を引き起こし、喉の渇き、頻繁な飲酒、喉の乾燥、唇の乾燥などの陰の損傷の症状を伴うことがよくあります。 3. 熱は風邪を引き起こしやすく、血液の流れを悪くします。病熱が人体に侵入すると、肝経を焼いたり、陰液を枯渇させたり、腱や静脈の栄養を失わせたり、肝風を引き起こしたりします。その結果、高熱、昏睡、せん妄、手足のけいれん、上目遣い、後弓反張などの症状が現れます。同時に、邪悪な火と熱は血液の循環を促進し、血管を焼いて、吐血、鼻血、血便、血尿、皮膚の斑点など、さまざまな出血を引き起こす可能性があります。 4. 熱は腫れや潰瘍を引き起こしやすくなります。火熱邪は血液に入り込み、局所的に集まり、肉と血液を腐食させ、癰、潰瘍、傷を引き起こします。臨床症状は、局所的な発赤、熱、腫れ、痛みが特徴です。 |
推薦する
ヨモギ温湿布の効果
現代人は健康維持に対する意識が強く、身体に問題がないときや問題が生じたばかりのときは、さまざまな方法...
湿気と毒素を取り除く漢方薬の症状
私たちの生活の中で、多くの人は体内に多くの水分を持っています。水分がひどい場合、湿気や毒素を引き起こ...
漢方薬は温めて飲まないといけないのでしょうか?
漢方薬を実践している友人たちは、体の回復を早めたいなら漢方薬を飲む必要があることを知っています。では...
習慣性便秘の治療法
便秘とは、排便回数が週3回未満で、便が乾燥して硬い症状を指します。この状況の一般的な原因は、異常な食...
尿道がチクチクしたらどうすればいい?尿道炎に注意
尿道口に刺すような痛みを引き起こす最も一般的な病気は尿道炎です。尿道炎は急性または慢性の可能性があり...
汗蒸しの機能は何ですか?
日常生活では、日常生活を規則正しくするだけでなく、何らかの健康管理措置を講じる必要があります。そうす...
腎臓を養うための漢方薬を服用するには通常どのくらいの期間かかりますか?
人体に腎虚や腎機能不全があると、体が弱って無気力になり、性生活にも一定の影響を及ぼします。一般的に、...
背中のニキビ
多くの人の肌にニキビがあります。顔や背中にできる人もいます。背中にニキビができる原因は、主に脂性肌に...
低血糖の危険性は何ですか?
低血糖の問題は、その影響が非常に大きいため無視できません。低血糖は、空腹感、めまい、動悸、顔色不良、...
生理が5日早く来ました
月経が5日早く来るのはよくあることです。これは女性の日常生活や仕事における過度のプレッシャーに関係し...
月経が10日遅れた後の乳房の痛み
女性の月経は毎月規則的で、各周期は約 28 ~ 30 日です。これらの期間は非常に正常です。数日遅れ...
足の爪についた白い泥が悪臭を放つ場合の対処法
足の爪の内側に白い泥があり、特に不快な臭いがある場合、この状況の最も一般的な原因は、真菌感染によって...
腰痛の治療法は何ですか?
腰痛は深刻な病気ではありませんが、一度発症すると患者さんの日常生活に重大な影響を及ぼすため、積極的な...
移動性疼痛の治療
全身に移動する痛みの原因は何でしょうか? この状況は、通常、10代の若者に発生します。おそらく、彼ら...
月経が早まる原因は何ですか?
月経不順は、女性に非常に多い病気です。過度のストレス、過度のダイエット、不規則な食事などが原因で、女...