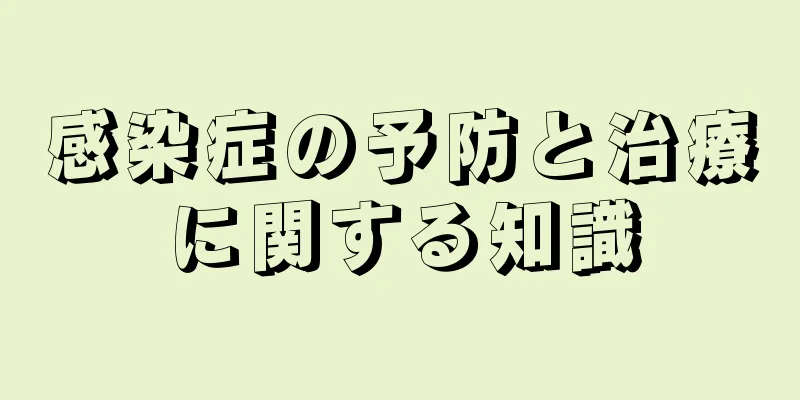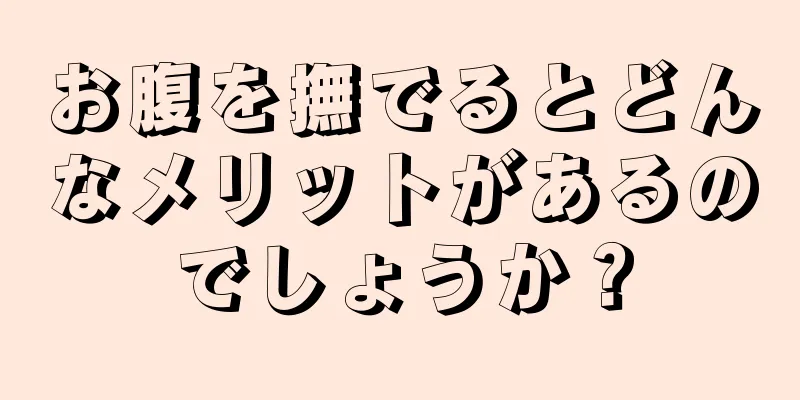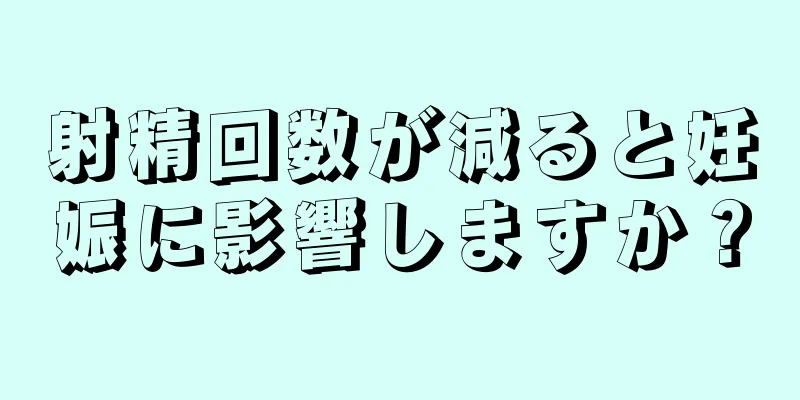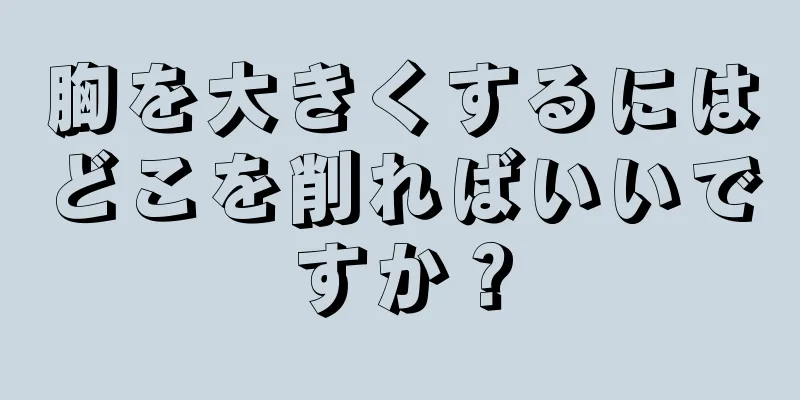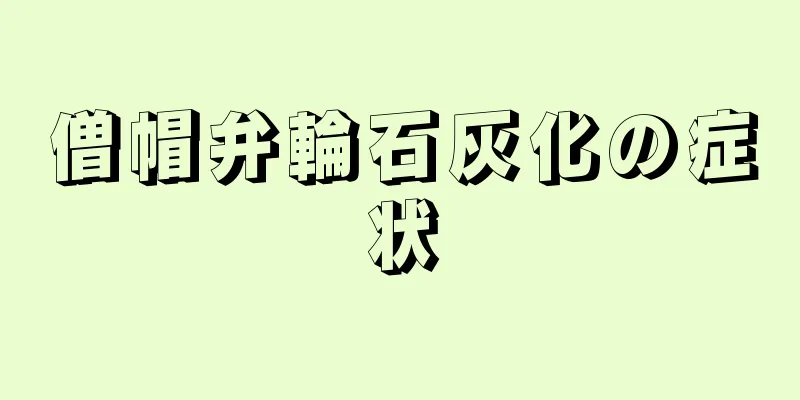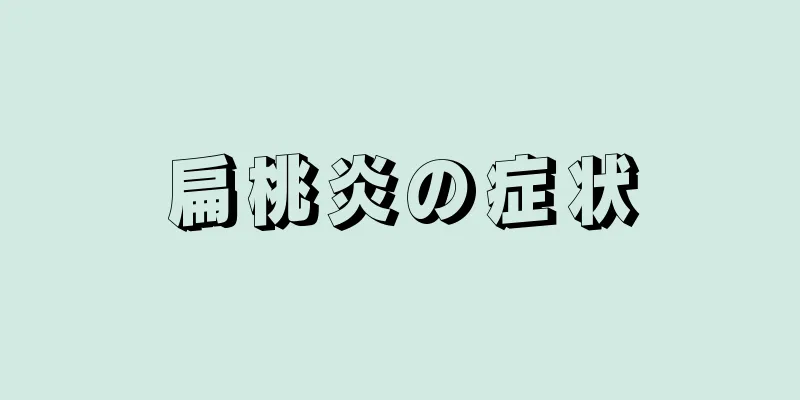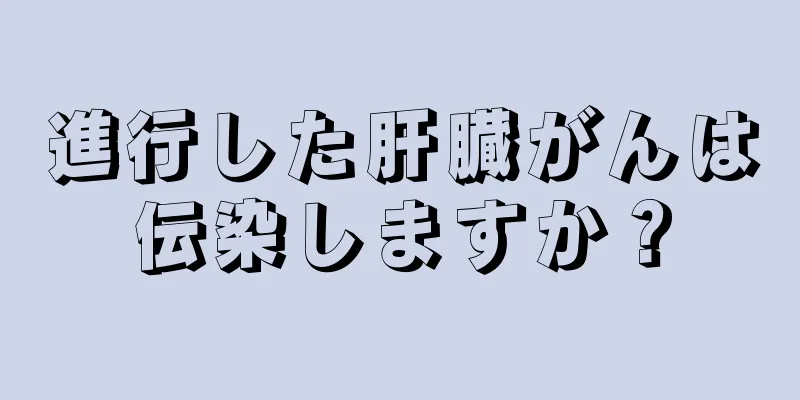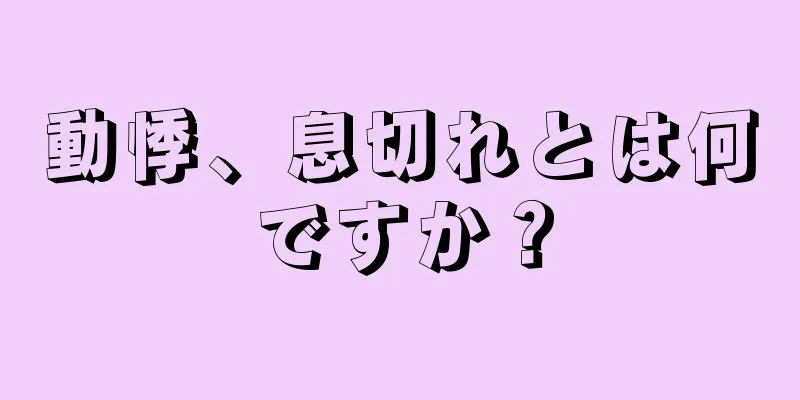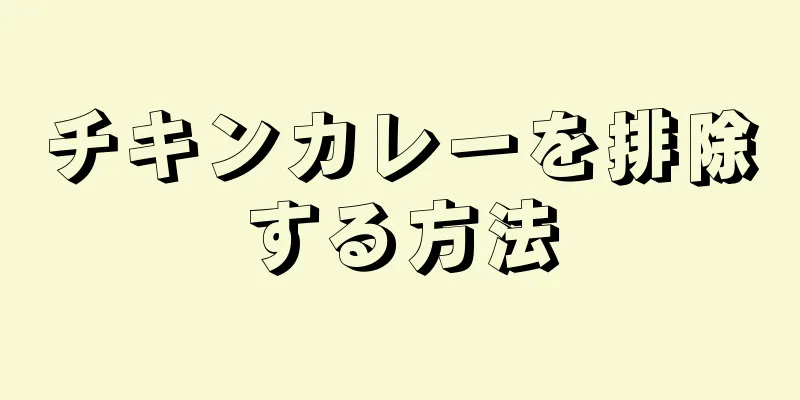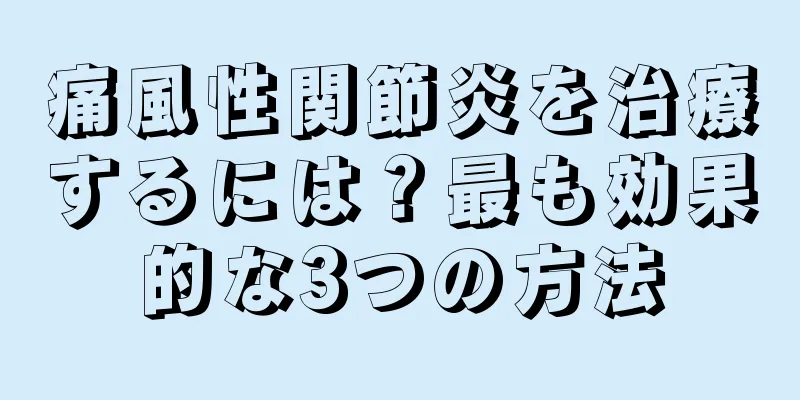爪囲炎の効果的な治療法は何ですか?
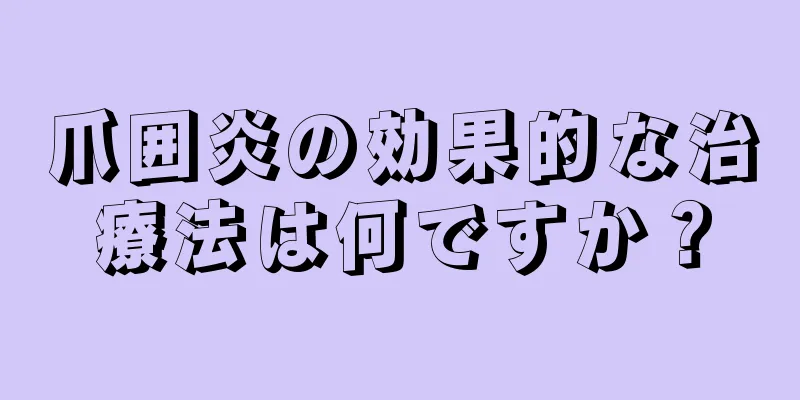
|
爪囲炎は多くの患者に大きな迷惑をかけるため、正しい治療法を採用する必要があります。初期段階では、温湿布、理学療法、外用療法を採用できます。症状が重く、化膿する傾向がある場合は、外科的治療を行うことができます。また、生活の中で良好な衛生習慣を身につけることにも注意する必要があります。 1. 治療方針 初期段階では、温湿布、理学療法、外用などの処置が取られ、ヨードアミンや抗生物質が塗布されます。膿の形成は切開によって排出することができます。爪床の下に膿が溜まっている場合は、爪を除去する必要があります。 2. 対症療法 初期段階では、患部の指をお湯や温湿布に浸したり、軟膏を塗ったり、理学療法を行ったり、患部を上げたりするなどの治療法で、通常は症状を解消できます。 3. 外科的治療 膿がある場合は、爪溝を縦に切開して膿を排出します。感染が爪の根元の皮下組織に広がった場合は、両側の爪溝に縦に切開を入れ、爪の根元の上皮シートをめくり、爪の根元を取り除き、ワセリンガーゼやラテックスシートを小片にして膿を排出させます。爪床の下に膿が溜まっている場合は、爪を除去するか、膿瘍腔の上の爪を切る必要があります。爪を抜くときは、将来的に新しい爪が変形するのを防ぐために、爪床を傷つけないように注意してください。 4. 日常のケア 衛生習慣を身につけ、爪の周りのささくれを勝手に取り除かないでください。ささくれが現れたら、はさみで切り、無理に取り除かないようにしてください。爪は短く切りすぎないようにしてください。指に軽い傷がある場合は、感染を防ぐためにヨードチンキを塗ってから滅菌ガーゼで包帯を巻いてください。普段から指のケアに気を配りましょう。手を洗った後や寝る前にワセリンやスキンケアクリームを塗って、爪の溝の周りの皮膚の抗菌力を高めましょう。 5. 食生活の調整 軽めの食事、果物や野菜を多く摂り、食事のバランスを適度に保ち、十分な栄養に気を配ることが推奨されます。 |
推薦する
フェンネルの効果と機能は何ですか?
フェンネルには多くの機能と効果があり、食欲を刺激し、気を調整し、風邪を治す効果があります。また、食欲...
右腎嚢胞性病変
右腎嚢胞性病変は主に成人男性に発生する疾患であり、通常は片側性疾患であり、患者の年齢が高くなるほど発...
へその周りのかゆみを伴う赤いぶつぶつ
気温が上がってきた今、おへその周りの小さな赤いぶつぶつは発疹かもしれません。まずは病院に行って原因を...
機嫌が悪いと健康に悪影響を及ぼします。ツボマッサージは「感情的なトラウマ」を癒す
人は日常生活の中で、悲しみ、怒り、不安、心配などの感情を常に抱えています。これらのネガティブな感情を...
健康診断当日の朝に水を飲んでも大丈夫ですか?
結婚前検査、妊娠検査など、多くの場合、健康診断が必要であることは誰もが知っています。また、一部の公的...
通常の出産中に膣が緩んだ場合の対処法
赤ちゃんは生まれると膣から出てくるので、出産後に膣が緩くなると感じる女性が多くいます。女性の平均深さ...
湿疹に効くスベリヒユ
スベリヒユは田んぼのそばに生える山菜です。普段はあまり山菜を食べることがないので、知らない人も多いか...
ニンニクとクルミのワインの効能
ニンニクとクルミはどちらも非常に人気のある食品です。特に栄養価が高く、健康志向の人々に好まれています...
気血不足はシミの原因になります。気血を補う食べ物を多く摂りましょう。
気血が不足している女性は、顔にシミができやすい傾向があります。多くの女性がそばかすを除去するスキンケ...
新生児に破傷風ワクチンを接種する方法
新生児は母親のお腹から出たばかりで、外の世界のすべてに馴染みがなく好奇心が強いため、事故に遭いやすい...
ランニング中に皮膚がかゆくなる原因は何ですか?
ダイエットのために走ることは、多くの人にとってフィットネスの第一選択です。走る前のエネルギー補給、朝...
半月板損傷の治療に使われる絆創膏は何ですか?
半月板が損傷した場合、治療は容易ではなく、回復に長い時間がかかる可能性があります。そのため、治療中に...
妊婦がひどい風邪の咳をした場合、どうすればいいでしょうか?
現実の生活では、咳は一般的な肺疾患であり、咳は多くの種類に分けられます。風寒咳は冷たい空気の侵入によ...
特殊な体質を調整する方法、中医学には従うべき処方箋がある
特殊体質について知っている人はほとんどいないかもしれません。実は、特殊体質は伝統的な中国医学で言及さ...
2日間運動した後、左胸に痛みがあります。
多くの研究により、健康を保つためには運動が必要であることがわかっています。毎日、毎週、どれくらいの運...