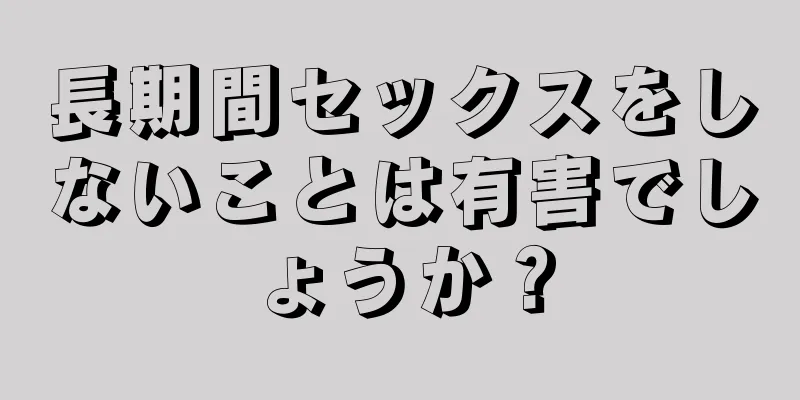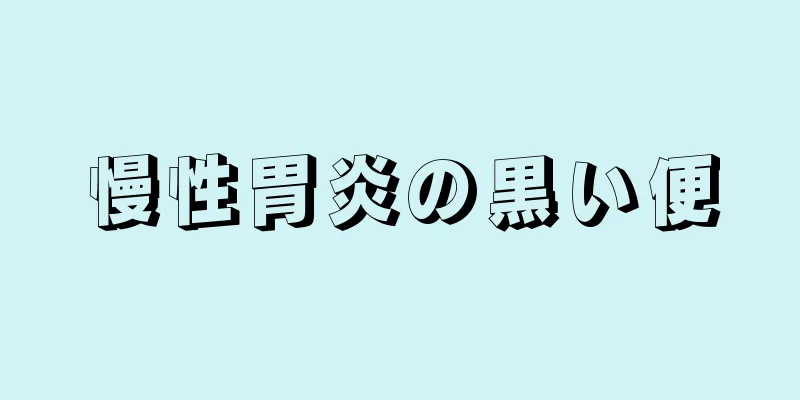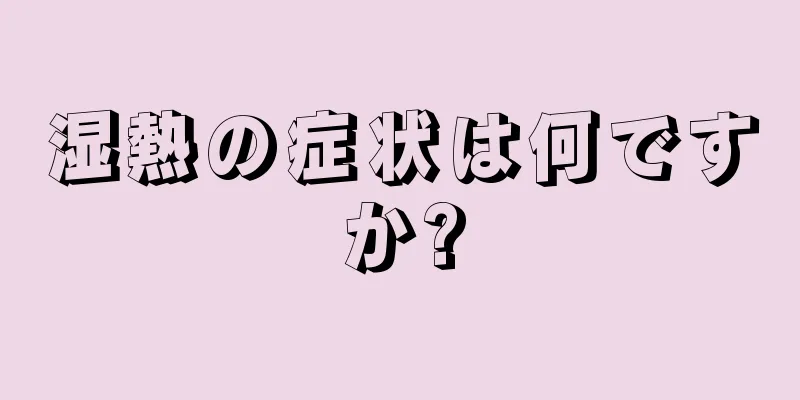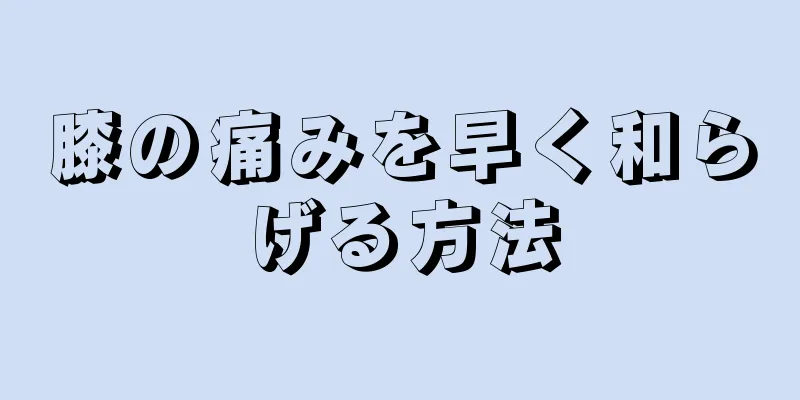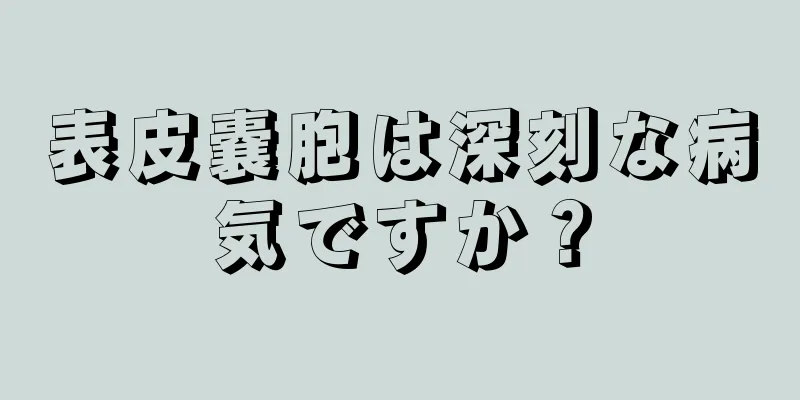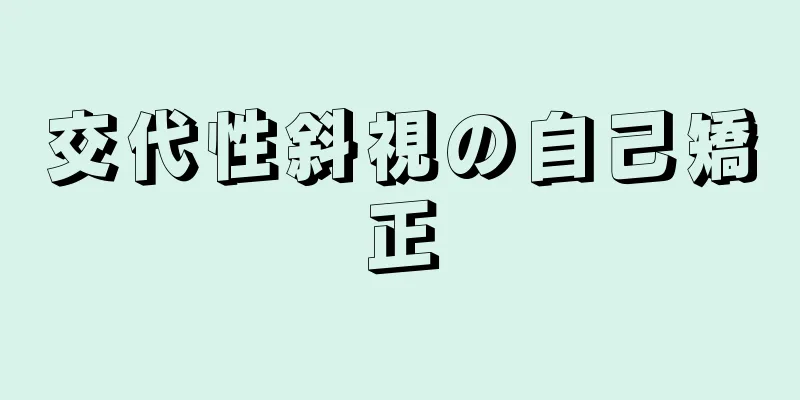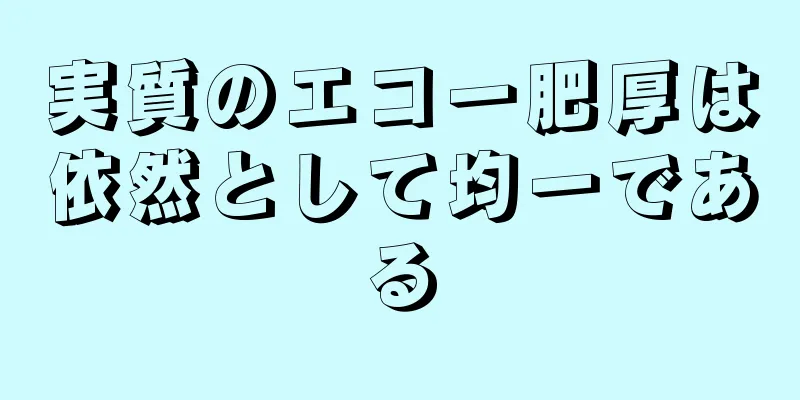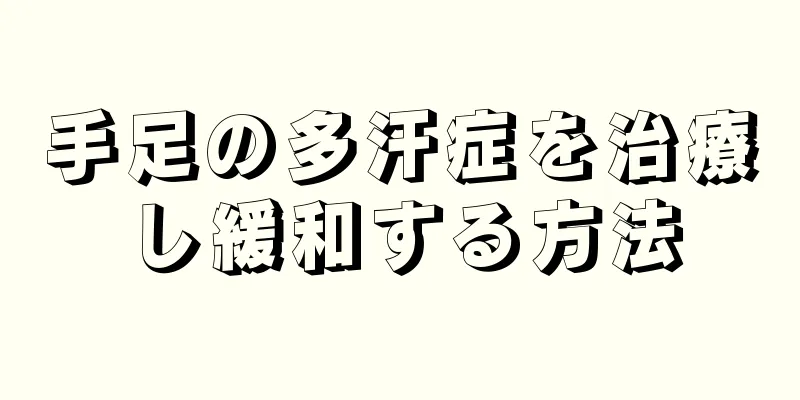マンニトール使用上の注意
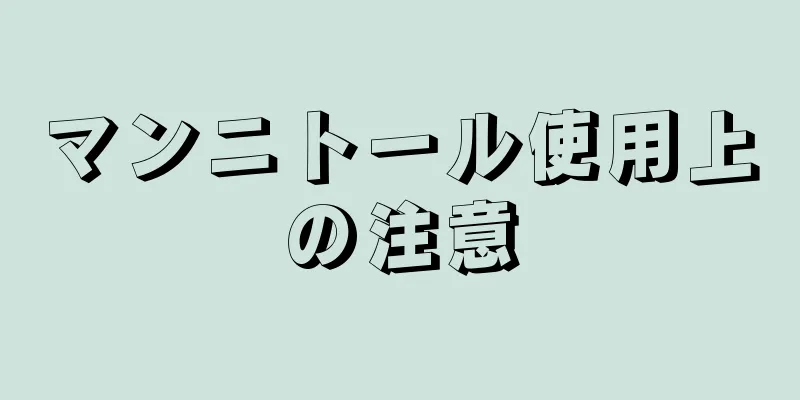
|
マンニトールを使用する際は、注意事項にも注意する必要があります。組織の脱水に適しており、何らかの原因で生じた脳浮腫の治療に効果があります。頭蓋内圧を下げることができます。通常は静脈内に投与されます。薬を使用する際には禁忌に注意する必要があります。たとえば、心肺機能が低下している場合は、慎重に使用する必要があります。高カリウム血症または低ナトリウム血症の患者も慎重に使用する必要があります。 マンニトール使用上の注意 1. 腸管洗浄を除き、すべての薬剤は静脈内投与する必要があります。 2. マンニトールは冷えると結晶化する傾向があるため、使用前によく確認してください。結晶が見つかった場合は、熱湯に入れるか、結晶が完全に溶解するまで激しく振ってから使用してください。マンニトール濃度が15%を超える場合は、フィルター付きの輸液セットを使用する必要があります。 3. 症状に応じて適切な濃度を選択し、高濃度や大量投与の不必要な使用は避けてください。 4. 低濃度のマンニトールを含む塩化ナトリウム溶液を使用すると、過度の脱水や電解質の不均衡の可能性を減らすことができます。 5. サリチル酸中毒またはバルビツール酸中毒の治療に使用する場合は、尿をアルカリ化するために重炭酸ナトリウムを併用する必要があります。 6. 次の状況では慎重に使用してください: (1) 明らかな心肺機能障害のある患者: この薬剤による血液量の急激な増加により、うっ血性心不全を引き起こす可能性があります。 (2) 高カリウム血症または低ナトリウム血症。 (3) 循環血液量減少症: 使用後の利尿により症状が悪化したり、一時的な循環血液量増加により元々の循環血液量減少が隠されたりする可能性があります。 (4) 重度の腎不全および排泄低下により、この薬剤が体内に蓄積し、血液量が著しく増加して心臓負荷が増大し、心不全を誘発または悪化させる可能性があります。 (5) マンニトールに耐えられない患者。 7. 利尿反応なしにマンニトールを大量に投与すると、血漿浸透圧濃度が著しく上昇する可能性があるため、高浸透圧の発生に注意する必要があります。 8. フォローアップ検査:(1)血圧、(2)腎機能、(3)血中電解質濃度、特にNa+とK+、(4)尿量。投与量1. 成人の通常投与量:(1)利尿剤:通常投与量は体重1kgあたり1~2gで、通常20%溶液250mlを静脈内に点滴し、1時間あたりの尿量が30~50mlになるように投与量を調節する。 (2)脳浮腫、頭蓋内圧亢進症、緑内障の治療:体重1kgあたり0.25~2gを15~25%の濃度に調製し、30~60分以内に点滴静注する。患者の衰弱がひどい場合は、投与量を 0.5 g/kg に減らしてください。腎機能を注意深く追跡します。 (3)腎前性乏尿と腎性乏尿の鑑別:20%濃度で体重1kg当たり0.2gを3~5分以内に点滴静注する。投与後2~3時間経過しても1時間当たりの尿量が30~50ml未満であれば、最大でもう1回まで試す。それでも反応がない場合は投与を中止する。心機能障害または心不全の患者は慎重に使用する必要があります。 (4)急性尿細管壊死の予防:まず10分以内に12.5~25gを点滴静注する。特別な事情がない場合は、1時間以内に50gを点滴静注する。尿量が1時間あたり50ml以上を維持できる場合は、5%溶液を点滴静注で継続する。効果がない場合には、直ちに投薬を中止する。 (5)薬物中毒または毒物中毒の治療:20%溶液50gを点滴静注する。尿量が1時間当たり100~500mlになるように投与量を調節する。 (6)腸管準備:手術の4~8時間前に、10%溶液1000mlを30分以内に経口摂取する。 2. 小児の一般的な投与量:(1)利尿剤:体重1kgあたり0.25~2g、または体表面積1㎡あたり60gを15~20%溶液として、2~6時間以内に点滴静脈内投与する。 (2)脳浮腫、頭蓋内圧亢進症、緑内障の治療:体重1kgあたり1~2g、体表面積30~60g/㎡、濃度15~20%溶液を30~60分以内に点滴静注する。患者の衰弱がひどい場合は、投与量を 0.5 g/kg に減らしてください。 (3)腎前性乏尿と腎性乏尿の鑑別:体重1kgあたり0.2gまたは体表面積1m2あたり6gを、15~25%の濃度で3~5分間点滴静注する。投与後2~3時間経過しても尿量に明らかな増加が見られない場合は、再度投与してもよい。それでも反応が見られない場合は、再度投与してはならない。 (4)薬物中毒または毒物中毒の治療:体重1kgあたり2gまたは体表面積1m2あたり60gの割合で5%~10%溶液を点滴静注する。 |
推薦する
婦子利中丸
薬は非常に一般的で、特に風邪、咳、発熱、アレルギーの治療薬はよく使われています。薬は購入しやすく、使...
目のかゆみの原因は何ですか?
目の炎症は目のかゆみであり、目のかゆみにはさまざまな原因があります。目は人体の中で最も傷つきやすい部...
Sanfu ステッカーを貼ってからどれくらい経ったらシャワーを浴びることができますか?
夏は気温が高く、三福シールを貼った後すぐに人体の皮膚の毛穴が開き、熱を急いで排出する必要があります。...
お灸にはどの季節が適していますか?
お灸には長い歴史があり、技術の継続的な発展により、お灸で治療できる病気はますます増えています。お灸は...
血液検査が正常であれば敗血症を除外できますか?
定期的な血液検査の結果が基本的に正常であれば、敗血症の可能性は排除できます。同様の症状が再び現れても...
赤ちゃんの嘔吐や下痢を和らげる方法
赤ちゃんは末っ子なので、その健康状態が両親にとって最大の懸念事項です。しかし、子供が若ければ若いほど...
葛粉の効能と機能
多くの人はクズウコン粉についてあまり知りません。クズウコン粉は、クズウコンという比較的一般的な植物か...
A型肝炎は治癒できますか?
肝臓は主に人体の解毒を助けるために使われています。アルコール依存症など、多くの悪い生活習慣は肝臓にダ...
最も強力な結石除去薬
結石症は比較的よく見られる病気で、内容物も多く、最も一般的なものは腎臓結石、膀胱結石、胆石などです。...
腫れやうっ血を軽減する最速の方法
通常、捻挫やその他の原因により、うっ血や腫れが生じることがあります。このとき、腫れを軽減し、血液の停...
酢Bupleurumの効果と機能は何ですか?
酢ミズキの主な効果は、熱を下げ、細菌やウイルスと戦うことです。特にウイルス性の風邪にかかっている場合...
脇腹の痛みの症状
脇腹に刺すような痛みを感じる現象は、実は急性胸部および肋骨痛と呼ばれています。しかし、脇腹に刺すよう...
手術から2か月経っても切開部は赤くなっています。
手術後2か月で切開部が赤くなるのは、主に帝王切開後の傷口のケアが不十分だったために生じた傷口の感染が...
突然の喉の詰まり
突然喉に詰まりを感じたら、咽頭炎が原因かもしれません。咽頭炎は比較的よくある病気です。患者は喉に異物...
子宮内膜の厚さ 16
専門知識のない人は、女性の身体に特有の現象である子宮内膜について特によく理解していませんが、女性の友...