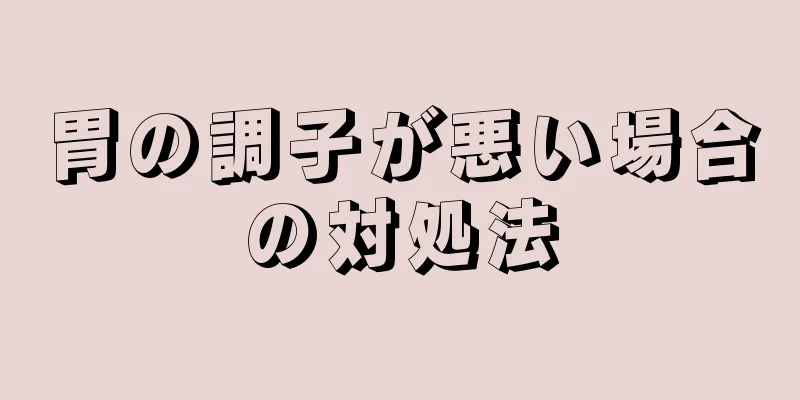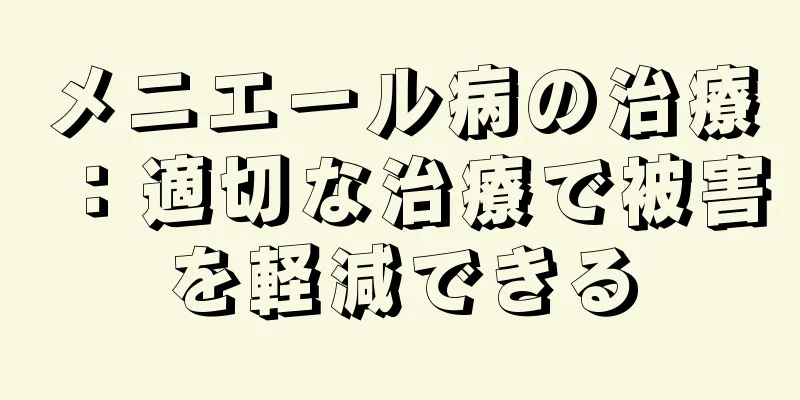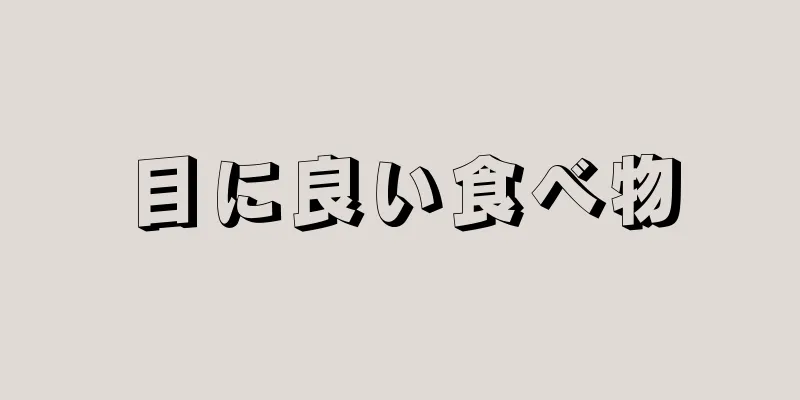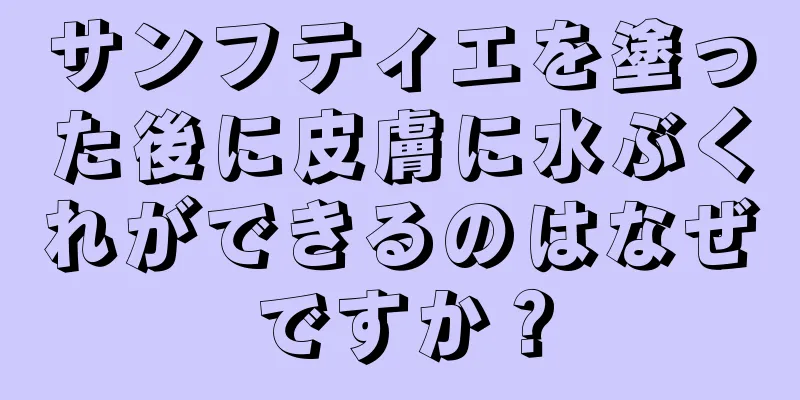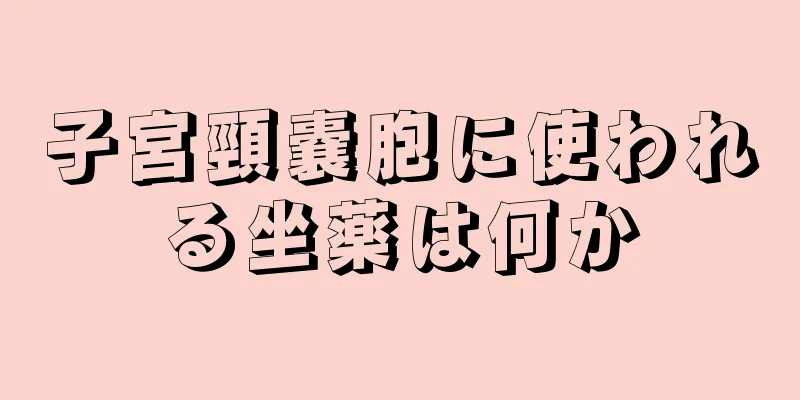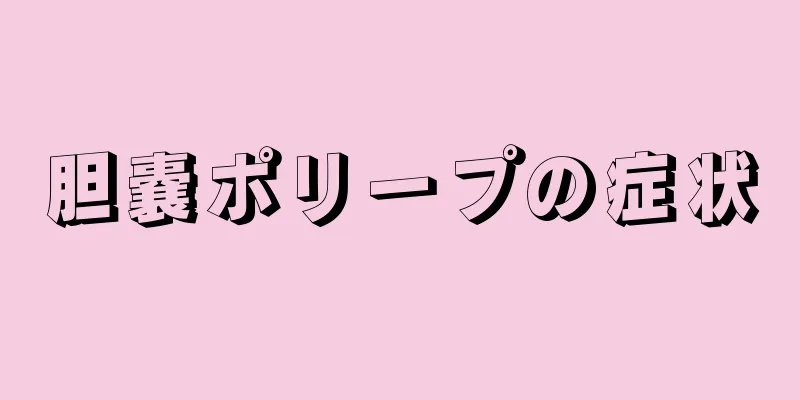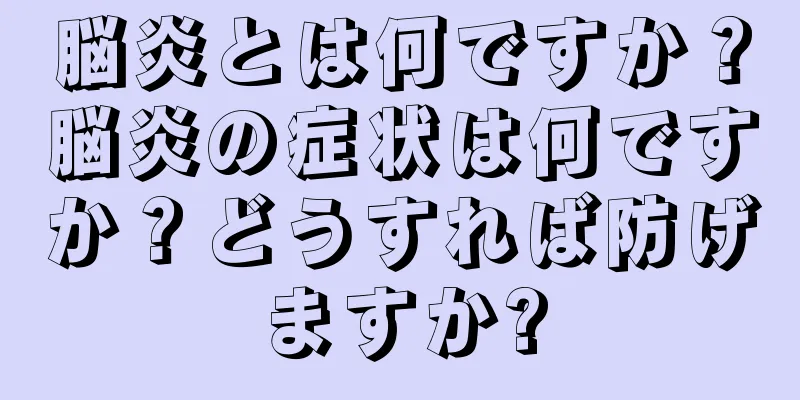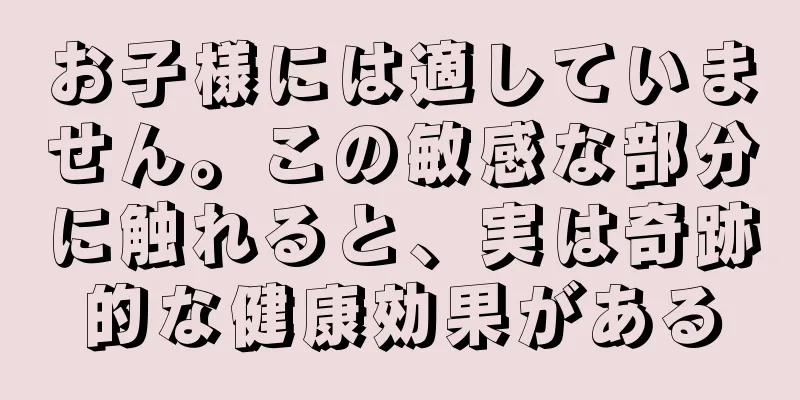パチョリの葉を水に溶かして飲むことのメリット
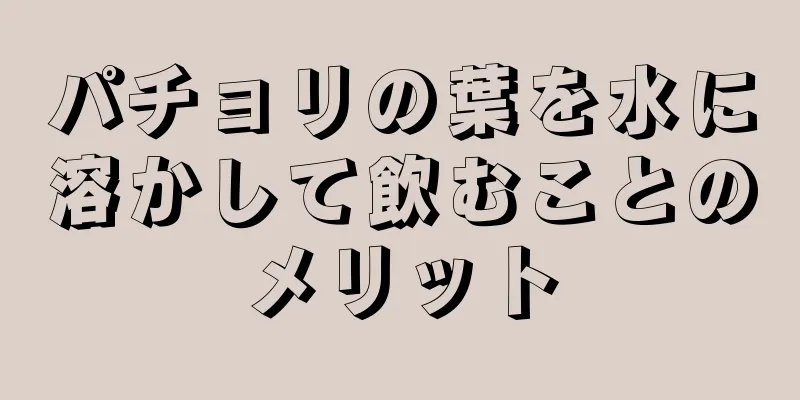
|
夏は熱中症の発生率が高い季節なので、特に夏には火香正気水を飲んだことがあるはずです。熱中症は非常に不快ですが、火香正気水は熱中症の症状を緩和することができます。火香正気水の主成分はパチョリで、独特の味と効果を持つ漢方薬です。では、このパチョリの葉を水に入れて飲むとどのような効果があるのでしょうか。この質問については、記事の詳細な紹介を見てみましょう。 パチョリは木本植物です。草本部分は薬として、果実はスパイスとして使用できます。葉と茎には揮発性物質を含む芳香油が含まれており、非常に香りがよいです。そのためスパイスとしても使えます。パチョリの葉の機能と効果を見てみましょう。 1. 脾臓を養い、気を高め、胃を調和させる。胃腸の湿潤、腹部膨満、湿熱の初期症状に用いられる。湿が中焦を塞いで腹部膨満や食欲不振を引き起こす場合は、紫蘇(シソ)と組み合わせて使用できます。湿熱が始まったばかりの場合は、薄荷、ヨモギ、柴胡(サイコ)と組み合わせて使用できます。 2. 嘔吐を止め、下痢を治す:嘔吐、下痢などに使用します。不潔、嘔吐、下痢に悩む場合は、紫蘇の葉、芍薬、生姜、朴皮、茯苓を併用します。胃寒、嘔吐に悩む場合は芍薬を併用します。寒湿に悩む場合は、黄連、竹皮を併用します。脾胃虚弱、寒に悩む場合は、人参、甘草を併用します。妊娠中の嘔吐に悩む場合は、白茯苓を併用します。 3. 熱を鎮める:夏バテや湿気の症状に用いられます。暑熱を問わず、暑熱湿疹の治療に用いられ、臨床医学ではシソと併用されることが多い。 4. 発汗補虚:熱悪寒、嫌寒熱、胸腹部膨満感、息苦しさなどに用いられます。シソの葉とポリアココスを添えて。 5. 目の透明感:ビタミンDは目の成長と発達に非常に重要な役割を果たし、眼底の黄斑桿体細胞に光感受性物質を生成します。目の病気に対する抵抗力を高め、夜盲症を予防します。 6. その他の効果:副鼻腔炎の治療には、豚の胆汁と併用されることが多い。 パチョリの葉の機能と効果は現在では知られています。パチョリの葉の栄養価は非常に高いことは特筆に値します。鉄分、カルシウム、炭水化物、ビタミンAが豊富です。そのため、成長と発達を促進し、骨の成長を助け、貧血を予防することができます。 |
推薦する
断食の利点と欠点は何ですか?
断食のメリットは、一般的には体内の解毒を促進することであり、減量や痩身にも役立ちます。また、脾臓や胃...
偽陣痛と子宮膨隆の違いは何ですか?
偽陣痛は、女性が妊娠中に経験する症状で、主に妊婦が出産する前に起こり、その感覚はより強くなります。偽...
咽頭炎と口臭は厄介ですが、お茶を一杯飲めば解決できます!
今は秋で、気温も下がり、空気も乾燥してきています。ぐっすり眠った後、目覚めたときに喉の乾燥や痛み、嚥...
深海魚油とレシチンの効果、深海魚油摂取の禁忌
深海魚油は深海魚から抽出した不飽和脂肪成分です。深海魚油を補給すると、血中脂質の調整、血液凝固の予防...
足首の周りの赤い斑点
足首の周りに赤い斑点が現れた場合、それは通常、湿疹が原因です。この場合は、特定の薬で治療でき、抗アレ...
陰を養い肺を養う食べ物
陰を養い、腎を補うことは非常に重要です。肺が弱いと、咳や胸の圧迫感、さらには気血の不均衡や活力の欠如...
頭を押すとなぜ痛いのでしょうか?
頭痛についてはよくご存知でしょう。頭痛の原因は様々で、脳神経の痛みや風邪による頭痛などがあります。頭...
ウィルムス腫瘍
赤ちゃんが生まれたばかりの頃は、体のあらゆる機能が発達段階にあります。成長段階であるからこそ、赤ちゃ...
肝臓、脾臓、胃の問題を調整するにはどうすればいいですか?
伝統的な中国医学では、人体の臓器は身体の健康と密接な関係があります。臓器が正常に機能していれば、身体...
薬物による中絶後にカニを食べても大丈夫ですか?
カニは私たちの日常生活でよく食べられる食べ物です。特に秋には多くの人がカニを食べるのが好きです。カニ...
心房細動手術の成功率、手術難易度の高さ
心房細動の治療では、高周波アブレーションなどの外科的治療も一般的ですが、この治療法は非常に難しく、多...
歩くとお腹の右側が痛くなるのはなぜですか?
今日の引退した高齢者は、主に子供の世話、料理、運動、スクエアダンスに時間を費やしています。花を育てた...
舌苔の原因は何ですか?
伝統的な中国医学の観点から見ると、舌苔の色の変化は身体に何らかの問題がある可能性を示しており、特に風...
血風根の効能と機能
血風根は血風蔓とも呼ばれ、一定の薬効を持つ薬用物質であり、多様な機能と効果を発揮し、人体の健康を改善...
鍼治療はどのくらいの頻度で行うべきですか?
一般的には、鍼治療は1日おきに行うのがベストですが、1日1回行うこともできます。病気の重症度に応じて...