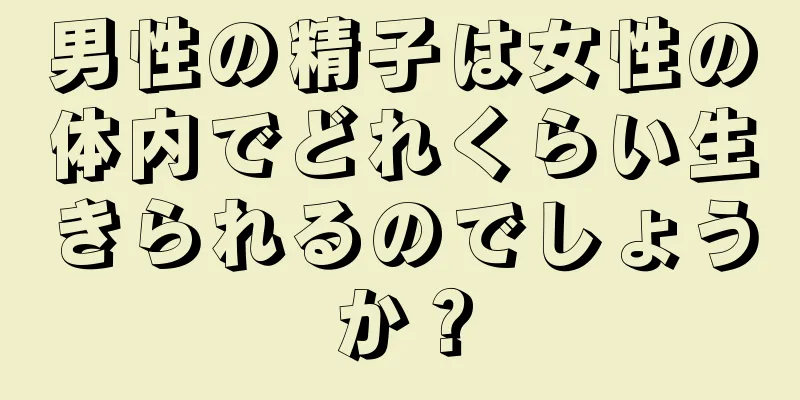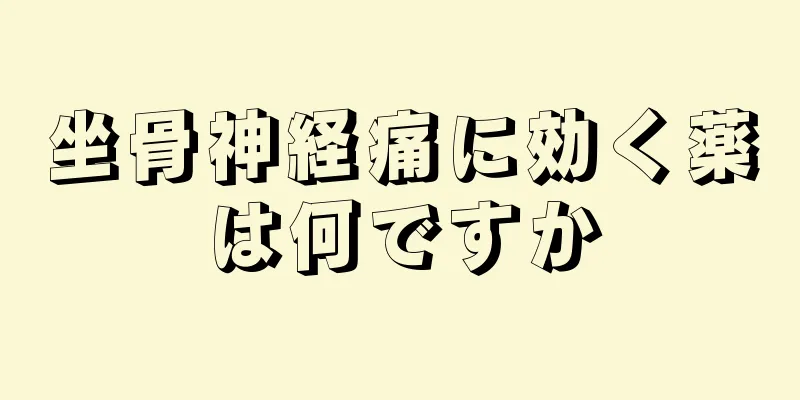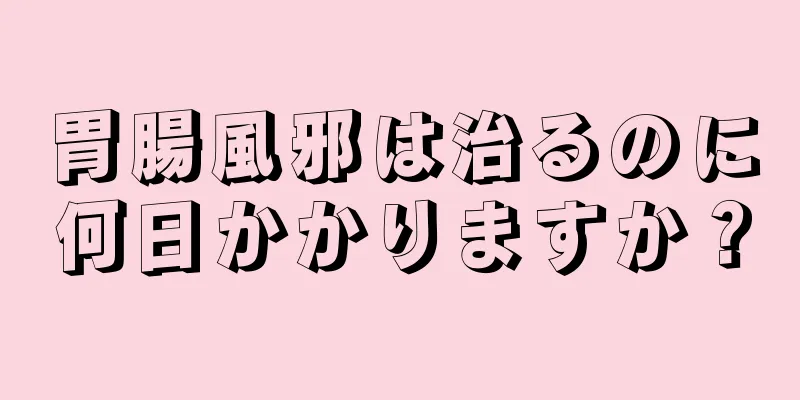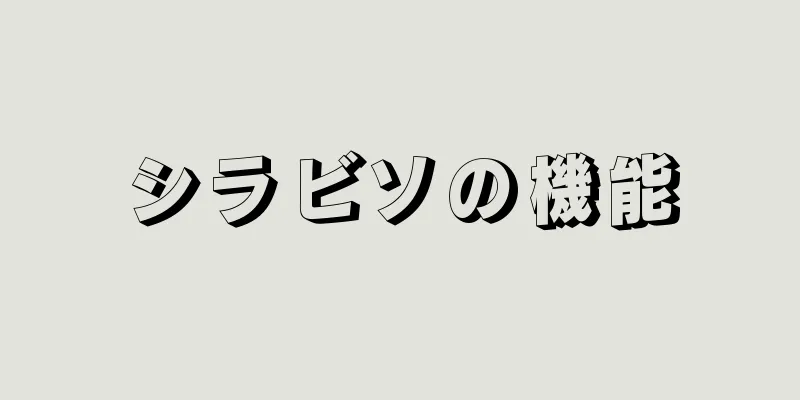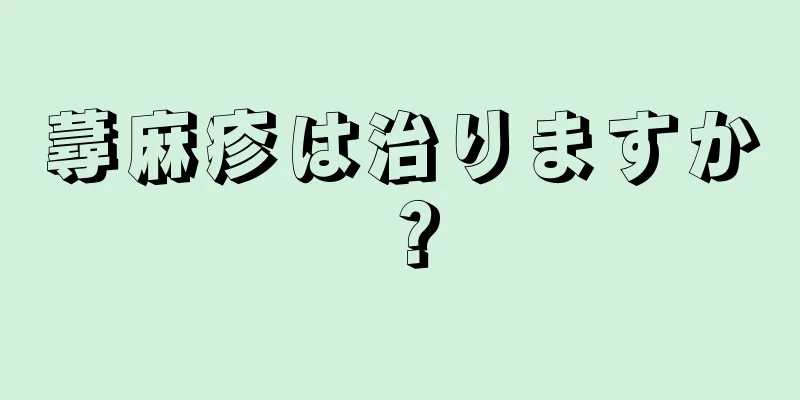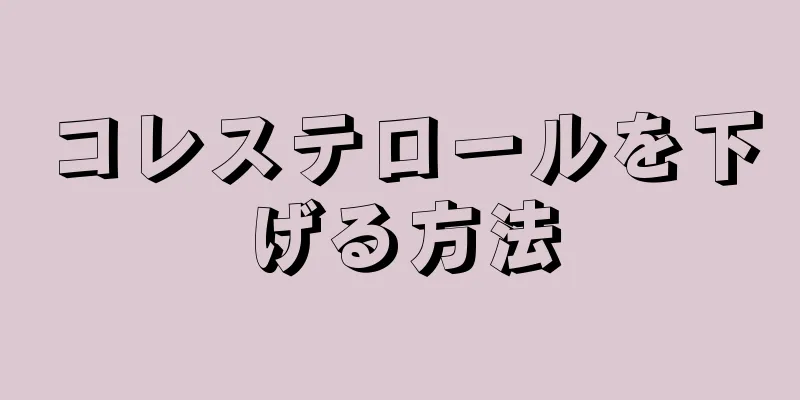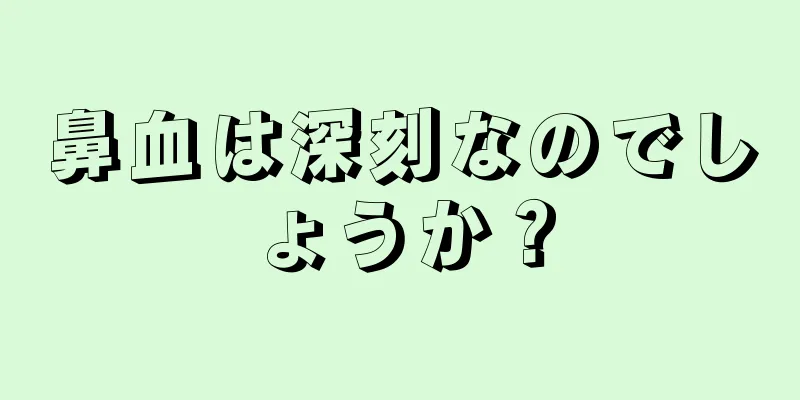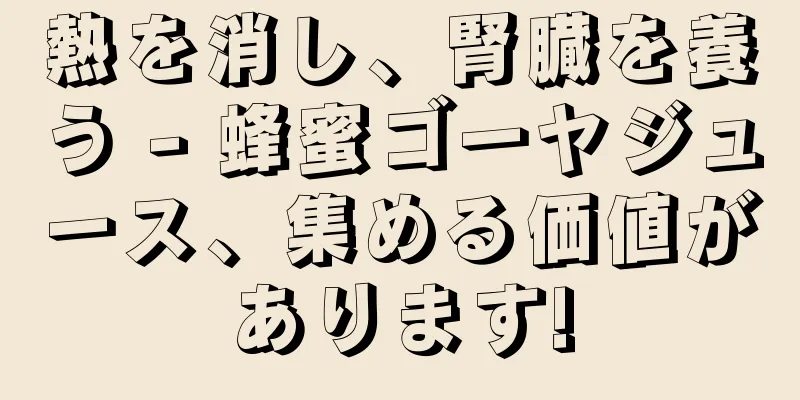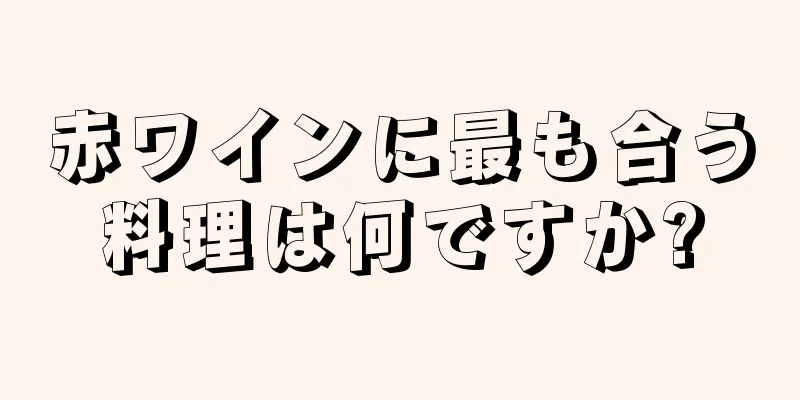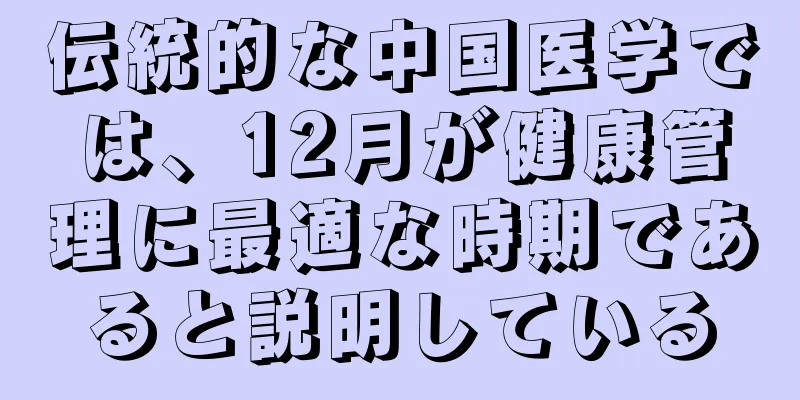伝統的な中国医学における脾臓と胃の調整方法
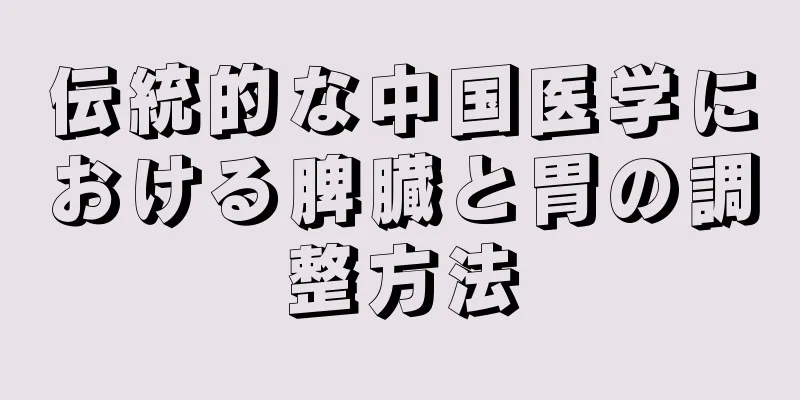
|
脾臓や胃の不調は、臨床現場では非常によく見られる症状です。このような患者は通常、過度の精神的ストレス、不規則な食事、過度の疲労に悩まされています。脾臓と胃が弱くなると、患者の健康に大きな害を及ぼし、正常な仕事にも影響を及ぼします。したがって、生活の中で必要な調整を行う必要があります。では、漢方では脾臓と胃をどのように調整するのでしょうか?いくつかの治療法については、以下の紹介をご覧ください。 1. 脾臓と胃を強くするには、まず気分を養わなければなりません 脾臓と胃には「情」があり、「情養」とは脾臓と胃を養うことでもあります。日常生活では、落ち込んで気分が落ち込んでいるときは食欲がなくなり、リラックスした環境と幸せな気分のときは食欲が増すという経験をすることがよくあります。 研究によると、胃の問題の約 70% は感情に関連しており、胃の機能不全の人は平均的な人よりもうつ病やその他の感情的な病気に苦しむ可能性が 3.1 ~ 4.4 倍高いことがわかっています。 「感情」の変化は胃腸機能の変化を引き起こすことが多いため、胃は人間の感情の変化の「バロメーター」と呼ばれています。 伝統的な中国医学では、「感情は胃を傷つける」ということは古くから認識されており、古代の賢者は胃の問題を治療するために「感情の調整」を用いていました。これは、ある程度、感情が脾臓と胃に重要な影響を与えることを示し、脾臓と胃を養うためには、まず感情を養わなければならないということです。 2. 全粒穀物食は脾臓と胃を強くする 脾臓と胃は貯蔵臓器です。食生活と健康管理は脾臓と胃を養うことから始まります。 水と穀物は人間の生命の基盤であり、胃は水と穀物を受け取る役割を担っているため、脾臓と胃を養うのに最適なものは穀物です。 『黄帝内経』には「五穀は滋養、五果は補養、五畜は利養、五菜は腹を満たす」とある。これは、穀物(主食)が人間の生存の基盤であり、果物、野菜、肉類はいずれも補助的で滋養強壮の役割を果たすという意味である。 3. 足指を頻繁に動かして脾臓と胃を強くする 同時に、脾臓は手足を制御し、適切な運動は脾臓と胃を強化します。伝統的な中国医学の観点から見ると、経絡系は人体の四肢全体に分布しているため、適切な運動は経絡の気の循環を促進し、脾臓と胃に影響を与え、それらの機能を高めることができます。 一般的に、脾胃の機能が強い人は、四肢の筋肉がより発達しています。女性の場合、脾胃が健康な人は、乳首を通って胃経が通っているため、通常、胸が豊かです。脾胃の機能が強く、胃経の気が十分であることが、胸の発達と豊かさに重要な役割を果たします。 漢方で脾臓と胃を整えるには?人生がどんなにストレスに満ちていても、私たちは心をリラックスさせ、イライラしたり不安になったりせず、自分自身へのプレッシャーを和らげることを学び、ストレスを解消するために運動に出かけるべきです。もう一つは、日々の生活習慣を改善し、毎日時間通りに食事をし、消化しやすい食べ物を摂り、辛いものや脂っこいものは食べないようにすることです。もう一つは、毎日休息を取り、時間通りに起きることです。 |
推薦する
頸椎症の治療方法
頸椎症の発症率と発生頻度が増加するにつれて、頸椎症によって引き起こされる痛みは特に耐え難いものになっ...
女性の脱毛の深刻な原因
女性の脱毛は日常生活でよく見られる現象で、日常生活の悪い習慣、精神的要因、過度のストレス、仕事上の理...
出産後40日目の黄色い膣分泌物
出産後2週間で悪露が排出されます。この悪露は帯下でも月経でもありません。不要なものです。排出すること...
赤ちゃんが風邪をひいたときの治療法は何ですか?
幼い子供の場合、身体がまだ十分に発達しておらず、抵抗力や免疫力が弱いため、季節の変わり目や天候が暑す...
右胸の圧迫感、しゃっくり、胃酸の逆流を引き起こす病気は何ですか?
私たちの生活の中で、胸焼けは今でも非常によく起こります。胃の中に硫酸があり、それが熱く感じるのと同じ...
更年期の女性はこうやって健康を維持していることが判明
閉経後、女性は身体的、精神的に何らかの変化を経験し、憂鬱、イライラなどの否定的な感情を経験するように...
ジャガイモの皮は足裏の炎症を治すことができますか?
タコとは、足の裏に角質層が現れることです。この角質層は比較的厚いため、歩くときに痛みや不快感を引き起...
咽頭炎症状の改善過程
咽頭炎といえば、誰もがよく知っていると思います。ご存知のとおり、実生活では多くの人がこの点で問題を抱...
男性尿道肥大
男性における尿道肥大の発生は比較的異常な現象です。この問題は、それはおそらく性器イボの症状です。性器...
肺熱咳嗽とは
咳は人体で非常によく見られる症状です。風邪をひくと咳が出やすくなります。しかし、咳の原因は風邪だけで...
銀枝黄の副作用
銀枝黄という薬材は主に新生児高ビリルビン血症の治療に使われますが、新生児に黄疸がよく見られる症状で、...
アストラガルスの摂取方法
黄耆は誰もが知っている人気の漢方薬です。黄耆の主な効果は、体の気を補充し、体の免疫力を効果的に高める...
溶接光が皮膚を傷つけた場合の対処法
溶接工として、溶接中に皮膚に傷がついた場合は、感染を防ぐために必要な措置を速やかに講じる必要がありま...
高トリグリセリドの原因は何ですか?
現在、人々の生活水準や食生活は以前よりもはるかに向上しており、多くの中高年が何らかの心臓血管疾患や脳...
目の下のたるみを取るにはどのツボをマッサージすればよいでしょうか?
目は心の窓であり、目を見れば心の中がわかると言われています。しかし、目の下のたるみがあると、印象がか...