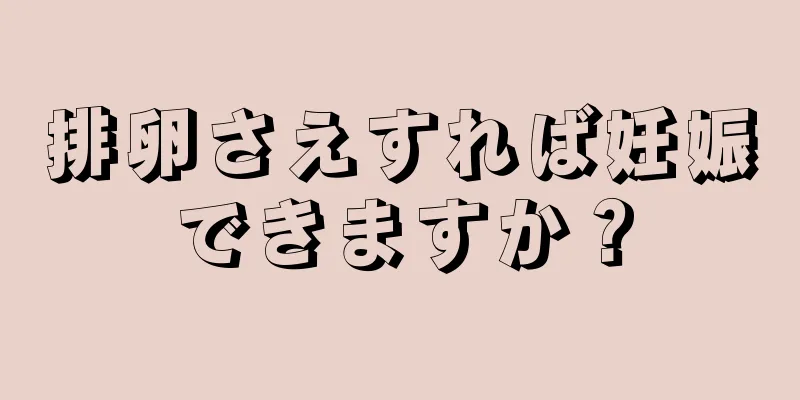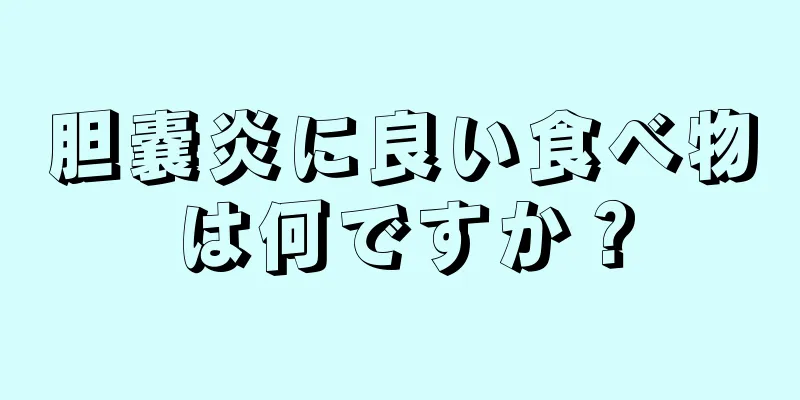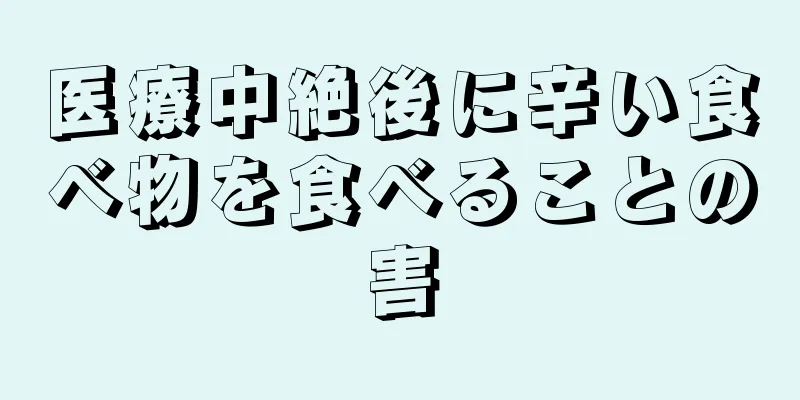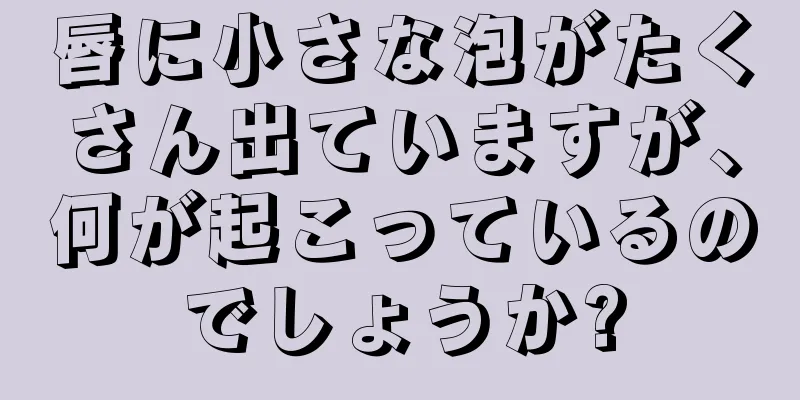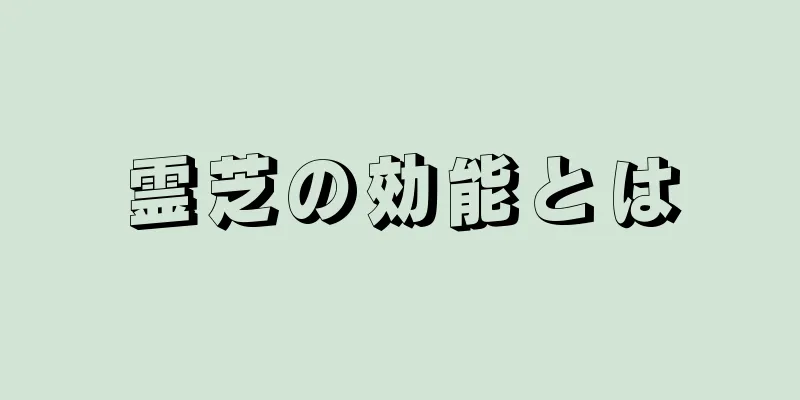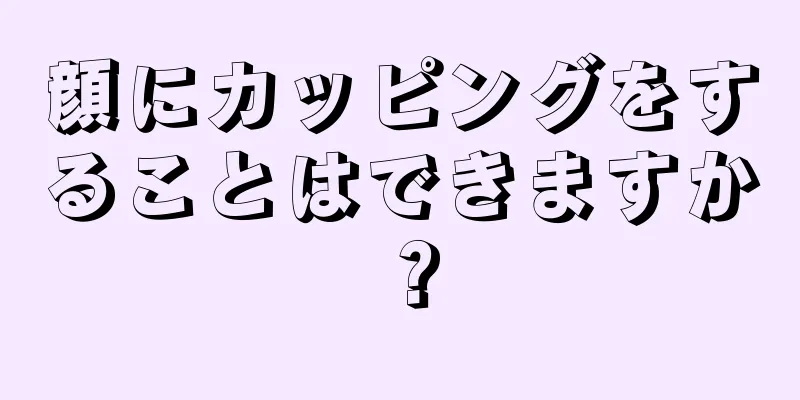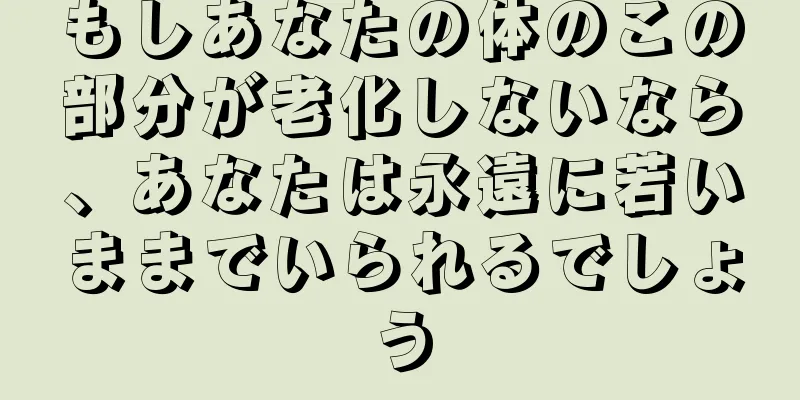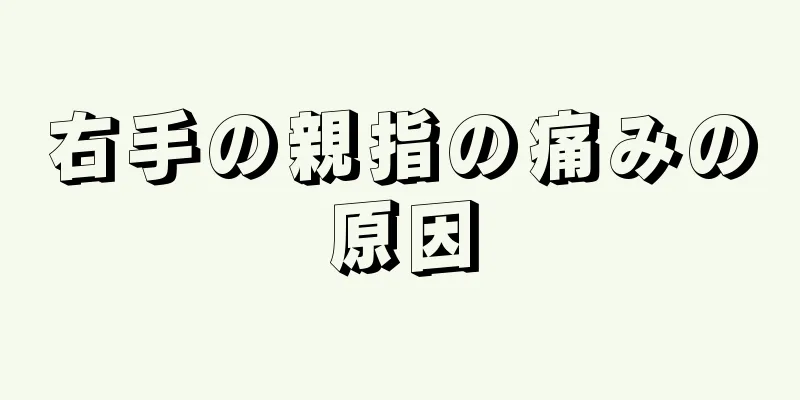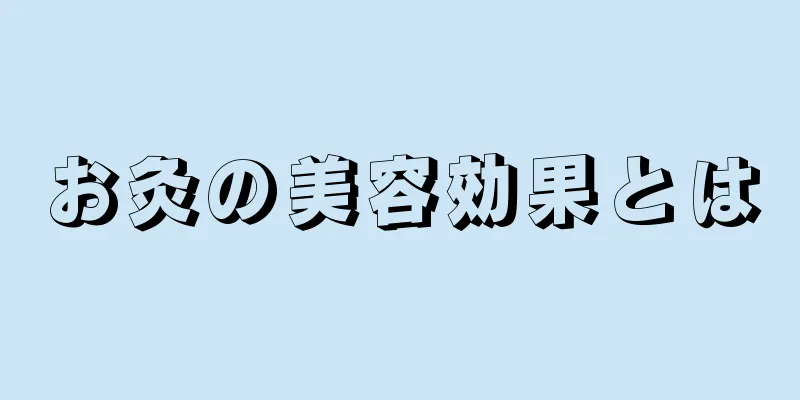尿ミクログロブリン値が高い
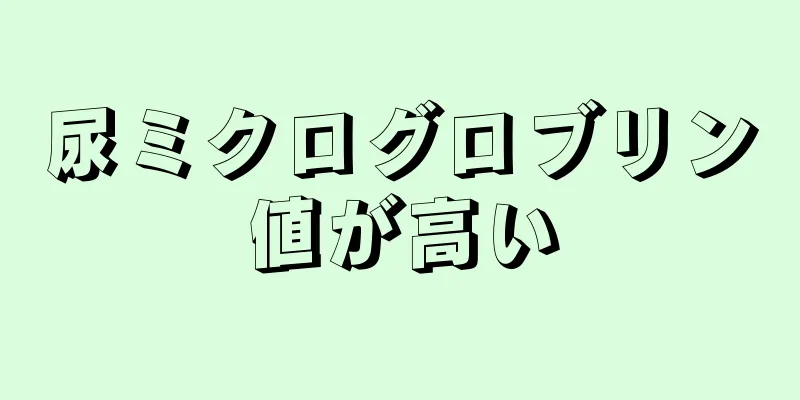
|
尿中ミクログロブリンは、β2-ミクログロブリンとも呼ばれます。通常の状況では、β2-ミクログロブリンの含有量は比較的安定しており、人間の血液、唾液、尿に広く存在します。尿ミクログロブリン値が上昇すると、健康上の問題がある可能性があることを示します。これは多くの状況に分けられます。検査の各部分の意味は異なります。急性および慢性の腎盂腎炎、尿路感染症などの検出に重要な役割を果たします。 血清β2ミクログロブリンの増加は、糸球体濾過機能が損なわれているか、濾過負荷が増加しているかを反映します。 尿中のβ2ミクログロブリン排泄量の増加は、腎尿細管の損傷または濾過負荷の増加を示します。 急性および慢性の腎盂腎炎では、腎臓の損傷により尿中のβ2ミクログロブリンが増加します。 対照的に、膀胱炎の患者ではβ2ミクログロブリン値は正常です。 腎臓移植患者の血液と尿中のβ2ミクログロブリン濃度は著しく上昇しており、これは体が拒絶反応を起こしていることを示しています。β2ミクログロブリンの合成が加速されるため、腎クリアランスは増加しますが、血液中のβ2ミクログロブリン濃度は依然として上昇しています。通常、血中β2ミクログロブリンは移植後2~3日でピークに達し、その後徐々に減少します。腎移植後の血液および尿中のβ2-ミクログロブリンの連続測定は、糸球体および尿細管病変の敏感な指標として使用できます。例えば、腎臓移植患者は乏尿になることがあります。しかし、血中β2ミクログロブリンが減少すれば予後は良好であることがわかります。拒絶反応が起こると、Cr の前に血中 β2-ミクログロブリンが増加します。β2-ミクログロブリンを測定すると、潜在性段階の腎拒絶反応を診断するのに役立ちます。 尿中 β2 ミクログロブリンの測定は、上部尿路感染症と下部尿路感染症を区別するのにも役立ちます。上部尿路感染症は、腎尿細管による分子タンパク質の再吸収に容易に影響を及ぼし、尿中 β2 ミクログロブリンの上昇をもたらしますが、下部尿路感染症では尿中 β2 ミクログロブリンの上昇は生じません。 β2-ミクログロブリン(略称β2-MG)は、糖尿病患者の軽度の腎機能障害を測定し、治療効果を観察するためのシンプルで正確かつ感度の高い方法であると考えられています。したがって、β2-ミクログロブリンの測定は臨床現場でさまざまな価値を持っています。 1.この検査は主に近位腎尿細管機能のモニタリングに使用されます。急性尿細管障害や壊死、慢性間質性腎炎、慢性腎不全などの場合には、尿中β2-MGが著しく増加することがあります。腎臓移植患者の血液および尿中のβ2-MG濃度は著しく上昇しており、これは身体が免疫拒絶反応を起こしていることを示しています。腎臓移植後のβ2-MGの継続的な測定は、糸球体および尿細管機能を評価する感度の高い指標として使用できます。糖尿病性腎症の初期段階では、腎尿細管機能の変化と尿中β2-Gの上昇が見られます。 2.尿中β2-MGは、全身性エリテマトーデスの活動期や慢性リンパ性白血病などの造血悪性腫瘍でも増加する可能性があります。血中β2ミクログロブリンと同時に測定し、上記疾患の診断に併用することができます。基準値は0~0.2mg/Lです。 血尿の一般的な病気 ↑ = 主に糸球体濾過機能の低下により起こり、急性・慢性腎炎、腎不全などによく見られます。 =↑ 主に腎尿細管再吸収機能の著しい障害が原因で、先天性近位尿細管機能不全、ファンコニ症候群、慢性カドミウム中毒、ウィルソン病、腎移植拒絶反応などでみられます。 ↑ ↑ 主に体の特定の部分での過剰な生成、または糸球体や尿細管の損傷が原因で、慢性肝炎や糖尿病などでよく見られます。高齢者では、血液中および尿中のβ2ミクログロブリン値の上昇もみられることがあります。 |
推薦する
乳房のオレンジの皮のような変化の原因
乳房にオレンジの皮のような変化が起こる主な原因は乳がんである。乳がんと診断されると、リンパ管が詰まり...
左腕が痛い場合、どんな病気に気をつければよいでしょうか?
気分が悪くなった場合は、すぐに医師の診察を受け、症状の緩和や治療を医師に依頼してください。現代人は毎...
腎不全の症状は何ですか?
腎機能の低下は人体の健康に非常に有害であり、頻繁に体力不足や疲労感、食欲不振、さらには吐き気や嘔吐な...
体を強くする伝統的な中国医学
主な材料: 牛肉、ヒシの実、大根、川芒、たけのこ、ニンニク、シーフードソース、オイスターソース、チュ...
唇が黒くなる原因は、次の3つが最も一般的です。
唇の色の違いは、多くの場合、人の体のさまざまな病気を示すことがあります。その中でも、唇の黒ずみは最も...
なぜ女性は無力症になるのでしょうか?
女性は水でできていると言われています。実は、これは女性の体格が男性より弱いことを反映しています。体の...
龍爪菊の効果的な食べ方
龍爪菊は白酒の原料として生で食べることもできるほか、お湯で沸かしてお茶として飲むこともできます。 1...
鼻炎は漢方薬で治療できますか?
鼻炎は秋から冬にかけてよく見られる呼吸器疾患です。主な症状としては、鼻づまり、鼻水の過剰、嗅覚の低下...
喉の痛みに効く食べ物
秋の初め、夫はいつも喉が痛くて、時には乾いて痰が絡んでいました。毎朝起きると長い間気分が悪かったです...
蚊に刺された跡を消す
夏は暑さが気になるだけでなく、蚊も大量発生します。蚊は人間の血を吸うことを好むため、夏の害虫の一つと...
内分泌障害はなぜ起こるのか?主な原因はこれです
内分泌障害が発生したら、原因を突き止めて調整する必要があります。栄養不足が原因の場合は、食事で栄養を...
耳鳴りや難聴を治療するための伝統的な中国医学の鍼治療の方法は何ですか?
難聴と耳鳴りは日常生活でよく見られる耳の病気です。難聴と耳鳴りの基本的な症状は、聴力の低下と耳鳴りで...
中を温めて冷えを解消する処方箋は何ですか?
日常生活では、良い食習慣を身につけることに注意を払わない人もいますが、特に夏には、生の冷たい食べ物を...
脾胃虚弱、冷え症の内外治療に用いられる漢方薬
漢方薬の利点は副作用が少なく、治療効果が高いことです。では、脾臓や胃が弱い人は生活の中でどのような薬...
伝統的な中国医学は胃の問題を治療する優れた処方箋である
最近、なぜ胃の不調に悩む人が増えているのでしょうか? かつては、胃の不調は主に成人に見られましたが、...