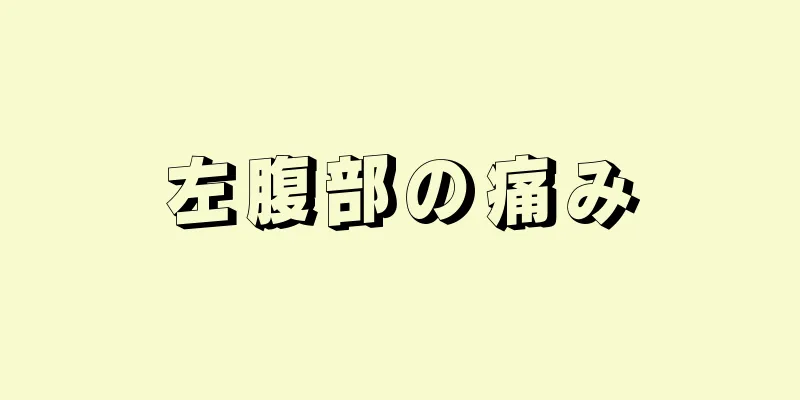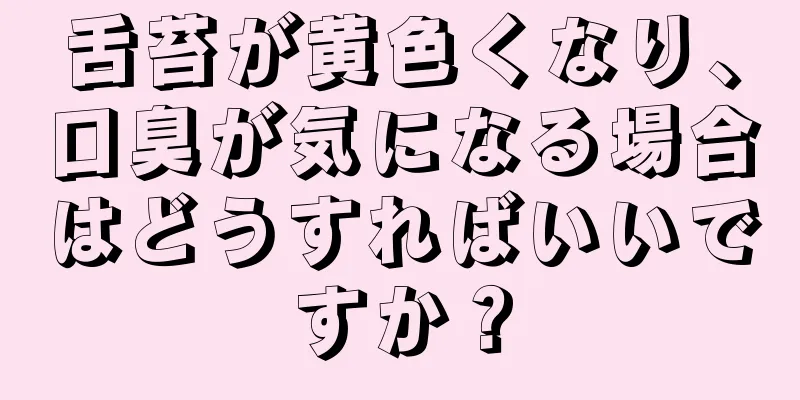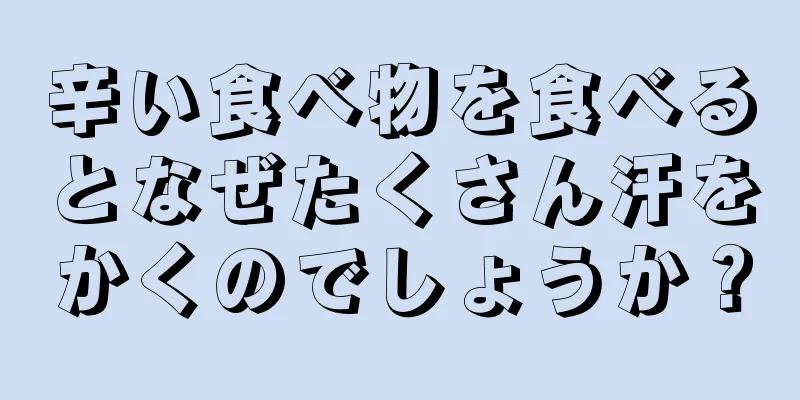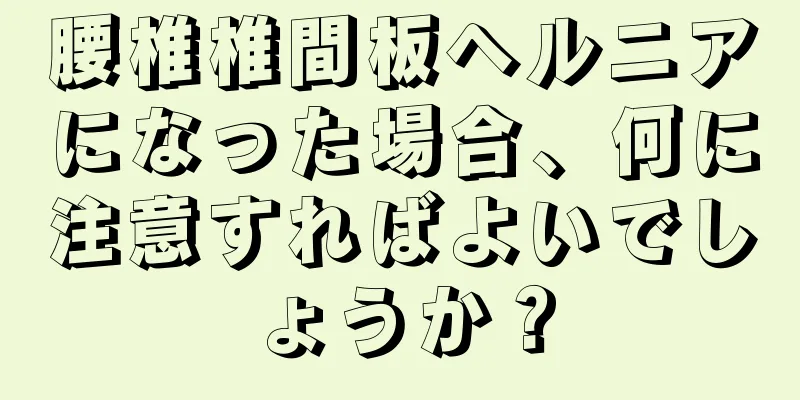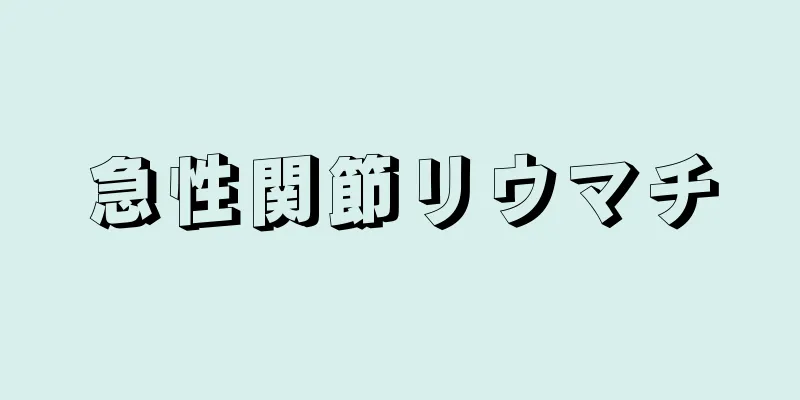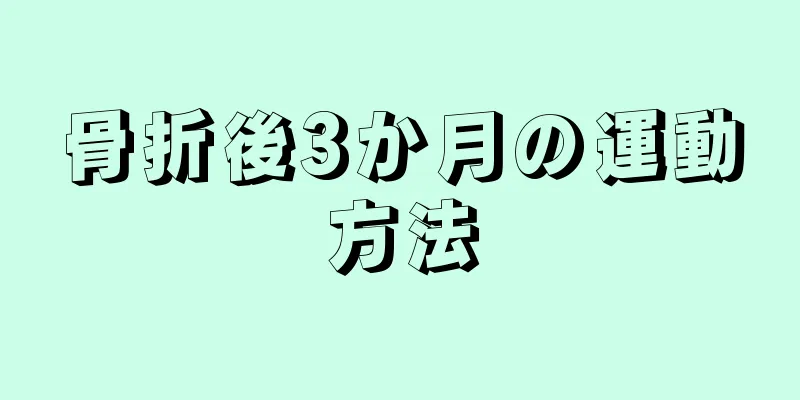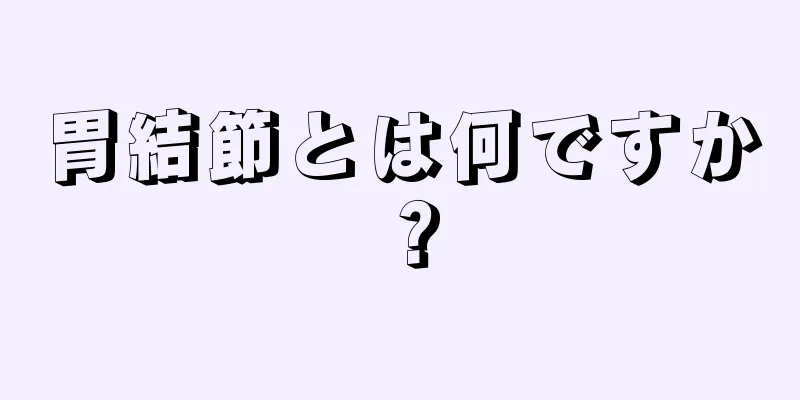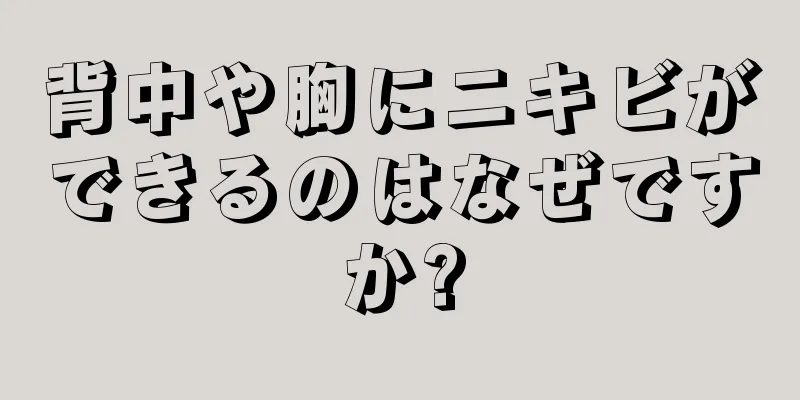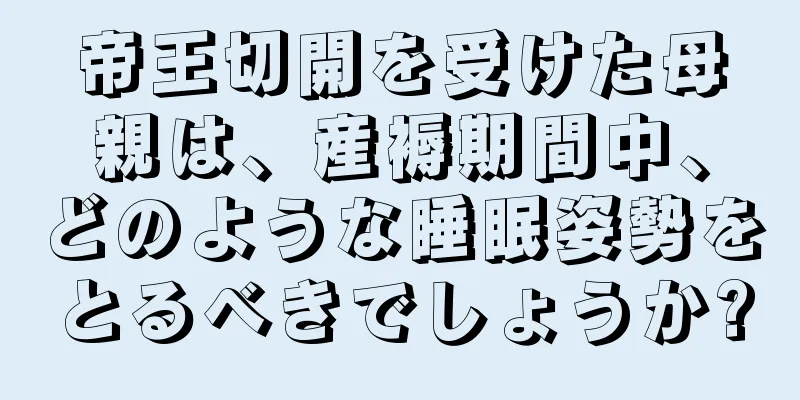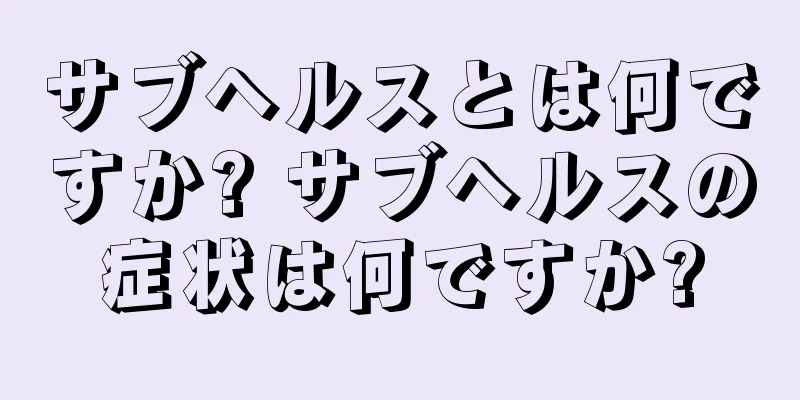親知らず抜歯時の抗炎症薬
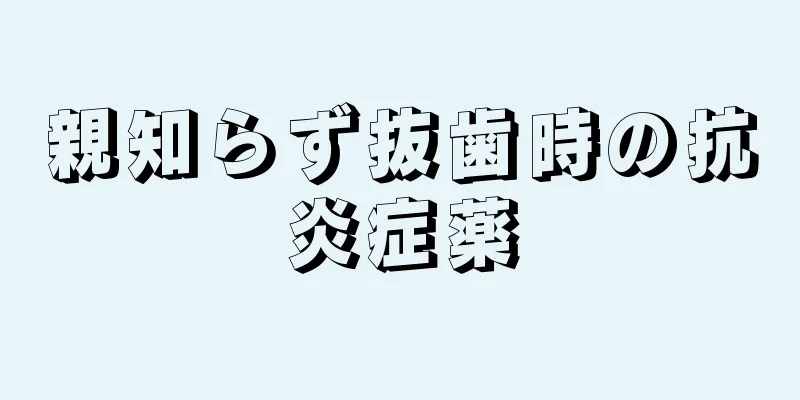
|
歯は私たちの体にとって非常に重要な部分です。歯茎の上にある歯は規則に従って成長し、体に何の影響もありません。しかし、親知らずなど、日常生活に大きな影響を与える歯はそうではありません。多くの場合、症状を和らげるために抗炎症薬を服用しますが、問題を解決するために抜歯もよく使用されます。抜歯後、歯茎が損傷し、炎症が発生することがよくあります。また、日常の食生活にも大きな影響を及ぼします。では、このとき症状を和らげるためにどのような抗炎症薬を服用すればよいのでしょうか。 一般的に、感染を防ぐために、抜歯の前後に抗炎症薬を使用して治療する必要があります。治療にはレボフロキサシン、メトロニダゾール、イブプロフェンなどを経口摂取し、口を清潔に保つことが推奨されており、良い効果が得られます。 レボフロキサシンなどの広域スペクトル抗生物質とメトロニダゾール、チニダゾールなどの抗嫌気性薬を使用するのが最適です。 意見と提案:メトロニダゾールとチニダゾールは胃にわずかに刺激を与えるため、食後に服用できます。抜歯前に服用する必要はありません。 メトロニダゾールをアモキシシリンまたはリジュンザと併用し、1 回 1 錠を 1 日 3 回、5 日間連続して経口摂取します。病院に行って抗炎症薬の注射を受けることをお勧めします。 2. 抜歯後に抗炎症薬を服用する必要がありますか? 抜歯後に抗炎症薬を服用する必要はありません。抜歯後に治療を続けるために薬を服用する必要があるかどうかは、抜歯した歯の状態と抜歯プロセスの複雑さによって異なります。 傷が小さく、抜歯もスムーズで、抜歯後の不快感もない場合は、身体に抵抗力があるため、抗炎症剤を服用する必要はありません。抜歯に時間がかかり、傷が大きく、抜歯後に激しい痛みがある場合は、抗炎症剤を3日間経口摂取することができます。かかりつけの病院に行き、医師に薬を処方してもらってください。 抜歯後に薬を飲む必要はありません 影響を受けた歯が感染しておらず、抜歯のプロセスが比較的簡単な場合は、抜歯後に薬を投与する必要はありません。通常、歯の出血は2時間後に止まり、腫れや痛みは3~5日以内に徐々に治まります。 抜歯後に薬を服用する必要がある場合 患歯がすでに炎症を起こしている場合、抜歯に時間がかかり、外傷が重く、出血が多い場合は、手術後の感染や腫れなどの不快感を軽減するために、抗生物質やグルココルチコイドなどの薬剤を使用する必要があります。抜歯後は、局所的な腫れを抑えるために頬にアイスパックを当てることも必要です。 3. 親知らずを抜くのに最適な時期はいつですか? ほとんどの専門家は、埋伏智歯を抜く最適な時期は20歳前後であることに同意しています。この時期は、歯冠周囲炎がピークに達しておらず、隣在歯に長期間食物が蓄積されておらず、隣在歯の遠心う蝕や歯間骨の吸収はほとんど発生しません。この時期の親知らずの歯周スペースは広く、周囲の骨は緩んでおり、抜歯に対する抵抗は少なくなります。実際の臨床では、25~40歳の患者様の親知らずの抜歯が多く見られます。この時期は、隣在歯の歯冠周囲炎や歯髄炎のピーク時期です。埋伏智歯は、隣在歯の遠心う蝕や隣在歯間の骨吸収が過剰であることなどから抜歯されることが多いのですが、隣在歯に修復不可能なダメージを与えてしまっています。そのため、20歳前後の患者様は、保定に適さないものは予防的に抜歯することが推奨されています。 |
>>: 掻爬術後に抗炎症薬を服用して胃に不快感を覚えた場合はどうすればいいですか?
推薦する
冬蜂蜜の効果と働きは何ですか?
冬蜂蜜は冬に採れる蜂蜜です。冬は花が咲く植物が少ないため、冬に採れる蜂蜜は一般的に値段が高く、品質も...
女性が突然この異常を示したら、彼女は病気に違いありません!
強い男性に比べて、女性は身体の健康にもっと気を配る必要があります。では、どんな症状が病気の兆候なのか...
大腸炎の治療
大腸炎はよくある病気です。大腸炎の治療は比較的長く、治療中に再発しやすいため、治療は簡単ではないこと...
手首の靭帯の捻挫の症状
靭帯は2つの骨をつなぐ組織です。手首の靭帯が捻挫すると、手の動きに影響を及ぼし、激しい痛みを引き起こ...
心膜切除術
心膜切除術は、収縮性心膜炎の治療によく用いられる方法であり、最も効果的な治療法でもあります。まず、患...
お腹が冷える
胃の冷えの問題は無視してはいけません。胃の冷えは、胃の冷えや胃内の他の臓器の病変によって引き起こされ...
6種類の貧血は輸血で治療できる
貧血の場合、症状を緩和するために医師が輸血を行うことがあります。輸血は貧血患者の症状を速やかに緩和し...
松葉は血糖値を下げることができますか?
松葉とは、一年中採取できる松の葉のことを指します。旧暦の12月に採取した松葉には最高の薬効があります...
冬は関節炎に注意
関節炎は環境や気候によって発症する可能性があり、発症すると身体に非常に不快な症状が現れるため、非常に...
気血虚の症状は何ですか?
日常生活で、顔色が青白かったり、濃い黄色の人を見かけると、その人の顔色は非常に悪く、何らかの病気にか...
全部水だ
便は人体のバロメーターでもあります。便の形や色は、その人の食習慣や胃腸の健康状態を効果的に反映します...
上顎洞滲出液の原因は何ですか?
上顎洞滲出液は、人体の上顎領域でより一般的に発生する病気です。この病気の原因は多数ありますが、そのほ...
高位対麻痺とはどういう意味ですか?また、症状は何ですか?
いわゆる高位対麻痺とは、胸椎第二位より上に生じる対麻痺を指します。この病気に罹患した患者は、感覚障害...
月経不順で早く妊娠する方法
女性の身体が成熟すると、毎月卵子が体内で生成され、男性の精子と結合するのを待ちます。卵子と精子が結合...
サボテンの花の薬効は何ですか?
サボテンの外側はトゲで覆われていますが、内側は柔らかいです。サボテンを見たことがある人は多いですが、...