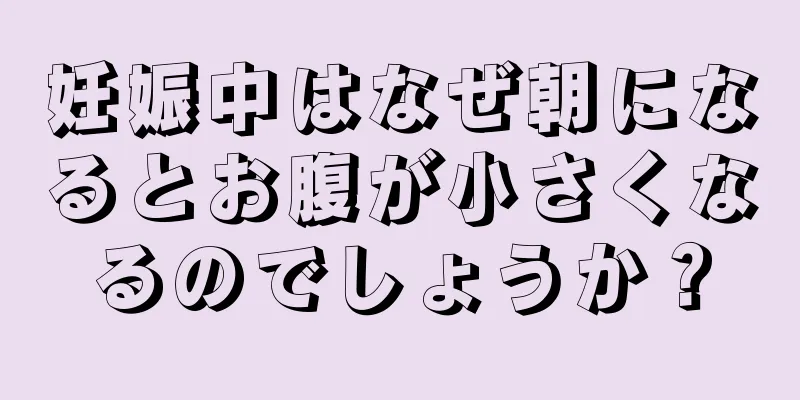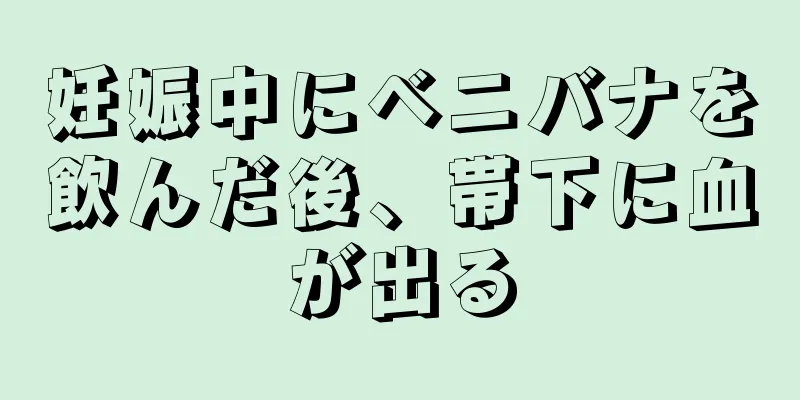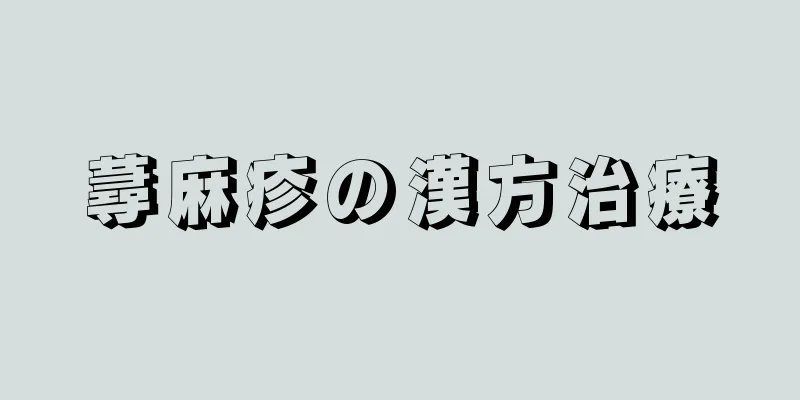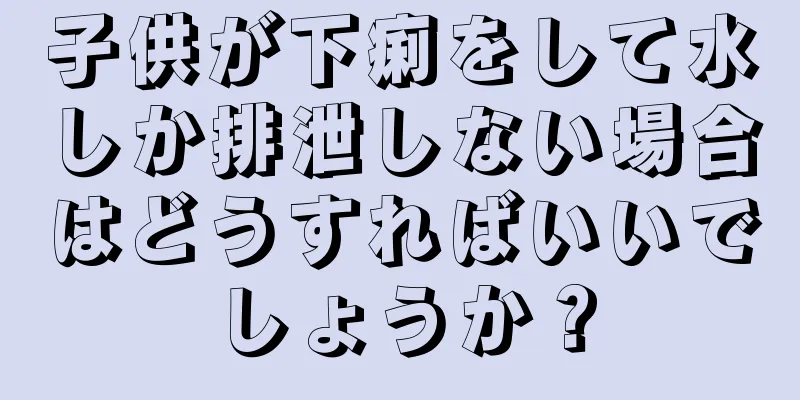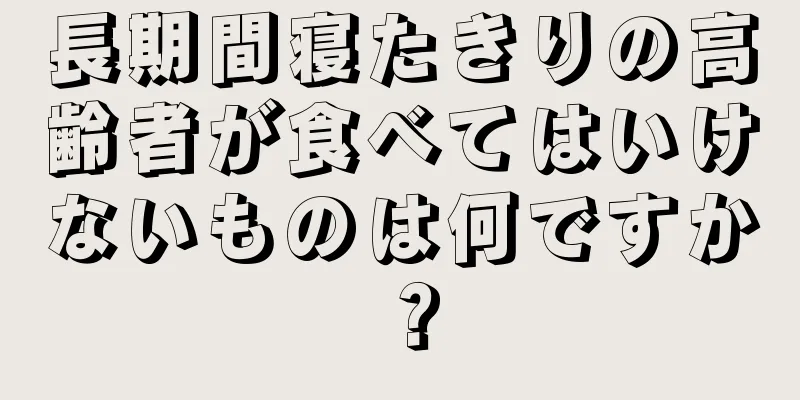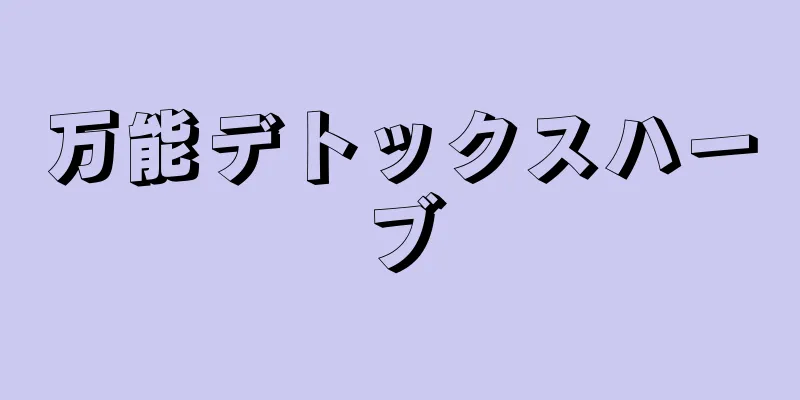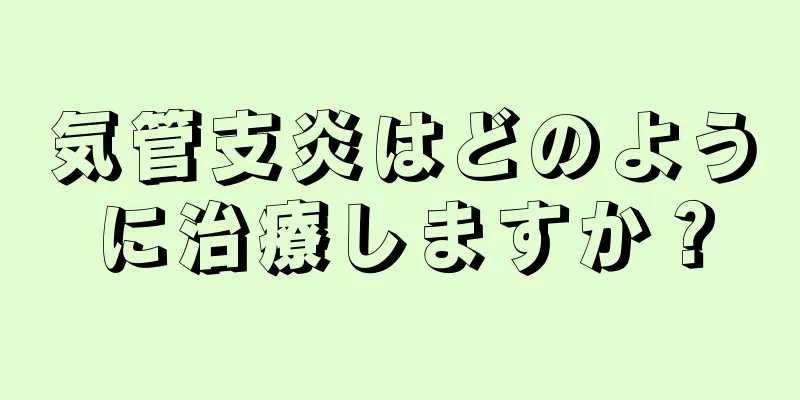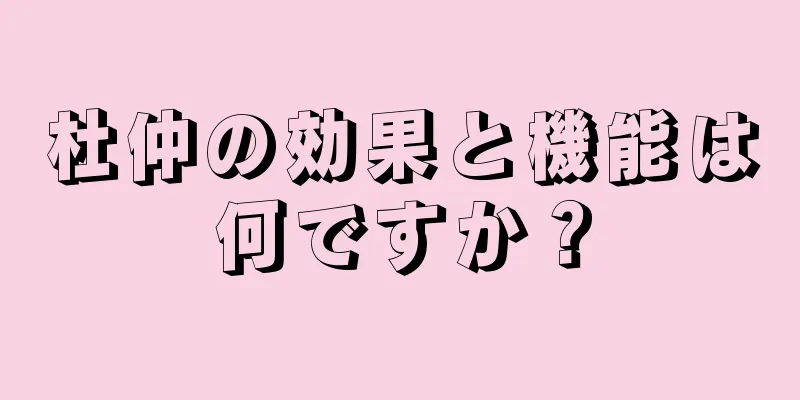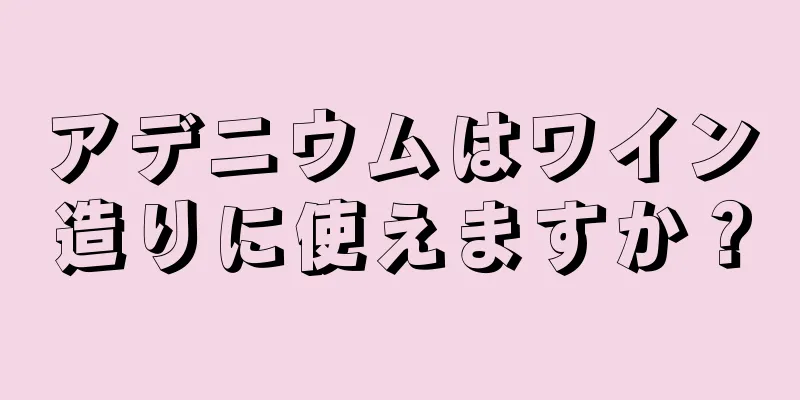伝統的な中国薬である黄耆と黄耆は同じものですか?
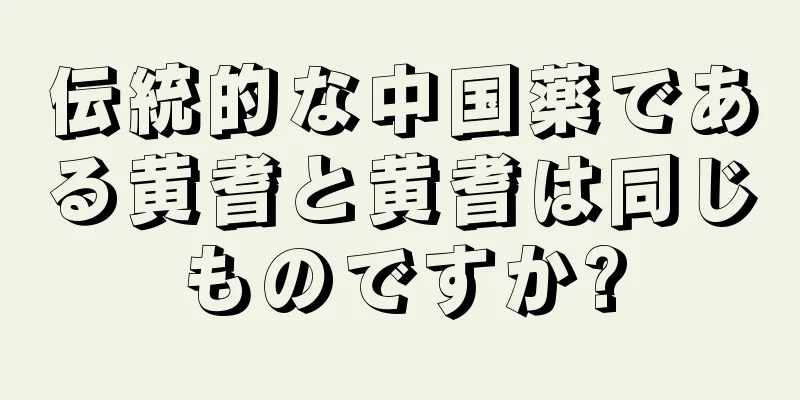
|
黄耆と北耆はどちらも生薬であり、どちらも煎じて飲む薬の一種ですが、本質的には異なります。私たちの多くは、黄耆と北耆の違いは何かと尋ねるかもしれません。摂取する際にはどのような点に注意すべきでしょうか。多くの疑問が頭に浮かぶでしょう。編集者は、黄耆と北耆の違いについて皆さんにお伝えします。皆さんが自分に合った薬を選ぶことができるように。 黄耆は日常生活でよく使われる補気薬で、次のような働きがあります:まず、気を補い、陽を高めます。気虚による直腸脱、子宮脱、不正出血、めまい、倦怠感などに用いられ、サラシミツロウやミズキなどと併用されることが多い。 2つ目は、外側を強化して汗を抑えることです。主に体力の低下による自発的な発汗に使用されます。外気がしっかりしておらず、風寒と発汗に悩まされている場合は、黄耆に大芎、芎を合わせて治療します。長期間服用すると効果があります。 3つ目は、傷口を支えて膿を排出することです。長期間潰瘍化せず内側に陥没した傷に用い、潰瘍化を促進し、その局在を制限する効果があります。長期間治癒しない潰瘍の治療に用いられ、組織の再生と治癒を促進する効果があります。スイカズラ、ムクロジ、オオバコなどと組み合わせて使用されることが多いです。 4番目に、利尿作用と腫脹抑制作用があります。陽気不足による無力性浮腫に用いられ、芍薬、枸杞子、白朮などと併用されることが多い。 まとめると、高麗人参と黄耆の効能は似て非なるものなので、気虚の場合には併用しないでください。併用すると、症状が悪化する可能性があります。 北耆は、東北黄耆とも呼ばれ、膜莢黄耆とも呼ばれています。北耆は、中国北部で豊富に生産されるため、北耆と名付けられました。主に吉林省の長白山地域の県で生産されています。黄耆はマメ科の多年生草本植物です。主根は深く長く、棒状です。茎は直立し、上部に多数の枝があります。葉は羽状複葉で、小葉は卵形から披針形です。茎と葉の両方に白い軟毛があります。花序は対生し、小さな淡黄色の蝶形の花をつけます。鞘は膜状で、晩秋に開花します。 7月~8月、結実期は8月~9月。アストラガルスは涼しく乾燥した気候を好み、排水性が良く土壌層が深い砂質土壌を好みます。主に標高800~1300mの高地で栽培されます。 標高100〜200メートルの日当たりの良い丘陵の斜面または茂みの端。黄耆の根は強壮薬であり、『神農本草経』に初めて記載され、最高級の薬として挙げられています。李時珍は『本草綱目』でこれを「最高の強壮薬」と評しており、黄耆が強壮薬として長い歴史を持っていることがわかります。 編集者は黄耆と北耆の違いをまとめました。それぞれの薬効に関する情報を調べ、自分の体調に合わせて摂取する必要があります。そうしないと、体に良い効果は得られません。一般的に言えば、この2つの薬の効果は異なるので、自分の体に不足している薬を自分で見つける必要があります。 |
>>: Glechoma longitubaの薬効は何ですか?
推薦する
なぜ私の子供はいつも吐き気を催すのでしょうか?
吐き気や嘔吐という現象を経験したことがある人は多いと思います。吐き気や嘔吐を引き起こす原因はさまざま...
中絶薬を服用する際の注意事項
多くの少女たちは、自分が妊娠していることを知ると、それほど苦労せずに薬を使って中絶することを簡単に考...
動脈瘤はどのように形成されるのでしょうか?
動脈は人体の生命の通路であり、体に必要な栄養素や血液を絶えず運んでいます。動脈が破裂したり弱くなった...
腰椎椎間板ヘルニアのせいで腰が曲げられない?
腰椎椎間板ヘルニアの患者は、健康にもっと注意を払う必要があります。直接前屈みにならないようにするのが...
ゴールデンチェリーミートの効能と機能を知ってください
ゴールデンチェリーは、別名ロクスバーグイとも呼ばれ、江西省原産で、南部地域でよく見られます。ゴールデ...
パーキンソン病は遺伝性ですか?早めに詳しく知りましょう
パーキンソン病は遺伝性があるとはいえ、遺伝との関連は特にはっきりしていません。そのため、この病気にか...
よもぎ足湯の効能と機能
わが国では、ヨモギは長い歴史を持つ漢方薬として広く利用されています。民間文化では、人々はヨモギを病気...
私たちはなぜ汗をかくのでしょうか?
身体の発汗は生活の中でよく見られます。身体の発汗は、身体の虚弱によって起こることが多く、最も一般的な...
茶色い分泌物が出るまでどのくらいかかりますか?
妊婦の出産時期は、把握しにくい時期です。出産予定日があっても、予測が難しいこともあります。しかし、出...
肋骨骨折の症状は何ですか?
肋骨骨折の場合、患者自身が実際に強く感じ、つまり胸部に激しい痛みが生じます。手足を激しく動かしたり、...
髪が黄色くなる原因は何ですか?
髪が乾燥して黄色くなるのは、体質のせいかもしれません。特に酸性体質の人は、髪が乾燥して黄色くなる可能...
臓器の解毒に最適な6つの時間帯!
体内の毒素を排出する最良の方法は、日常生活で良い生活習慣を維持し、いくつかのヒントを活用する方法を知...
喉が痛いときは何を飲めばいいですか?
喉は人体で最も重要な組織です。喉は人が話したりコミュニケーションをとったりするのに使う道具です。喉の...
腰椎椎間板ヘルニアの原因は多くの要因によって引き起こされます。
腰椎椎間板ヘルニアは、現在では中高年に多く見られ、近年では若年化が進んでいます。腰椎椎間板ヘルニアに...
耳鍼パッチの機能は何ですか?
耳鍼パッチは一種の医薬品で、外傷など人体の多くの病気の治療に使用できます。耳鍼は鎮痛や抗炎症など、他...