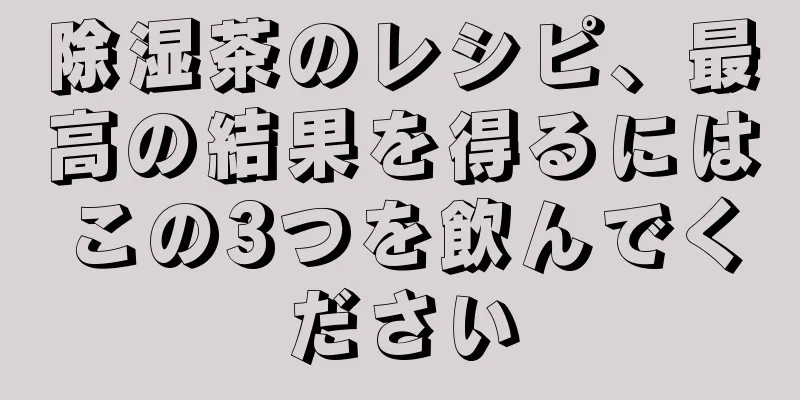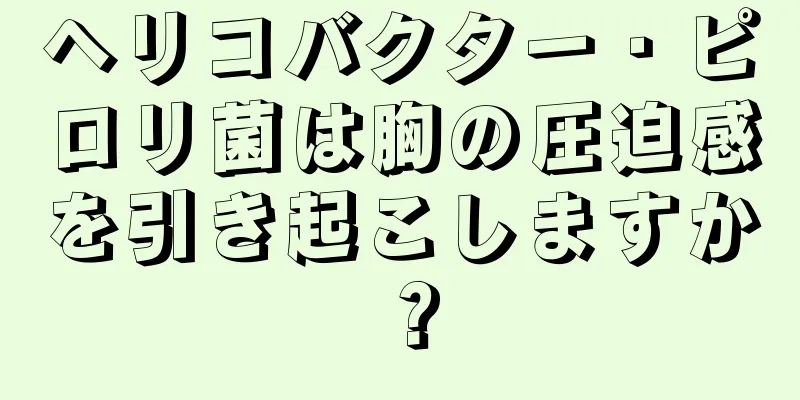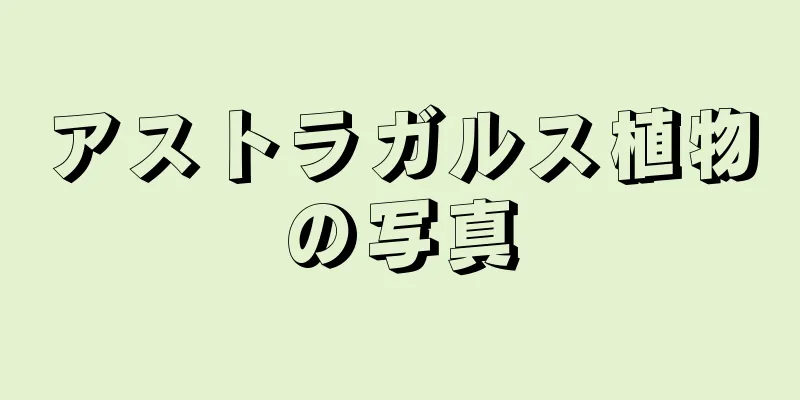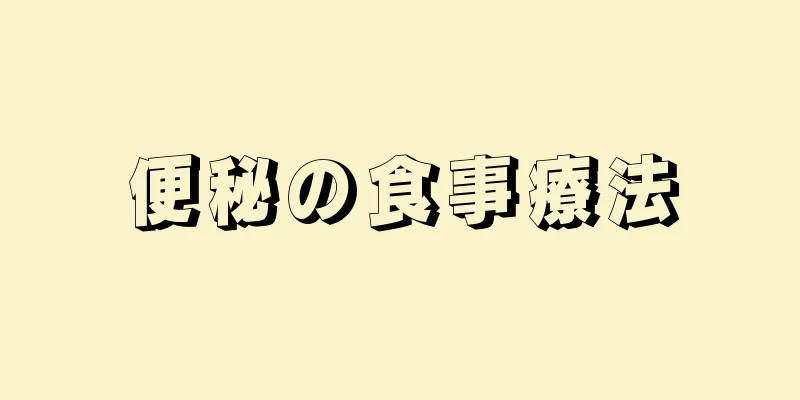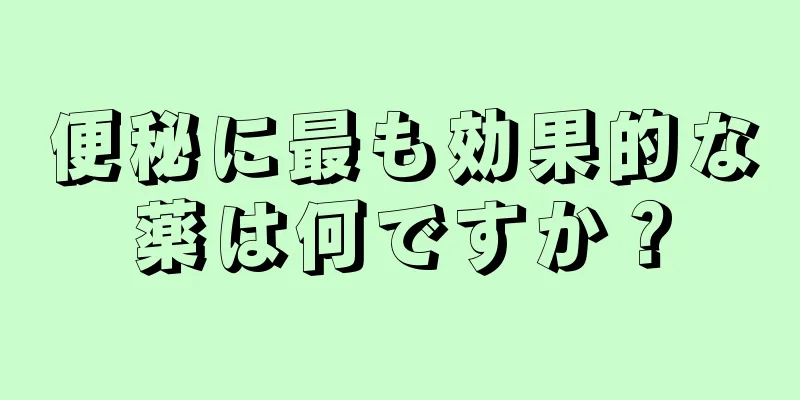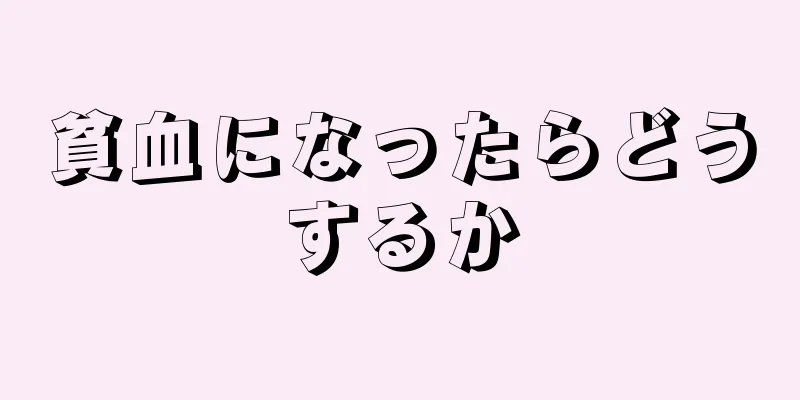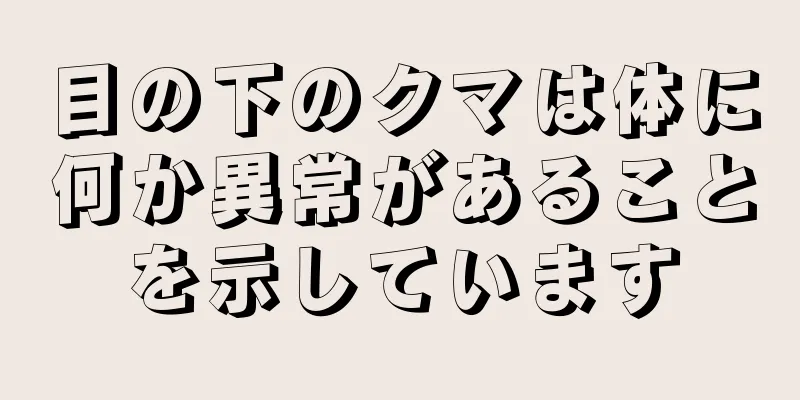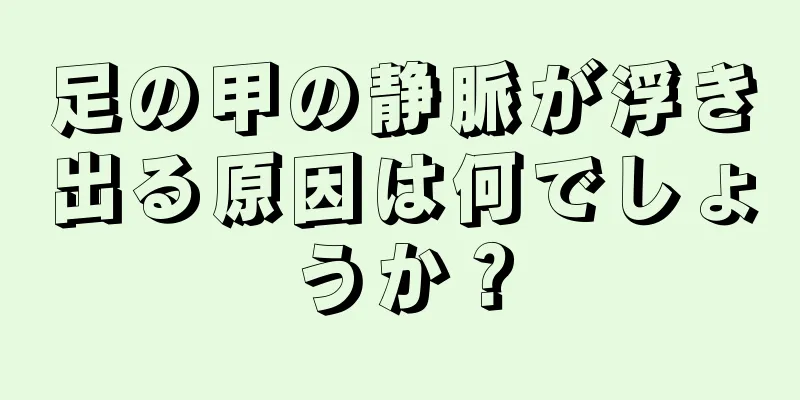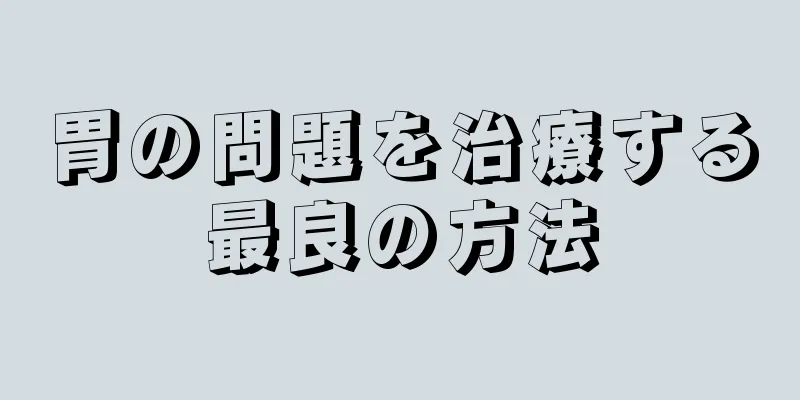慢性痛風の治療方法と日々の食事に注意する方法
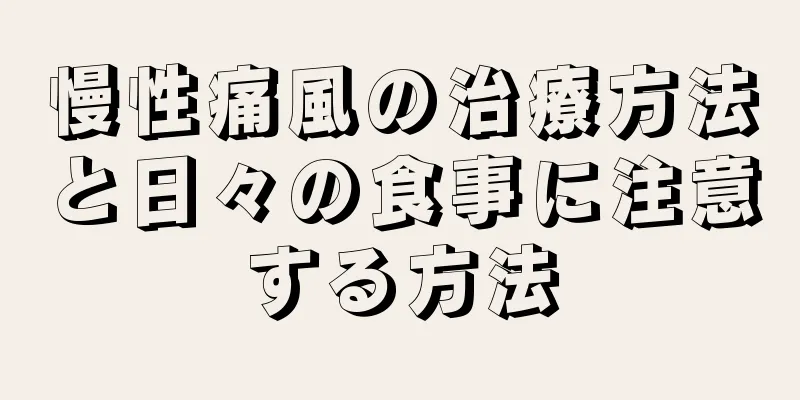
|
閉経後の女性や中年の男性は、関節の赤み、痛み、腫れ、熱感などの症状を経験することが多く、これらは痛風の症状です。痛風は再発を繰り返し、時間が経つと関節の変形や関節機能障害を引き起こす可能性があるため、人体に大きな影響を与えます。 1: 慢性痛風の治療方法1: 1日の総エネルギー摂取量を制限し、炭水化物の摂取を減らします。安静時の理想体重に基づいて計算すると、通常は1日あたり25~30kcal/kgを超えません。 ②三大栄養素がバランスよく配合されています。総カロリーを制限するという前提の下で、配分原則は、高炭水化物、中程度のタンパク質、低脂肪です。その中には、野菜や果物を含む炭水化物が総カロリーの 65 ~ 70% を占める必要があります。タンパク質:総カロリーの11~15%を占める必要があります。標準体重に対するタンパク質供給量は0.8~1.0g/kgで、主に植物性タンパク質です。動物性タンパク質は牛乳とその製品、卵タンパク質から選択でき、肉、鶏肉、魚は使用しないようにしてください。脂肪: 通常1日40~50g、動物性脂肪と植物性脂肪の比率は1:1.5です。 2: タンパク質の摂取を制限し、プリン体の少ない牛乳、チーズ、脱脂粉乳、卵を多く選びましょう。さらに、ショ糖や蜂蜜は果糖が多く含まれており、尿酸の生成を促進するので、摂取量を減らしてください。野菜の中でも、若いレンズ豆、インゲン豆、新鮮なエンドウ豆にはプリン体の含有量が多いため、摂取量も制限する必要があります。 3: プリンの摂取を制限する。プリンは細胞核の成分です。細胞を含む食品にはすべてプリンが含まれており、動物性食品にはより多くのプリンが含まれています。動物の内臓、エビやカニ、濃厚なスープ、食用キノコ、海藻、アンチョビ、イワシ、ハマグリ、豆、ビールなど、プリンを多く含む食品の摂取は避けるか控えてください。 4: 野菜、ジャガイモ、果物など、血液や尿の酸性度を下げるアルカリ性の食品を多く食べましょう。スイカや冬瓜はアルカリ性食品であるだけでなく、利尿作用もあるため、痛風患者にとってより有益です。 5: アルコールの摂取は避けてください。アルコールには尿酸の排泄を阻害する作用があります。少量のアルコールを長期間摂取すると、プリン体の合成増加を刺激することもあります。特に飲酒中に肉や鶏肉を食べると、プリン体の摂取量は2倍になります。 6:唐辛子、カレー、コショウ、花椒、マスタード、ショウガなどの香辛料は、自律神経を刺激して痛風発作を引き起こす可能性があるため、できるだけ摂取を控えるべきです。 2:医師の指導のもと、尿量を減らす薬を使用することができます生成物は代謝され、尿中に排泄されます。特に、血液と尿の pH 値を高め、関節や軟部組織に沈着した尿酸結晶を中和、溶解、排泄します。急性発作時には、厳格な低プリン食が採用されます。慢性寛解期には、急性発作期の食事療法を週 2 日間実施し、残りの 5 日間はプリン含有量の多い食品を避け、プリンを控えた食事療法を実施することが推奨されます。 |
推薦する
凍傷後、指が黒くなって乾燥しているが炎症がない場合は、切断する必要がありますか?
凍傷は寒い天候で起こりやすくなります。影響を受ける体の部位は通常、手足です。手足は人間の道具であり、...
再発性口腔潰瘍の原因
最近では人々の食生活も多様化しており、食べたいものの多くは階下でも見つかります。昔は、鍋やバーベキュ...
高尿酸血症の原因
高尿酸血症は、臨床的にはあまり一般的ではない症状です。その病因は主に体内のプリン代謝の障害によるもの...
子供の腹部膨満を治す最も早い方法は何ですか?
赤ちゃんがお腹が張るのは、人生でよくある現象です。実は、お腹が張るのは主に消化不良が原因です。一般的...
水に浸した冬虫夏草を飲むことの効能
冬虫夏草は比較的貴重な漢方薬で、定期的に摂取すると、体調を整え、免疫力を高める効果があります。一般の...
痛風に効くニンジン
にんじんは私たちの生活に欠かせない野菜です。シャキシャキとした食感と味が特徴で、カロチン、ビタミン、...
ヘリコバクター・ピロリの正常レベルはどのくらいですか?
ヘリコバクター・ピロリ菌は胃や十二指腸のさまざまな場所に生息しています。胃粘膜に軽い慢性炎症を引き起...
洞性徐脈の治療方法
心拍数が遅い人は、弱って無力なことが多く、虚弱に見え、刺激を与えることができず、心臓病を発症する可能...
麻酔後どれくらいで出産できますか?
出産可能年齢の女性の場合、特定の病気の治療時に麻酔が必要な場合、たとえば抜歯など、麻酔治療が必要にな...
睡眠中に口が乾く原因は何ですか?
最も良い睡眠状態は夜明けまで眠ることです。夜中に突然目が覚めてしまうと、睡眠の質は大きく低下してしま...
内痔核の最良の治療法
痔は肛門の周囲によく起こる病気で、大部分は便秘が原因です。多くの患者がこの病気によって苦しみ、悲惨な...
胃腸の病気が半年も治らないのですがどうすればいいですか?
消化器疾患は慢性疾患であることが多く、一度発病すると長期にわたって悩まされることになります。胃腸疾患...
洞性不整脈は突然死を引き起こしますか?
日常生活の中で不整脈に悩まされたことがある人は多いでしょう。一般的に、この種の病気の場合、適切な治療...
腫瘍を抑制するためにハトムギの種子を食べる方法
多くの人は日常生活でトウモロコシを食べる習慣があり、ヨクイニン自体は一種の漢方薬であり、体を養うだけ...
肺性心
人生において、肺性心症を患う高齢者は少なくありません。特に近年、中国では高齢化が加速しており、わが国...