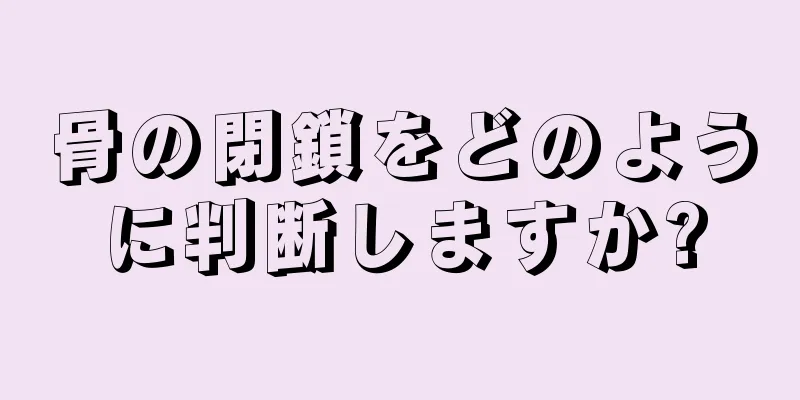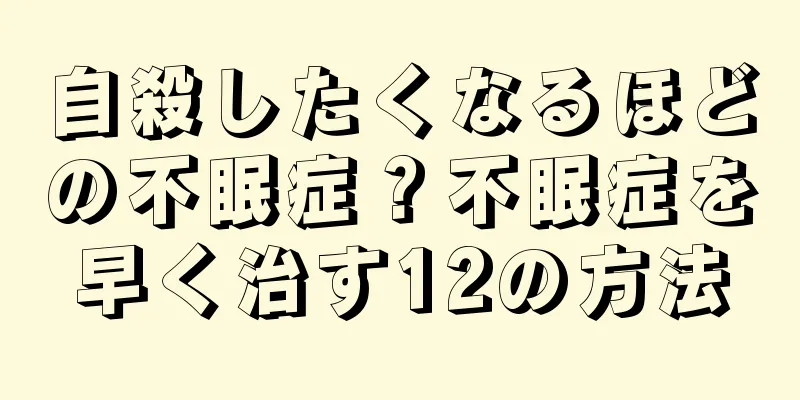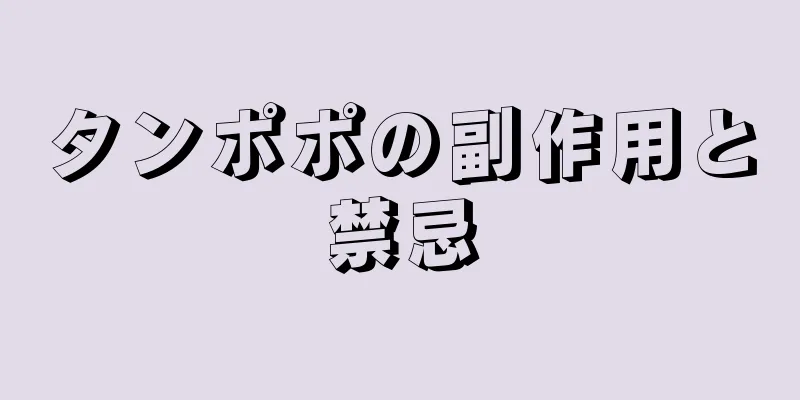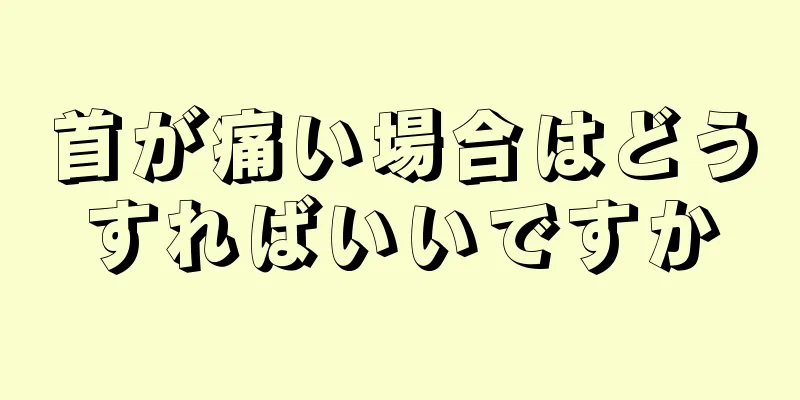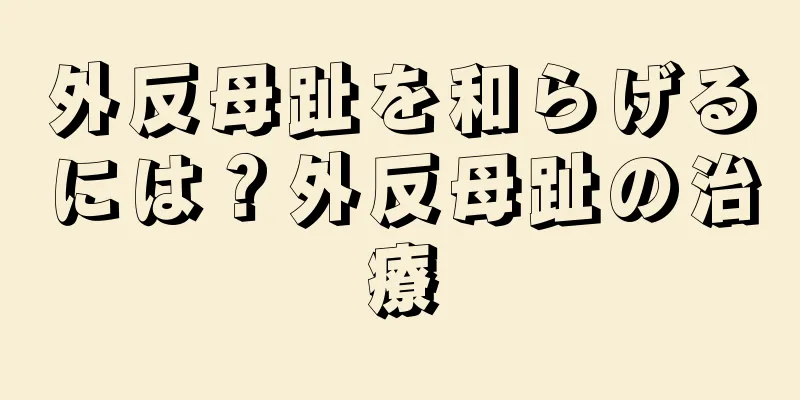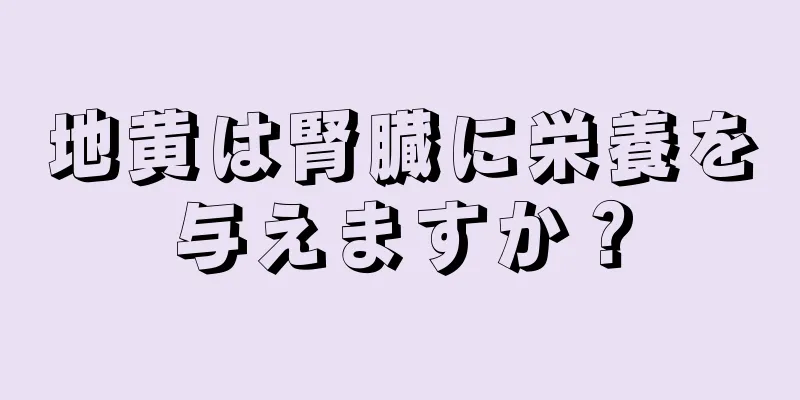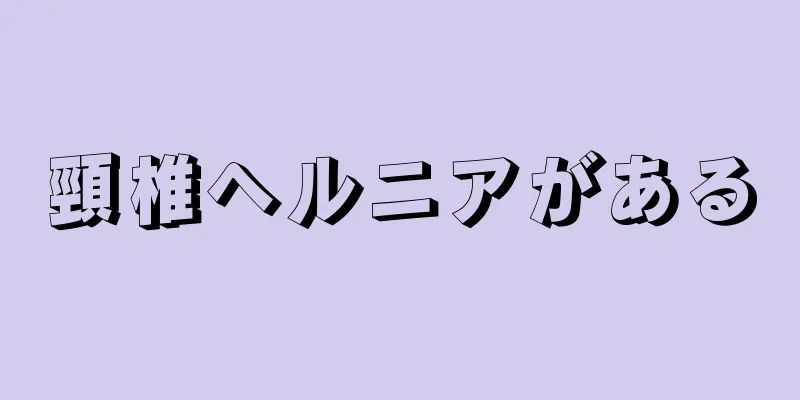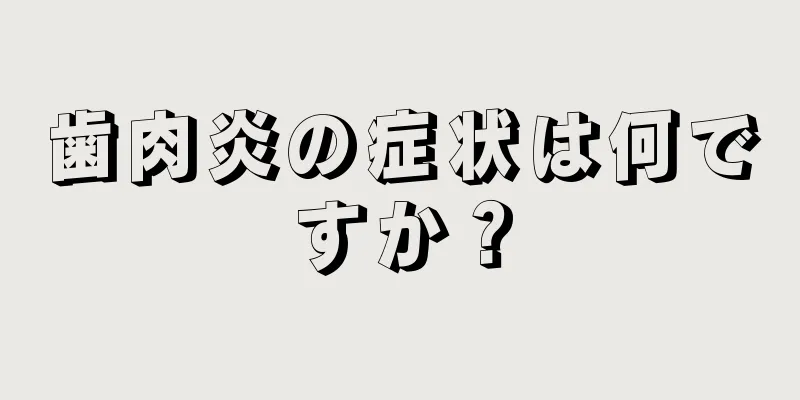寝ているときにお腹が張る場合はどうすればいいですか?
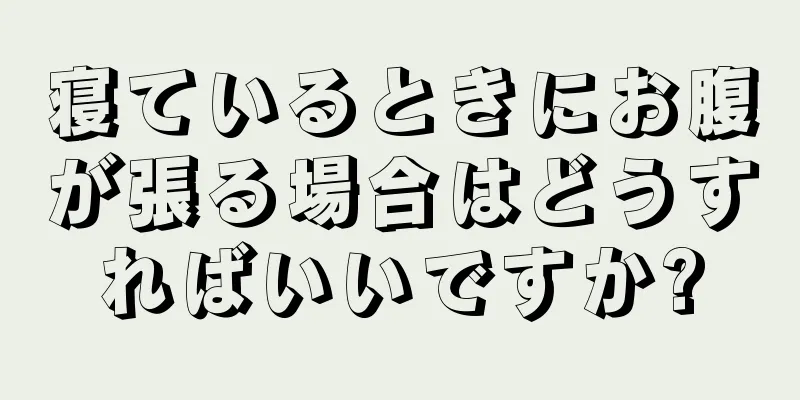
|
就寝時にひどい膨満感を感じる人は多いです。これは、夕食に食べ過ぎたり、合理的な食事パターンをとらなかったりして膨満感が生じるためです。したがって、バランスの取れた栄養を摂取するよう最善を尽くしてください。夕食では、消化しにくいものや膨満感を引き起こすものを食べないでください。合理的な食習慣を身につけ、適切な腹部マッサージを行って、胃腸の運動性を高め、膨満感を軽減してください。 一般的に腹部膨満は腹部の膨満感を伴います。腹部膨満が上腹部に限局する場合は、胃や横行結腸にガスが溜まっている場合が多いです。小腸ガスによる腹部膨満は中腹部または腹部全体に限局する場合があります。結腸ガスによる腹部膨満は下腹部または左下腹部に限局する場合があります。幽門閉塞の場合は、上腹部に胃の形態や蠕動波がみられることがあります。腸閉塞の場合は、腸の形態や蠕動波がみられ、腸音が亢進または弱くなることがあります。腹膜炎患者では圧痛や筋緊張がみられることがあります。 ガスが出そうになったら、我慢しないでください。一時的に人混みを避けることはできますが、胃腸の圧力を緩和するためにガスを放出する必要があります。 腹部の膨満感を解消するのが難しい場合は、へその周囲にペパーミントオイルを塗って腹部の膨満感を解消することができます。 ガスや膨満感を和らげるためにミントティーや柑橘類のお茶を飲みましょう。 1. 消化しにくい食べ物を食べない 揚げ豆や固いパンケーキなどの硬い食べ物は消化されにくく、胃腸管内に長時間留まるため、ガスが発生しやすくなり、膨満感を引き起こす可能性があります。 2. 食物繊維の多い食品を控える ジャガイモ、パスタ、豆、キャベツ、カリフラワー、玉ねぎなどの食品は、胃や腸でガスを発生させやすく、最終的には腹部の膨張につながります。 ジャガイモは胃や腸内でガスを発生させやすく、最終的には膨満感につながります。 3. 早食いの習慣を変える 食べるのが速すぎたり、歩きながら食べたりすると、大量の空気を飲み込んでしまう可能性があります。また、ストローで頻繁に飲み物を飲むと、大量の空気が胃に入り、膨満感を引き起こす可能性があります。 4. ネガティブな感情を克服する 不安、心配、悲しみ、欲求不満、憂鬱などの否定的な感情は、消化機能を弱めたり、胃を刺激して胃酸を過剰に分泌させ、胃ガスの増加や腹部膨満感の増加を引き起こす可能性があります。 5. 食物繊維を適度に補給する 高繊維食品は膨満感を引き起こすだけではありません。逆に、高脂肪食品を摂取した後の膨満感を軽減できる場合もあります。その理由は、脂肪分の多い食べ物は消化吸収されにくいため、胃や腸に長く留まる傾向があるからです。食物繊維を加えると、詰まった消化器官がすぐに解放される可能性が高くなります。 6. 適切な運動をする 毎日1時間程度適度に運動すると、ネガティブな感情を克服できるだけでなく、消化器系の正常な機能を維持するのにも役立ちます。 7. 特定の病気に注意する アレルギー性腸炎、潰瘍性大腸炎、膀胱腫瘍など、一部の病気では、腹部膨満は前兆、または症状の 1 つです。 |
推薦する
高熱とけいれん
風邪や発熱は非常によくある現象です。誰もが人生でこれを経験します。ただ、人によってはすぐに良くなる一...
月経中に血の塊が出る原因は何ですか?
女性にとって不便な日が月に数日あります。月経は、すべての女性にとって本当に苦痛です。子宮内膜は、ほぼ...
羊の潰瘍の迅速な治療
口内炎は口内炎ウイルスによって引き起こされる病気で、春と秋によく発生する急性感染症です。主に接触感染...
冬虫夏草は1ポンドあたりいくらですか
冬虫夏草の価格は現時点では比較的高価です。良質の冬虫夏草の価格は1グラムあたり約200元、1キログラ...
口内炎の治療方法
病気には多くの種類があります。病気の治療においては、方法の選択が非常に重要です。多くの人は、病気の治...
新生児の体重を早く増やす方法
親は新生児の体重に細心の注意を払っており、1~2週間ごとに子供の体重を測ります。なぜなら、体重は子供...
陰部の白い斑点は絞り出してもいいですか?
ニキビに悩まされている方は多いですよね。厄介なニキビはかゆみだけでなく、肌の美しさにも影響を及ぼしま...
静脈瘤に効くサプリメント
静脈瘤の治療後は、食生活を強化する必要があります。そうすることで治療効果を高めることができます。食生...
胃が痛くて薬がない場合はどうすればいいですか?
胃痛は誰もが経験したことがあると思います。不適切な食生活が原因で胃の不調に悩まされている人は多くいま...
デンドロビウムティーを定期的に飲むと、このような効果が得られます
デンドロビウム茶は比較的健康的な食べ方です。デンドロビウムを洗った後、沸騰したお湯に浸してそのまま飲...
早く排尿するために何を食べるべきか
排尿は、人体が余分な水分や不要な代謝産物を排泄するために行う行為です。この行為は人体にとって比較的良...
脳挫傷から回復するにはどのくらい時間がかかりますか?
頭痛、脳梗塞、脳挫傷などの頭部疾患に悩まされる人は多いです。脳挫傷は頭部への外部からの衝撃によって引...
喉が痛いときに牛乳を飲んでも大丈夫ですか?
牛乳は栄養価が高く、カルシウムやタンパク質が豊富で、睡眠にも役立ちます。そして牛乳は子供、高齢者、女...
お灸は血熱の治療に使えますか?
血熱は比較的よく見られる症状です。血熱はいくつかの悪影響を示します。血熱のある患者は、いらいらしたり...
外傷性足首関節炎
足首は足と下肢をつなぐ関節です。足首は構造が単純ですが、非常に怪我をしやすい部位でもあります。また、...