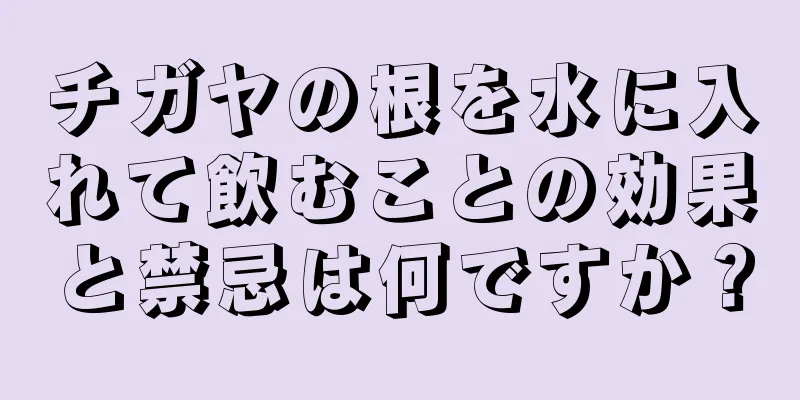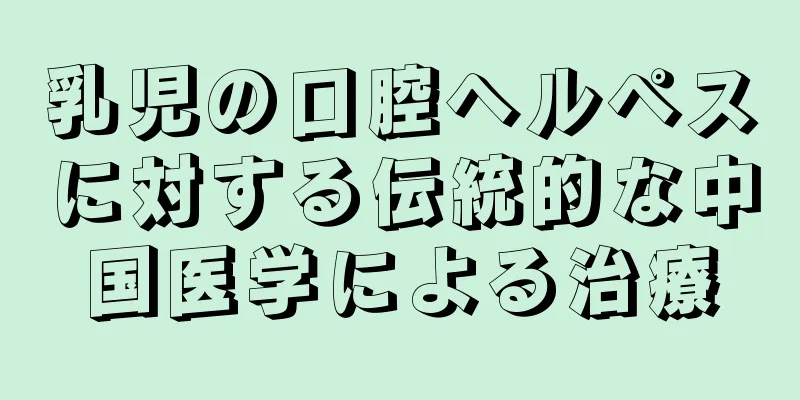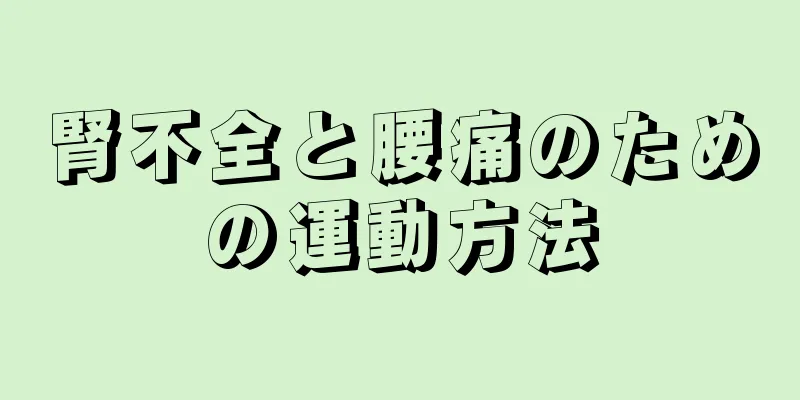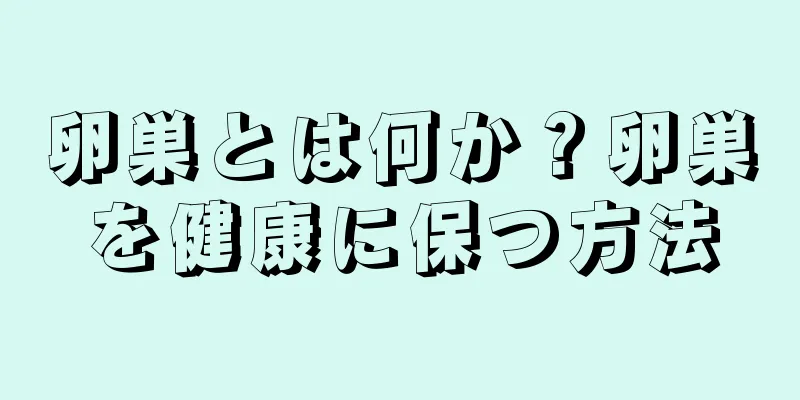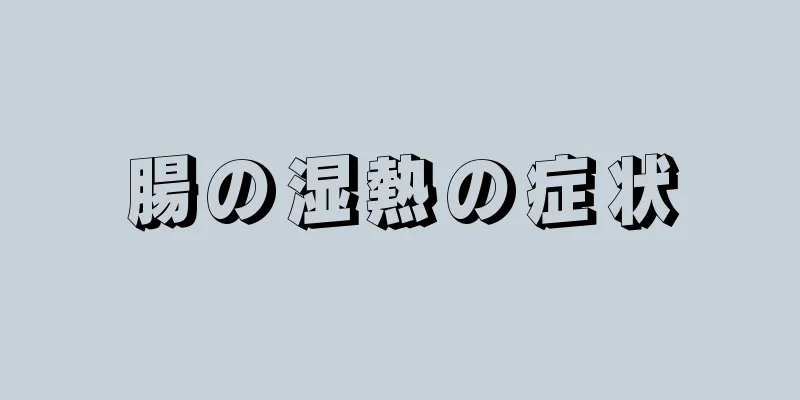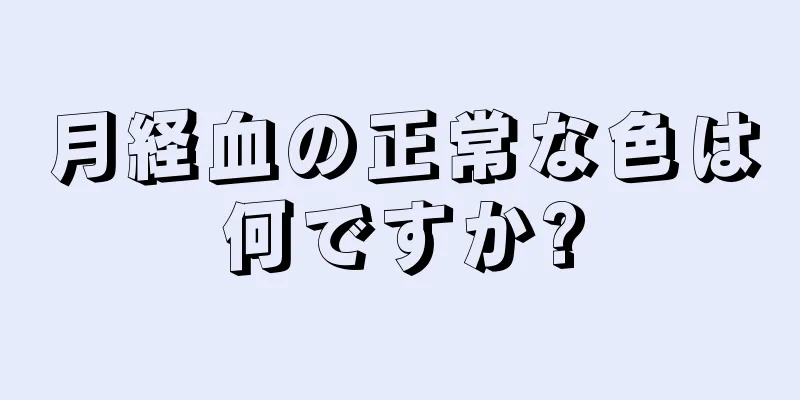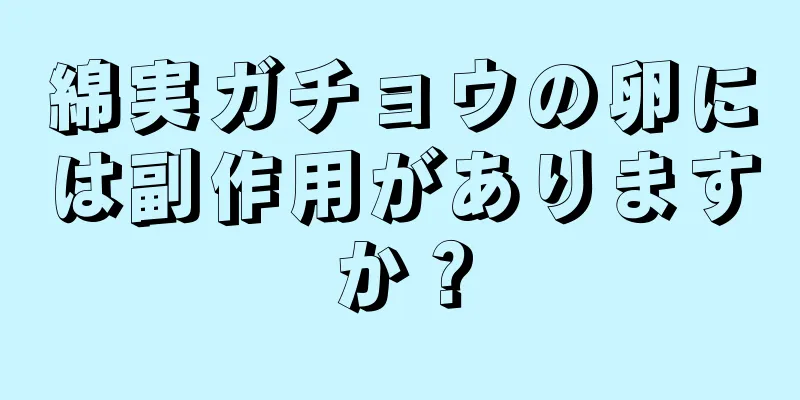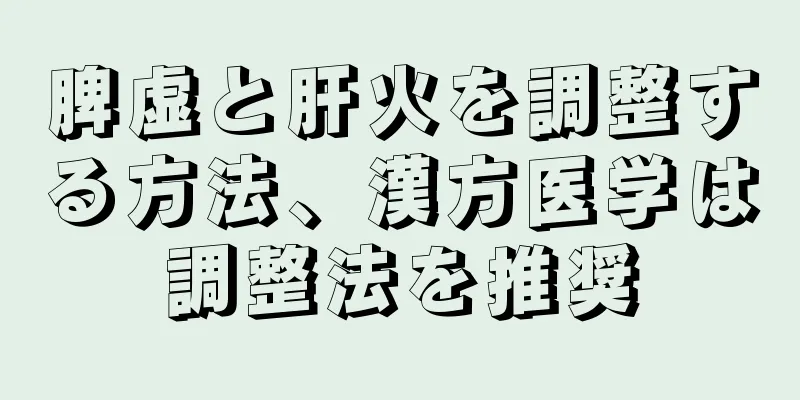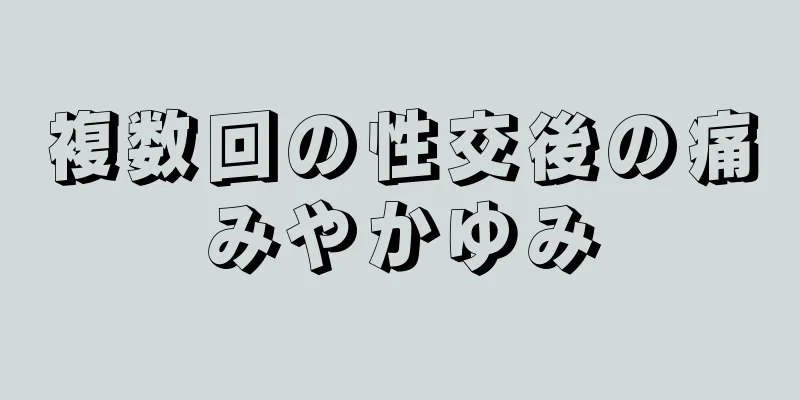くも膜下出血
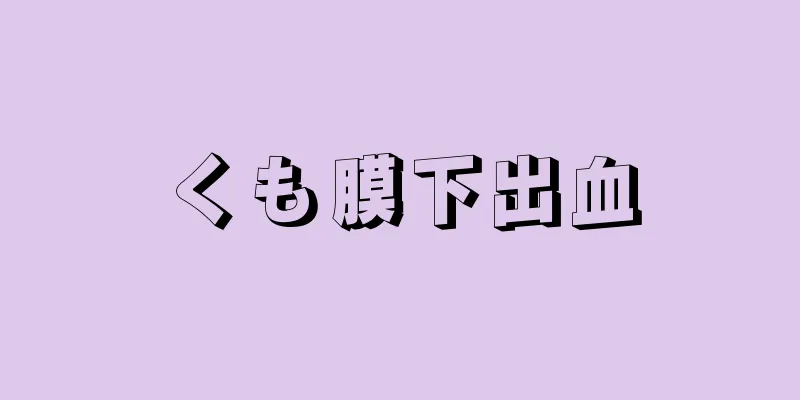
|
くも膜下出血について、これまでにお話しされたことがあるでしょうか。今日は、この病気がなぜ起こるのかを簡単にご紹介します。この記事を読んでいただければ、より理解が深まると思います。今後の人生で、そのような状況に直面したとき、あなたは容易に対処し、冷静さを保つことができるでしょう。 専門家が特別な研究を行った結果、喫煙と飲酒はくも膜下出血と密接な関係があることが判明しました。その中で、喫煙は血圧を上昇させ、脳血管の脆弱性を高め、血管破裂や出血のリスクを高める可能性があります。また、多量のアルコールの摂取も血圧を上昇させ、くも膜下出血を加速させる可能性があります。 くも膜下出血はあらゆる年齢層の人に起こり得ますが、若年層と中年層の人に多く見られます。感情的に興奮したり、力を加えたりしたときに急性に起こることが多く、患者によっては再発性の頭痛の病歴がある場合もあります。 1. 頭痛と嘔吐 突然の激しい頭痛、嘔吐、顔面蒼白、全身に冷や汗。頭痛が特定の領域に局在する場合、局在性の意味があります。たとえば、前方頭痛はテント上痛と大脳半球(片側痛)を示し、後方頭痛は後頭蓋底の病変を示します。 2. 意識障害および精神症状 ほとんどの患者は意識障害はありませんが、イライラすることがあります。重篤な患者は、せん妄、さまざまな程度の意識喪失、さらには昏睡を経験する場合があります。少数の患者は、てんかん発作や精神症状を経験する場合もあります。 3. 髄膜刺激症状 若年および中年の患者によく見られ、首や背中の痛みを伴います。高齢患者、出血の初期段階にある患者、または深い昏睡状態の患者では、髄膜刺激の兆候が現れない場合があります。 4. その他の臨床症状 微熱、腰痛、足の痛みなど。軽度の片麻痺、視覚障害、脳神経 III、V、VI、VII の麻痺、網膜出血、乳頭浮腫も見られることがあります。さらに、上部消化管出血や呼吸器感染症を合併することもあります。 5. 臨床検査 (1)定期血液検査、定期尿検査、血糖値。重症くも膜下出血の急性期には、定期血液検査で白血球数の増加、尿糖陽性、尿タンパク質陽性がみられることがあります。急性期の血糖値の上昇はストレス反応によるものです。血糖値の上昇は体の代謝状態を直接反映するだけでなく、病気の重症度も反映します。血糖値が高いほど、ストレス性潰瘍、代謝性アシドーシス、高窒素血症などの合併症の発生率が高くなり、予後も悪くなります。 (2)均一な血性脳脊髄液は、くも膜下出血を診断するための主な指標です。発症直後の腰椎穿刺に注意してください。血液がまだくも膜下腔に入っていないため、脳脊髄液は陰性であることが多いです。患者に明らかな髄膜刺激症状がある場合、または患者が腰椎穿刺を通過してから数時間経過すると、陽性率が大幅に増加します。脳脊髄液は、血栓のない均一な血性内容を示します。くも膜下出血のほとんどの症例では、脳脊髄液圧が上昇し、大部分は 200 ~ 300 mmH2O です。一部の患者では、くも膜下腔を塞ぐ血栓が原因で、脳脊髄液圧が低下することがあります。 脳脊髄液中のタンパク質含有量が増加し、1.0g/dl に達することもあります。タンパク質の増加は出血後 8 ~ 10 日で最大となり、その後徐々に減少します。脳脊髄液中の糖分と塩素含有量は、ほとんどが正常範囲内です。 くも膜下出血後、脳脊髄液中の白血球は、異なる期間に3つの特徴的な進化過程を経ます。①脳脊髄液中の血球反応は、6時間から72時間までは好中球が主で、72時間後には大幅に減少し、1週間後には徐々に消失します。 ② 3~7日目にリンパ単核食細胞反応が現れ、免疫活性化細胞が著しく増加し、赤血球食細胞が出現する。 ③ 3~7日目にヘモジデリン含有食細胞が脳脊髄液中に出現し始め、14~28日目に徐々にピークに達する。 上記の症状があると思われる場合は、早めに病院に行き、治療を受け、全身検査、できれば脳の CT スキャンを受ける必要があります。この病気の発生率はそれほど高くありませんが、突発的な病気であり、突然発症すると命に関わることもあるため、日常生活の中で予防策を講じ、定期的にチェックする必要があります。 |
推薦する
天地黄の効能・効果と禁忌
天地黄は、地耳草とも呼ばれ、漢方薬です。ガルシニア科の地耳草から採取されます。この植物の乾燥した草で...
ヘビの胆嚢を生で食べることの長所と短所
蛇の胆を生で食べると、体に良い効果があります。蛇の胆の胆嚢には、特にコブラ、ブンガルス、キングコブラ...
目の中の膿疱は自然に破裂するのでしょうか?
目から膿が出るのは、たいていの場合、ものもらいが原因です。ものもらいは外麦粒腫と内麦粒腫に分けられま...
下腹部の痛みの原因は何ですか?
腹痛の原因は多岐にわたります。この説明だけに基づいて正確な原因を突き止めるのは非常に困難です。腹痛は...
抗アレルギー漢方薬とは何ですか?
アレルギー体質の人は、人生においてアレルギーに悩まされることが多いです。これは生まれつきのもので、変...
以前は脇の下の臭いはなかったのですが、今は臭います。
以前は脇の下の臭いがなかったのに、今は臭います。これはよくあることです。脇の下の臭いは体臭とも呼ばれ...
心拍数が遅くなる原因
一般的に、心拍数は人それぞれ異なりますが、それは各人の体調に関係しています。心拍数が速い人もいれば、...
帝王切開には何層の縫合が必要か
妊娠中に胎児の位置異常などの問題を経験する妊婦もいますが、帝王切開はこれらの問題を効果的に解決する産...
妊娠初期の手足の冷え
多くの妊婦は初めての妊娠を経験するため、身体に異常な変化があれば注目するでしょう。流産に苦しむ女性の...
紅茶を長期にわたって飲むと腎臓に害がありますか?
紅茶は比較的一般的なお茶です。紅茶を定期的に飲むことは体に良いです。一般的に言えば、腎臓機能に影響を...
睡眠不足に灸をすえる場所
灸は近年登場した新しい健康法で、ツボを刺激して身体の病気を治療する、伝統的な中国医学の範囲内の治療法...
子供が繰り返し嘔吐する理由は何でしょうか?
乳幼児は脾臓や胃の機能が弱いため、腸の蠕動運動が遅く、胃や食道などの発達が未熟です。もちろん、親の不...
妊娠中にクルミを食べるのに最適な時期はいつですか?
妊娠中、クルミを適切に食べることは、妊婦の体調を整えるのに役立ちます。クルミには、脳を強化し、疲労を...
インディゴの効果と機能は何ですか?
清朝時代の多くのテレビドラマでは、宮廷の女性が眉を描くのに藍を使うという話がよく出てきます。実は藍に...
白い斑点は狂気の兆候ですか?
白斑は現在では比較的一般的な病気で、先天性と後天性の2つの要因に分けられます。主に皮膚の色素が失われ...