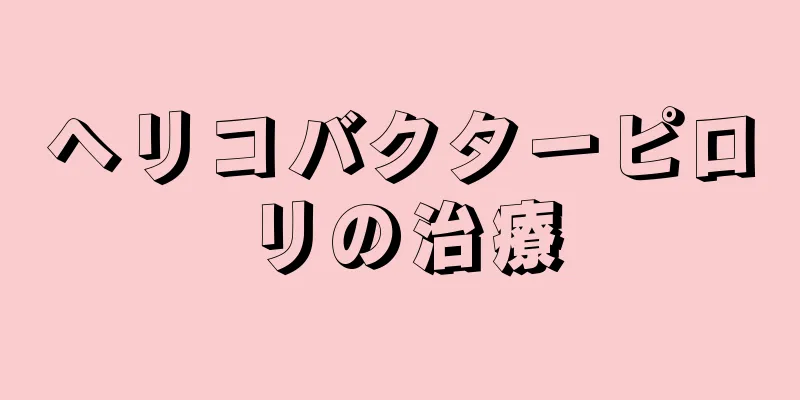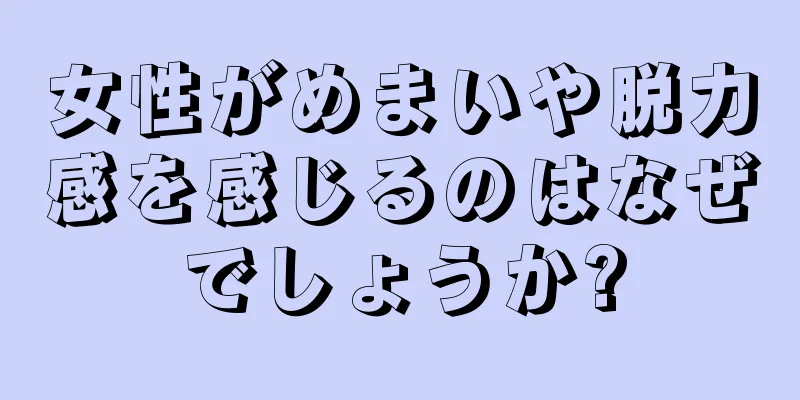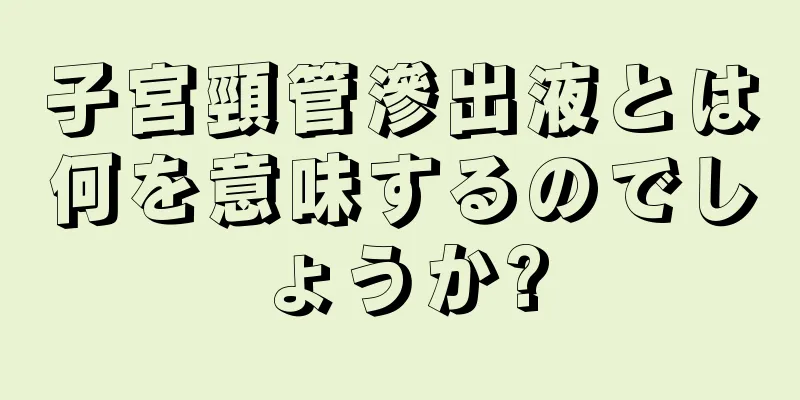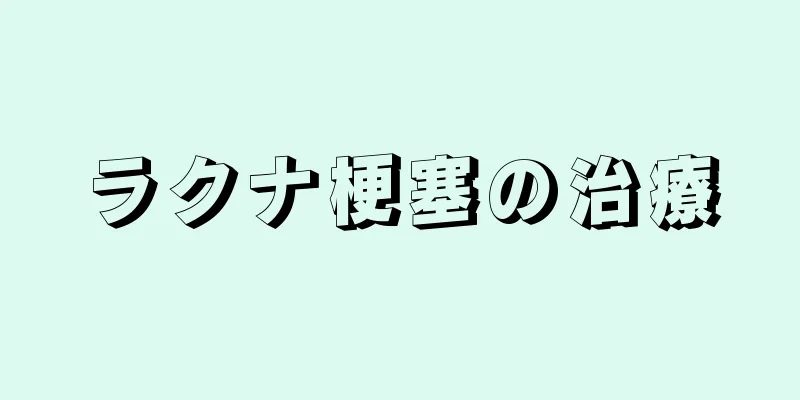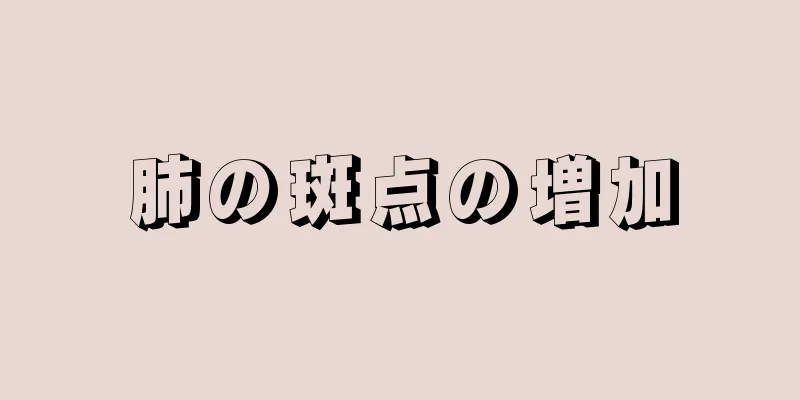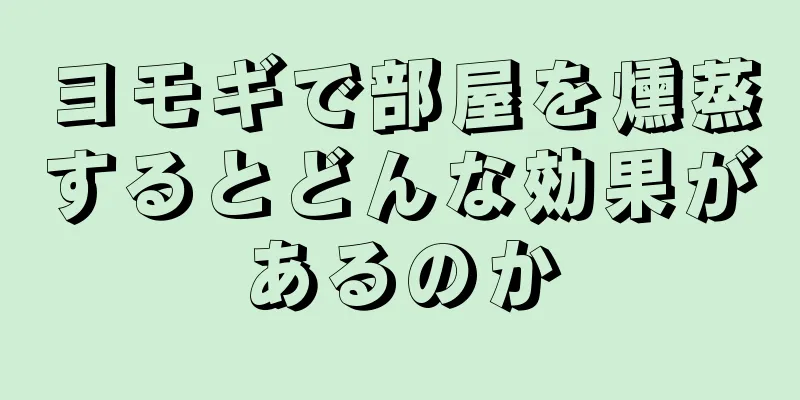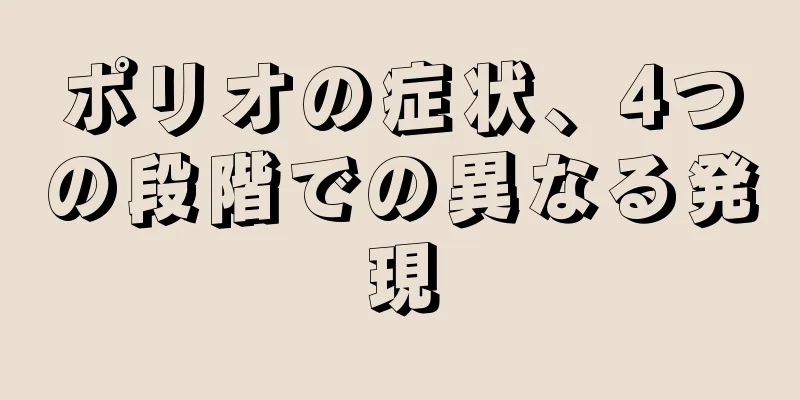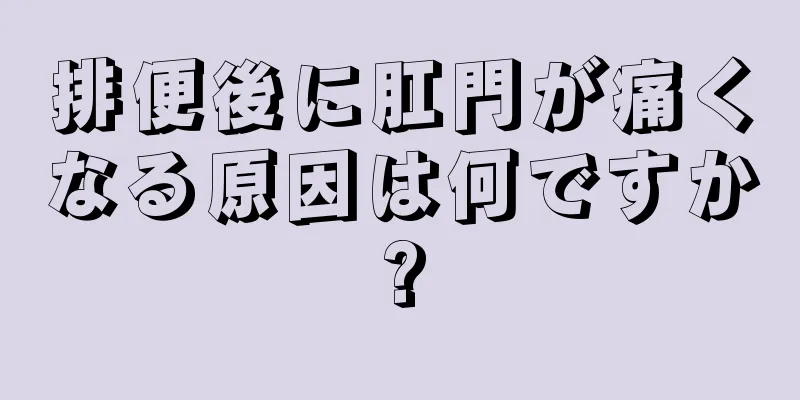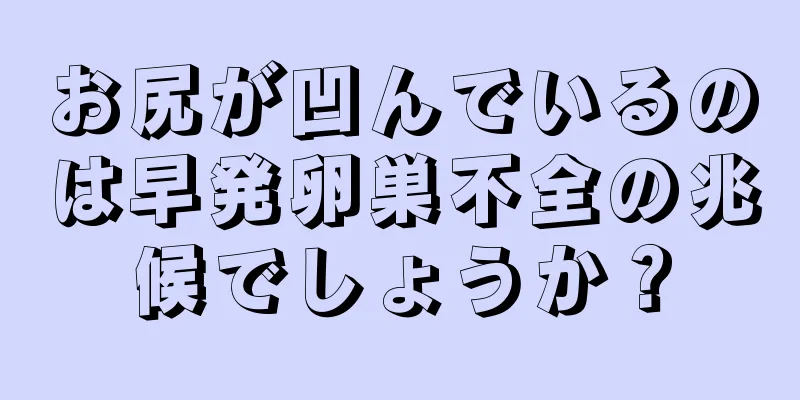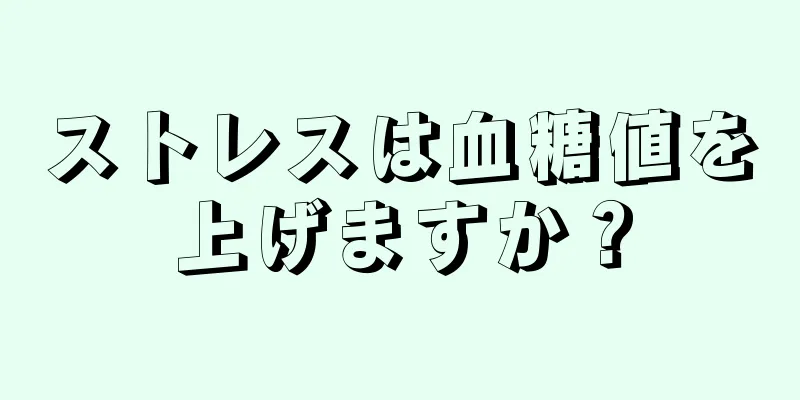足の親指の陥入爪の原因

|
足の親指の爪が肉の中に生えてしまう状況は、爪囲炎や陥入爪が原因である可能性があるため、生活の中でこのような状況に遭遇した場合は、タイムリーな治療を受ける必要があります。親指の爪が肉の中に生えると、親指の炎症やびらんを引き起こす可能性があるため、生活の中で親指の爪が肉の中に生えた場合の治療法について、誰もがある程度理解しておくことが望ましいと私たちは考えています。 爪囲炎や陥入爪は治療しなければ自然に治ることはなく、時間が経つにつれて化膿してしまいます。足の爪を長期間治療しないと、ひどく変形し、爪床が損傷して、最終的には足の爪が失われます。重症の場合は、爪の成長が止まることもあります。足の爪が繰り返し炎症を起こすと爪下膿瘍になりやすく、重症の場合は骨髄炎を引き起こすこともあります。患者によっては長期間治療を受けず、爪領域の免疫力が低下し、爪の自然な保護バリア機能が失われ、真菌性疾患である爪白癬(爪白癬)に感染することもあります。爪白癬は感染力の強い真菌性疾患です。治療しないと、頭部白癬や手白癬などの一連の疾患を引き起こす可能性があります。 陥入爪とは、足の爪が肉の中に伸びてしまうことです。陥入爪はよくある足の病気です。陥入爪は、爪を深く切りすぎたり、低く切りすぎたり、先のとがった細い靴を履いて足指を圧迫したりしたときに起こります。初期段階では、陥入爪は痛みを引き起こすだけです。陥入爪は、臨床的には爪囲炎と呼ばれる爪溝組織感染症を合併する可能性が非常に高く、この段階では、局所に明らかな赤み、腫れ、熱感があり、激しい痛みを伴います。化膿すると、膿性の分泌物が局所的に流れ出します。 現在有効な治療法は、足の爪の端を少し切り取り、爪の根元の胚層を治療して、足の爪の端に新しい爪が生えないようにし、陥入爪を完全に治すという目的を達成することです。この手術は時間が短く、回復期間も短く、外傷も少なく、術後の患者の痛みも少なく、術後の入浴や足洗いにも影響がありません。 陥入爪の治療に関する誤解: 誤解 1: ペディキュアは陥入爪の治療に使用されます。陥入爪のほとんどの人は自宅で自分で爪を切りますが、症状が軽い人はペディキュアセンターに行って爪を切ってもらいます。どちらの方法でも、痛みに耐えて肉に突き刺さった爪の部分を取り除く必要がありますが、爪が伸びると、まだ肉に突き刺さってしまいます。繰り返し爪を切ることで慢性的な刺激を受け、爪溝の組織が増殖して厚くなり、爪が肉の中に食い込みやすくなります。さらに、ペディキュアを行う場所は医療施設ではなく、厳格な消毒対策も講じられていないため、爪白癬などの他の病気が広がりやすいのです。 誤解2: 繰り返しの爪除去治療。特に爪囲炎を併発している患者の中には、治療のために病院に行く人もいます。ほとんどの病院では、陥入爪の治療に抜爪を行うのが一般的で、爪の根元の胚層には何の治療も行いません。そのため、新しい爪が生えた後も、元の方向に成長し、最終的には肉の中に成長します。さらに、この方法は非常に痛みを伴い、治癒に長い時間がかかり、最も重要なことは、陥入爪を治すことができないことです。 人生の中で不幸にも親指の爪が肉の中に生えてしまった場合、適時に消毒する必要があります。肉の中に生えた爪は多くの細菌に感染している可能性があるため、消毒することで親指の炎症を防ぐことができます。さらに、多くの人が陥入爪の治療方法について多くの誤解を抱いています。 |
推薦する
首がねじれたらどうすればいい?
普段、首を誤ってひねってしまうことがあります。多くの人がこの現象に遭遇しています。首がひねられると、...
灼熱感や痛みを伴う皮膚は帯状疱疹に注意が必要です
皮膚の灼熱感や痛みが生じたら、帯状疱疹に注意してください。気候が比較的乾燥しているとき、ウイルスがよ...
急性気管支炎
急性気管支炎は3つのタイプに分けられます。1つ目は風寒肺阻型、2つ目は風熱肺侵犯型、3つ目は乾熱肺傷...
肩こりマッサージ
肩こりはマッサージで治すことができます。マッサージ後は首がとても楽になり、首の痛みも徐々に消えていき...
太子神の効果と機能
誰もが高麗人参が生活にもたらす効果を知っていると思います。高麗人参は最高級の強壮剤なので、多くの人が...
外ほくろの症状は何ですか?
痔に悩まされると、仕事や生活に非常に深刻な影響を及ぼします。まず、痔は肛門周辺の病変で、座ることがで...
白癬は伝染しますか?
白癬菌は、通常、背中や手に生えますが、時には脚や足にも生えます。肌が白くまだらになり、見た目が不快で...
肺の右中葉に線維性病変が現れる理由は何ですか?
多くの友人は、普段は咳や胸の圧迫感などの肺の不調を感じませんが、健康診断で肺の右中葉に線維性病巣が見...
手の怪我の術後ケア
手は人体の中で最も働き者な器官ともいえるため、怪我をする可能性も最も高くなります。手は非常に力強く、...
不安障害の予防と治療
不安障害は不安神経症とも呼ばれ、非常に一般的な病気です。この病気が発生すると、めまい、胸の圧迫感、動...
漢方薬の服用方法
現在、多くの漢方薬煎じ薬は効果が長く続くため、多くの人が病気の治療にこの方法を選んでいます。漢方薬で...
便に血が混じっていたらどうすればいい?
便に血が混じる原因が何であれ、特別な注意を払う必要があります。便に血が混じるのは、肛門自体の問題が原...
子どもが体内に熱を持っていて発熱している場合はどうすればいいでしょうか?
子どもの身体の健康は、外的要因によって非常に簡単に損なわれます。たとえば、天候の気温の変化により、子...
鼻炎粘膜浮腫のケア方法
鼻粘膜浮腫は比較的よく見られるもので、ほとんどは鼻炎やアレルギー性鼻炎が原因です。例えば、風邪、ほこ...
新生児溶血性疾患を予防するには?
赤ちゃんの誕生は家族にとって祝う価値のあることです。しかし、病気を持って生まれてくる赤ちゃんもおり、...