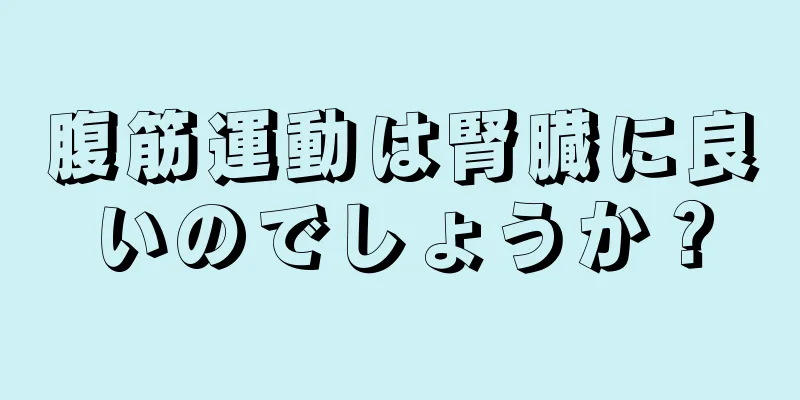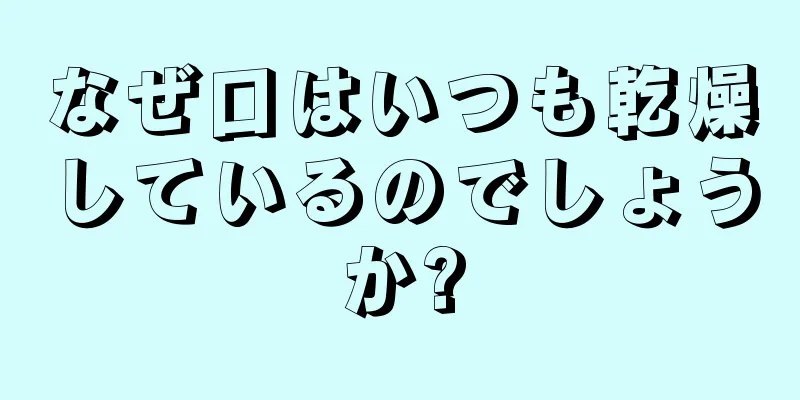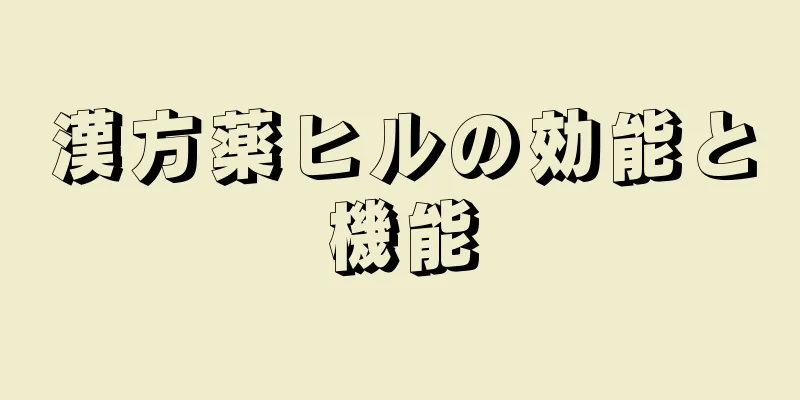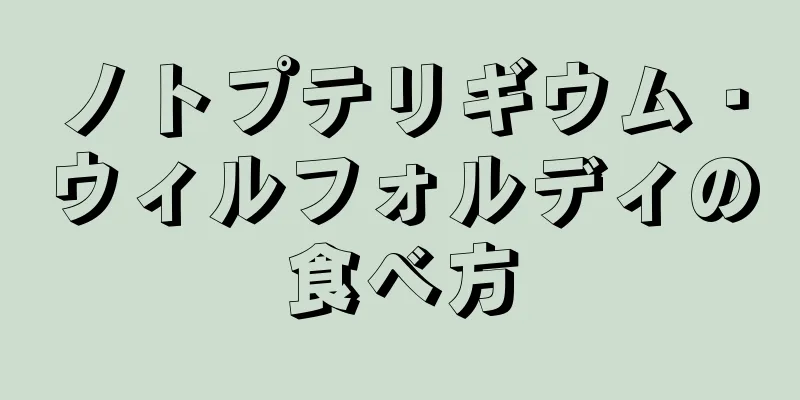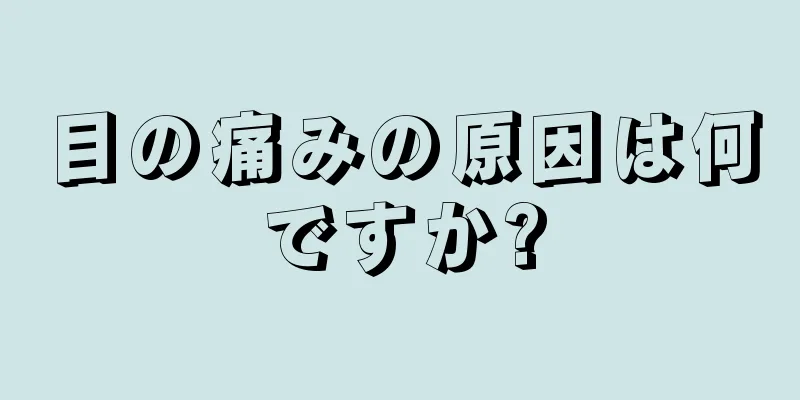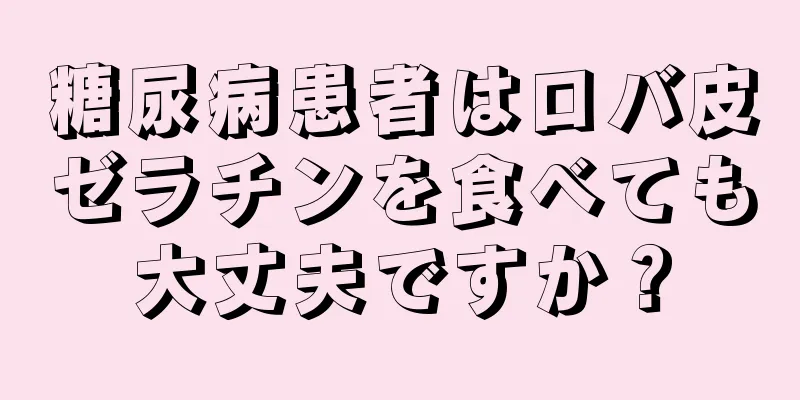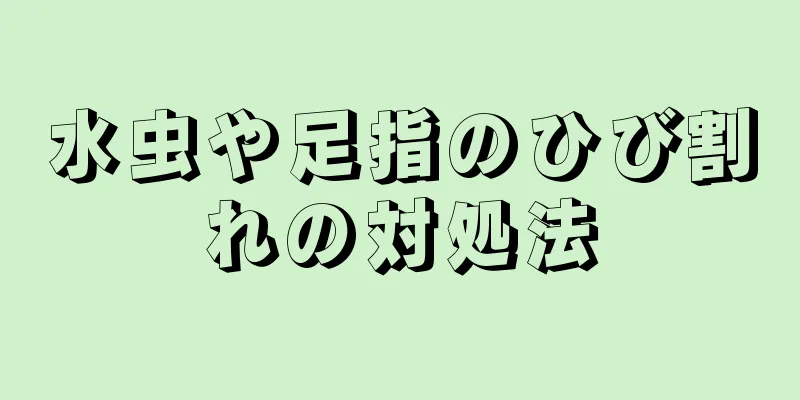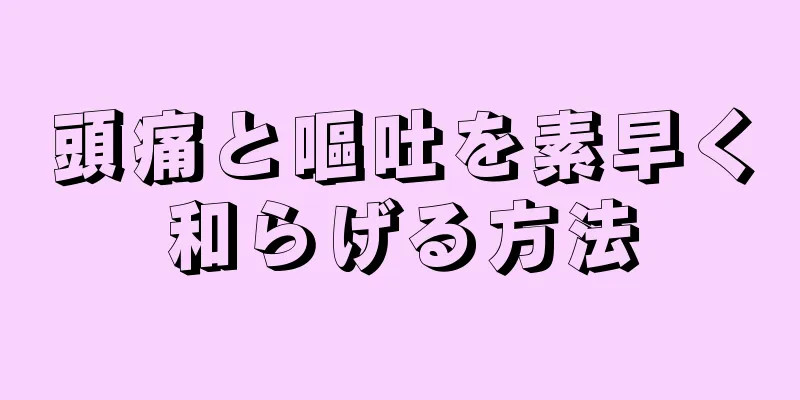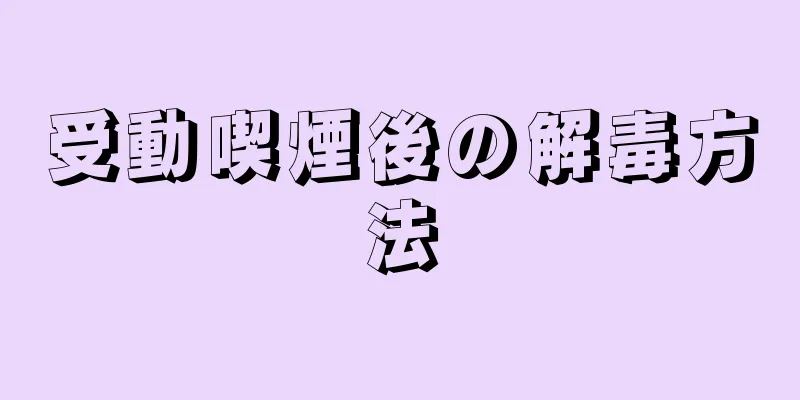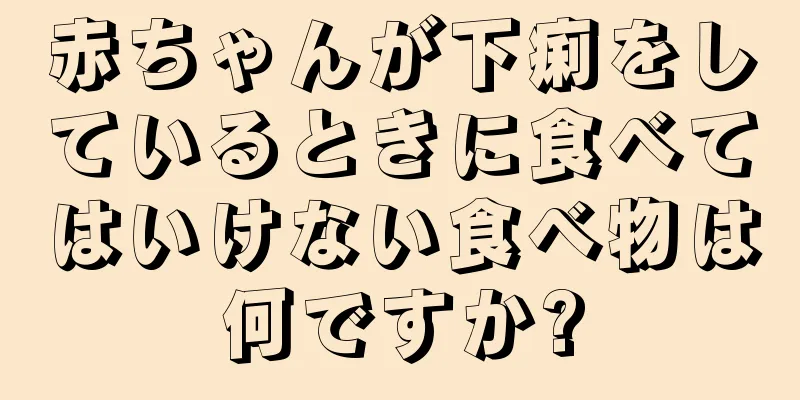流産後も産後ケアを続ける必要がありますか?流産後の産後期間中、どのように自分をケアすればいいですか?
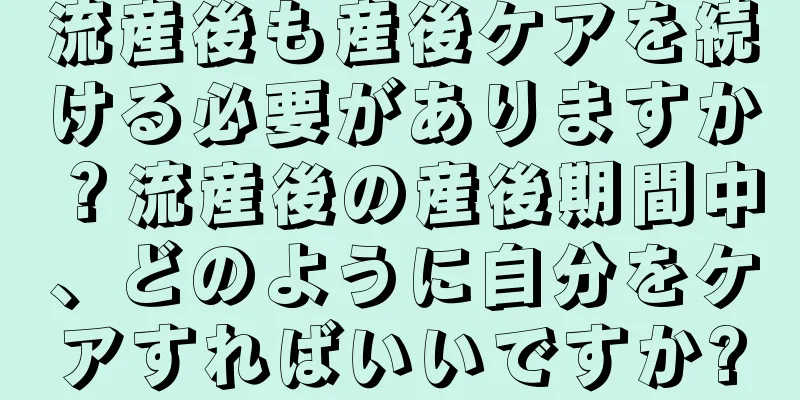
|
女性は妊娠または流産後、1か月間の産後ケアを受ける必要があります。このとき、女性の身体は大きなダメージを受け、非常に弱っています。流産後の産後ケアは、女性の身体の回復期間でもあります。食事や生活習慣に注意する必要があります。では、流産後の1か月間の産後ケアはどのように受ければよいのでしょうか。 流産後のケア方法 流産後は「小一ヶ月の産休」を取る必要があると言う人もいます。流産後は正常な妊娠が中断されるため、身体はゆっくりと徐々に適応する過程を経ないため、人体の健康に一定の影響を与えます。流産後、妊婦は精神的緊張が高まり、子宮に激しい痛みを感じるため、交感神経の興奮性が高まり、アドレナリンの分泌が増加し、体の代謝率が上がり、エネルギー消費量が増加します。同時に、母親の子宮内膜は必然的に損傷を受けます。セルフケアの強化に注意を払わないと、膣出血が長引いたり、腰痛、腹痛、月経障害、無月経などを引き起こす可能性があります。したがって、流産後の効果的なセルフケアは、身体と生殖器官のスムーズな回復を促進するために非常に重要です。 1. 休息と栄養強化に留意する。 流産後は、2~3 日間ベッドで休んでください。その後、ベッドから出て動き回り、活動する時間を徐々に増やしてください。流産後半月以内は、重労働をしたり、冷たい水に触れたりしないでください。流産後、子宮が回復するまでには約1か月かかりますので、栄養を増やし、十分なタンパク質を摂取し、体の病気に対する抵抗力を高め、損傷した臓器の早期修復を促すことに注意する必要があります。流産後は、体の回復を早めるために、魚、肉、卵、豆製品などのタンパク質を豊富に含む食品や、ビタミンを豊富に含む新鮮な野菜を多く食べる必要があります。 2. 外陰部を清潔に保ち、衛生的に保ち、性交を避けてください。 流産後、子宮頸管はまだ閉じておらず、子宮内膜も修復過程にあります。この期間中は、外陰部を清潔に保ち、衛生的に保つことに特に注意する必要があります。半月以内に浴槽に入浴しないでください。汚れた水が膣に入り、細菌の侵入や感染につながるのを防ぐためです。流産後1か月以内に性行為を行わないように注意してください。 3. 出血状況を観察し、症状の悪化を防ぎます。 流産後の膣出血が1週間以上続き、下腹部の痛み、発熱、濁った臭いのする帯下などの症状を伴う場合は、早めに病院に行って検査と治療を受ける必要があります。 4. 再度妊娠しないように避妊に注意してください。 流産後、卵巣と子宮の機能は徐々に回復し、卵巣は予定通りに排卵します。避妊を守らないと、すぐにまた妊娠してしまいます。中絶後、同じ月に再び妊娠する女性もいますが、これは身体に大きな影響を及ぼします。したがって、信頼できる避妊手段を選択する必要があります。中絶は、避妊が失敗した後の最後の手段としての治療手術としてのみ使用できます。女性の心身の健康を守るための避妊手段として中絶を使用することは決してありません。 |
<<: 流産後何日で女性は外出できるのでしょうか?何に注意すればいいでしょうか?
>>: 流産後何日経ったら髪を洗ってもいいのでしょうか?何に注意すればいいのでしょうか?
推薦する
下垂体腫瘍による死亡率
体内の多くのホルモンの分泌には下垂体の関与が必要であるため、下垂体は人間の脳の重要な内分泌器官です。...
吐き気や嘔吐にはどんな薬を飲めばいいですか?
吐き気や嘔吐は、人生でよくある現象です。この現象の原因は、胃腸の運動が遅いために起こる消化不良か、胃...
陥没した傷跡を修復するには?
陥没した傷跡は多くの人にとって非常に見苦しく、一般的な方法では除去するのが困難です。陥没した傷跡を修...
低血糖の原因は何ですか?
低血糖の問題に直面したときは、原因を理解することに注意する必要があります。インスリンに拮抗するホルモ...
蜂蜜は酔い覚めに役立ちますか?蜂蜜で酔いを覚ます最速の方法をお教えします
多くの人にとって、飲酒は娯楽であり、遠慮なく飲みます。過度の飲酒は人体に一定の影響を及ぼすため、飲酒...
肺熱咳嗽に対する漢方処方は何ですか?
肺熱咳という病気を聞いたことがありますか。これは通常、肺の熱が停滞し、肺の気の流れが悪くなることで咳...
肛門と陰嚢の間のかゆみ
男性の肛門と陰嚢は非常に近い位置にあるため、どちらかに皮膚疾患が発生すると、もう片方に広がる可能性が...
Achyranthes bidentata の機能と効果は何ですか?
あなたは、アキランサス・ビデンタタの機能や効果に注目したり、学んだりしたことがありますか?トチバニン...
赤ちゃんのネブライザー治療にはどのような薬を使うべきでしょうか
赤ちゃんが喘息や気管支炎などの病気にかかっている場合、ひどい咳が出ることがよくあります。このとき、薬...
オオバコの利点は何ですか?
オオバコは、一般的にあまり背が高くなく、根と不規則な鋸歯状の葉を持つ他のイネ科植物に似た多年生草本で...
心拍数が60未満だと何を意味するのか?心拍数が遅い場合は注意が必要
心拍数が 60 未満の場合は徐脈とみなされます。正常な心拍数は 60 ~ 100 です。徐脈には、長...
腰椎椎間板ヘルニアはなぜ繰り返し起こるのでしょうか?
腰椎椎間板ヘルニアの治療では、腰痛の症状がなくなると病気が治ったと考える患者が多くいます。実は、この...
左薬指のしびれ警告
多くの場合、血管が圧迫されると、しびれが起こりやすくなります。この状況は、特に睡眠時の姿勢が間違って...
首のしこり
多くの人は自分の体にあまり注意を払っていません。体内の病気がすでに警告メッセージを発している場合もあ...
不眠症に対する漢方薬
不眠症は誰もがよく知っていることであり、多かれ少なかれ誰もが不眠症の問題に遭遇したことがあると思いま...