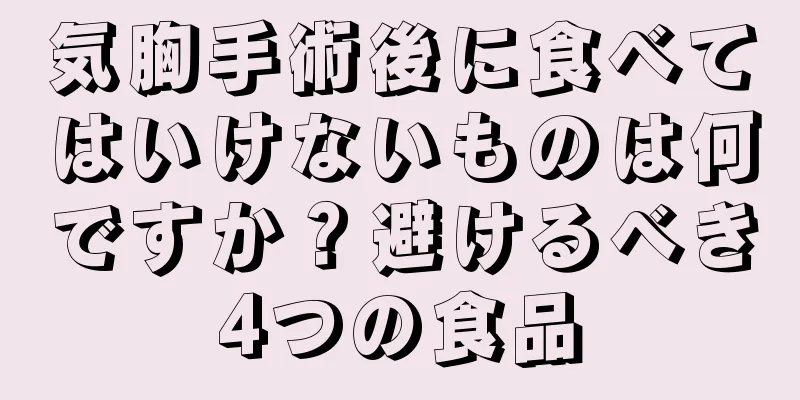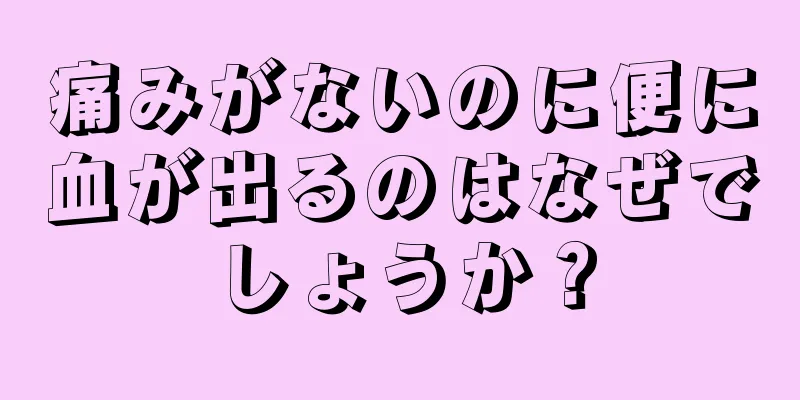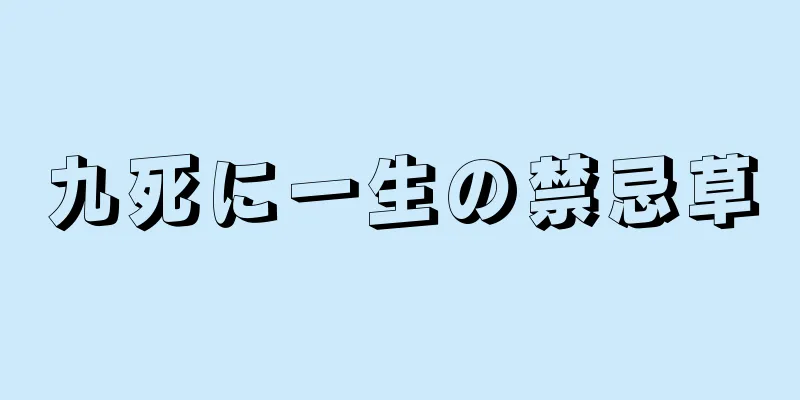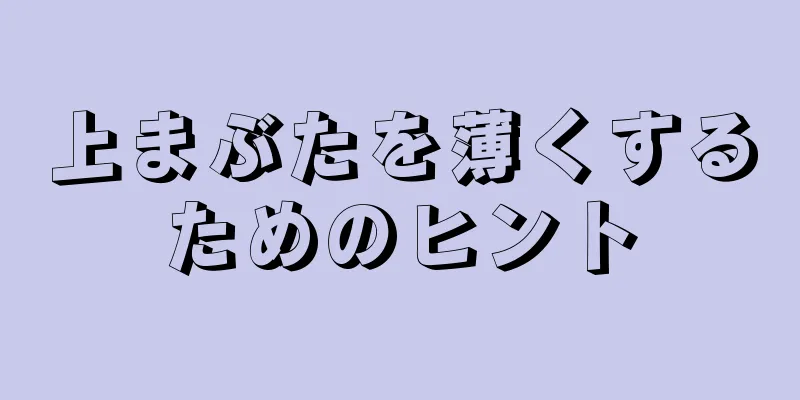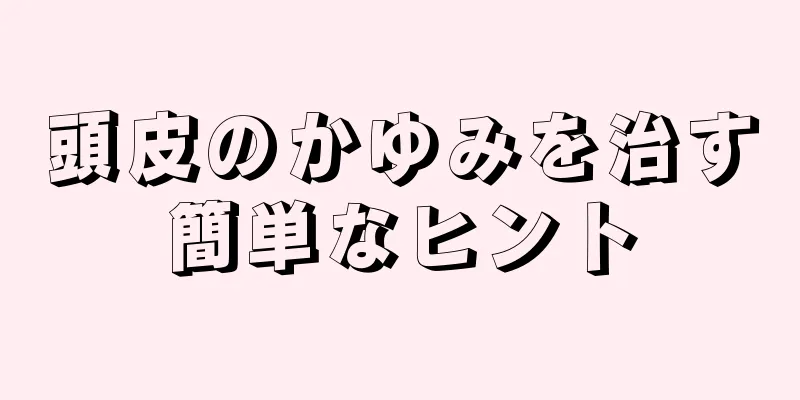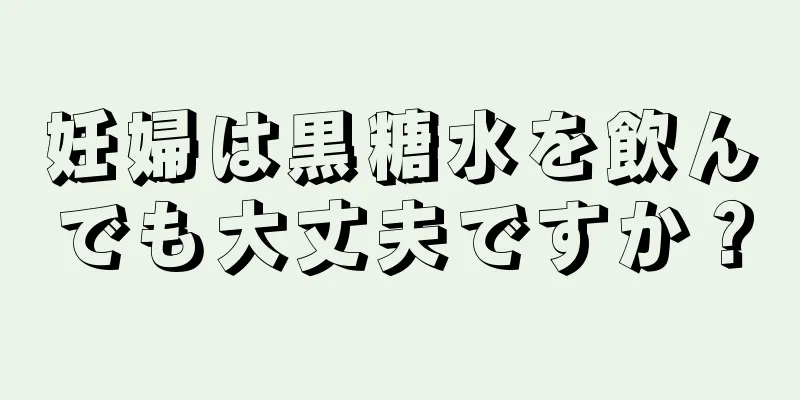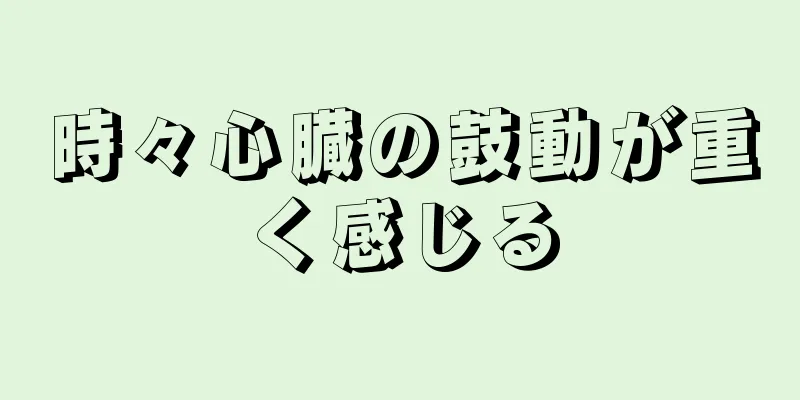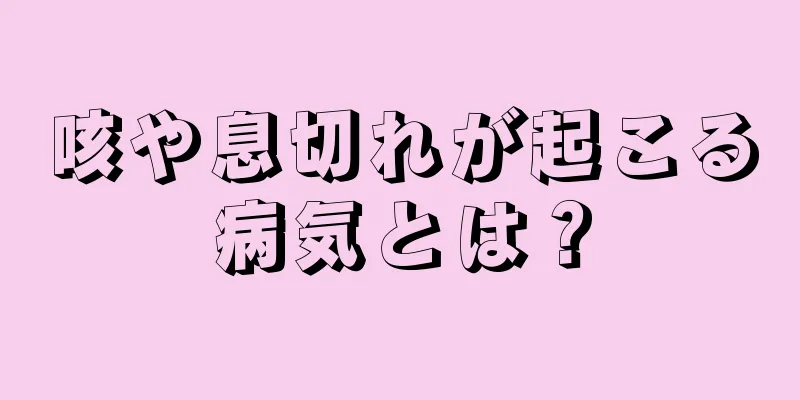地黄丸にはどんな種類がありますか?
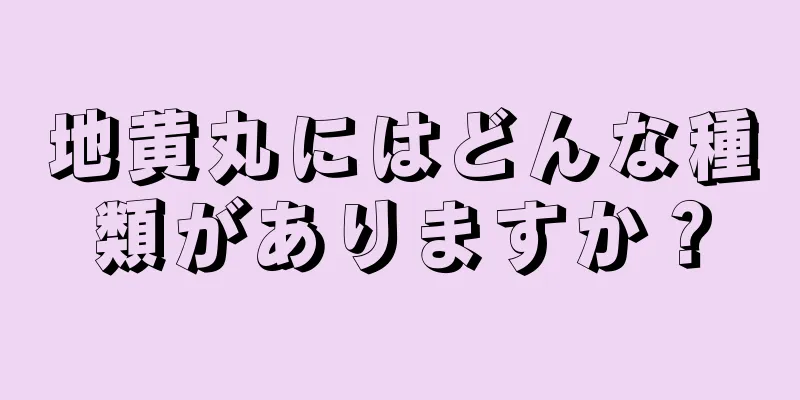
|
「地黄丸」ファミリーは巨大であり、六味地黄丸はそのうちの一つにすぎません。多くの栄養豊富で健康維持に役立つレシピが、これに基づいて簡素化され、改良されています。 「地黄丸」と同じ名前ですが、治療薬の成分が若干異なります。誤用を避けるために、使用前によく確認する必要があります。六味地黄丸は、調理した地黄、サンシュユ、ヤマイモ、オオバコ、シャクヤクの樹皮、ヨクイニンから作られています。 その特徴は、補気と下気を兼ね、穏やかで甘く、騒がしくもなく温かくもなく、補気して滞らず、滋養して脂っぽくもなく、陰を養う代表的な処方の一つです。腎陽不足、熱虚によるめまい、耳鳴り、腰痛、喉の渇きなどに効果があります。麦味地黄丸は「六味」にオウゴンジャポニカと五味子を加えて作られており、八仙長寿丸とも呼ばれ、優れた保護特性を持っています。寝汗、喉の渇き、喀血、めまい、耳鳴りなどの肺腎陰虚に適しています。また、長期にわたる咳によって陰が傷つけられることによって起こる喉の渇き、口の渇き、咳、痰に血が混じる症状、あるいは活動性肝炎(結核など)にも非常に良い効果があります。現代の科学的研究によれば、肺性心を伴う慢性閉塞性肺疾患の治療にも使用できることが分かっています。 「六味」処方に芝麻と黄耆を加えた芝白地黄丸は、腎陽の不足を補い、虚熱を清める効能を高めます。更年期障害、神経性難聴、慢性咽頭炎、びまん性口腔潰瘍などの患者で、陰虚火多動、寝汗、喉の乾燥と味覚の乾燥、喀血、黄色と赤色の尿、歯茎の腫れと痛みなどの症状がある場合は、陰虚火多動に属し、この治療薬が適しています。奇莒地黄丸は「六味」にクコと黄菊を加えたものです。六味地黄丸との違いは、前者は肝臓を養い、視力を改善する効果を高め、主に腎臓を養うのに対し、後者は不足している腎陽を養う点です。伝統的な中国医学では、通常、腎臓から眼疾患を治療します。 奇莒地黄丸は、めまい、視力低下、かすみ目、腎不全に伴うその他の眼疾患、高血圧、糖尿病を治療することができます。亀兔地黄丸は、六味地黄丸に川芎と赤芎を加えたもので、婦人科疾患の万能薬です。陰を養い火を減らし、肝臓を柔らかくし、腎臓を養い陽を強化することができます。女性の月経期間中の過度の出血は陰にダメージを与える可能性があります。この薬は、女性の腎虚による月経出血、めまい、疲労感、腰痛、脚痛、耳鳴りなどを重点的に治療します。明木地黄丸は、「六味」に加え、クコの実、菊、当帰、シャクヤクの根、ハマビシ、桂皮から作られています。主に眼疾患、特に腎虚によるドライアイ、かすみ目、涙目などの治療に使用されます。 桂枝地黄丸は「六味」をベースに桂皮粉と大黄を加えて作られ、陰を養い腎を補う陽気増強薬です。脾腎虚と命門火の衰えによる高齢者の腰痛、膝痛、身体のむくみ、排尿困難、頻尿の治療に用いられます。陽虚を見分ける非常に簡単な方法は、舌苔を見ることです。舌苔の色が薄くて厚い場合は、ほとんどの場合、陽虚の兆候です。また、陽虚の人は寒さを恐れ、手足が冷たくなります。 |
推薦する
朝に喉から血を吐く
朝起きたときに喉に血が混じっている場合は、慢性咽頭炎の症状である可能性があります。慢性咽頭炎は比較的...
肥満の症状は何ですか?
肥満の人は人生においてかなり一般的です。これは体型の違いですが、太りすぎは肥満などの病気である可能性...
卵管閉塞は自然に解消されますか?
女性の卵管閉塞は、不妊の重要な原因となることがよくあります。また、子宮外妊娠も引き起こしやすいため、...
湿気は体重増加の原因になりますか?
湿気は伝統的な中国医学の範疇に属します。人体の湿気が特に重くなると、特に女性の場合、一連の病気を引き...
鼓膜が破れるとどうなるのでしょうか?
多くの人は、鼓膜が破れる可能性があると考えています。実際には、この状況は鼓膜の穿孔であり、完全な破裂...
咳に良い食べ物は何ですか
咳が出るときは、喉をすっきりさせて肺に良い食べ物を食べるといいでしょう。緑の葉野菜には比較的良い抗酸...
出っ歯と出っ歯のどちらが良いのでしょうか?
日常生活において、上顎の歯が下顎の歯を覆えない状態をオーバーバイト、またはその逆と呼んでいます。これ...
1 つのツボで 8 つの病気を治療できるので、集める価値があります。
全粒穀物を食べるとさまざまな病気を引き起こす可能性があるため、病気が発症した後でも、さまざまな優れた...
目が炎症を起こして腫れてしまったらどうすればいいでしょうか?この治療法は早く回復するのに役立ちます!
私たちにとって、目は非常に重要な器官ですが、非常に壊れやすい器官でもあります。目が炎症を起こしたり、...
トウゴマの加工方法
梔子は比較的一般的な漢方薬で、薬効が高く、体調を整える効果もあります。お茶にして飲むと、肝臓を清め、...
伝統的な漢方薬で気管炎を治療する方法
気管炎は一般的に細菌やウイルスの感染によって引き起こされ、臓器の炎症を引き起こします。特に冬や春にこ...
ネフローゼ症候群ではどれくらい生きられるのでしょうか?
医療技術がますます高度化するにつれ、いくつかの病気の生存期間を判定したり、その病気の患者の平均余命を...
化学的肝障害とは何ですか?
肝臓は人体で最も重要な臓器の一つです。肝臓は人体のさまざまな生理活動に関与しています。肝臓に問題があ...
耳の下のしこりの原因は何ですか?
人間の体は日々変化しています。小さな腫れが現れたり、皮膚が偶然に傷ついたりすることもあります。痛みが...
後骨髄球
日常生活では、病院に行ったり、職場で健康診断を受けたりするときに、血液検査のレポートを目にすることが...