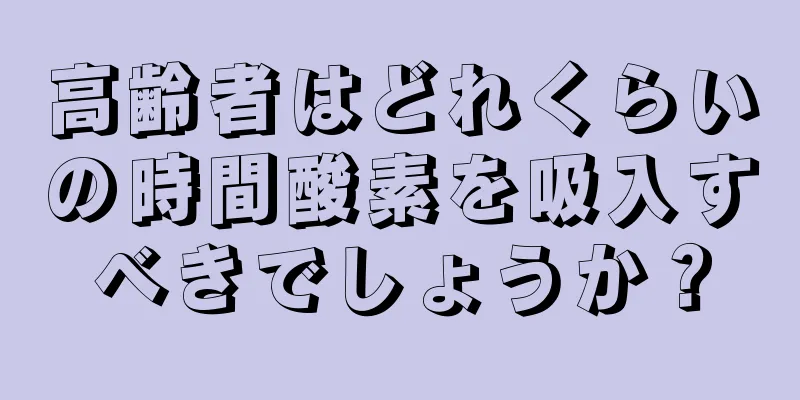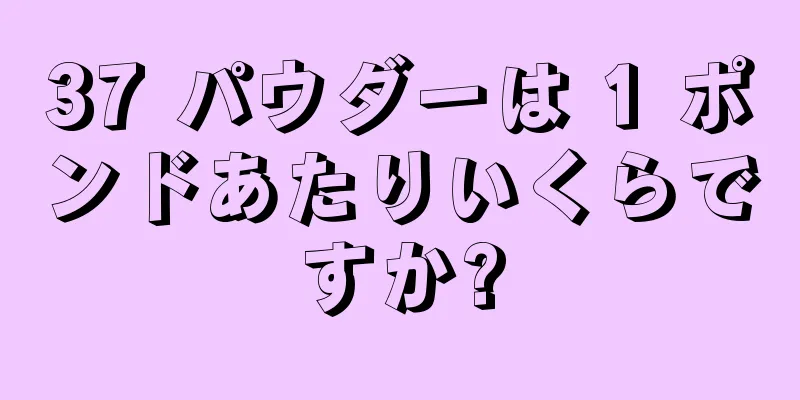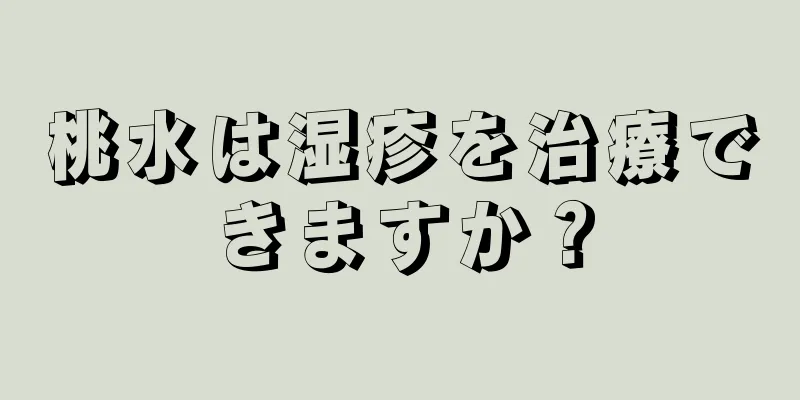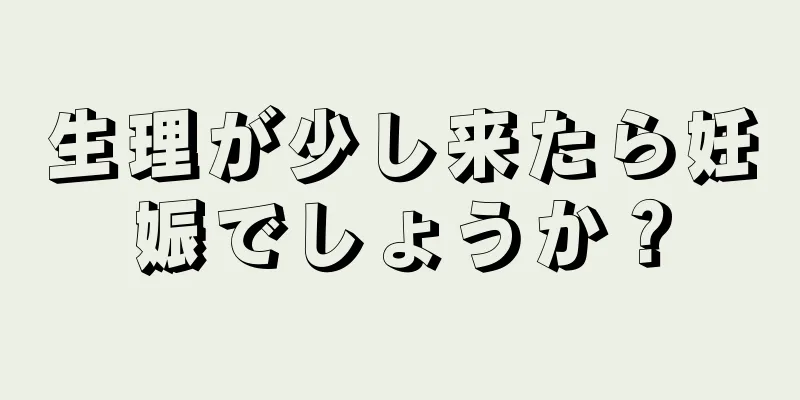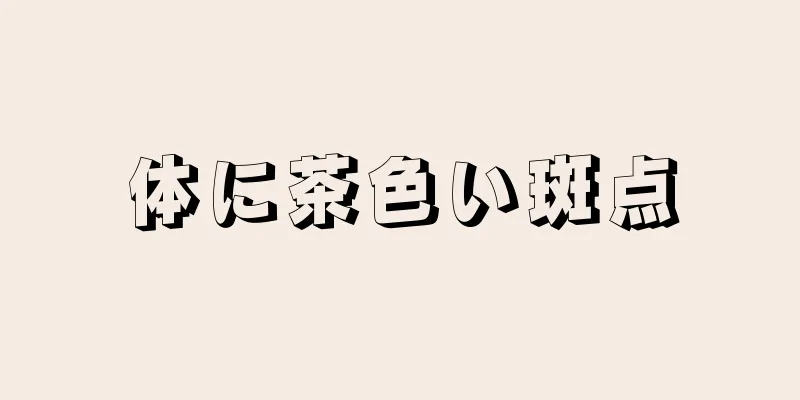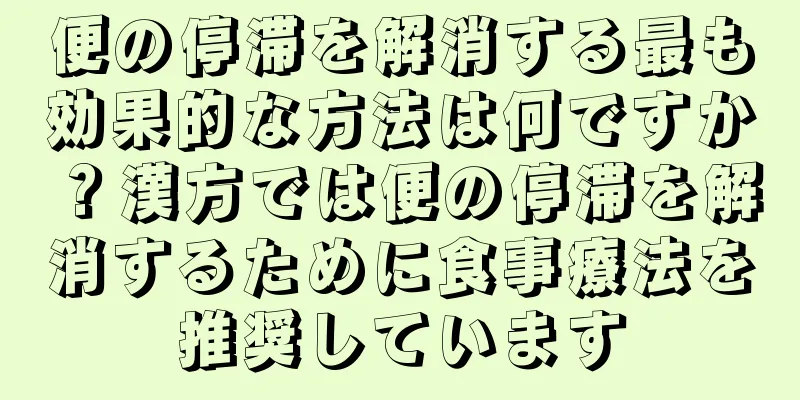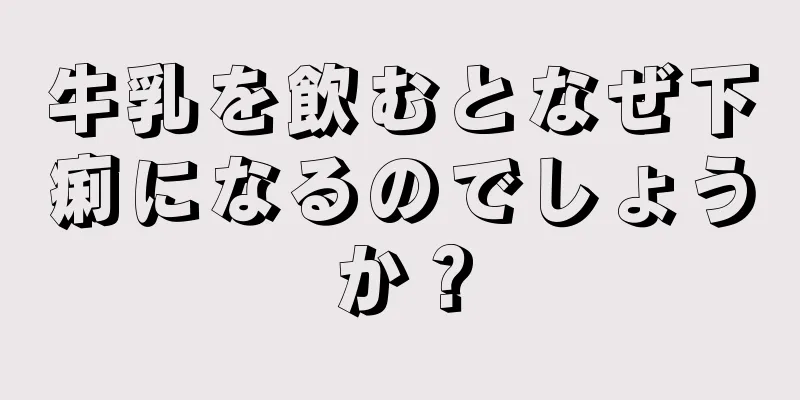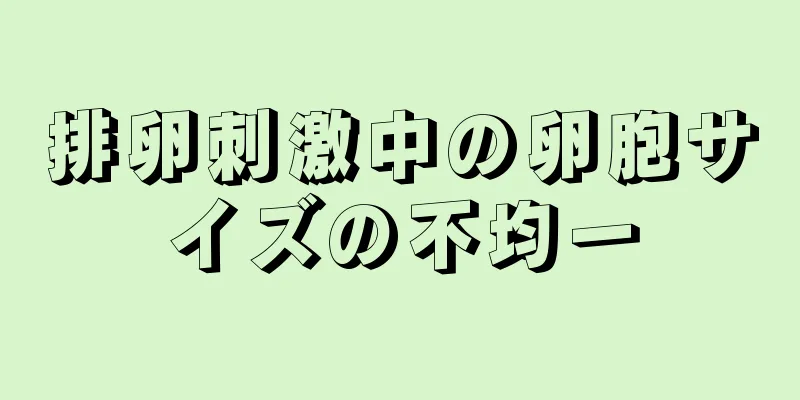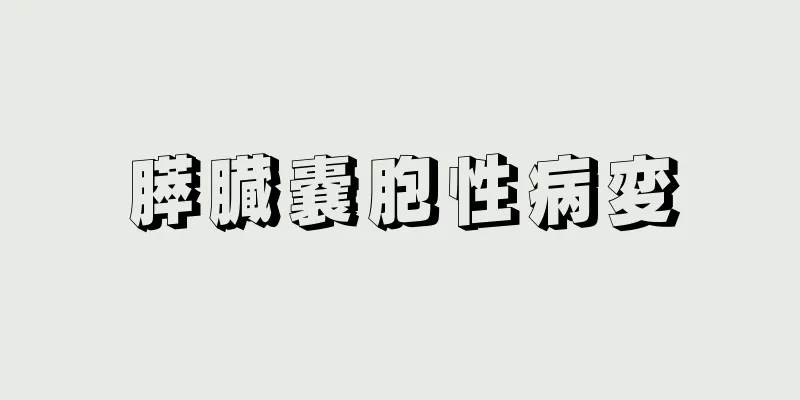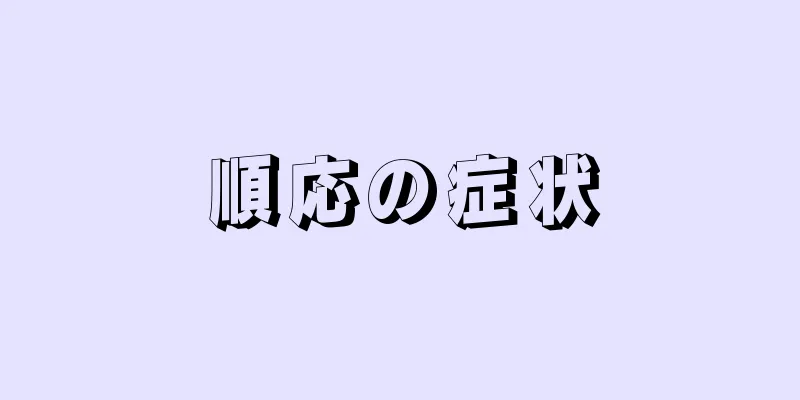食後の血糖値の正常値はどれくらいですか?
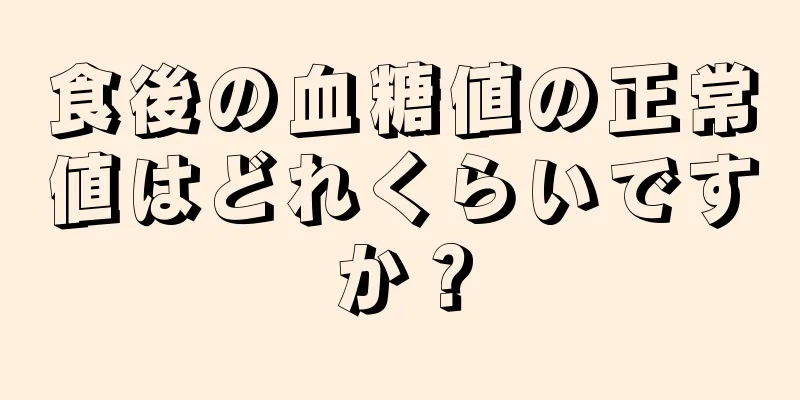
|
高齢者は、高血糖がめまいや吐き気などの一連の症状を引き起こす可能性があるため、高血糖を恐れています。人々の生活水準はますます向上し、よりおいしい食べ物を買うお金も増えています。しかし、あるものを食べ過ぎて血糖値が急激に上昇すると、人体に悪影響を及ぼすこともあります。では、食後の正常な血糖値とは何でしょうか?実は、さまざまな基準があり、人体は糖分を摂取したばかりのときは血糖値が比較的高くなりますが、時間が経つにつれて血糖値は徐々に低下します。 糖尿病患者の場合、糖分の摂取を厳密に制限する必要があります。私はすでに糖尿病を患っているため、食生活をコントロールしないと糖分の摂取量が基準を超えてしまい、体に深刻な影響が出る可能性が非常に高くなります。食後の正常な血糖値に関する参考資料をいくつかご紹介しますので、お役に立てれば幸いです。 食後1時間の正常血糖値:糖分を摂取してから最初の1時間の正常値は6.7~9.4 mmol/Lです。食後2時間の正常血糖値:2時間目の血糖値≤7.8 mmol/L。食後血糖値の正常値:3時間後の正常値:3時間後に正常に戻り、尿糖はいずれもマイナス。 空腹時血糖値(FPG)の正常値は3.9~6.1mmol/Lです。6.1~7mmol/Lは異常な空腹時血糖値(IFG)です。耐糖能異常(IGT)の場合、食後2時間の血糖値の正常値は7.8~11.1mmol/Lです。糖尿病の場合、空腹時血糖値が7.0mmol/L以上または食後2時間血糖値(P2hPG)が11.1mmol/L以上です。糖尿病になると、空腹時血糖値が正常より高くなり、糖分を摂取してから2時間後の血糖値は11.1 mmol/L以上になります。 血糖値 (GLU): 血糖値は臨床的には血液中のブドウ糖を指します。 IFG と IGT は、正常者と糖尿病患者の間の中間移行段階です。このような人々は糖尿病の高リスクグループおよび予備軍であり、真剣に受け止め、早期に介入する必要があります。 食後 2 時間の血糖値検査は、実際には簡易ブドウ糖負荷検査です。この方法は、経口ブドウ糖検査よりも採血回数が少なく、実施が簡単で患者にも受け入れられやすいため、臨床現場では空腹時血糖値が正常な糖尿病患者をスクリーニングして検出するために最も一般的に使用されている方法です。 食後2時間の血糖値を測定することには、診断のためと、耐糖能の回復を観察して膵臓の機能状態を反映するという2つの意味があります。治療期間の経過後、空腹時血糖値は正常に戻ったものの、食後血糖値が依然として高い場合、患者の耐糖能が依然として低く、インスリン分泌が依然として遅れていることを示している場合が多くあります。空腹時血糖値が正常で、食後血糖値も正常であれば、患者の耐糖能が良好で、膵島機能が改善されていることを意味します。 上記は皆様にとって関連のあるデータの参考です。血圧を測定する機器をお持ちでない場合は、血糖値を測定する機器を購入して、血糖値が正常値内かどうかを適時に知ることをお勧めします。血糖値が高くても低くても、どちらも良い兆候ではないので、高齢者はこの点にもっと注意を払う必要があります。そうでないと、何か悪いことが起こったときに、長期間入院しなければならない可能性があります。 |
推薦する
風邪の痰が緑色だと重篤ですか?
風邪をひくと痰が多く出やすくなります。痰が緑色の場合は注意が必要です。緑色の痰は一般的に呼吸器感染症...
大腸内視鏡検査後の穿孔の検出方法
大腸内視鏡検査は、腸内の状態を鮮明に映し出すことができ、腸の病気の有無を調べる検査としても非常に有効...
首に茶色い斑点ができる原因
「黄色い顔の女性」という言葉は、肝斑のある女性を表すのに最も適しています。きれいな顔と首が肝斑で覆わ...
痛風の合併症は何ですか?危険性は何ですか?
痛風は患者に耐え難い痛みを引き起こすだけでなく、一連の病気を引き起こす可能性があり、その一部は患者の...
尿管鏡レーザー砕石術はどれくらい安全ですか?
尿管鏡レーザー結石破砕術は、尿管結石を治療するための一般的な方法です。これは近年登場した新しいタイプ...
慢性的な足の冷えを予防するには?予防と治療を組み合わせる
老人性冷え性は高齢者に多く見られるため、中年以降は規則正しい生活、過労の回避、十分な睡眠の確保、栄養...
脳血管けいれんを治療するにはどうすればいいですか?治癒できますか?
脳血管けいれんは深刻な病気ですが、積極的に治療すれば治ります。適度な食事と運動に気を付けましょう。必...
肺が弱っている場合の対処法
肺気虚はよく見られる症状です。多くの子供や高齢者は肺気虚の不健康な症状を呈します。肺気が不足すると、...
一般的に使用されている止血薬は何ですか?
止血薬は特に私たちの健康に有益です。内出血であろうと外傷による出血であろうと、私たち一人一人はよく使...
涙管狭窄症の治療方法
涙管狭窄は主に女性の友人に発生します。この病気の原因は、女性の友人が悲しい状況に遭遇することが多く、...
歯が腐ってしまったらどうすればいい?
歯根腐れは日常生活でよく見られます。主な原因は虫歯です。虫歯がひどいと、このような現象が発生します。...
歯が生えているときに子供が熱を出したらどうしたらいいでしょうか?まずは観察し、盲目的に治療しないでください
子どもは誰でも一度は熱を出したことがあると思います。熱が出る原因はさまざまですが、最も一般的な原因は...
育毛のためのドクダミワインの作り方
ドクダミは食卓によく登場しますが、ワインに浸すと組織の再生を効果的に促進し、鎮痛作用や止血作用もある...
貧血に効く果物は?血液補給に最適な果物はこれ
貧血は体内の微量元素、特に鉄分の不足です。多くの妊婦は貧血になりやすいです。赤ちゃんの健やかな発育の...
脊髄麻酔の生理学的影響
脊髄麻酔とは、くも膜下腔に薬剤を注入して抑制効果を得る方法です。この麻酔法は脊髄麻酔とも呼ばれ、生理...