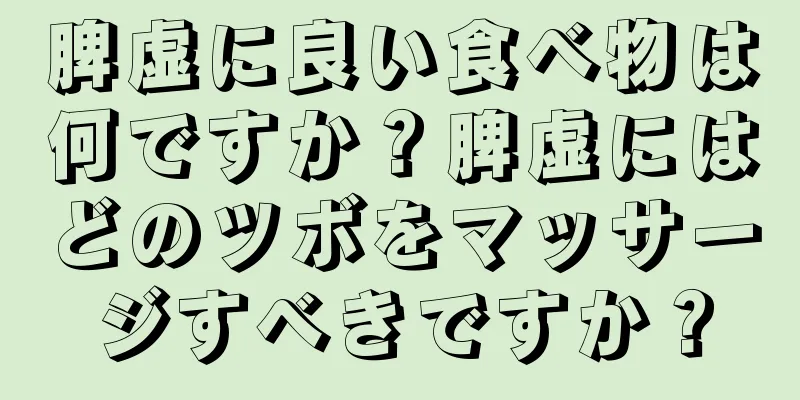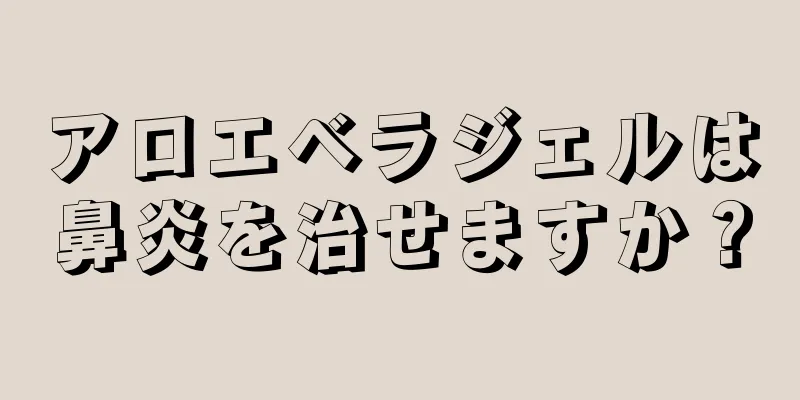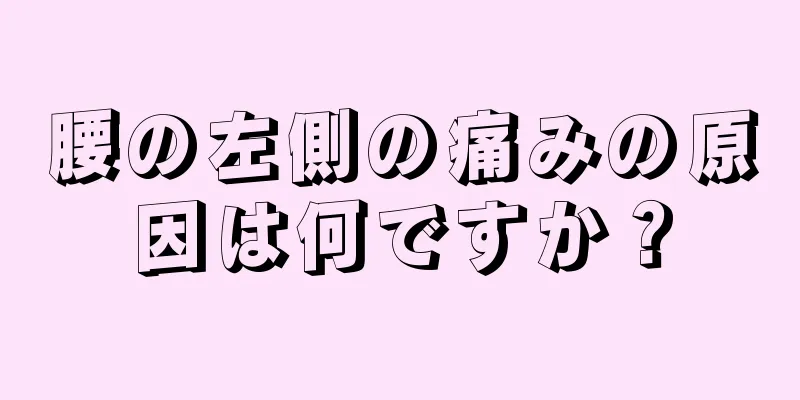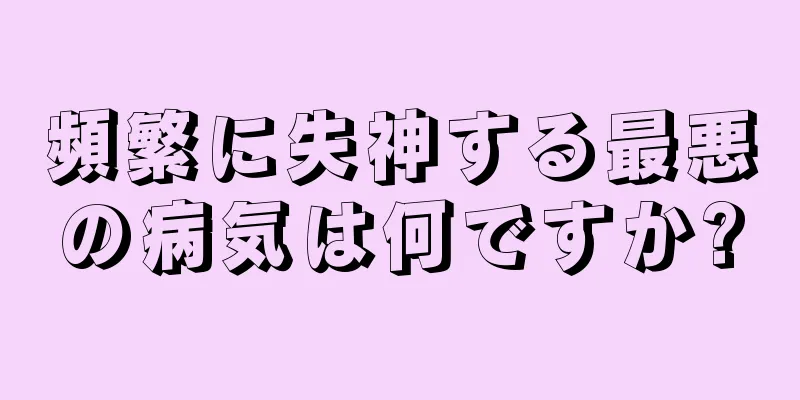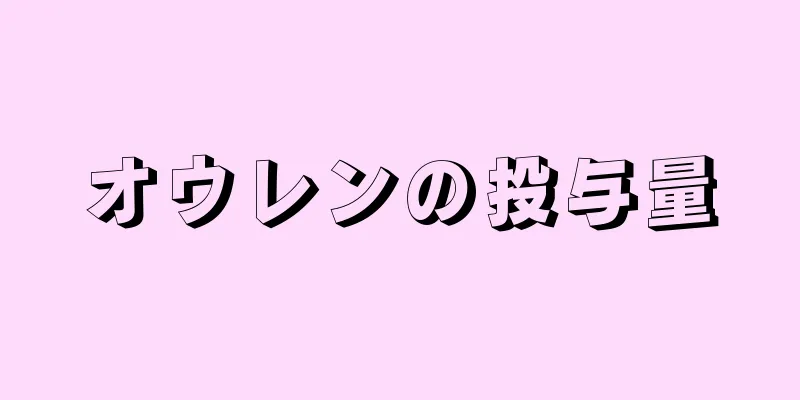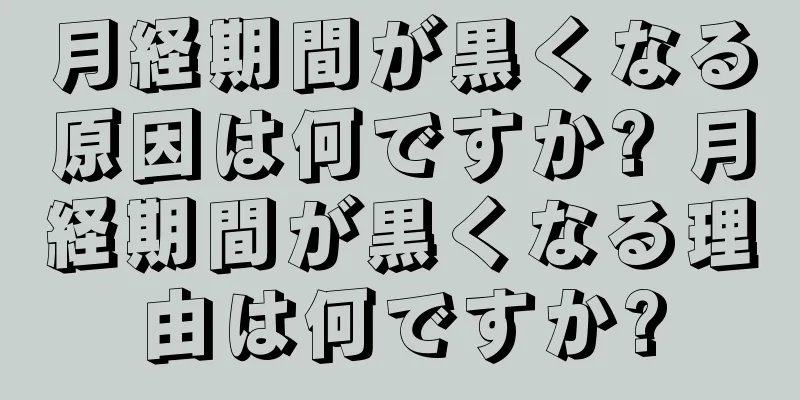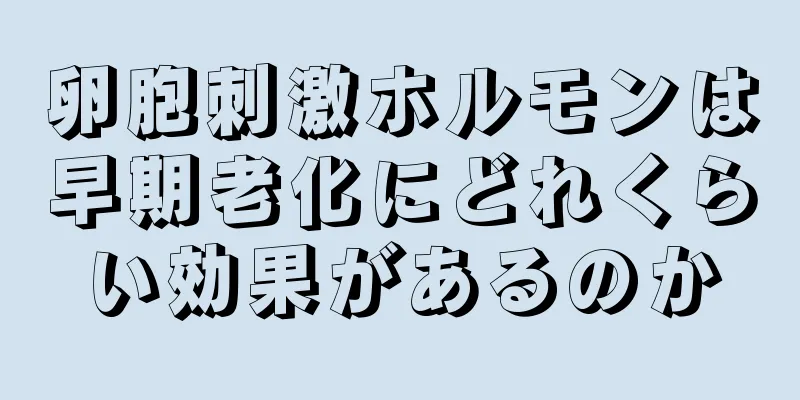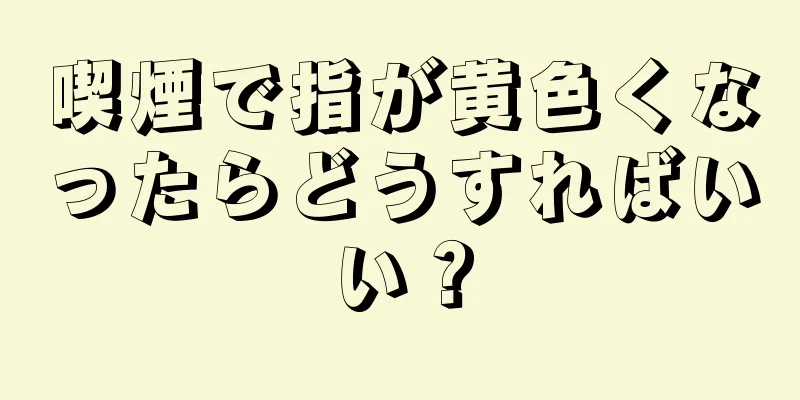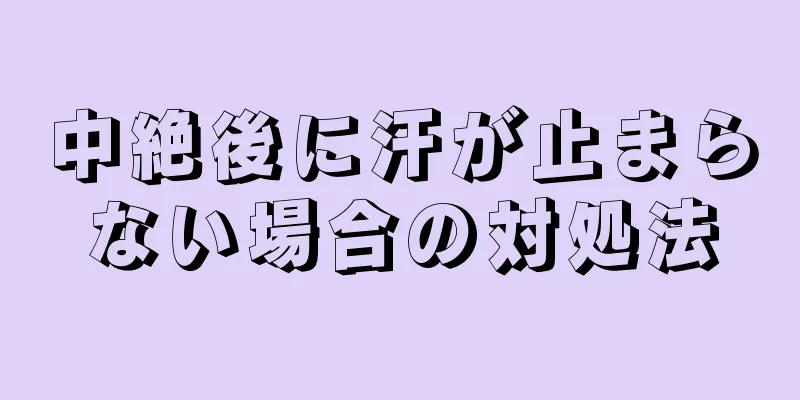お灸で湿気は取れますか?
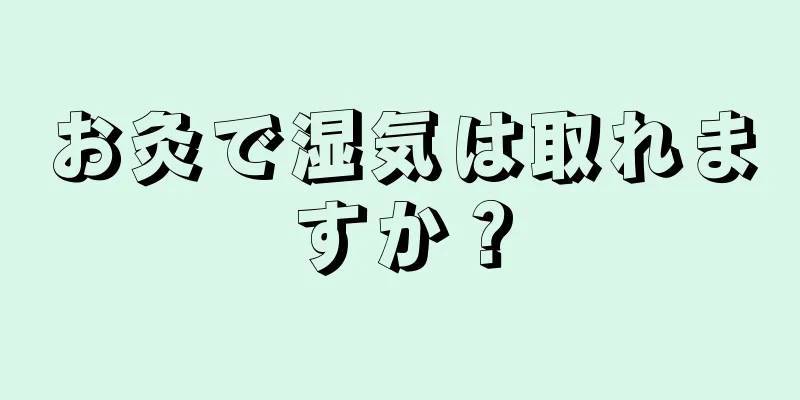
|
灸は我が国において2000年以上の歴史があり、数多くの臨床実践により、灸が夢精の治療や健康維持に効果があることが確認されています。お灸は身体に局所的な刺激を与え、温熱刺激によって皮膚の毛細血管を拡張し、皮膚の局所的なうっ血を引き起こし、リンパの循環と血液の循環を促進し、水分を除去する役割を果たします。 身体が湿っているかどうかの判断方法:髪が脂っぽい、顔がテカっている、寝ているときによだれを垂らしている(水分が飽和して流れ出ている)、便が粘ついて(簡単に流せない)、排便が多い、お腹が大きい、耳が湿っている(耳たぶが湿っている)、性器が湿っている。湿気は人体にとって非常に有害な邪気であると言えます。伝統的な中国医学では、人体には「風、寒、暑、湿、乾、火」という6つの病因があると考えられています。そのうち、湿は、リウマチ、寒湿、夏湿、乾湿、湿熱など、他の5つと組み合わされることがあります。そのため、体内に湿気が溜まると健康に影響を及ぼします。 除湿のためのツボ灸:伝統的な中国医学で最もユニークな治療法はツボ療法です。ツボを押すことも湿気の対処に一定の役割を果たします。程山経穴、玉府経穴、三陰交経穴を定期的に押すと、脾臓と胃が強化され、体内の水分を運び出すのにも役立ちます。広西中医薬大学付属第一病院仁愛分院中医学治療室の副主任である梁永秀氏は、指圧に加えて灸も使用できると提案した。お灸をするときは、火をつけたもぐさを皮膚から2~3cm上に垂らして煙を吸い、ツボを温めて赤くします。1回に20分以上お灸をするのが最適です。 実はお灸には多くの働きがあり、水分を取り除くだけでなく、経絡を調整することもできます。経絡理論は伝統的な中国医学における重要な理論であり、私たちの体全体が経絡によってつながっており、さまざまな臓器の機能を調節していると信じられています。お灸は経絡を浚渫し、身体の働きをスムーズにし、健康管理や健康維持の効果をもたらします。 |
推薦する
顎の下のリンパ節が腫れる原因は何ですか?
顎のリンパ節が大きくなると、体の健康に影響が出るのではないかと非常に心配になります。実際、リンパ節は...
細胞のマイコプラズマ汚染とはどういう意味ですか?
マイコプラズマ汚染細胞とは、細菌培養の過程でマイコプラズマ感染や汚染が発生する状況を指します。これは...
月経10日目には卵胞はどのくらいの大きさになっているはずですか?
排卵は女性の月経周期ごとに起こりますが、これは将来の正常な妊娠を保証する特徴でもあります。一般的に、...
耳の後ろにしこりがある
耳をよく見ると、裏側に小さな突起がたくさんあることに気がつきます。それを手で押すと、膿が出てくる可能...
腕が弱くなり、手が震える原因となる病気は何ですか?
スポーツや肉体労働で体力を使い果たしてしまうと、全身が弱ってしまい、歩くことさえ困難になります。この...
子供の鼻のかゆみを治療するためのヒントは何ですか?
春の到来とともに、鼻炎の発生率も増加します。この時期は、特に子供は花粉やカビアレルギーに最もかかりや...
腰に赤いぶつぶつができ、かゆみがある
敏感肌の人は、体に小さな赤いぶつぶつができやすいです。腰に赤いぶつぶつができ、かゆみがある場合は、皮...
大きなハートの影はどうしたの?
心臓影は通常、X 線検査で検出されます。心臓影とは、心臓の大きさが正常よりも大きいことを指します。心...
漢方薬を服用中の食事上のタブーは何ですか?
私たちは皆、日常生活で漢方薬を服用しています。漢方薬はさまざまな病気を治療できますが、漢方薬を服用す...
ヨモギ水で顔を洗っても大丈夫でしょうか?
ヨモギは一般的な漢方薬です。体の治療と維持に一定の役割を果たします。ヨモギ水で顔を洗うと、経絡を温め...
叔母はビタミンCを摂取してもいいでしょうか?
女性にとって、月経中の食事は非常に重要です。良い食事は月経困難症を予防し、腹痛を和らげ、月経をスムー...
破傷風の予防接種にアレルギーがある場合はどうすればいいですか?漢方と西洋医学による治療法の完全なリスト
誤って何かにぶつかって皮膚が破れて出血した場合、傷口が感染して悪化するのを防ぐために破傷風の予防接種...
尿失禁の原因は何ですか?
男性の体の抵抗力は女性よりも高いため、男性は基本的に病気になりにくいです。風邪や発熱もめったに起こり...
月経中は母乳の量が減りますか?
母乳育児は多くの家庭にとって第一選択であり、母乳の質や量は母親の体によって変化するため、母親の体調は...
不眠症の最良の治療法
不眠症は、現在多くの人が抱えている現象であり、特に一部のオフィスワーカーは不眠症の問題を抱えています...