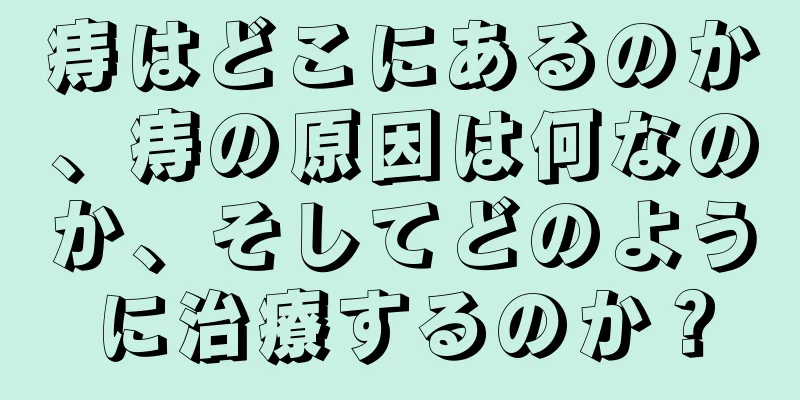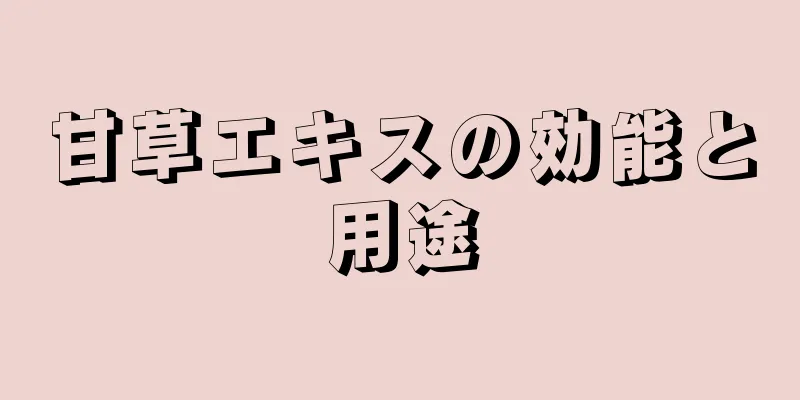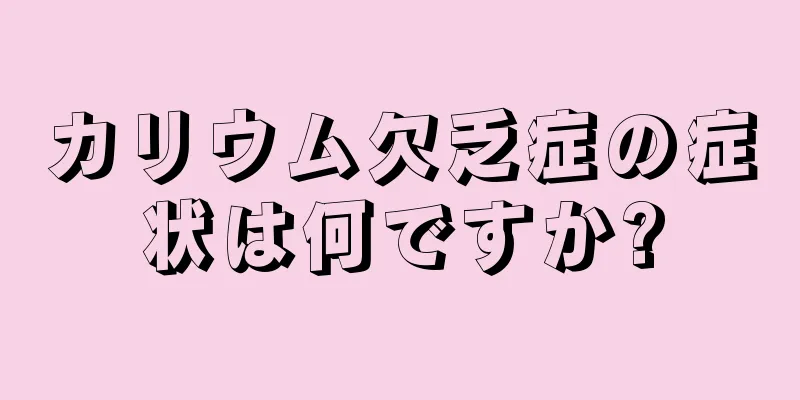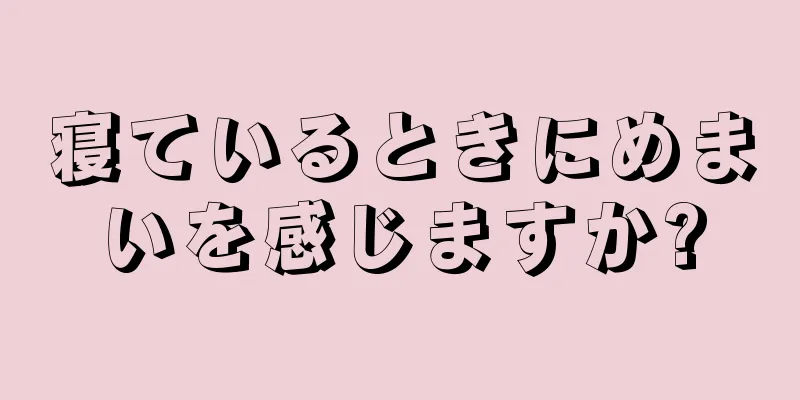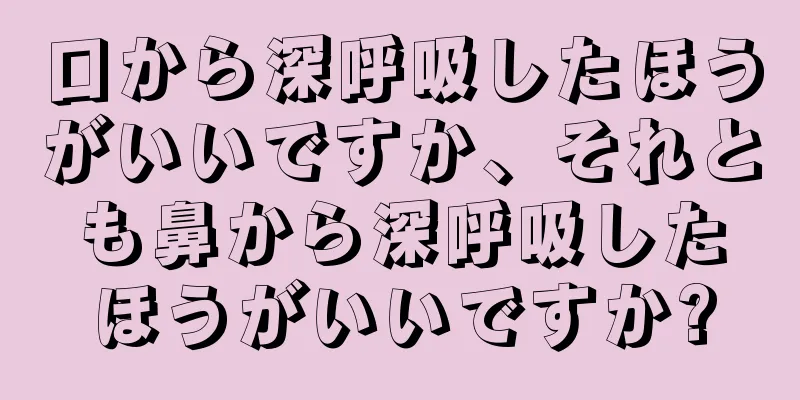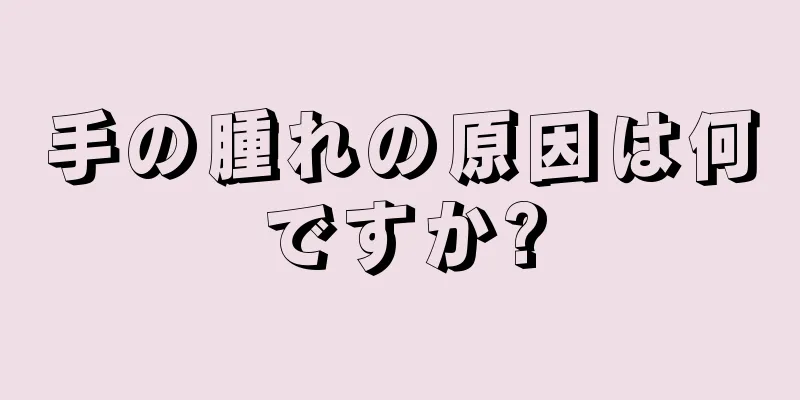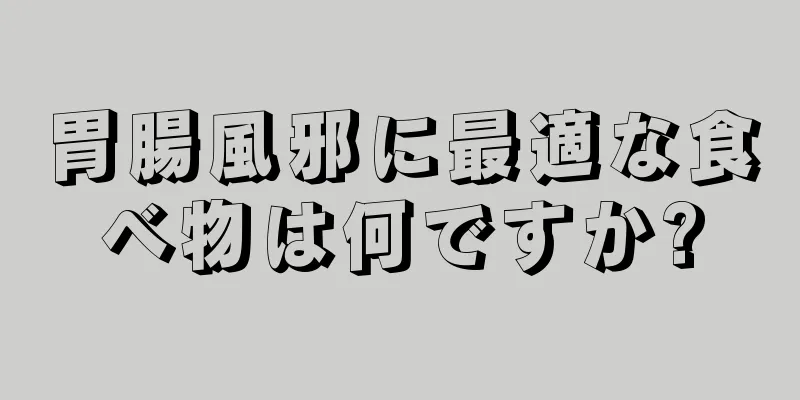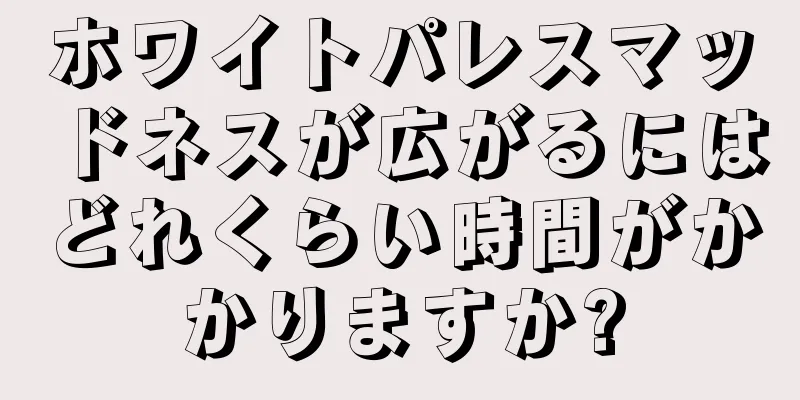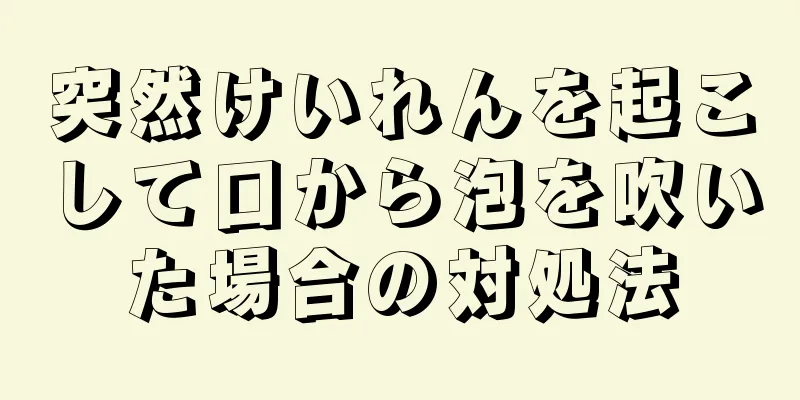オウレンの投与量
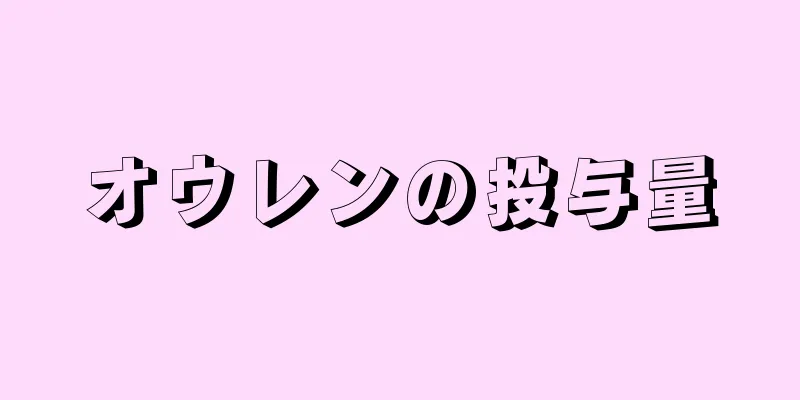
|
黄連は比較的一般的な薬材で、湿熱や落ち着きのなさを治療し、心火や嘔吐を取り除く効果もあります。しかし、黄連の摂取量には注意しなければならず、さもないと健康に影響を及ぼします。黄連の1日の摂取量は5gを超えないようにしてください。摂取方法は水で煮て飲むことです。胃の火や湿疹を取り除くのに非常に効果的です。黄連の注意事項について知ることができます。 オウレンの用途: 1.湿熱膨満、嘔吐、胃酸逆流。特に中火の熱を清めるのに優れています。紫蘇の葉と黄連の煎じ液など、紫蘇の葉と一緒に、湿熱が中火を塞ぎ気の流れが悪くなることで起こる腹部膨満、吐き気、嘔吐の治療によく使われます。または、Scutellaria baicalensis、乾燥ショウガ、Pinellia ternataと組み合わせて半夏希心煎じ薬として使用することもできます。石膏と組み合わせると、十連散のように胃熱や嘔吐を治療することができます。 2.湿熱性下痢。本剤は下痢の治療に重要な薬であり、単独で使用しても効果的です。 3. 血熱による高熱、昏睡、落ち着きのなさ、不眠、嘔吐、鼻血。特に心経の過剰な火を消すのに効果的です。心火過剰による昏睡や落ち着きのなさの治療に使用できます。 4. うどんこ病、せつ、目の充血、歯痛 5. 喉の渇きを治し、胃火を清めるのに使えます。胃火が多すぎることによる喉の渇き、食べ物を消化できないこと、空腹感を和らげることに使えます。よく、茯苓と一緒に小客丸として使われます。 6. 湿疹、湿疹、外耳道膿瘍の外用治療。軟膏を外用して皮膚湿疹や湿疹を治療します。汁を取って患部に塗り、外耳道の膿を治療します。煎じ液を目に滴下すると、赤くなったり腫れたりした目を治療することができます。 オウレンの使用法と投与量 1日の摂取量:2~5g。外用の場合は、適量を水で煎じて塗布するか、外用する場合は粉末にして外用してください。 オウレンの副作用 漢方薬の成分は複雑で、薬理作用はさらに複雑であり、現在の技術レベルでは黄連の副作用を正確に説明することはできません。しかし、一つ確かなのは、副作用がほとんどないということです。 オウレンは非常に苦くて冷たいので、過剰に摂取したり、長期間摂取したりすると脾臓や胃にダメージを与えやすく、下痢を引き起こし、胃腸機能に影響を与え、食欲を低下させて消化不良を引き起こします。体内に実際に熱がある場合を除いて、注意して使用してください。 オウレンには清熱、解毒、抗炎症の作用があり、大腸菌を抑制する効果もあります。水に浸して飲むこともできますが、脾臓や胃が弱い人には適していません。苦くて乾燥しており、体液を傷つける可能性があります。陰虚や体液損傷の人は、苦くて冷たいので注意して使用する必要があります。 一般的に、病気が治った後、薬を長期間服用することはお勧めできません。食後に服用するのが最善です。オウレンの投与量は、軽度の病気の場合は1日2〜3グラム、重度の病気の場合は1日5〜6グラムです。子供は脾臓や胃の機能が不完全であるため、黄連を盲目的に摂取すべきではありません。 |
推薦する
アスファルトが高い理由
高アスパラギン酸は主にアラニンアミノトランスフェラーゼの高値を指し、臨床現場でよく見られる症状です。...
変形性関節症に効く食べ物
変形性関節症は骨関節疾患、変形性関節症などとも呼ばれます。変形性関節症は一般的に2種類に分けられ、1...
午後になると顔が熱くなり赤くなります
日常生活では、すぐに顔が赤くなる人がいるはずです。緊張すると血流が促進され、顔が赤く熱くなります。こ...
カニが手を挟むとなぜ出血するのでしょうか?
生活の中で、カニを食べるのが特に好きな人はたくさんいます。市場にカニが大量に出回っているときは、買っ...
生後3~4ヶ月の赤ちゃんが下痢をした場合、どうすればいいでしょうか?
新生児は体質が比較的弱いため、大人による特別なケアが必要です。それにもかかわらず、非常に幼い年齢で予...
熱中症で腹痛になったらどうすればいいですか?
暑い夏は気温が非常に高く、長時間屋外で日光を浴びていると熱中症になりやすい人もいます。熱中症になると...
漢方薬はどれくらい煮沸すればいいのでしょうか?
漢方薬のほとんどは煎じ薬として使われており、薬の煎じ方は科学です。漢方薬の袋を持っている人は多くいま...
女性が口臭になる理由は何でしょうか?
口臭は多くの人が悩まされる問題です。一度口臭がきつくなってしまうと、歯磨きをしてもガムを噛んでも、完...
生姜水を飲むとどんな効果があるのでしょうか?
生姜は私たちの生活に欠かせない調味料です。料理を美味しくするだけでなく、生姜は漢方治療にも大きな役割...
子供の鼻のかゆみを治療するためのヒントは何ですか?
春の到来とともに、鼻炎の発生率も増加します。この時期は、特に子供は花粉やカビアレルギーに最もかかりや...
生理が1ヶ月遅れていて、まだ来ません。理由は何でしょうか?
月経は、すべての女性が毎月経験する生理現象です。月経の長さは、女性が健康であるかどうかを判断するのに...
ヘルペス性咽頭炎の症状は何ですか?またどのように治療しますか?
ヘルペス性咽頭炎は、幼児期によく見られます。通常の咽頭炎よりも症状が重く、伝染性があります。幼稚園や...
心膜上陥凹液の原因
心嚢に隠れた浸出液は心臓機能に問題があることを示し、この問題の主な原因は感染です。もちろん、心不全や...
最近、体がだるくて眠いです
多くの場合、私たちの体は弱っているように感じたり、常に眠いと感じることがあります。一般的に言えば、こ...
お腹が痛い、何が起こっているの?
胃痛は一般的に腹部の痛みを指します。腹痛と同時に胃痛が起こる場合、最も可能性が高いのは胃の不調、つま...