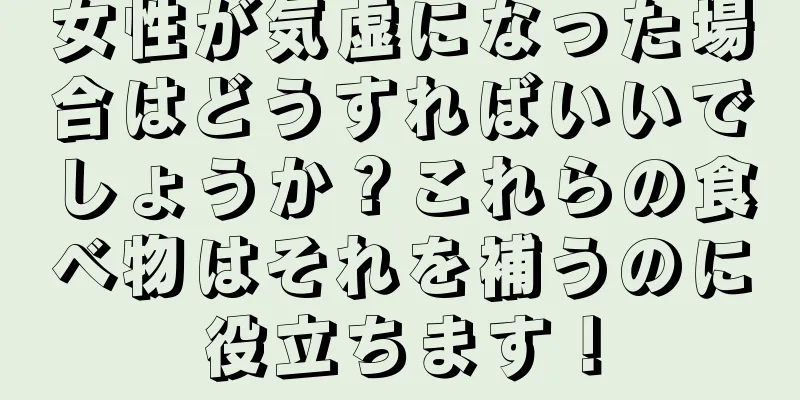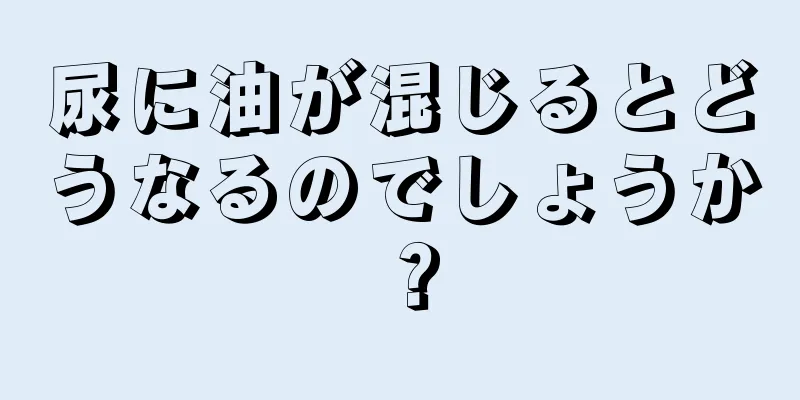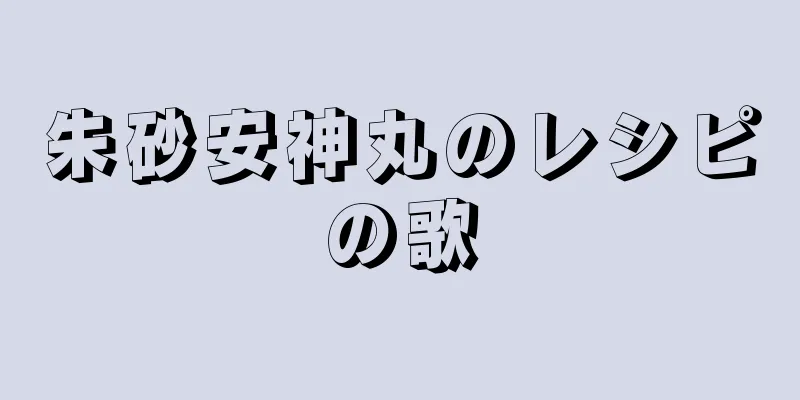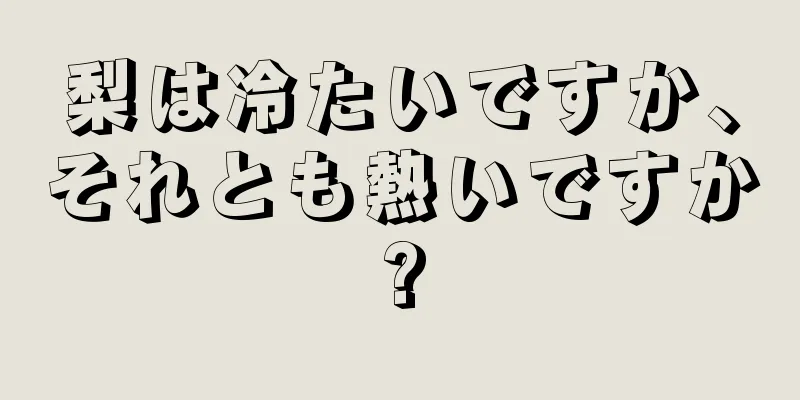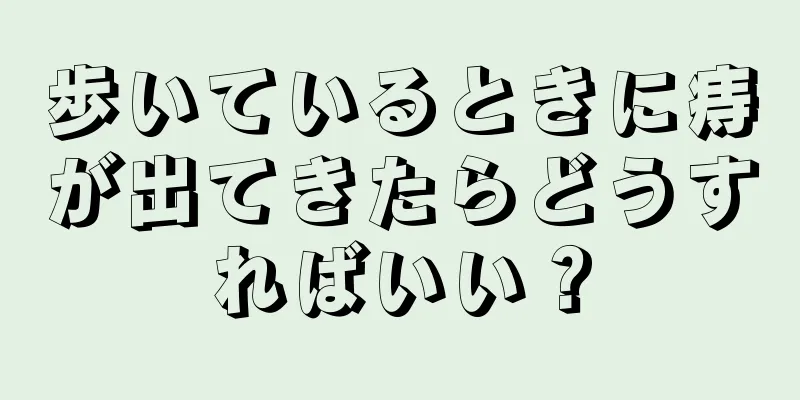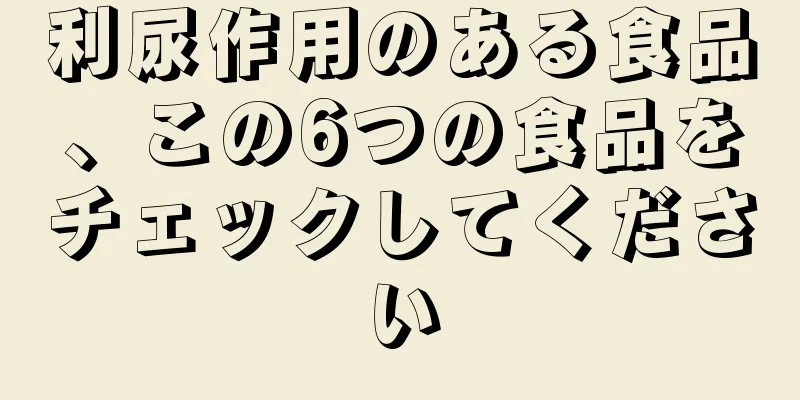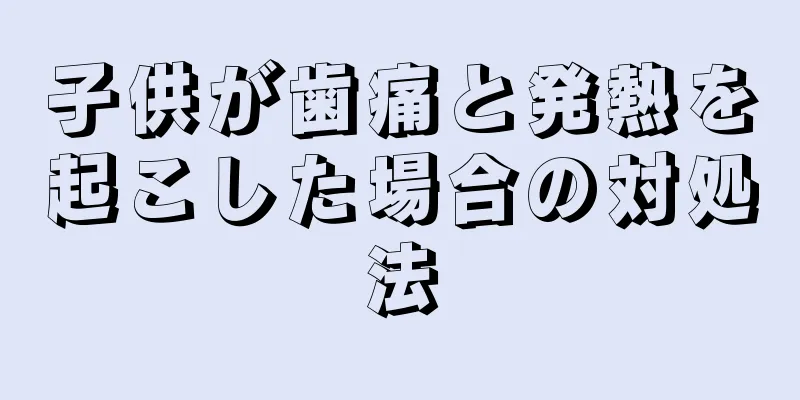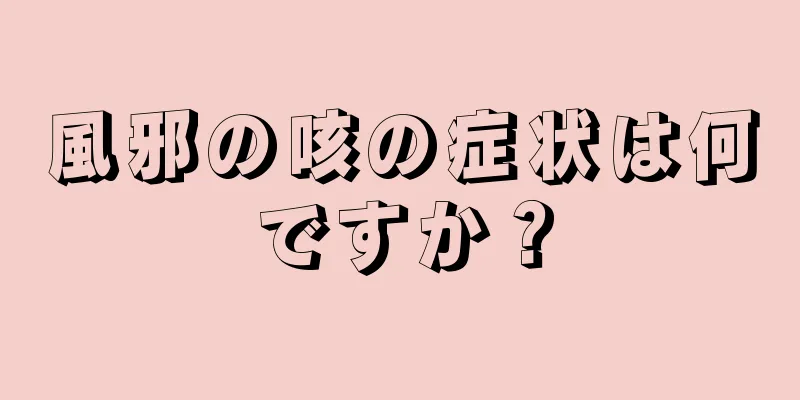ワイン作りに適した薬用原料は何ですか?
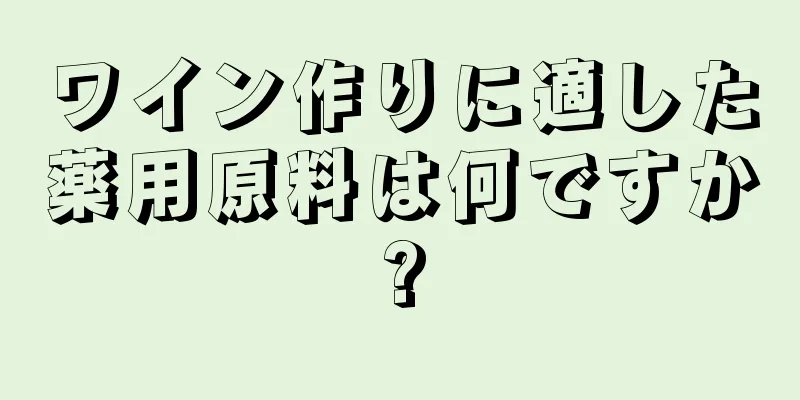
|
多くの人は家に薬酒を一瓶持っています。薬酒は主に中国の薬用原料から作られているため、人体の健康に良い効果を発揮します。ワインを作るための漢方薬の原料を選ぶ際には、人々のグループごとに異なる漢方薬の原料を選ぶ必要があります。漢方薬の原料は種類によって異なるため、そこから作られた薬酒には異なる薬理効果があります。ワイン造りに最適な漢方薬は何ですか? ワインを作るのにどんな薬用原料が使われますか?ワインを作るのによく使われる薬用原料 (1)アシカ鞭 アシカ鞭は、腎臓を養い、陽を強める効果があり、身体に非常に優れた強壮効果を持つ一般的な漢方薬です。 (2)地黄は私たちの日常生活にとても馴染みのある漢方薬です。地黄は陰を滋養し、血を補う効果があり、摂取すると血を滋養し、陰を滋養する働きがあり、腎虚や精液過多に良い治療効果があります。 (3)鹿のペニス 鹿のペニスも腎臓と陽を強化する一般的な漢方薬であり、服用後は腰と膝を強化する効果があり、腎臓の陽に優れた強壮効果もあります。難聴、夢精、早漏、頻尿などの症状がある場合は、鹿のペニスを摂取するとすぐに回復します。 (4)朮 朮は、潤いを与え、脾臓を補い、中枢を調和させる作用があります。食欲不振、腹部の膨満や浮腫、黄疸、めまいや寝汗などの症状がある場合、この生薬を服用すると回復に役立ちます。また、オオバコは妊娠中の女性にも非常に効果的で、摂取後は胎児を安定させる効果もあります。 (5)ヤムイモ ヤムイモは一般的な食材であるだけでなく、健康に有益な伝統的な漢方薬でもあります。昔の中国の医師は、これを摂取すると脾臓、胃、腎臓、肺を保護し、体力の低下を治療するのに非常に効果的だと言いました。 (6)高麗人参 高麗人参は貴重な強壮剤であり、体の失われた活力を効果的に補充し、体の基礎を強化する効果があり、さらに知能を向上させることもできるので一石二鳥です。 (7)クコの実 クコの実には、腎臓を養い、肝臓を維持する効果があり、摂取すると腎臓を強化し、陽を強化する役割を果たし、熱を取り除き、視力を改善する効果もあります。 |
推薦する
神経を落ち着かせるには、ナツメヤシとナツメヤシの種子のどちらが良いでしょうか?
仕事での大きなプレッシャーのせいか、あるいは最近の機嫌の悪さのせいか、要するに、夜なかなか寝付けず、...
黒クコの実を食べられない人はいますか?
黒クコの実は、その名前の通り、実は黒いクコの実を指します。この黒クコの実は、私たちが日常よく食べてい...
左金丸の成分
左金丸は一般的な中国の特許薬であり、主に黄連と茯苓から構成され、肝火を鎮め、胃腸を調和させる効果があ...
血液循環を促進し、血液の停滞を取り除く最も強力な漢方薬
血行促進、瘀血除去は、伝統的な中国医学の専門用語です。血行促進、瘀血除去ができる漢方薬とは、摂取する...
桑の葉でそばかすは消えますか?
桑の木は比較的一般的な木です。桑の実はそのまま食べられるだけでなく、桑の葉も漢方薬として利用でき、乾...
薬物による中絶後にエアコンを使用できますか?
薬による中絶後、女性は健康にもっと気を配る必要があります。夏であればエアコンを使うこともできますが、...
顔の赤みを抑える食事療法
女性の友人の場合、顔が赤くなったら注意が必要です。特に更年期の女性は、このような症状を起こしやすいで...
高齢者の涙管が詰まったらどうすればいいか
高齢者の涙管が詰まる主な原因は、眼器官が退化し始め、涙管狭窄の症状を引き起こす可能性があることです。...
髄芽腫は治癒できますか?
髄芽腫は一般的な腫瘍で、子供の脳疾患によく見られます。悪性神経膠腫です。髄芽腫は非常に原始的な無極性...
腰椎椎間板ヘルニアの治療に温熱療法は使えますか?
腰椎椎間板ヘルニアは、ますます一般的な腰椎疾患になっています。人生において、誰もができるだけ早く腰椎...
出血が少なく胎嚢も出ない中絶
薬物による中絶を受ける妊婦は、胎嚢が排出されるかどうかに注意する必要があります。なぜなら、胎嚢が排出...
子どもの高熱が続く
データによると、子供一人当たり年間4~6回高熱が出る可能性があるそうです。発熱は正常な生理現象です。...
頭の中でブンブンという音がする
頭の中で電気がパチパチと鳴る音は、脳への血液供給不足または頸椎症が原因である可能性が高いです。そこで...
ニキビと真珠の違い
性器イボと真珠様発疹は全く異なる病気なので、発症後は合併症や体への影響を避けるために慎重に判断しなけ...
食道火傷を治療するには?
食道火傷は過熱した食べ物によって引き起こされます。人体が耐えられる食品の最高温度は50〜60℃です。...