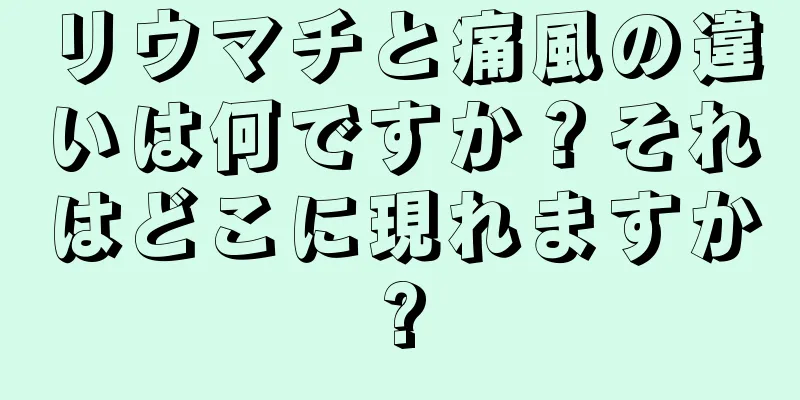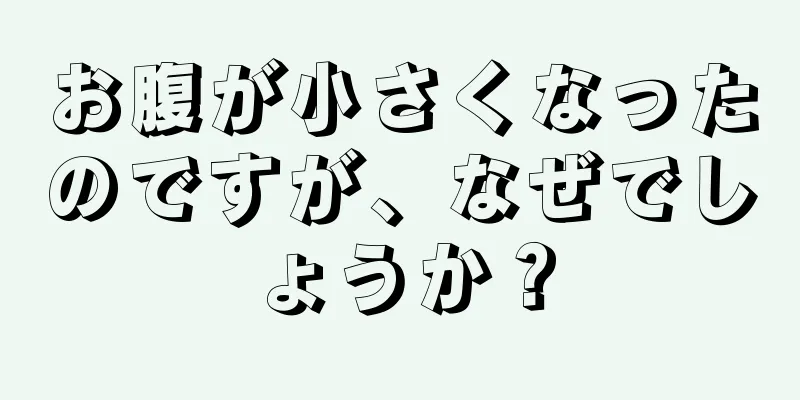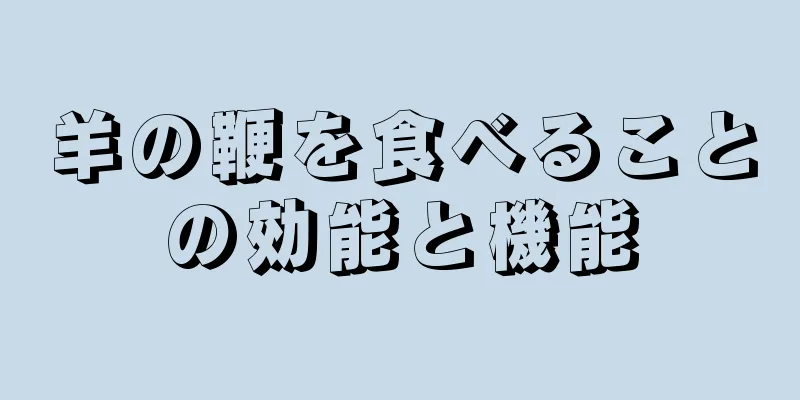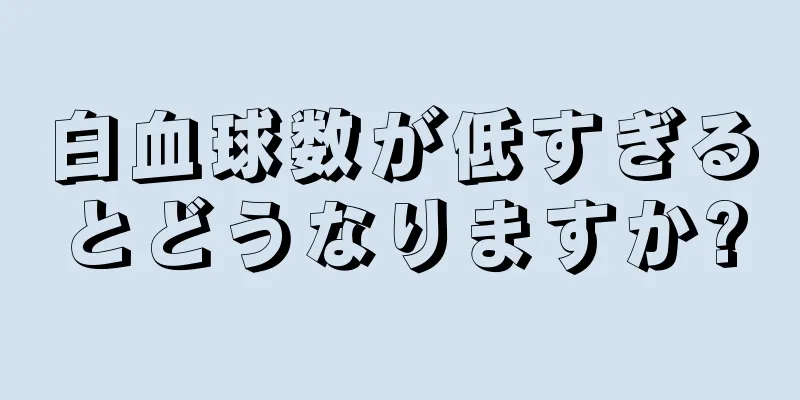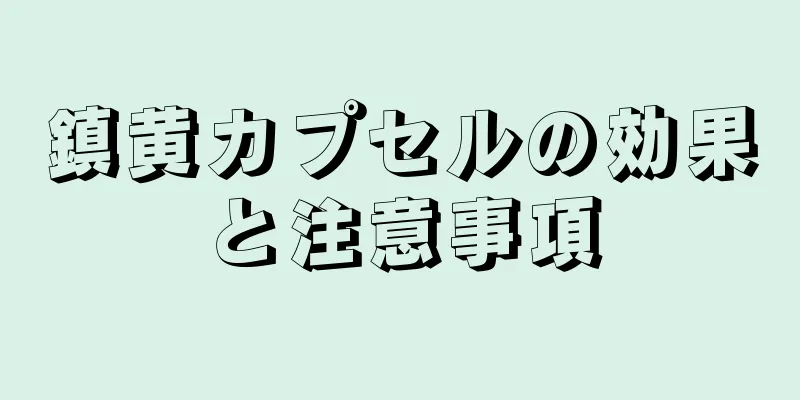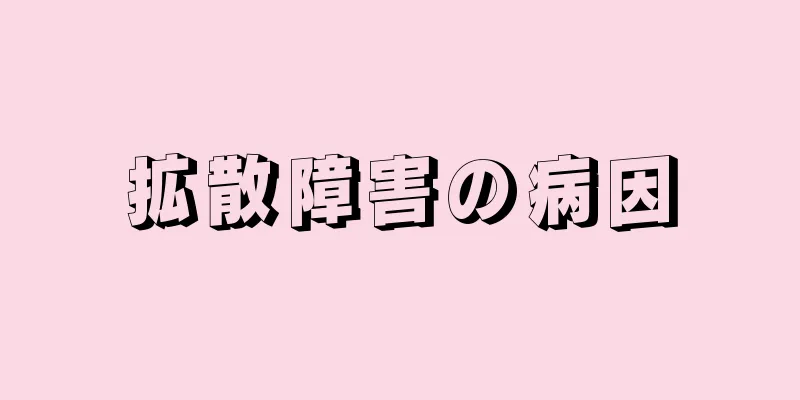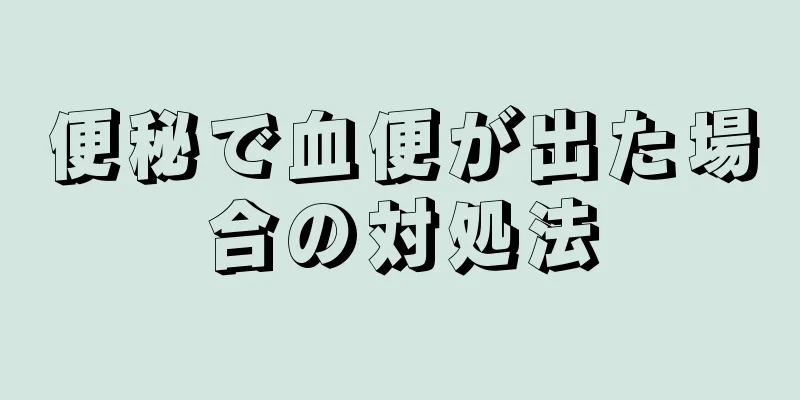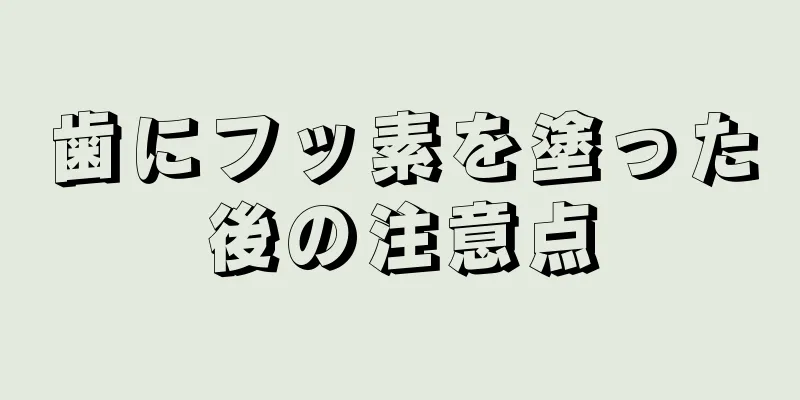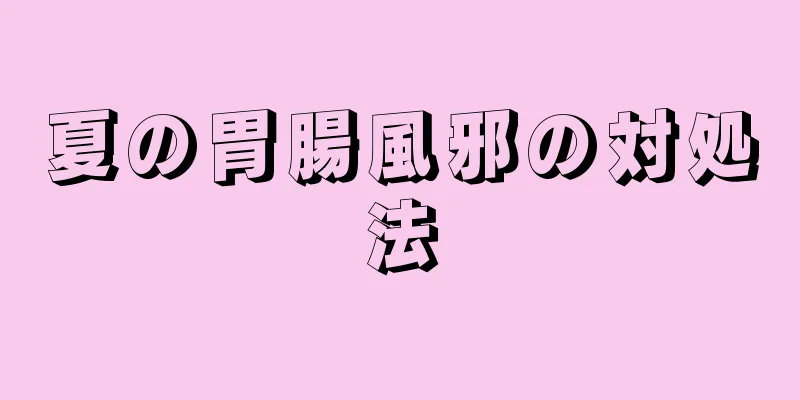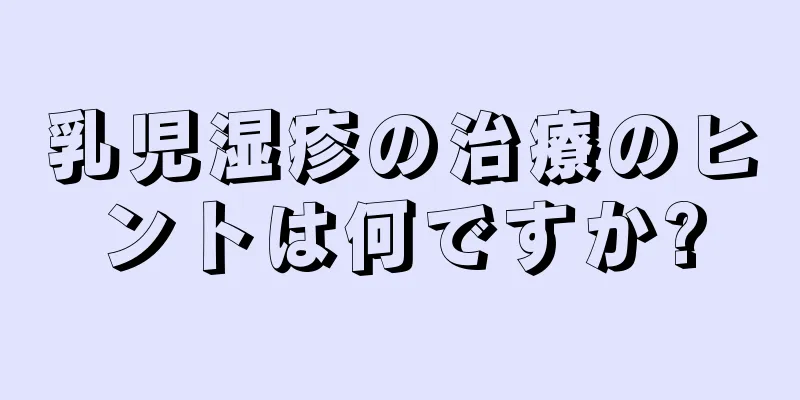高密度肺影とはどういう意味ですか?
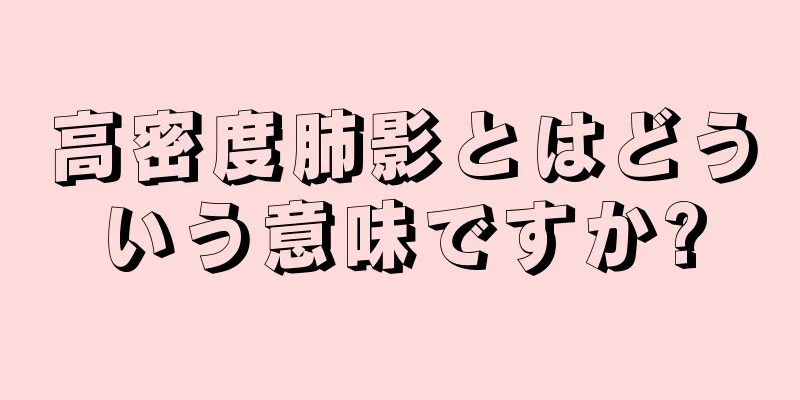
|
人々は人生の中で多くの病気に遭遇し、多くの病気が人々の通常の仕事や生活に影響を及ぼします。腹部の高密度の影はよくある病気です。レントゲン写真で肺の影の部分に高密度領域が見つかった場合、これを高濃度肺影と呼び、CTや胸部レントゲン写真では腫瘤や結節として現れることが多いです。では、高濃度肺影とはどのような意味なのでしょうか? まず、高密度肺影とはどういう意味でしょうか?肺影とは、通常、透視検査中に肺実質に高密度領域が発見されることを指し、胸部X線やCTスキャンでは腫瘤や結節として現れることが多いです。腫瘤の一般的な基準は直径4cm以上であり、結節は通常、直径3cm未満を指します。肺の腫瘤であろうと結節であろうと、最も一般的な原因は結核、感染症、腫瘍です。どちらにしても、多くの医師は抗炎症治療後の経過観察を推奨しています。これにより、結核や腫瘍患者、特に腫瘍の診断と治療が遅れる可能性があります。抗炎症治療では、腫瘍の周囲にさまざまな程度の炎症があるため、腫瘍の表面が縮小する可能性がありますが、結核の場合は治療期間が長引いたり、手術が必要になるなどの深刻な結果につながる可能性があります。したがって、肺に影が見られる限り、診断に基づいて適切かつ効果的な治療法を決定するために、さらなる診断が必要です。診断できない場合は、それを除外する方法を見つけなければなりません。中間の道はありません。 第二に、肺の影は必ずしも病気が重篤であることを意味するわけではありません。肺の影として現れる良性の病気も数多くあります。患者は肺の影を発見したら、過度に神経質になる必要はありませんが、積極的に専門医(胸部外科、呼吸器内科)に診てもらい、明確な診断を受ける必要があります。医師は患者の具体的な状況に応じて、胸部CT、ファイバー気管支鏡、CTガイド下穿刺、喀痰細胞検査など、他の補助検査方法を使用して、診断をさらに明確にします。診断が明確になると、医師は適切な治療計画を立てます。肺の影は肺がんと同じではありません。多くの病気が胸部X線写真でそのような症状を示す可能性があります。重要なのは、それらを明確に区別することです。一般的に、「肺の影」を引き起こす病気には主に3つの種類があります。 肺に高密度の影が現れるということはどういう意味ですか?上記の疾患のほかに、肺の先天性発育異常によっても肺の影が現れることがありますが、肺嚢胞、肺過誤腫、肺分画症など、一般的にはまれです。肺嚢胞は、主に男児や若い成人に発生します。胸部X線写真では、縁がはっきりした、単一または複数の丸い薄壁の影が見られます。嚢胞が気管支に繋がっている場合は、影の中に気液レベルが見られます。肺過誤腫の典型的な胸部X線写真は「ポップコーンパターン」です。肺分画症は肺の発達における先天異常です。肺の影は、鋭いエッジと均一な密度を持つ不規則な三角形、多角形、円、または楕円であることが多いです。このことから、多くの良性疾患も「肺の影」として現れる可能性があることがわかります。 「肺の影」がある場合は、胸部外科や呼吸器科を積極的に受診し、明確な診断を受ける必要があります。明確な診断があって初めて、正しい治療計画を立てることができます。 |
推薦する
脳挫傷の後遺症は何ですか?
人生においては、交通事故や高所からの転落などにより、身体の損傷、特に脳損傷が発生することがあります。...
頸椎症の人はどのように眠るのでしょうか?これらの事柄に注意を払ってください
通常、一日中疲れていた人は、ベッドに横になって休むと特にリラックスできるので、寝る姿勢はどのようなも...
四武堂とは何ですか?
四烏煎じは主に漢方薬に残された処方です。最も古い記録は主に宋代の処方箋にあります。主に地黄、白芍、当...
妊娠は7日以内に検出できますか?
女性は妊娠すると月経を経験しないので、妊娠しているかどうかを推測したい場合は、月経を境界として使用す...
喉や耳のかゆみの原因は何ですか?
喉や耳のかゆみは、体の炎症が原因である可能性があります。この症状に悩む友人は、体を適切に調整すること...
サラセミアの治療には食事療法が有効
貧血は比較的よく見られる症状であり、多くの人が人生の中で貧血に悩まされている可能性があります。貧血に...
高エコー頸動脈プラーク
頸動脈にプラークが現れる場合、一般的に人々は不安を感じます。頸動脈のプラークは、高齢者によく見られる...
女性の月経時の腰痛の原因は何ですか?
月経中の腰痛という現象は、日常生活でよく見られます。最も一般的な原因は女性の月経困難症で、腰痛や下腹...
妊娠初期に不安を感じたらどうすればいいか
妊娠初期には、これまでの3ヶ月間の経験から、流産を心配するかもしれません。特に、以前に流産の症状があ...
炎症がある場合、自然分娩は可能ですか?
多くの女性は結婚後に婦人科の炎症を患います。炎症が治っていない状態で妊娠した場合、炎症を抱えたまま自...
子供が頻繁に少量ずつ排尿する場合の対処法
排尿は人体の正常な代謝を促し、人体に不要な物質を排泄します。排尿に異常がある場合、特に頻尿や尿量が少...
肝気鬱滞の症状は何ですか?
伝統的な中国医学では、肝気は肝臓に存在します。肝気が正常であれば、肝臓は間違いなく健康です。肝気が異...
脂肪肝に効く食べ物
今では多くの人が脂肪肝を患っていますが、脂肪肝は独立した病気ではありません。肝硬変、脂肪性肝炎なども...
カテゴリー6の薬剤には熱湯を使用しないでください
沸騰したお湯で薬を飲むのは常識ですが、50~60℃以上のお湯で薬を飲むことを好む人もいます。一部の医...
漢方薬「鉄皮世傑」の効果とは
デンドロビウム・オフィシナールは私たちの日常生活でよく見かける植物です。健康野菜の一種で、漢方薬でも...