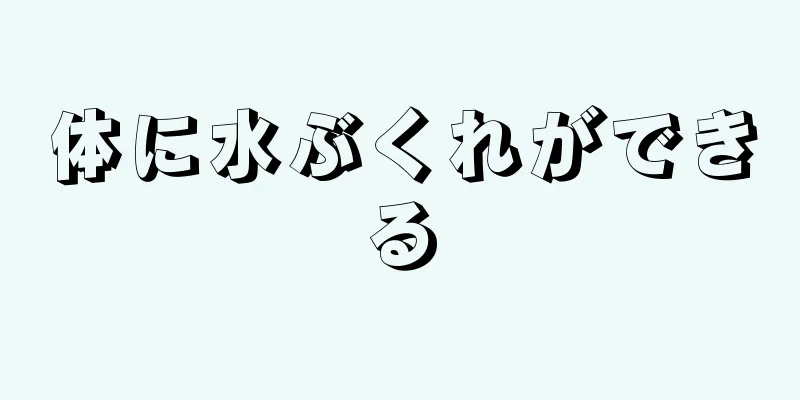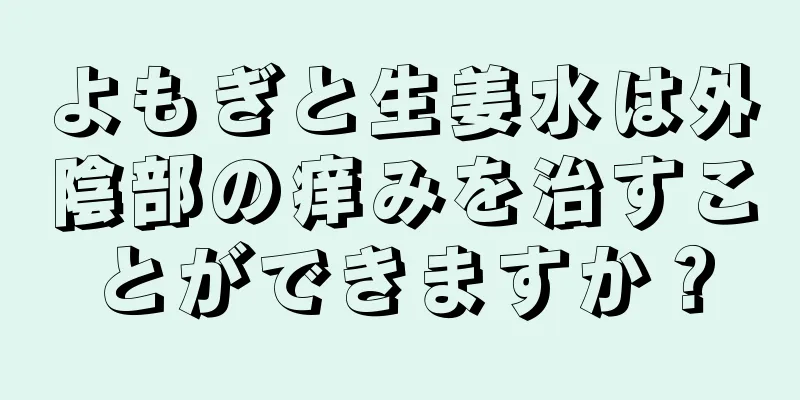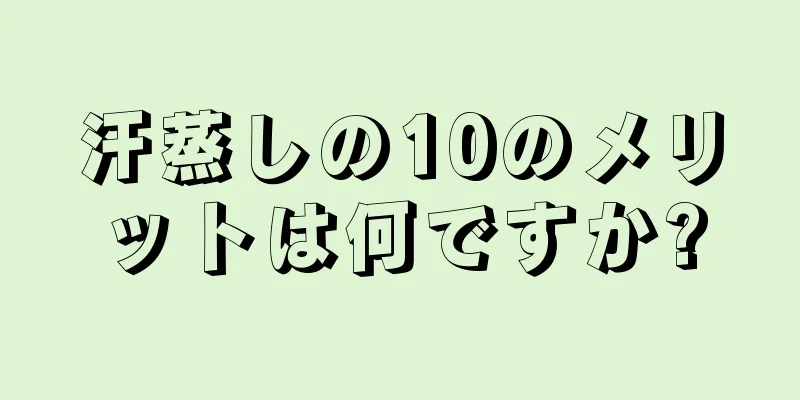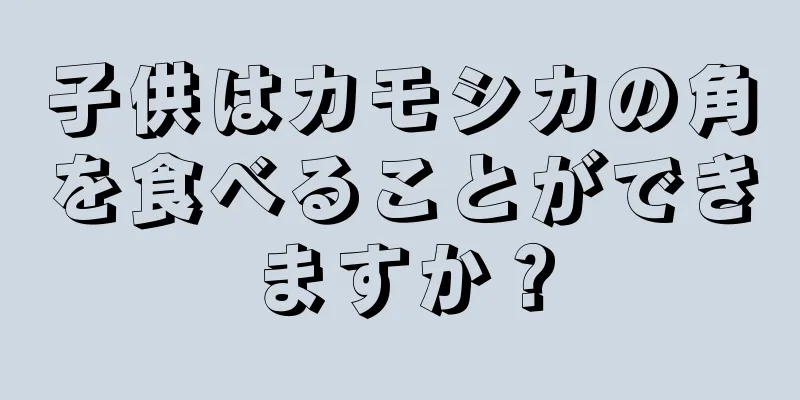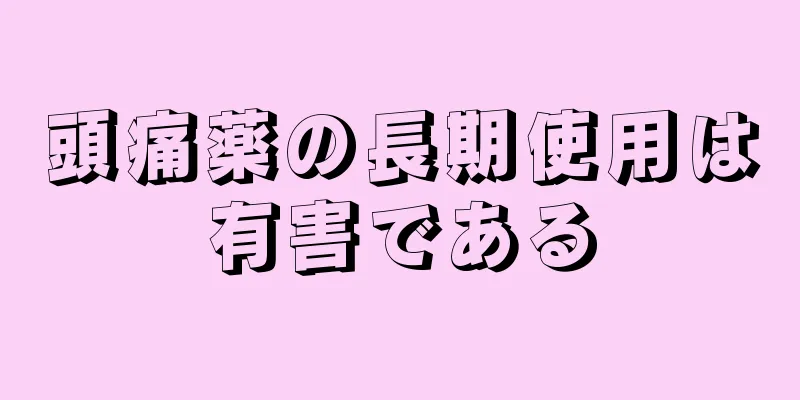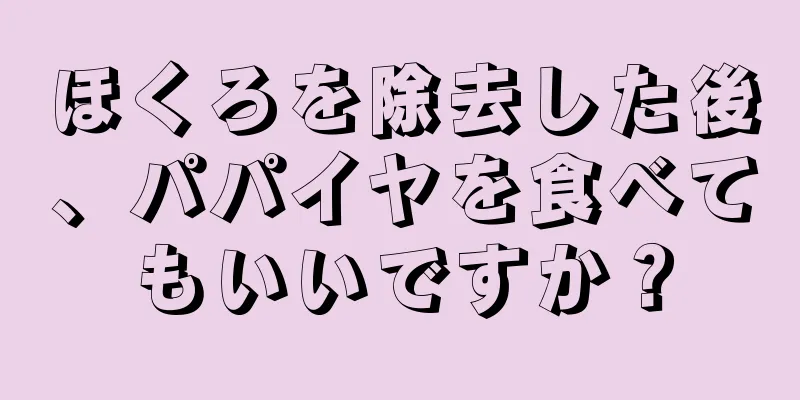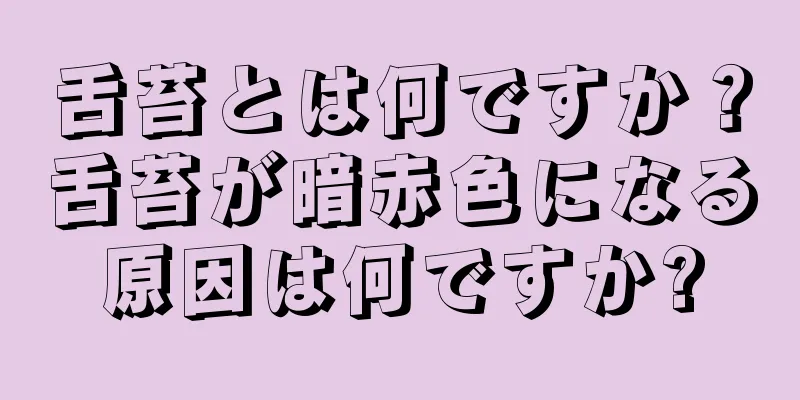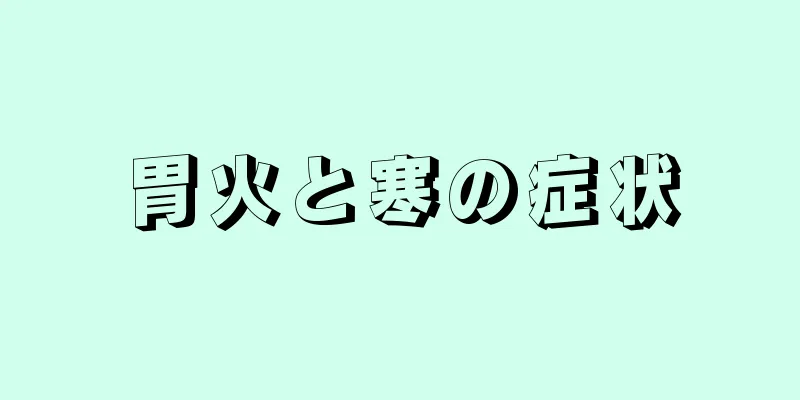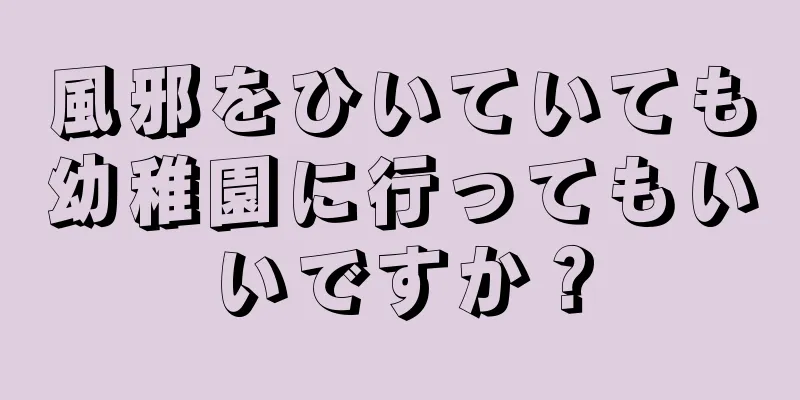風邪をひいて肺や気管が炎症を起こした場合はどうすればいいですか?どのように治療すればいいですか?
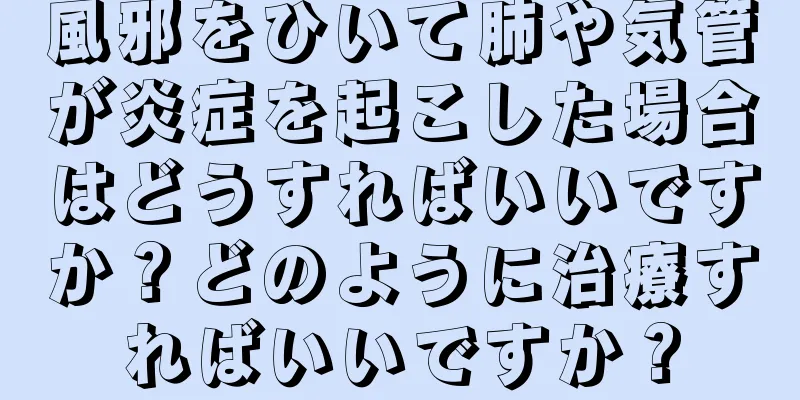
|
風邪は、人生において非常に一般的な感染症です。季節や時期、年齢を問わず発症する可能性があります。では、風邪が原因で気管炎になった場合はどうすればいいのでしょうか。 1. 感染の抑制: 細菌感染は、インフルエンザ菌、肺炎球菌、A 群連鎖球菌、ナイセリア菌によるものが一般的です。ペニシリンとキノロンは経口投与できます。重度の感染症の場合は、セファクロルまたはセフロキシムを経口投与できます。新世代のマクロライド系抗生物質も経口投与できます。抗菌治療の期間は一般的に7〜10日間です。症状が改善しない場合は、喀痰細菌培養感受性試験の結果に基づいて抗生物質を選択する必要があります。 2. 去痰・鎮咳:急性気管支炎、急性気管炎と同様。 3. 鎮痙・抗喘息:アミノフィリンおよびその徐放錠、β2受容体作動薬およびその徐放錠が治療に使用できます。発作性咳嗽は、多くの場合、さまざまな程度の気管支けいれんを伴います。気管支拡張薬を投与すると、症状が改善し、痰の排出が促進されます。 4. 喫煙をやめるか、煙による刺激を避けてください。 5. 体力を強化し、病気に対する抵抗力を高める:核カゼイン、トランスファーファクターなどを使用して、風邪や再発を減らすことができます。 6. 注射に用いられるワクチンは気管炎ワクチンで、通常は流行期前に開始し、週1回皮下注射します。投与量は0.1mlから開始し、毎回0.1~0.2mlずつ増加し、0.5~1.0mlが維持量となります。効果があれば1~2年は使用してください。核カゼイン注射液(麻疹ウイルスワクチンの培養液)は、1週間に2回、1回2~4mlを筋肉内または皮下に注射します。または、BCG注射液は、1週間に3回、1回1ml(BCG抽出物0.5mgを含む)を筋肉内に注射します。この薬は、病気の季節の前に使用し、風邪や慢性気管支炎の発生を減らすために3か月間継続して使用できます。バイオスティム(クレブシエラ・ニューモニエから抽出された糖タンパク質)は、最初の治療では 8 日間、2 mg/日を投与し、その後 3 週間投与を中止します。2 回目の治療では 8 日間、1 mg/日を投与し、その後 3 週間投与を中止します。3 回目の治療では 8 日間、1 mg/日を投与し、治療期間は 3 か月です。慢性再発性呼吸器感染症を予防できます。 7. 運動を強化して体質と病気への抵抗力を高める:運動を強化して体質を高めます。体調に合わせて、医療健康運動、太極拳、五琴戟などを選択できます。運動を続けると、体の病気への抵抗力を高めることができます。 上記の内容は、風邪気管炎の適切な治療法を紹介したものです。誰もがそこから何かを学べると信じています。皆さんがこの記事を注意深く読んでくれることを願っています。私たちにとって役立つと信じています。私たちも上記から学ぶことができます |
<<: 気虚と火過剰の症状は何ですか?気虚と火過剰の場合はどうすればいいですか?
>>: 交通性気胸とは何ですか?また、気胸の分類は何ですか?
推薦する
1歳の赤ちゃんはグルコン酸亜鉛経口液を飲んでも大丈夫ですか?
一般的に言えば、赤ちゃんが10か月以上であれば、どうしてもグルコン酸亜鉛経口液を服用する必要がある場...
喉の痛みを治す最も早い方法は何ですか?
理由もなく体がむくむのは、人生でよくある病気です。病気の原因は一般的には不明です。むくみは、明らかな...
ニキビに蒸しは効きますか?
ニキビは思春期の兆候であるため、多くの人がニキビの出現を避けることはできません。一部の人々は非常にオ...
なぜ真菌性膣炎になるのでしょうか?
真菌性膣炎は、カンジダ アルビカンスによって引き起こされる膣炎の一種です。カンジダは真菌の中でも一般...
濃い痰を吐くのは解毒作用ですか?
濃い痰を吐くことは、一定の解毒効果があります。日常生活では、風邪、気管支炎、喘息などの病気になると、...
お腹の脂肪吸引はできますか?
腹部の脂肪吸引も可能で、これも脂肪吸引の一般的な方法です。腹部は脂肪が最も蓄積しやすい場所です。特に...
月経量を増やす方法
女性の中には、月経期間中に月経血の量が少なく、痛みを感じる人もいます。月経血の量が少ない原因は、婦人...
初期の陣痛はどんな感じでしょうか?
陣痛は子宮の収縮であり、特に出産が迫っているときは、収縮がどんどん強くなり、胎児が生まれようとしてい...
化膿性脊椎炎の臨床症状
化膿性脊椎炎は主に血行性感染によって引き起こされます。このとき、細菌は血液を介して患部に到達し、患者...
昼寝後に体が弱くなったらどうすればいい?
昼寝をすると、全身がだるくなるという人もいます。昼寝をすることで元気になれると思っていたのに、意外に...
肝臓に斑点ができる病気とは
ご存知のとおり、肝臓は体内で最大の解毒器官ですが、肝臓には痛覚神経がないため、肝臓病を発見することが...
加湿器の正しい使い方は何ですか?
最近、屋内外を問わず空気の質はますます悪化しています。特に北部では、冬は空気がますます乾燥しており、...
パートリッジグラスの効果と禁忌は何ですか?
病気の時は、正しい薬を飲まなければなりません。そうしないと、多くの不必要なトラブルを引き起こします。...
走ると膝が痛くなるのはなぜですか?
ランニング中に膝に痛みを感じる人は多いでしょう。原因を理解するように注意する必要があります。ランニン...
肋軟骨炎
肋軟骨炎がどのような病気なのかを理解するには、まず肋軟骨がどこにあるかを知る必要があります。人体の両...