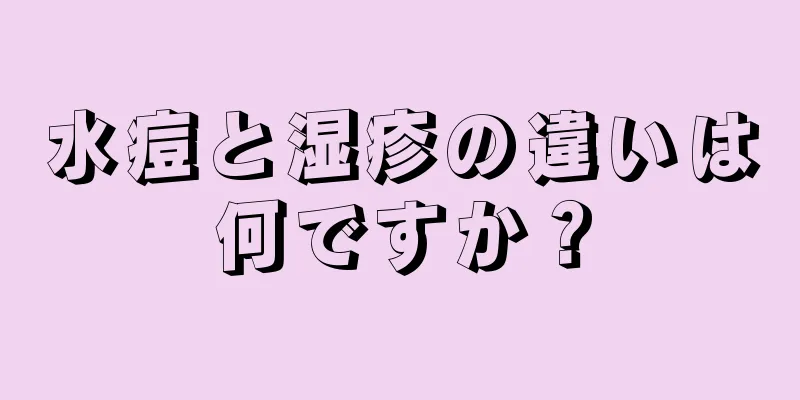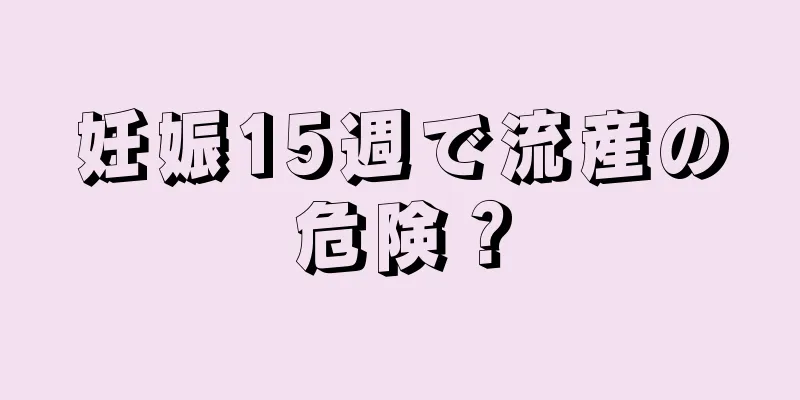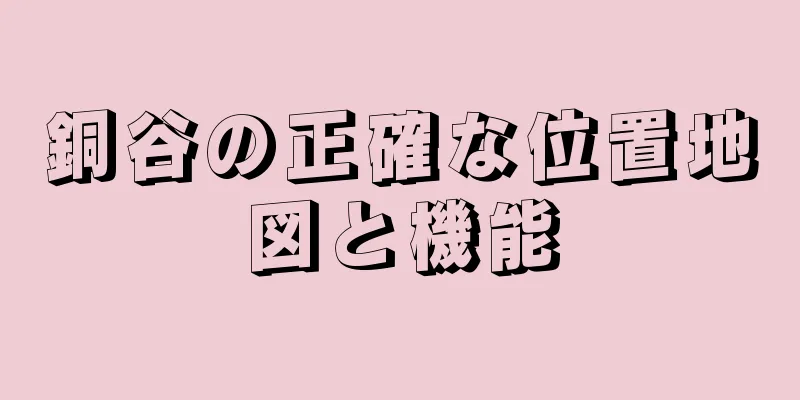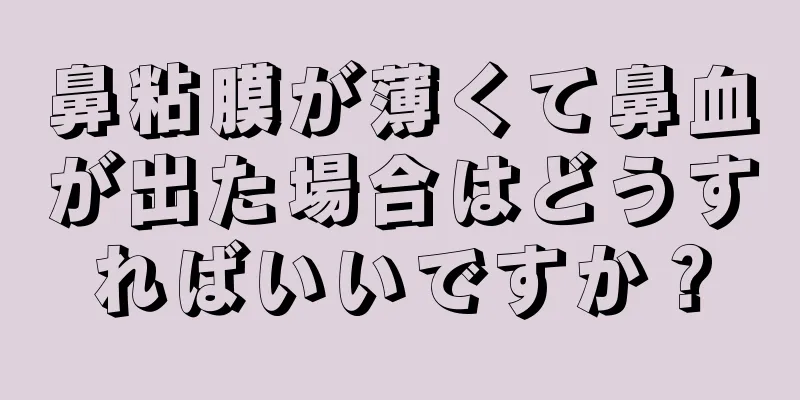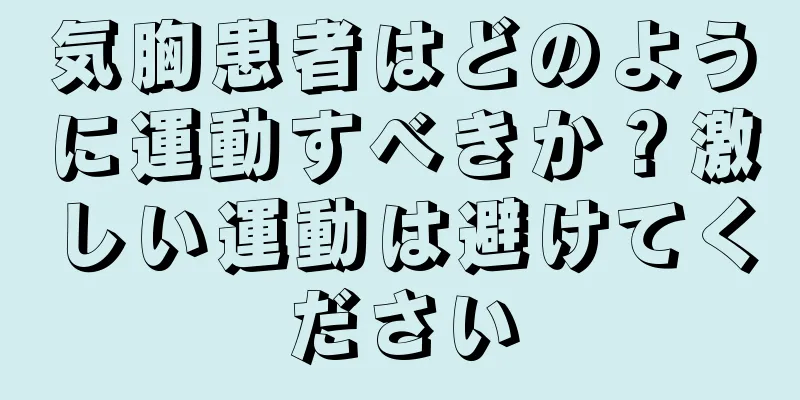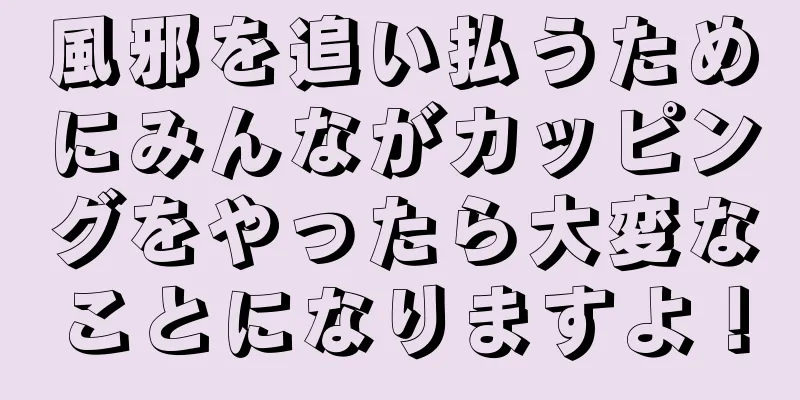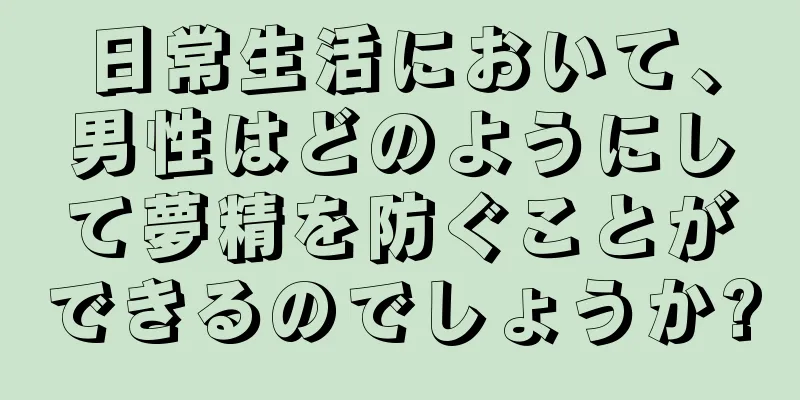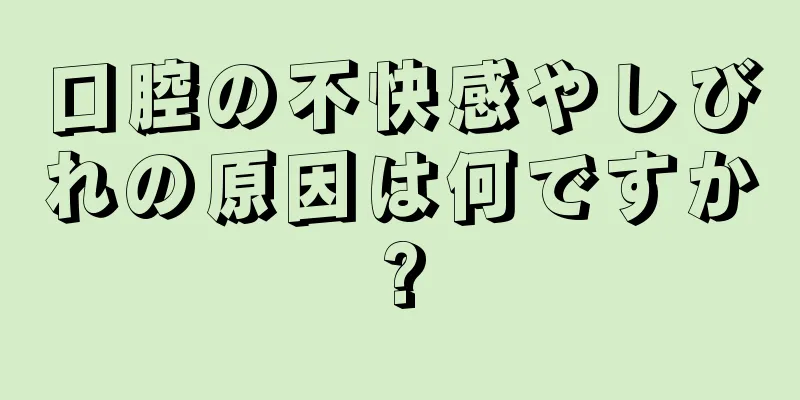頻繁に鼻血が出る原因と予防方法
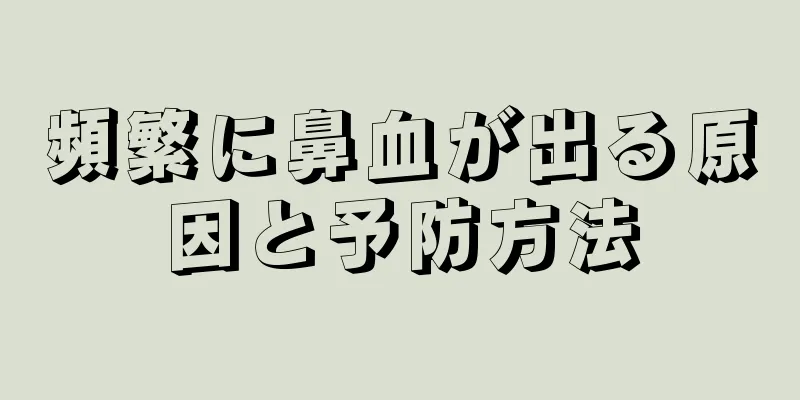
|
子どもから大人まで、誰もが鼻血の症状を経験したことがあると思います。鼻血は心身の健康に大きな影響を与えます。短期的には害は見られませんが、何らかの病気の兆候であるに違いありません。そこで、鼻血が頻繁に出る原因とその予防法について詳しく見ていきましょう。 頻繁に鼻血が出る原因は何ですか? 乾燥した天候、鼻ほじり、鼻炎、外力の衝突、鼻腔内の異物、特定の急性感染症、血液疾患、ビタミンC欠乏などはすべて鼻血を引き起こす可能性があります。また、次の状況でも鼻血が発生する可能性があります。 1. トラウマ。鼻や副鼻腔の外傷は、前頭蓋窩または中頭蓋窩の骨折を伴うことがあり、前篩骨動脈または内頸動脈を損傷します。出血は一般的に重度で生命を脅かします。鼻や副鼻腔の手術中に血管が損傷し、それが時間内に発見されなかったり、適切に治療されなかったりした場合、または鼻ほじり、強く鼻を振る、激しいくしゃみ、鼻腔内の異物、鼻腔内挿管、鼻粘膜の血管を損傷する急激な気圧の変化などにより、出血が起こる可能性があります。 2. 腫瘍。鼻、副鼻腔、または鼻咽頭の悪性腫瘍は、初期段階では少量の出血を繰り返しながら、潰瘍化して出血することがあります。末期段階では、大血管が損傷し、大量出血を引き起こす可能性があります。鼻咽頭血管線維腫や血管腫などの良性血管腫瘍からの出血は、一般的にもっと重篤です。したがって、鼻血に関しては、大量の出血だけでなく少量の出血にも注意が必要です。少量の鼻血が見つかった場合は、出血の原因を注意深く調べる必要があります。 3. 血管硬化症、高血圧、ビタミン欠乏症、血液疾患、血小板減少症など、多くの全身疾患が鼻血を引き起こす可能性があります。したがって、鼻血が出たときは、局所的な原因を探すだけではなく、全身の必要な検査を行って、本当の原因を治療する必要があります。 鼻血を防ぐ方法 頻繁に鼻をほじらないでください。鼻孔には鼻毛がたくさん生えていて、空気を浄化し、ろ過する機能があり、ほこりが肺に入るのを防ぐことができます。頻繁に鼻をほじると、鼻毛が傷つき、ほこりが直接肺に入り、肺疾患を引き起こします。鼻孔が乾燥したり、鼻にかさぶたができたりした場合は、綿棒を使って鼻腔内に抗炎症性の眼軟膏を塗ることができます。これにより、鼻腔を乾燥状態に保ち、潤いを与え、鼻血を防ぐだけでなく、鼻腔内の一部の細菌と戦い、抗炎症効果も得られます。 さらに、キウイ、ブドウ、イチゴ、キュウリなど、ビタミン C が豊富な果物や野菜をもっと食べるべきです。ビタミン C は血管の健全性を維持し、鼻血や滲出液を減らし、傷の修復にも効果があるからです。秋は気候が乾燥し、水分が蒸発しやすいため、水をたくさん飲む必要があります。鼻、口、皮膚が乾燥することがよくあります。人体の正常な代謝を維持するために、普通の人は通常、1日に7〜8杯の水を飲む必要があります。鼻血を防ぐには、まず鼻腔を湿潤状態に保たなければなりません。 |
<<: 喉を守るにはどうすればいいでしょうか?喉を守るために何を食べればいいでしょうか?
推薦する
けいれん患者への看護
けいれんを起こした患者に対する看護対策は何ですか?臨床的にはけいれんを起こす患者を神経性けいれんと呼...
白内障の原因は何ですか?
目は誰にとってもとても大切なものですが、目が十分に保護されていないと、さまざまな病気が発生する可能性...
卵子採取や血管造影検査は痛いですか?
体外受精の生殖技術はますます進歩しており、不妊に悩む多くの女性が体外受精を選択しています。体外受精を...
乳房滲出液の症状
乳房は女性の身体の非常に重要な部分です。生活の中で、多くの女性が乳房にもっと注意を払っています。もち...
毎日射精するとどうなるでしょうか?
毎日射精することは過度の贅沢であり、実際のセックスであれ、自慰であれ、体の健康に非常に有害です。そう...
大根は西洋薬を溶かすのでしょうか?
大根は西洋薬を溶かすという言い伝えがあります。実際、医学の専門家は、大根は西洋薬を溶かすことはできな...
高血圧を予防する方法
高血圧は人間の健康に有害です。このような病気にかかったら、すぐに治療しなければなりません。さもないと...
痛風が再発したらどうすればいい?中国の老医師がいくつかの小さな治療法を推奨
痛風は中高年に多い病気です。人間の体は一定の年齢に達すると免疫機能が低下し、症状が再発しやすくなりま...
左親指のしびれの病気とは
食事をするときも、飲み物を飲むときも、コンピューターで作業するときも、指なしでは何もできません。しか...
出血性肉芽腫
腕にしこりがあり、触ると痛いものの、他に不快な症状がないため、あまり気にしない人もいます。しかし、時...
子宮内膜の正常な厚さはどのくらいですか?子宮を健康に保つ方法
女性の友人にとって、子宮内膜の厚さは妊娠時期の選択に影響します。それでは、子宮内膜の正常な厚さはどれ...
呼吸をすると左胸に痛みを感じます。
呼吸時に胸が痛む、脇腹が刺されるような症状が出ることがあります。激しい運動中にウォーミングアップ不足...
伝統的な中国医学におけるカッピングのツボとは何ですか?
夏になると、多くの女友達が美しい服を着るために、さまざまな方法でダイエットを始めます。多くの女友達は...
高麗人参粉末は1日に何回摂取すればよいですか?
三七人参の粉末は、伝統的な中国医学で非常に一般的な漢方薬です。昔から、三七人参は外用薬として、主に打...
生後2ヶ月の赤ちゃんの手のひらに汗をかくのはなぜでしょうか?
子どもが生まれた後、特に子どもがまだ話せないときは、親は子どもが病気になったり無視されたりしないよう...