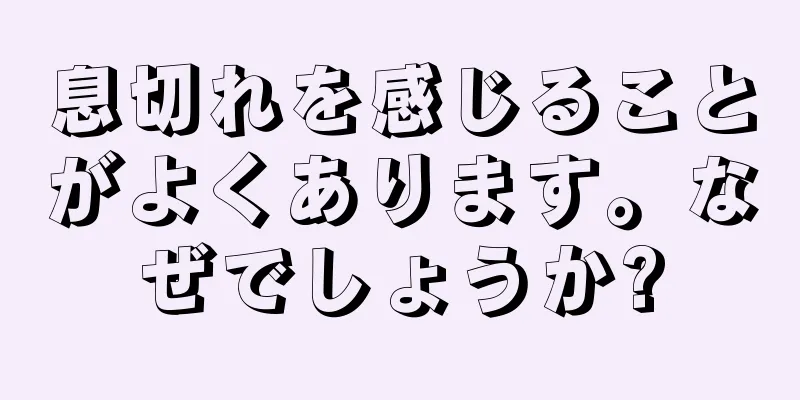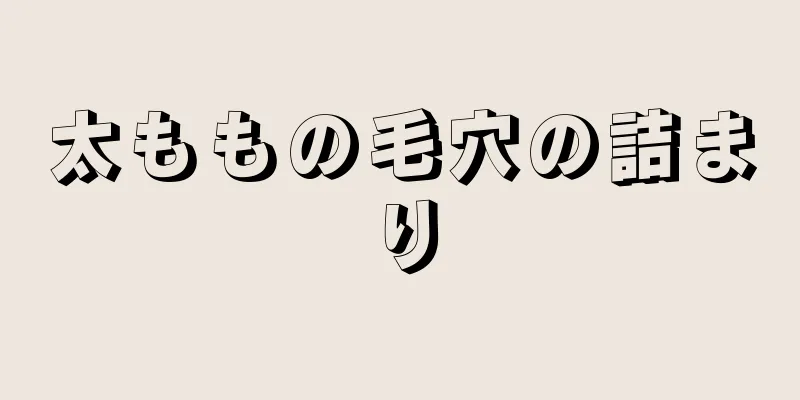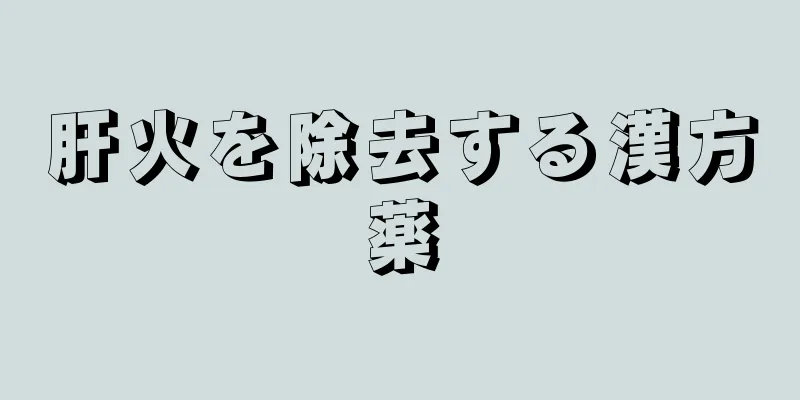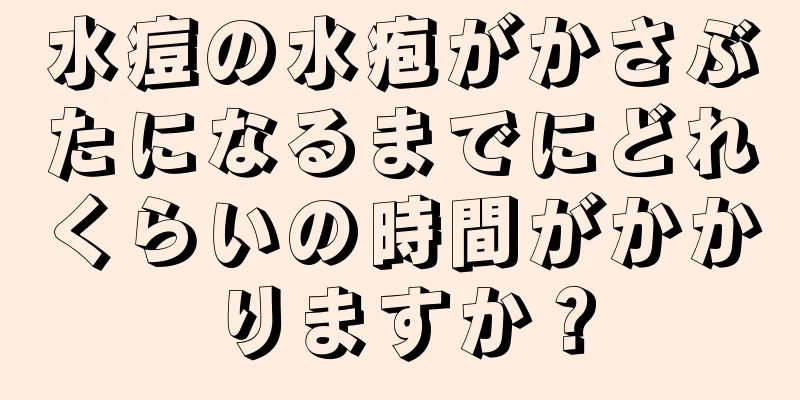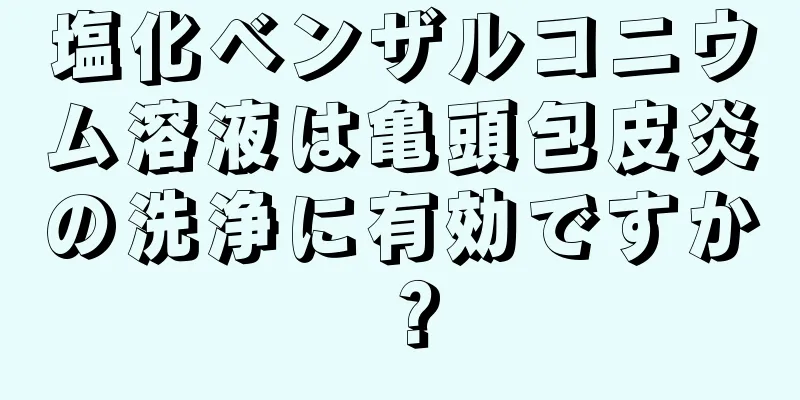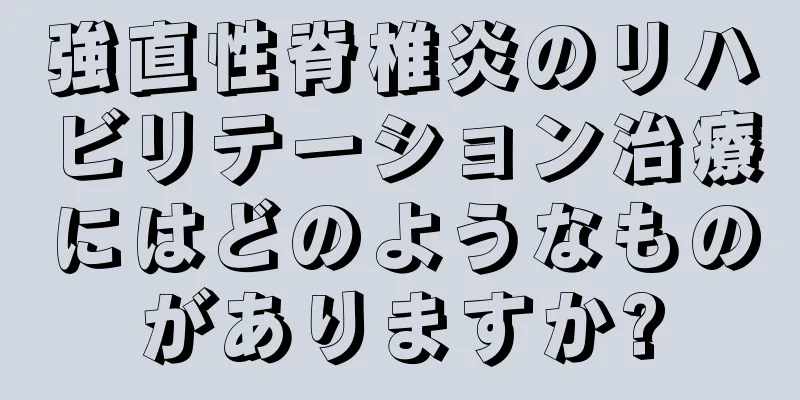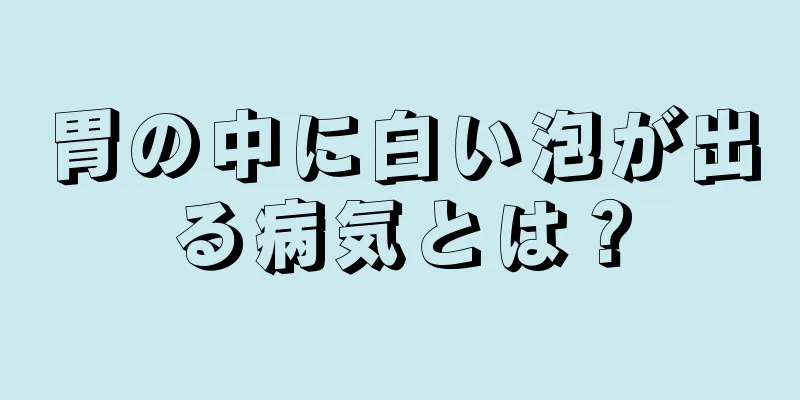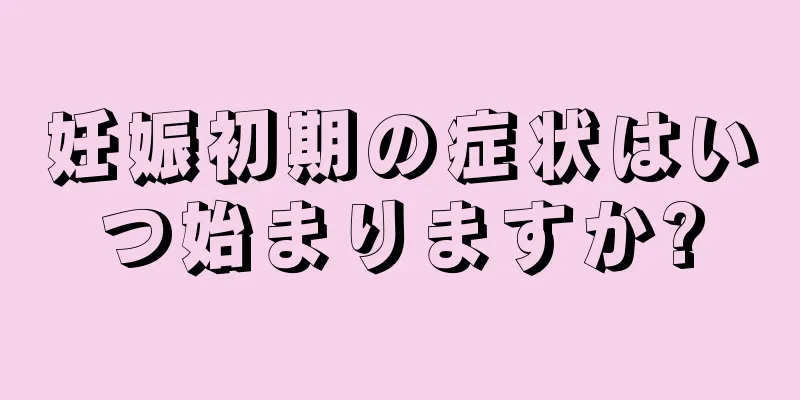下痢の原因

|
通常、ほとんどの人は1日に1回排便をします。排便回数が1日2~3回の場合もあれば、2~3日に1回の場合もあり、その場合の便の特徴は正常です。これは正常です。ただし、1日に3回以上排便があったり、水っぽい便、血便、ジャムのような便など、便の形状が異常な場合は、下痢、または軟便と呼ぶことがあります。 日常生活において、下痢は非常に一般的な症状です。胃腸炎、ウイルス感染など、多くの病気が下痢を引き起こす可能性があります。ただし、便の形状は病気によって異なります。便の形状に基づいて、どのような病気にかかっているかを知ることができます。次に、下痢の原因を理解しましょう。 1. 急性下痢の原因 食中毒を含む腸の感染症は、急性下痢の最も一般的な原因であり、次のように分類できます。 (1)細菌感染: ①細菌性赤痢:発症は比較的急速で、悪寒、発熱、腹痛、下痢、しぶり腹などの症状が現れることが多く、吐き気や嘔吐を伴うこともあります。下痢は、便の中に粘液、膿、血液が混じる症状で、日によって頻度が変わります。顕微鏡で見ると、便には大量の赤血球と白血球が含まれていることがわかり、便培養では赤痢菌が検出されます。 ②サルモネラ感染症:不潔な食物を摂取したことがあることが多く、腹部膨満、腹痛、下痢の症状を伴うことが多い。便は主に軟便または水様便で、膿や血は少なく、排便回数は1日3~5回です。便培養により病原菌(サルモネラ菌やチフス菌など)を検出できます。 ③大腸菌腸炎:不潔な食生活の履歴がある場合が多い。発症は比較的急性で、症状には悪寒、発熱、腹痛、下痢などがあり、嘔吐を伴うこともあります。下痢は主に水っぽい便ですが、粘液、膿、血液が含まれることもあります。便培養により病原菌を検出することができます。 ④ カンピロバクター感染症:症状は一般的に軽度で、下痢を伴う上腹部と中腹部の痛みとして現れ、軟便または水様便が主な症状であり、抗生物質で効果的に治療できます。 ⑤ 小腸・大腸のエルシニア感染症:臨床症状はカンピロバクター感染症とほぼ同様で、下痢などの症状はより軽度であることが多い。 ⑥腸管黄色ブドウ球菌感染症:発症は比較的急性で、悪寒、発熱、腹痛、下痢などの症状が現れることがあります。下痢は主に軟便ですが、少量の粘液、膿、血液が伴うこともあります。便培養により診断を確定できます。この病気は、広域スペクトルの抗生物質、ホルモン、または大規模な外科手術の使用後に発生することが多いです。便培養により黄色ブドウ球菌が検出されることがあります。 ⑦急性出血性壊死性腸炎:現在では、クロストリジウム・パーフリンゲンスやクロストリジウム・ディフィシルの感染が原因と考えられています。発症は急性で、腹痛や下痢などの症状は一般的に重篤です。腹痛は重篤で、腹部全体に広がることがあります。持続的な痛みの場合もあれば、発作性の場合もあります。下痢の初期段階では、1 日に 10 回以上、軟便または水様便が出て、その後は血便になることがあります。重症の場合は、血便や水様便になり、悪寒、発熱、吐き気、嘔吐などの症状を伴うことがよくあります。この病気は思春期の若者によく見られます。 ⑧ 偽膜性大腸炎:抗生物質の長期・過剰使用後に発生し、免疫機能が低下した患者にも発生することがあります。これは主に、クロストリジウム・ディフィシルによる二次的な腸管感染によって引き起こされ、その毒素が腸粘膜を損傷します。臨床的特徴は頻繁な排便で、重症の場合は 1 日に 20 回以上排便することがあります。便には粘液、膿、血液、さらには血水が含まれることがあります。卵滴のような偽膜が排出されることもあり、発熱、動悸、脱水、電解質異常、低血圧、その他の全身中毒症状を伴うことがよくあります。便を嫌気性細菌の培養検査にかけると病原菌が見つかることがあります。メトロニダゾール、バンコマイシンなどが有効な治療薬です。 ⑨コレラ:コレラ菌の感染によって起こる。臨床症状の重症度は様々です。軽症の場合、症状は比較的軽く、1 日に数回の水様性下痢が多く、吐き気、嘔吐、腹痛などの症状を伴うことがあります。重症の場合、排便回数が増え、便が米のスープ状になることがあります。患者は発熱、脱水、低血圧などの全身中毒の症状を示すことがよくあります。便培養により病原菌を特定できます。 (2)原生動物および寄生虫感染症: ①アメーバ赤痢:発症は一般に急性で、発熱、腹痛、下痢などの症状がみられます。下痢は1日に数回から10回以上起こり、便には粘液、膿、血が混じります。便は暗赤色やジャム状で、量が多く、悪臭を放つこともあります。新鮮な便を検査してアメーバ栄養体が見つかった場合は、診断を確定することができます。治療にはメトロニダゾールまたはチニダゾールが有効です。 ②急性住血吸虫症:通常、初めて大量の住血吸虫セルカリアに感染した人に発症します。悪寒、発熱、腹部膨満、咳、腹痛、下痢などの症状がよく見られます。下痢は重篤ではなく、1日3~5回で、軟便または粘液便の場合があります。末梢血中の好酸球数が増加します。患者が繰り返し感染すると、肝脾腫などの症状が現れることが多いです。 ③ ジアルジア・ランブリア感染症:1日に3~5回の排便があり、ほとんどが水っぽいまたは軟便で、粘液はほとんど出ません。診断は便中に鞭毛虫が見つかることによって確定します。メトロニダゾールは治療に効果的です。 ④ トリコモナス感染症:腸のトリコモナス感染症も下痢を引き起こす可能性があり、排便は1日に数回から、主に軟便で粘液が含まれる場合もあります。 (3)ウイルス感染:腸管ロタウイルス感染や腸管アデノウイルス感染でよく見られます。臨床症状は一般的に軽度で、腹痛、下痢などを伴うことがあります。下痢は1日に数回起こることがあり、主に軟便または水様便です。 (4)真菌感染:抗生物質やホルモン剤の長期使用、または慢性消耗性疾患の中期から後期の患者は、腸内で真菌感染を起こす可能性があり、腸粘膜のうっ血、浮腫、びらん、潰瘍形成を引き起こし、下痢を引き起こし、排便回数の増加として現れます。軽症の場合、便は軟らかくゆるく、粘液が混じり、1日に数回排便され、時には卵白のような便になることがあります。重症の場合、便は粘液、膿、血のように見えることがあります。定期的な便検査または培養により病原菌が発見されれば、診断が確定します。 (5)食中毒: ① 黄色ブドウ球菌、サルモネラ菌、塩酸バクテリア、ボツリヌス菌などに汚染された食品を食べると、発熱、腹痛、嘔吐、下痢、脱水などの症状が起こることがあり、これを食中毒といいます。患者の便は軟便または水様便で、粘液を伴うことが多く、少数ではあるが膿や血液が含まれることもあります。 ②毒キノコ、フグ、大型魚の胆嚢、その他ネズミ毒、農薬などの有毒化学毒物を摂取すると下痢を起こすことがあります。下痢は主に、少量の膿と血液を伴う軟便または水様便を特徴とし、嘔吐や腹痛などの症状を伴うことがあります。下痢に加えて、上記の毒物には独自の特別な症状もあります。 (6)アレルギー反応:食物アレルギー(牛乳、魚、エビ、魚介類など)は腹痛や下痢を引き起こすことがあります。アレルギー性紫斑病などの疾患は腸の運動亢進や下痢を伴うことがあります。下痢は、多くの場合、ゆるい水っぽい便を特徴とし、腹痛を伴うことがよくあります。 (7)薬物:エリスロマイシン、水酸化マグネシウム、ネオマイシン、リンコマイシン、硫酸マグネシウム、ソルビトール、マンニトール、5-フルオロウラシル、レセルピン、プロプラノロールなど、さまざまな薬物が下痢を引き起こす可能性があります。これらの薬物が下痢を引き起こすメカニズムはそれぞれ異なりますが、リン、ヒ素、水銀、アルコール中毒などの特定の化学物質はすべて急性下痢を引き起こす可能性があります。下痢は、多くの場合、軟便や水様便を特徴とし、粘液、膿、血液は含まれません。 2. 慢性下痢の原因 慢性下痢の原因は様々ですが、一般的には以下の 7 つの側面に分けられます。臨床現場では慢性下痢のほうが一般的であるため、識別を容易にするために、関連疾患の特徴を簡単に説明します。 (1)腸管感染症:慢性下痢の最も一般的な原因です。 ①細菌感染: A. 慢性細菌性赤痢: 急性細菌性赤痢は、完全に治癒しない場合は慢性疾患に発展する可能性があり、慢性疾患を基礎として急性発作として現れる場合もあります。急性発作は、1 日に 3 ~ 5 回の排便で現れ、粘液、膿、血液が伴い、しぶり腹の感覚を伴うことがよくあります。少数の患者は左下腹部に痛みを感じます。慢性細菌性赤痢における便培養の陽性率は低く、一般的には 15% ~ 30% に過ぎないため、病原菌を検出するには繰り返し培養を行う必要があります。 B. 腸結核:青年期および中年期に多く、男性よりも女性に多く見られます。この病気は、末端回腸または右結腸で発生する可能性が最も高いです。潰瘍性腸結核の主な症状は下痢ですが、便秘と交互に現れることもよくあります。下痢は、ドロドロした便や水っぽい便が特徴で、1日に3~5回、重症の場合は1日に10回以上排泄され、発熱や寝汗などの結核中毒の症状を伴うことがよくあります。バリウム注腸X線検査または大腸内視鏡検査で診断を確定できます。 ② 原虫・寄生虫感染症: A. 慢性アメーバ赤痢(慢性アメーバ腸炎とも呼ばれます):便は 1 日に 3 ~ 5 回排泄され、粘液や血液を伴う粘液性で水っぽい状態です。慢性の場合、典型的なジャム状の便はまれです。病気の経過は数か月から数年にわたり、病気の経過中に急性発作が繰り返し起こります。アメーバ栄養体は、繰り返し発作を起こした後の新鮮な排泄物中に見つかることがよくあります。 B. 慢性住血吸虫症: 慢性住血吸虫症の患者は、1 日に 3 ~ 5 回の下痢を起こすことがあります。下痢の多くは軟便で、粘液や膿、血液が混じることもあります。患者は、住血吸虫症関連の肝線維症の症状を示すことがよくあります。診断は血清抗体検査と便または直腸粘膜生検中の卵の検出に基づいて行われます。 C. ジアルジア・ランブリアまたはトリコモナス感染症: 慢性の場合、1 日に数回排便があり、排便は軟便または水様便であることが多く、粘液を伴うこともあります。診断は、便中にジアルジア・ランブリアまたはトリコモナスが見つかることによって確定します。 ③慢性真菌性腸炎:抗生物質やホルモン剤の長期使用後に発症することが多く、慢性消耗性疾患の末期にも発症しやすい。下痢の症状が現れ、重症の場合は粘液や膿、血を伴い、再発することもある。便の中に真菌が見つかることで診断が確定します。 (2)非特異的または非感染性の腸炎: 1. 慢性非特異性潰瘍性大腸炎:一般的に自己免疫疾患と考えられており、近年中国で増加傾向にあり、若年層と中年層に多く見られます。病変は主に直腸、S状結腸、下行結腸に浸潤し、右結腸に浸潤することもあります。病変は軽症、重症、劇症の3つのタイプに分けられます。ライトタイプが最も一般的です。軽症の場合、患者は1日に3〜4回排便しますが、重症の場合、患者は1日に10回以上排便することがあります。便は粘液、膿、血液が混じったペースト状またはゆるい便です。重症の場合、便は出ず、粘液、膿、血液のみが排出されます。 2. 慢性放射線腸炎:子宮頸がんまたは骨盤悪性腫瘍の患者が放射線治療後数週間または数ヶ月以内に下痢を発症した場合は、放射線腸炎の可能性を考慮する必要があります。主な症状は便に粘液と血液が混じることであり、しぶり腹や直腸の局所的な痛みを伴うことも少なくありません。大腸内視鏡検査では、病変粘膜(放射線治療後に損傷した粘膜)に充血、侵食、または出血が見られることがあります。この病気は回復することなく何年も続くことがあります。 (3)吸収不良症候群:吸収不良症候群の分類は非常に複雑である。吸収不良は、胃や小腸の病気、または肝臓、胆嚢、膵臓の病気によって引き起こされることがあります。 ①一次性吸収不良: A. 熱帯性脂肪便症: 熱帯性スプルーとも呼ばれ、熱帯地域で発生します。原因はまだ不明です。一般的には、タンパク質、葉酸、ビタミン B の欠乏に関連していると考えられています。下痢は大量の悪臭のある便が特徴で、患者の約3分の1に脂肪便がみられます。 B. 非熱帯性脂肪便:グルテン腸症、原発性脂肪便、セリアック病とも呼ばれます。患者の腸粘膜にはペプチド分解酵素が欠如しているため、毒性のあるアルファグルテニンを分解できず、腸絨毛と腸上皮細胞が損傷し、最終的に吸収不良につながります。下痢は脂肪性下痢を特徴とし、大量の脂っこい便、悪臭、1日に数回の排便を伴います。 ②二次性吸収不良: A. 胃切除後:胃全摘出術およびビルロート II 手術後によく見られます。食べ物が小腸に素早く入るため、エンテロキナーゼ、膵臓の消化酵素、胆汁の分泌が不十分になったり、膵液や胆汁が食べ物と十分に混ざらなかったりして、吸収不良を起こし、下痢を引き起こすことがあります。さらに、消化管手術後に細菌の過剰増殖(盲ループ症候群)が発生すると、細菌の分解と胆汁酸塩の結合が微粒子の形成に影響し、脂肪便を引き起こす可能性があります。 B. 慢性肝胆道疾患:慢性肝炎、肝硬変、肝内胆管閉塞、肝外胆管閉塞などは、胆汁酸塩の不足により脂肪の乳化と輸送が妨げられ、脂肪便を引き起こす可能性があります。 C. 小腸疾患:過度な小腸切除(例えば、小腸の全長の75%以上が切除されたり、120cmしか残らなかったりすると、短腸症候群と呼ばれます)、胃結腸瘻、胃回腸瘻は、いずれも小腸の吸収面積の減少により下痢を引き起こしたり、食物が小腸や空腸を通過せずに瘻孔から直接大腸に流れ込んだりすることがあります。 D. 慢性膵疾患:慢性膵炎、膵臓癌などでは、膵液分泌不足や膵酵素不足により下痢を引き起こし、脂肪やタンパク質の消化吸収障害を引き起こす可能性があります。 E. 小腸粘膜のびまん性病変:小腸悪性リンパ腫やホイップル病など、いずれも小腸粘膜の損傷やリンパ管の拡張・閉塞により脂肪便を呈します。強皮症の場合、消化管粘膜や粘膜下層の萎縮により最終的に消化吸収障害が起こり下痢を呈します。 (4)内分泌疾患:多くの内分泌疾患は下痢症状を伴います。患者は下痢のために初めて消化器科を受診することもあるため、鑑別が必要です。 ① 甲状腺機能亢進症:甲状腺機能亢進症患者の10%~15%に下痢がみられますが、一般的に下痢は重篤ではなく、1日に数回起こり、ほとんどが軟便または水様便で、粘液、膿、血液は含まれず、腹痛を伴うことはまれです。患者は発汗、動悸、体重減少、甲状腺肥大、眼球突出などの症状を経験することがよくあります。 ② 糖尿病:下痢の原因は膵外分泌機能障害と腸管運動異常に関係しています。下痢は軟便または水様便の場合もあれば、粘液、膿、血液を伴わない脂肪性下痢の場合もあり、1日に数回起こることもあります。少数の患者では持続的な下痢がみられる場合があります。 ③副甲状腺機能低下症、甲状腺髄様腫瘍:前者は低血中カルシウムによる神経筋の過敏性亢進により下痢を起こすことがありますが、下痢の回数は1日2~3回程度と重篤なものではありません。後者は腫瘍によるカルシトニンの放出によって引き起こされ、下痢を引き起こします。 ④副腎機能不全:副腎皮質機能が低下すると、胃酸やペプシンの分泌が低下し、小腸の吸収障害を伴うことが多く、下痢が起こることがありますが、ドロドロした便が多く、頻度は多くありません。 ⑤ 膵コレラ症候群:中国で散発的に症例が報告されている稀な疾患で、腫瘍細胞による血管作動性腸管ペプチド(VIP)の異常分泌によって引き起こされます。成人患者の VIP は主に膵島細胞腫瘍から生じ、小児患者の VIP は主に神経節腫または神経節神経腫から生じると考える人もいます。この病気の臨床的特徴は、水様性下痢、低カリウム血症、真性無酸症です(国内の報告例では、胃酸分泌が正常な患者も含まれています)。腫瘍を検出するには、VIP 測定、B 超音波、CT または MRI 検査によって診断を確認する必要があります。 ⑥ガストリノーマ:膵臓の非β細胞腫瘍がガストリンを大量に分泌することで発生します。大量のガストリンは壁細胞を刺激し、大量の胃酸を分泌させます。下痢は大量の胃酸と胃液の分泌に関係しています。この病気は、胃と十二指腸に複数の潰瘍が形成されることを伴っていることがよくあります。診断には、胃液分析、ガストリン濃度測定、腫瘍を検出するための超音波、CT、MRI 検査が必要です (腫瘍のほとんどは膵臓組織にあり、腹腔内の他の部分にもいくつかあります)。 (5)腫瘍性疾患:良性または悪性の腫瘍。 ① 消化管悪性リンパ腫:消化管リンパ腫の最も脆弱な部分は回腸であり、大腸への影響は少ない。下痢に加えて、腹痛や腹部腫瘤を伴うことが多く、少数の患者では血便が主な症状となることもあります。 ②カルチノイド症候群:カルチノイド細胞から分泌される5-ヒドロキシトリプタミン、ブラジキニン、セロトニンなどの血管作動物質が大量に分泌され、下痢を引き起こします。カルチノイドの発生部位として最も多いのは虫垂ですが、腸の他の部位にも発生することがあります。下痢に加えて、患者は顔、首、上半身の皮膚に発作性の赤みを呈することが多く、気管支喘息の症状を呈する患者も少数います。 ③大腸がん:直腸がんやS状結腸がんの中期から末期になると、便に粘液、膿、血が混じり、左下腹部の痛みやしぶり腹を伴うことがあります。下痢は右側結腸がんの重要な症状であり、多くの場合、明らかな粘液、膿、血液を伴わない軟便またはどろどろした便として現れます(ただし、顕微鏡で見ると赤血球や膿細胞が見つかることがよくあります)。患者は通常、腹痛、体重減少、貧血などの症状を経験します。左側結腸がんの主な症状は便秘または慢性腸閉塞ですが、感染やがんの破裂を伴う場合は血便が現れることがあります。 ④ 腸管腺腫性ポリープまたはポリープ症:ポリープ表面の出血、びらん、潰瘍により分泌性下痢が起こることがあります。下痢に加えて、血便も腸ポリープの重要な症状の 1 つです。 (6)胃腸機能障害:過敏性腸症候群などIBS は、異常な排便を伴う腹部の不快感や痛みからなる腸機能障害症候群のグループです。患者の腸には器質的病変や異常な生化学的指標はありません。以前は粘液性大腸炎、過敏性大腸、アレルギー性大腸炎と呼ばれていたものが、現在では総称してIBSと呼ばれています。この病気の発生は、精神的ストレスや感情的興奮と密接に関係していることが多く、つまり、精神的および心理的要因が病気の発症に重要な影響を及ぼします。さらに、ストレスや腸の感染症(赤痢、腸炎など)もIBSの重要な引き金となることがよくあります。近年、IBS の病因が詳細に研究され、IBS は内臓感覚の異常と大腸の刺激に対する感受性の増大を特徴とし、それが異常な排便 (下痢または便秘、あるいは下痢と便秘の交互) につながると考えられています。 2000 年に、IBS の最新の診断基準であるローマ II 基準が国際的に公布されました。その要点は次のとおりです。 ① 診断:この病気では、まず症状の原因が組織構造や生化学的異常によるものではないことを確認する必要があります。 ② 1年以内に、以下の3つの異常排便のうち2つを伴う腹痛または腹部不快感が3か月以上繰り返される。 A. 排便後の腹痛が軽減または緩和されます。 B. 排便頻度の異常(1日3回または週3回など)。 C. 異常な便の形状(軟便または乾燥した硬い便)。 Rome II 基準は、多くの国の消化器専門医によって徐々に受け入れられつつあります。下痢型IBSの患者は、腹痛や腹部の不快感の後に下痢を起こすことがよくあります。排便後、腹痛や腹部の不快感は軽減または緩和されます。便はゆるくて柔らかいのが特徴で、水っぽい便もいくつかあります。1日の排便回数はさまざまで、3回以上排便されることがよくあります。便には膿や血液は含まれておらず、粘液が混じっている場合もあります。中医学では「早朝下痢」と診断され、IBSの症状とみなすことができます。患者は夜明け前に腹痛や不快感を感じることが多く、その多くは腸の音が過活動で、腹痛が治まった後に痛みが和らいだり軽減したりします。一般的に、朝食前に2~3回下痢を起こし、朝食後に下痢が止まることが多いです。少数の患者は、食後に腹痛と下痢を起こしやすい傾向があります。これは、食後に胃結腸反射亢進が起こるため、つまり、胃に食物が入った後、結腸の蠕動運動亢進が起こるためです。患者は腹痛または不快感を覚え、その後、便意を催します。この症状も結腸機能障害によって引き起こされると考えるべきです。 (7)その他の要因: ① 腸内細菌叢の不均衡:下痢は主に広域スペクトル抗生物質の長期使用により腸内細菌叢の正常なバランスが崩れることで引き起こされます。重症の場合は偽膜性腸炎を引き起こす可能性があります。 ② 尿毒症:尿毒症性腸炎による下痢で、1日3~5回の排便があり、便はドロドロまたは水っぽいものが多い。 以上が下痢の原因です。下痢の原因はたくさんあることが分かります。体調不良で下痢になった場合、下痢があるからといって胃腸の病気だと単純に考えてはいけません。これは非常に間違った考え方です。この場合は、早めに病院に行って検査と治療を受けるべきです。 |
推薦する
微熱、めまい、吐き気、全身倦怠感は何が問題なのでしょうか?
発熱は一般的な臨床疾患です。発熱には主に高熱と微熱の 2 種類があります。発熱は他の合併症と同時に起...
頸椎症の場合、手のどの部分を圧迫すればよいですか?
頸椎症は頸椎に起こる病気です。この病気は私たちの体に多くの影響を及ぼし、私たちの生活にもさまざまな程...
白髪治療のための黒米粥
黒米は日常生活で幅広い用途があり、お粥やスープを作るのに使用したり、直接蒸したりすることができます。...
腰椎椎間板ヘルニアのときによく眠るには?
腰椎椎間板ヘルニアは非常に一般的な脊椎疾患です。腰椎椎間板ヘルニアは、隣接する脊髄神経根の刺激または...
脳梗塞の薬や食事はどんなものがありますか?
脳梗塞は高齢者に起こりやすい病気で、多くの患者さんの生活に大きな支障をきたします。では脳梗塞にはどん...
ドライアイの治療法は何ですか?
目は心の窓であると言われています。誰もが魅力的で美しい目を持ちたいと願っています。しかし、注意を払わ...
特定の催奇形性薬剤は妊婦には禁止されている
妊婦は比較的特殊なグループなので、薬を服用しているときも日常生活でも特に注意する必要があります。注意...
胆嚢に嚢胞がある場合の対処法
胆嚢に嚢胞がある場合の対処法検査中に卵子に嚢胞が見つかった場合、多くの患者は困惑し、症状が非常に深刻...
身体に触れると簡単に傷がつく
体の特定の部分に打撲傷が見つかることがありますが、いつ、どこで打撲傷ができたか思い出せず、打撲傷の箇...
何か有害なものを食べてしまったらどうすればいいでしょうか?漢方薬で治療する7つの方法
食害は食習慣を適切にコントロールしないことによって引き起こされます。食べ過ぎると、胃腸が食べたものを...
神経障害の症状
現在、神経症の患者は多くいますが、神経症の症状がいくつかあるにもかかわらず、精神疾患にかかっているこ...
生のアトラクチロデス・マクロセファラは便秘治療に効果がある
便秘は非常によくある症状です。多くの人は、便秘は胃腸の病気だと考えています。この症状が起こると、胃腸...
胆嚢ポリープは深刻な病気ですか?
胆嚢ポリープは胆管の一般的な病気であり、日常生活でもよく見られます。胆嚢ポリープは主に一般的な痛み、...
心房細動とはどういう意味ですか? 症状と兆候は何ですか?
心房細動は発作性の場合と慢性の場合があります。これは一般的な不整脈です。多くの器質性心臓疾患が心房細...
ガルナットとセンニジウム・モニエリの効能
没食子もセンキュウも薬効が高く、病気の治療だけでなく健康維持にも効果があるため、広く使われている薬用...