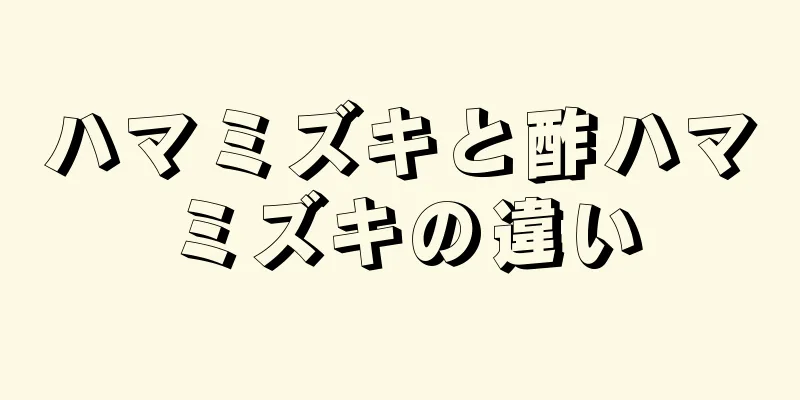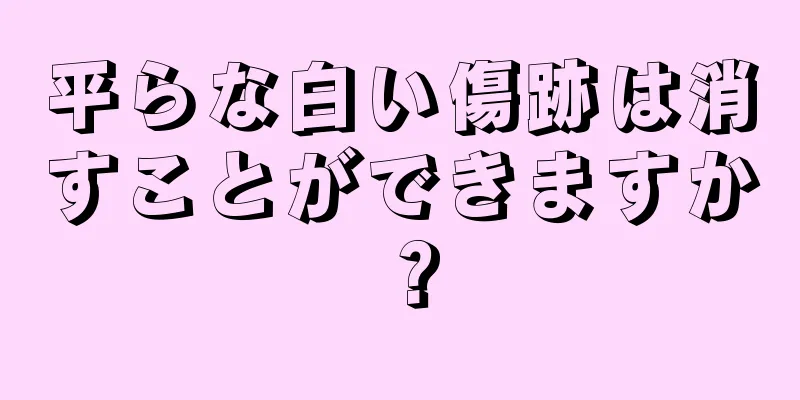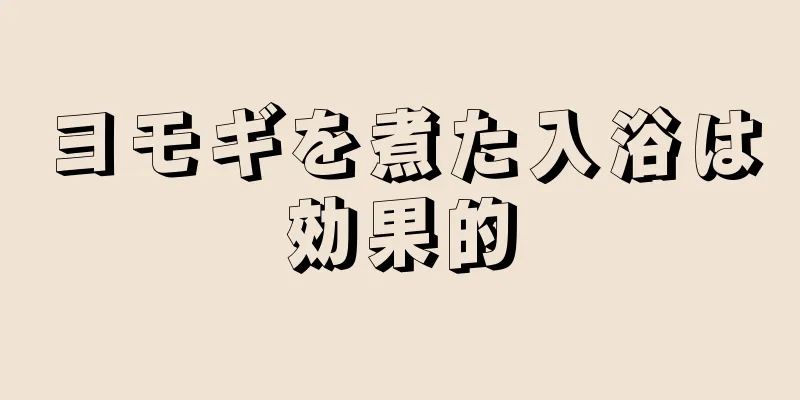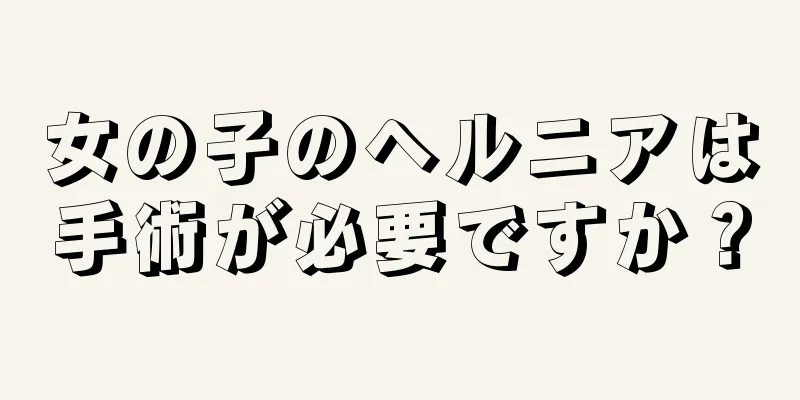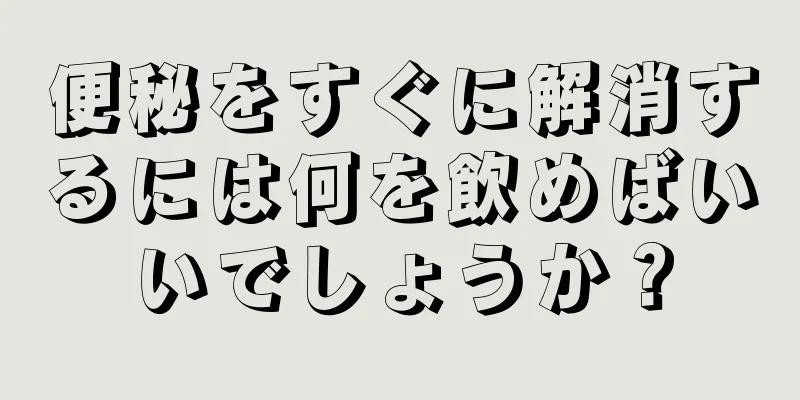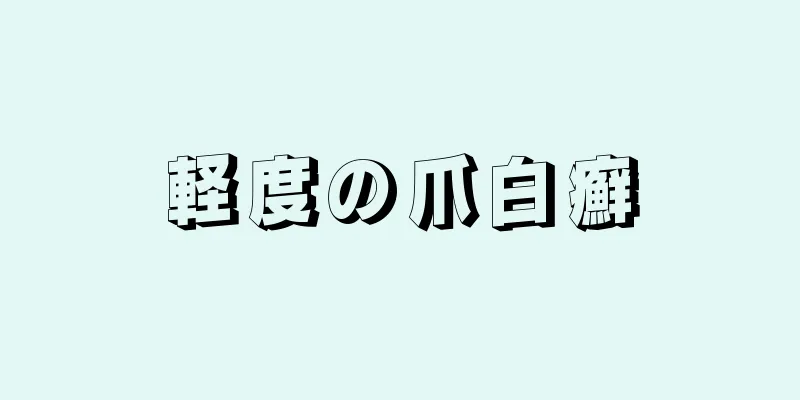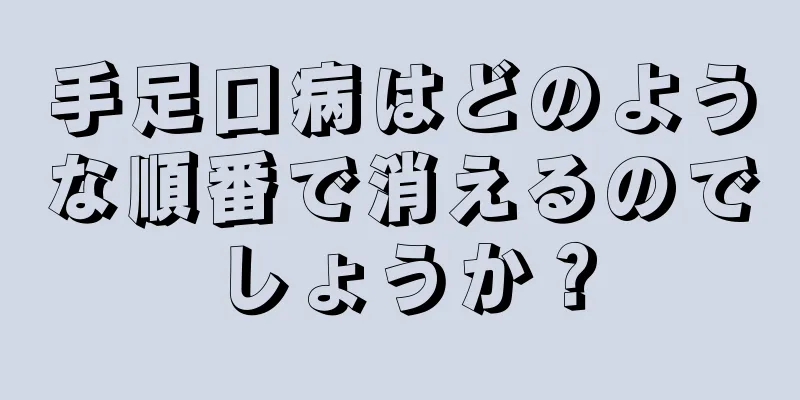血液は薄い方が良いですか、それとも濃い方が良いですか?
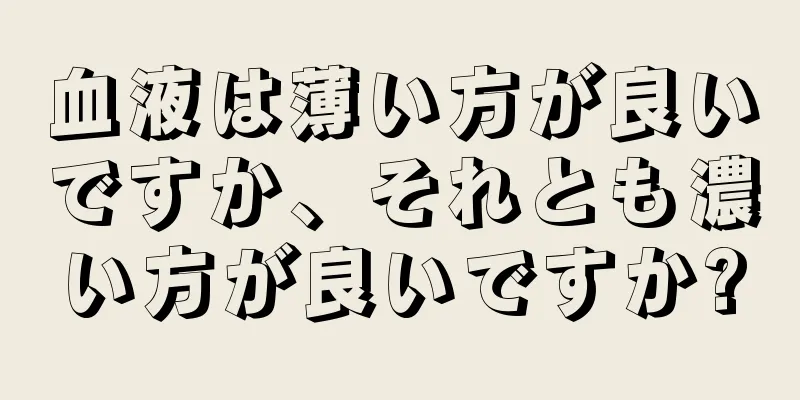
|
血液は私たちの体の中で最も重要な液体です。なぜなら、私たちは日常生活の中で血液を見たことがあるからです。例えば、血液の色は赤みがかっており、血液は一定時間空気にさらされると凝固します。医学的に言えば、血中濃度も非常に重要な指標です。濃度が高すぎると血液が濃くなるので、「血が濃い」という言い方もあります。では、血液が薄い方が良いのか、それとも血液が濃い方が良いのか? 中程度がベスト 粘性は心臓血管疾患や脳血管疾患を引き起こしやすい 薄すぎると栄養が足りなくなります。 健康診断を受けると、次のような指標が出てきます。 血液が濃いという話をよく耳にしますが、これは実は医学用語ではありません。血液がドロドロになるということは、血液の粘度が高くなり、血栓ができやすくなること、あるいは血栓ができる前の兆候であると考えられます。また、血中脂質濃度の上昇が原因となる場合も多いとされています。血液が濃くなることを医学では過粘稠度と呼び、中高年によく見られ、血液レオロジー検査で診断できます。 提案: 1. 水をもっと飲みましょう。水は即効性のある希釈剤と言えます。一晩の深い睡眠後に失われた水分と、食べ物を消化する際に摂取した水分は、どちらも血液の粘性を高める要因となります。水を飲むとすぐに血液が薄まります。しかし、水を飲むことは科学的であるべきです。まず、朝起きたとき、食事の1時間前、夜寝る前に200mlの水を飲むなど、適切な時間を把握する必要があります。第二に、希釈効果の良い水を選びましょう。塩水は細胞の脱水を促進する可能性があるため、お勧めできません。冷水は胃腸の血管収縮を刺激し、血液への水分の吸収を妨げるため、飲用には適していません。精製水は「純粋」すぎるため、低張状態により水分が細胞に素早く入り込み、血液を希釈する効果が理想的ではありません。理想的な希釈水は20〜25℃の沸騰したお湯または薄いお茶で、その張力と密度は血液や組織細胞のそれに近いため、推奨する価値があります。 2. 血液を薄める働きのある食品を多く摂りましょう。血小板凝集を抑制し、血栓症を予防する黒キクラゲ、タマネギ、ピーマン、キノコ、イチゴ、パイナップル、レモンなどの果物がこれにあたります。アスピリンに似た抗凝固作用のある食品にはトマト、赤ブドウ、オレンジ、ショウガなどがあり、脂質を下げる作用のある食品にはセロリ、ニンジン、こんにゃく、サンザシ、海藻、昆布、トウモロコシ、ゴマなどがあります。野菜や果物には多量の水分が含まれているほか、ビタミンCや粗繊維も豊富に含まれています。ビタミンCは血中脂質を下げ、粗繊維は腸内でのコレステロールの吸収を防ぎ、血液の粘度を下げるのに役立ちます。黒キクラゲは甘くてマイルドな性質を持ち、炭水化物、無機塩、硫黄、マグネシウム、ビタミンBが豊富です。陰を養い、体液を促進させ、血液循環を活性化し、抗癌作用があります。血小板凝集を薄め、血液粘度を低下させます。 |
推薦する
肛門のかゆみが続く
持続的な肛門のかゆみは比較的深刻な症状です。主に肛門周囲の皮膚損傷を指します。この病気は若年層と中年...
動悸、息切れ、気血不足、適時に調整する必要がある
気血不足は、私たちの体の健康状態が悪いことの兆候であり、特にホワイトカラーの女性によく見られます。気...
少陰注射とは
少灰注射は痔の出血を治療できる薬で、漢方薬の複合製剤です。この注射には血液を冷やし、出血を止める効果...
海馬多辺丸が効果を発揮するまでに何日かかりますか?
海馬多辺清功丸は、ヤモリ、牛鞭、馬鞭、犬鞭、紅参などから構成されており、その機能は陽を強化して腎臓を...
11歳で月経が起こるのは普通ですか?
女の子は一定の年齢に達すると初潮が始まりますが、初潮の時期は個人の体調によって異なります。一般的に言...
これらの症状は体内に水分が多すぎることを示しています。
喫煙や飲酒などが健康に有害であることは誰もが知っていますが、日常生活における小さな習慣は見落とされが...
漢方シャンプー
毎日髪を洗う人もいれば、2日に1回洗う人もいれば、週に1回洗う人もいます。髪を洗うことは、個人衛生の...
先天性腰椎仙骨化症?
先天性腰椎仙骨化症は非常に一般的です。一般的に、先天性腰椎仙骨化症は特別な治療を必要としません。先天...
新鮮なドクダミをどれくらい煮るか
新鮮なドクダミを水に入れて煮るのに通常約5分かかります。水を沸騰させた後、ドクダミを加え、火を止める...
二重まぶたにアイシャドウを塗る方法
二重まぶたにアイシャドウを塗るのは、一般的なメイク方法です。アイシャドウを上手に塗れば、目が立体的に...
普通の人は小柴胡煎じ薬を飲むことができますか?
小柴胡煎じ液は比較的一般的な漢方薬です。その最も顕著な効果は咳を和らげることです。風邪による咳に優れ...
赤ちゃんが下痢をしているときにニンジン水を飲んでも大丈夫ですか?
親として、私たちは赤ちゃんの食事に特別な注意を払う必要があります。赤ちゃんは何を食べられるのでしょう...
鹿角血酒の効能と使用法
鹿角には素晴らしい効能があると多くの人が言いますが、鹿角の血から作られた酒はさらに効能があることを知...
リウマチと痛風の違いは何ですか?それはどこに現れますか?
リウマチと痛風はどちらも関節痛を引き起こす可能性があるため、多くの人がリウマチと痛風を混同し、予防と...
目の恐怖に対処する方法
人の目は、その人の内面の考えや行動を直接表現すると言われており、日常のコミュニケーションにおいて重要...