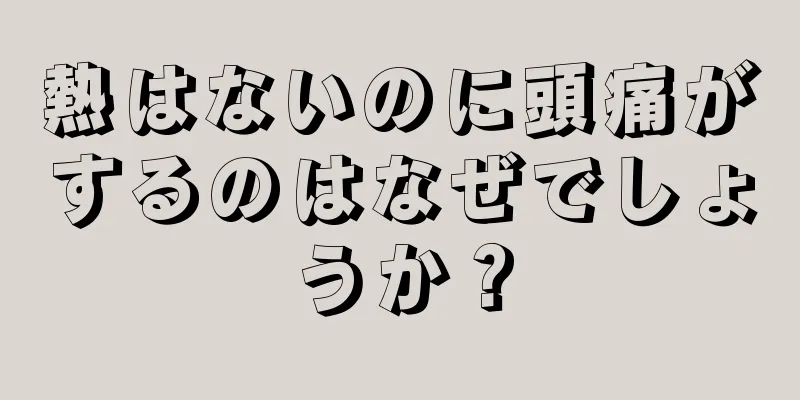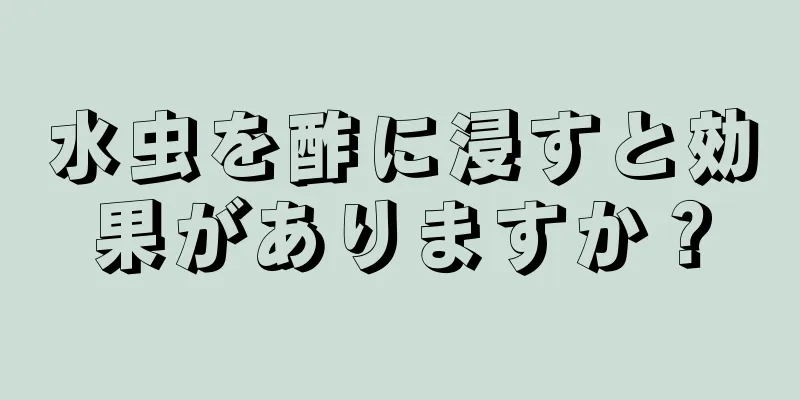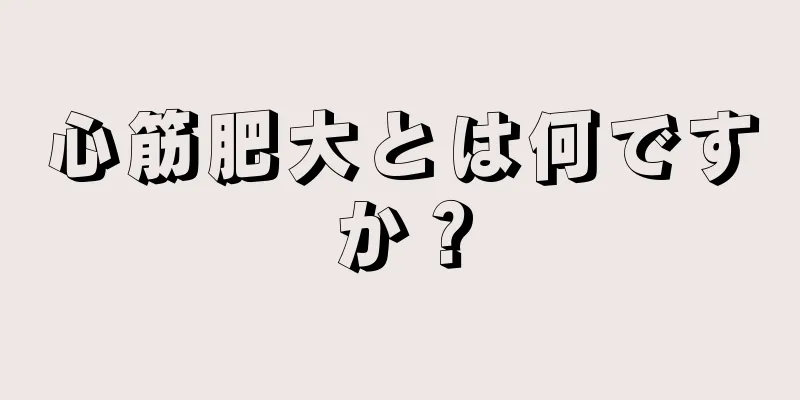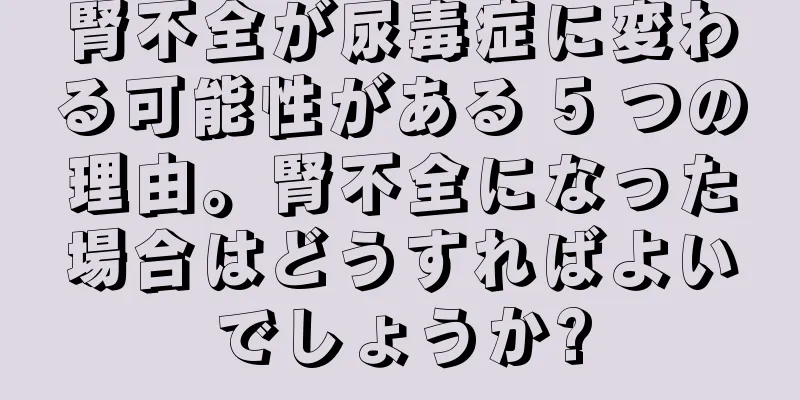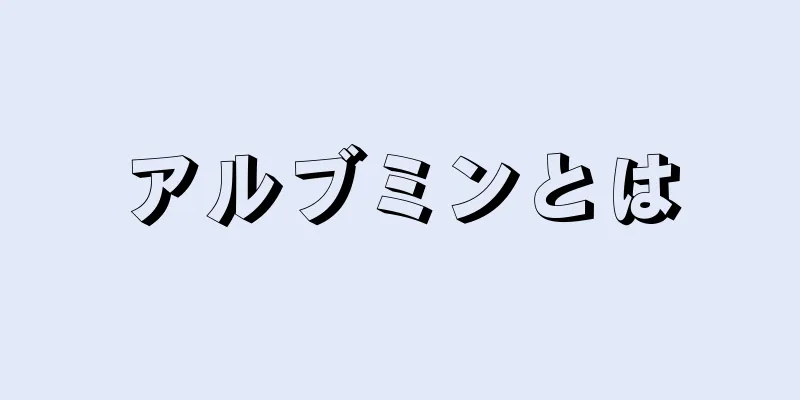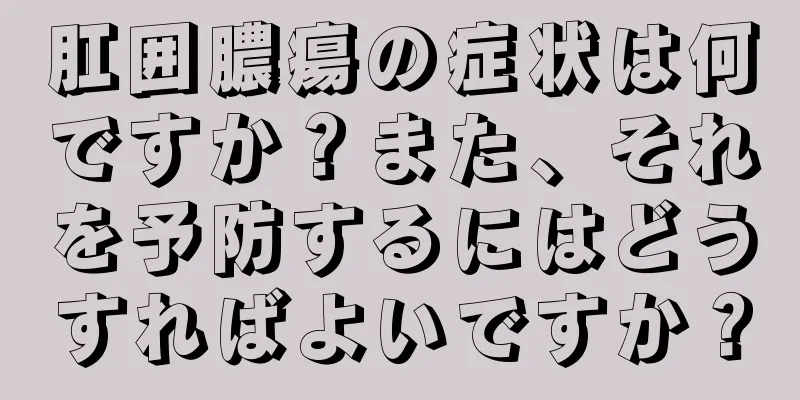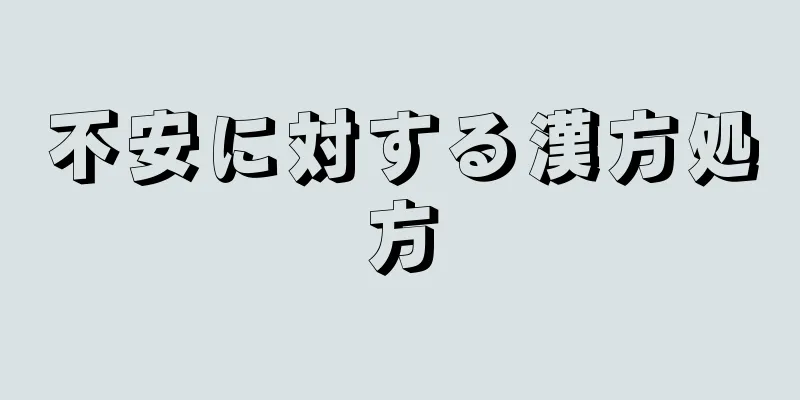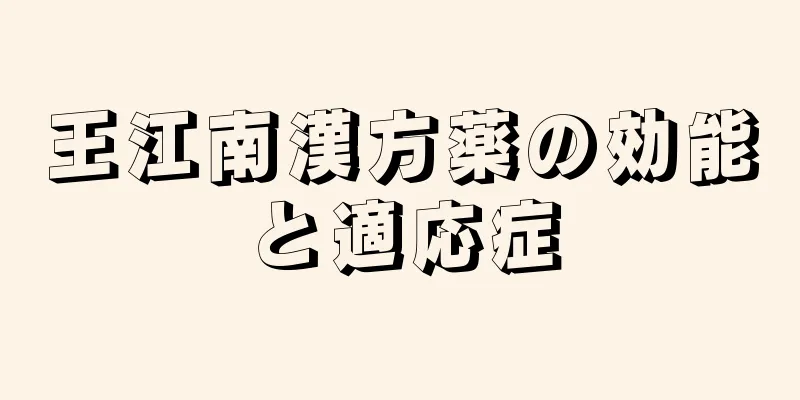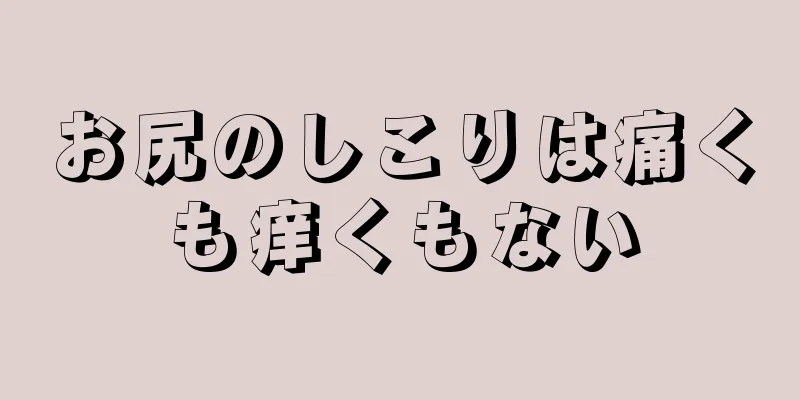漢方薬を1日3回飲んでも大丈夫ですか?
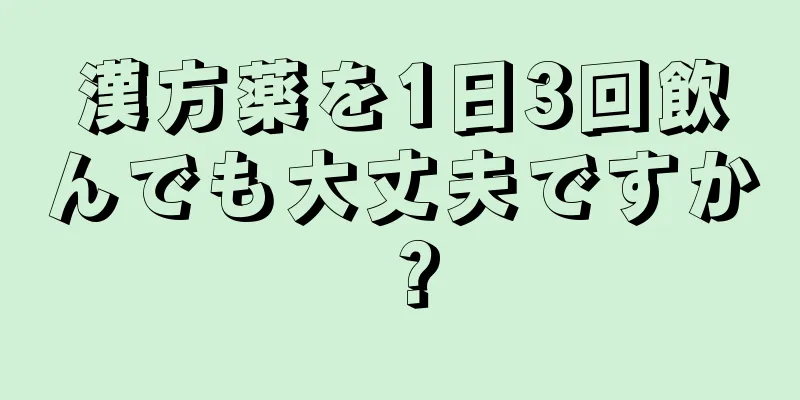
|
漢方薬を服用することで、患者の体はゆっくりと調整され、漢方薬を服用することによる体への副作用は比較的小さいため、体調を整えるために漢方薬を服用することを選択する人が増えています。しかし、患者さんによって身体の病気は異なるため、漢方薬を服用する頻度や回数も異なります。このとき、漢方薬は1日3回飲んでも大丈夫なのかと疑問に思う人もいるかもしれません。 投薬の頻度、時間、投与方法は、患者の状態と客観的な状況に基づいて決定されます。薬を飲む頻度を決める主な要因は何でしょうか? 1つは病気の原因です。外邪によって生じた病気であれば、外邪を祓い、風寒を払い、清熱湿を清め、清熱解毒をし、清熱湿を清め、清風を祓わなければなりません。このような外邪の侵襲による病気の場合、薬を一日二回服用するのではなく、もっと頻繁に服用しなければなりません。『熱病論』や『金閣』には、一日三回夜に一回服用する、一日三回夜に三回服用するなどの記載があります。したがって、薬を服用する頻度は、さまざまな病原体とその性質に応じて決定する必要があります。 もう一つは、病気の重症度に応じて薬の服用頻度を決めることです。熱が高い場合は、症状が治まるまで2時間または1時間ごとに薬を服用してください。症状が軽い場合は、薬の服用頻度を減らしてください。 また、脾臓や胃の機能に応じて薬の服用頻度を決める必要があります。脾臓や胃の機能が良くない場合、薬を1日2回服用したり、一度に全部服用するよう指示すると、胃が耐えられず、病気を悪化させる可能性があります。この場合、脾臓や胃の機能に深刻な影響を与えないように、少量ずつ数回に分けて服用するように指示することができます。脾臓や胃が弱い患者は少量ずつ頻繁に食事を摂るべきであり、薬を飲む場合も同様です。嘔吐のある患者は、一度に薬を多く服用しないでください。多量に服用すると、薬が効き始める前に吐き出してしまい、痛みが増します。 漢方薬を服用する際のタブーは何ですか? 1. 薬の効果に影響を与える可能性のある食品を避けてください。例えば、生の冷たい食べ物、濃いお茶、辛い食べ物や脂っこい食べ物、大根、魚料理などです。これらの種類の食品の中には、薬効を中和して効能を低下させるもの、吸収を低下させるもの、さらには有害な影響を及ぼすものもあります。したがって、漢方薬を服用する場合は、医師のアドバイスに従い、特定の食品を避ける必要があります。 2. 即効性を求めて漢方薬を過剰に、または長期間服用することはお勧めできません。例えば、カシア種子には血中脂質を下げる効果がありますが、カシア種子を長期にわたって摂取すると下痢を引き起こす可能性があります。干し草は脾臓を養い、気を補充し、熱を消し、解毒する働きがありますが、長期にわたって摂取すると高血圧を引き起こす可能性があります。 「薬はどれもある程度毒である」という民間の諺は、まさにこの真実です。 3. 特別な身体疾患のある人は、漢方薬を慎重に服用する必要があります。例えば、脾臓や胃が弱い人は、野菊を配合した漢方薬を服用すると、胃の不快感や腸のゴロゴロといった症状を経験することがあります。自分の体の状態を把握するには、まず漢方医に相談するか、自己検査を行うのが最善です。典型的な身体症状がある場合は、漢方薬を服用する前に、対応する禁忌を理解しておく必要があります。 |
>>: サフランは沸騰したお湯に浸したほうがいいですか、それともぬるま湯に浸したほうがいいですか?
推薦する
肺炎球菌性肺炎の治療方法
肺炎には多くの種類があり、すべて原因に応じて名前が付けられているため、肺炎球菌性肺炎がどのようなもの...
紅麹の効能と禁忌
紅麹米について多くの人が同じような認識を持っており、単に料理に使う調味料だと思っていると思います。そ...
北木瓜粉の効果
バイモとカラスウリの粉末は、主に喉の乾燥や舌苔の白化、痰の吐き出しの困難などの一般的な問題の治療に使...
隠れた脳腫瘍、脳腫瘍の高リスク要因は何ですか?
腫瘍の初期段階では圧迫症状が現れない場合があります。腫瘍が大きくなるにつれて、さまざまな程度の圧迫症...
糖尿病患者の足は腫れますか?なぜですか?
脚の腫れは糖尿病患者によく見られる症状です。糖尿病患者の高血糖は血液の粘度を高めやすく、血管が詰まり...
頭から膿が出たり、排尿時に刺すような痛みが生じる原因は何でしょうか?
男性生殖器は比較的複雑な組織です。例えば、男性生殖器の先端は陰茎亀頭または陰茎亀頭とも呼ばれ、毛細血...
高齢者が冬に健康を保つには、これらのことを心に留めておく必要があります
高齢者は冬の健康問題に注意する必要がありますが、これは健康に良いことです。誰もがまず注意しなければな...
腹部膨満や便秘がある場合の対処法
便秘は日常生活の中で何度も起こるため、多くの人にとっては非常に馴染み深いものです。便秘にはさまざまな...
清林顆粒はどのような病気を治療しますか?
清林顆粒は、ナデシコ、ツルドクダミ、アケビ、オオバコ(塩炒め)、長石、クチナシ、オウレン、生甘草を原...
かゆいときに顔を洗う最良の方法は何ですか?
顔のかゆみを治療するには、まず原因を突き止め、適切な薬を処方してすぐに効くようにしなければなりません...
乳房に温湿布をすると痛みが和らぎますが、乳房の痛みを和らげる方法は他に2つあります。
乳房の痛みが生じた場合、通常は温湿布を当てることで痛みを和らげることができます。一般的に、乳房の痛み...
乾燥・熱体質を改善するには?軽めの食事がおすすめ
冷え性体質の人に比べて、熱性体質の人は心火が強く、暑さを恐れる傾向が強いです。特に夏場は、心火が過剰...
トン・レン・タン・シャーフー・シュガン・サン
多くの人が知っているように、黄耆は清熱鎮火、女性の子宮問題や月経問題を調整する伝統的な漢方薬です。こ...
野生のツル草は何を治療しますか?
野鶴草の薬効成分は苦味があり、風や湿気を取り除き、筋肉や腱をリラックスさせ、手足のしびれなどの症状を...
お腹がゴロゴロ鳴る
多くの人は、風邪をひいたり冷たい食べ物を食べた後、げっぷやおならが出たり、お腹がゴロゴロ鳴ったりする...