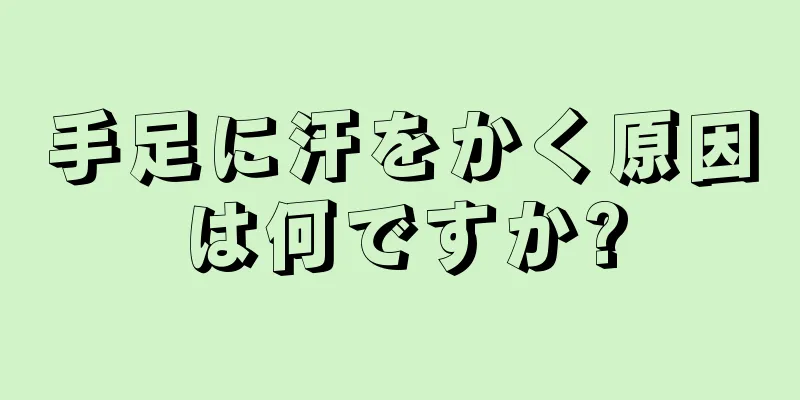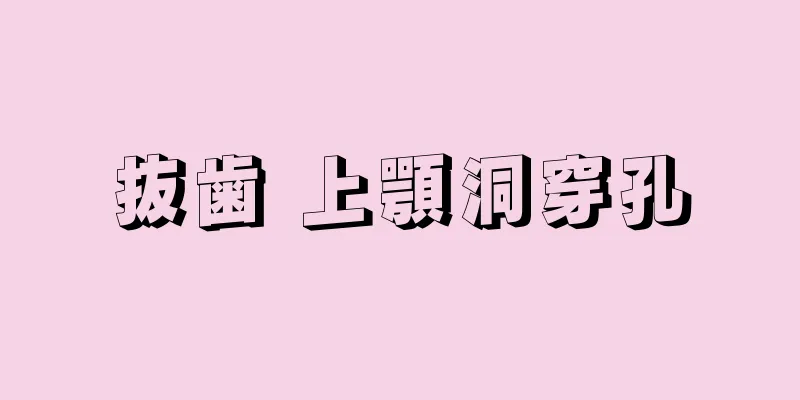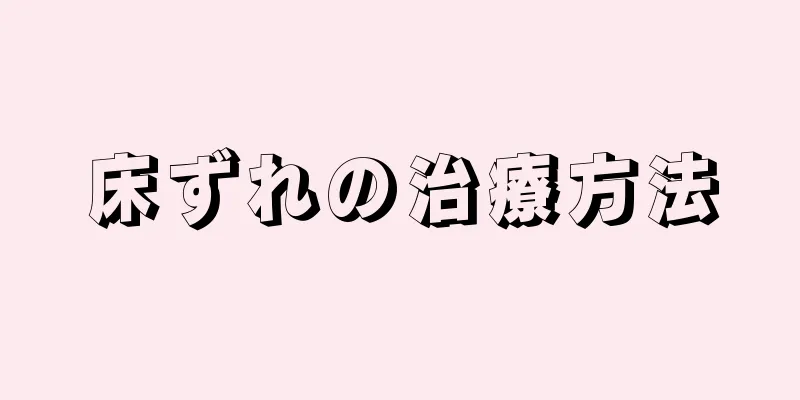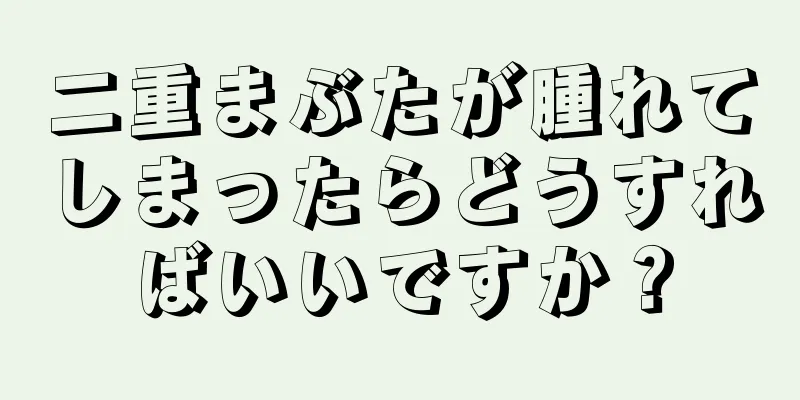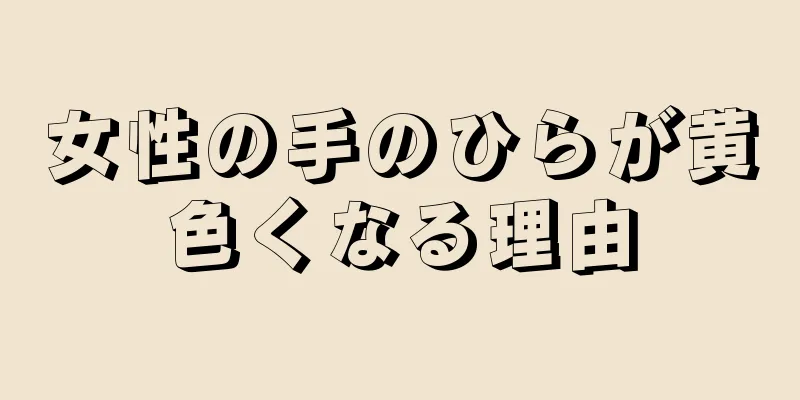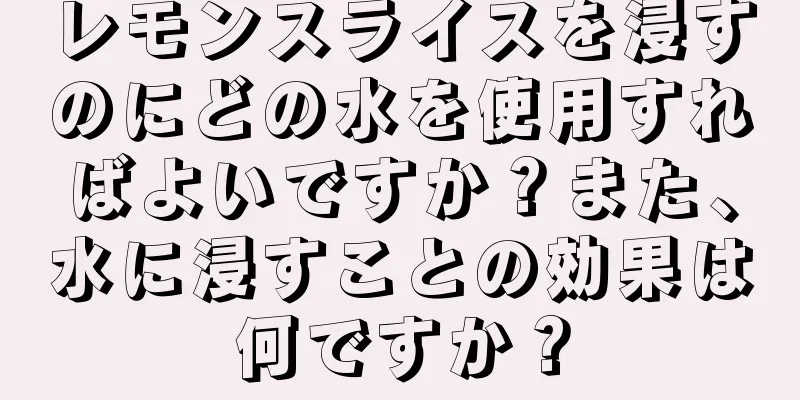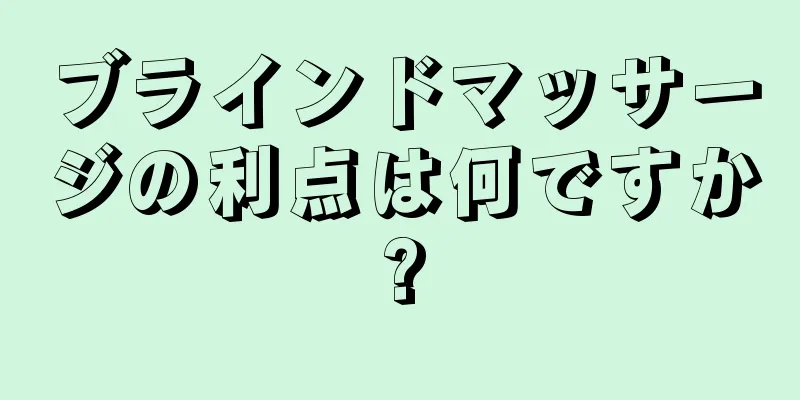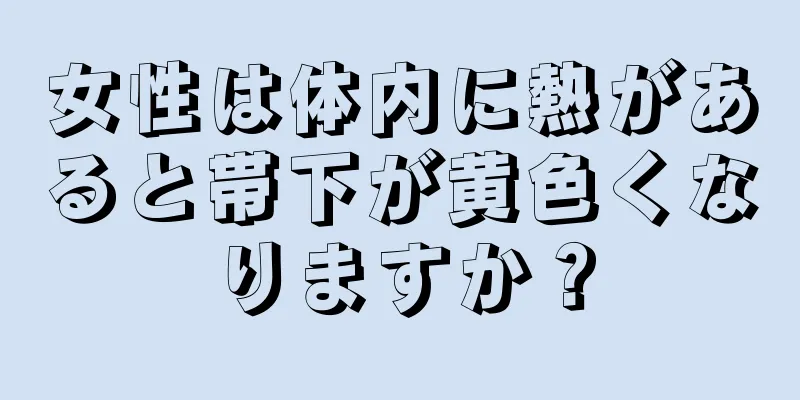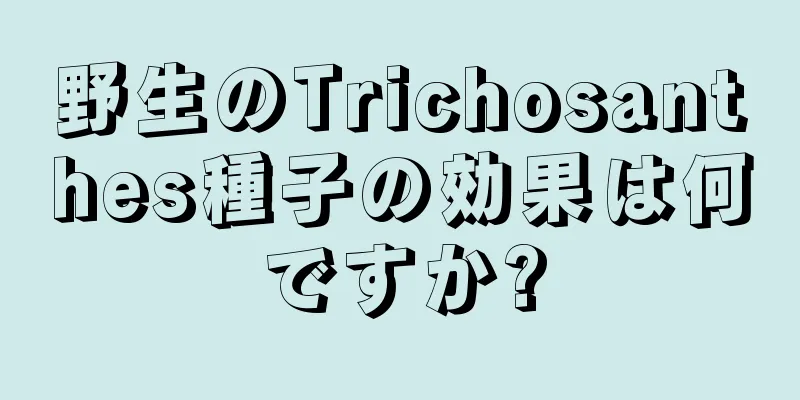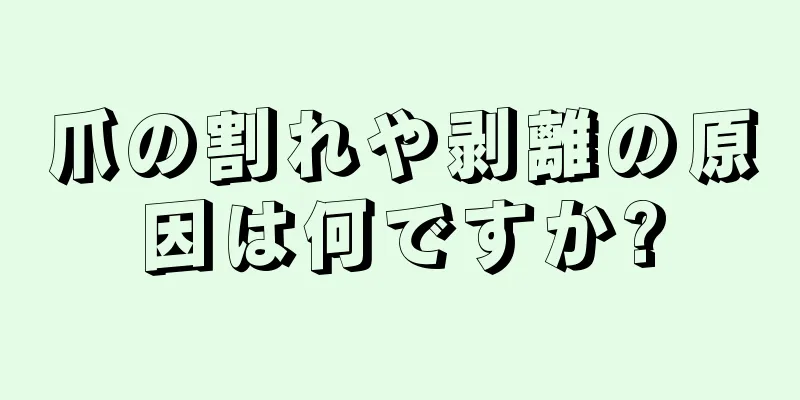足のトゲを取り除く方法
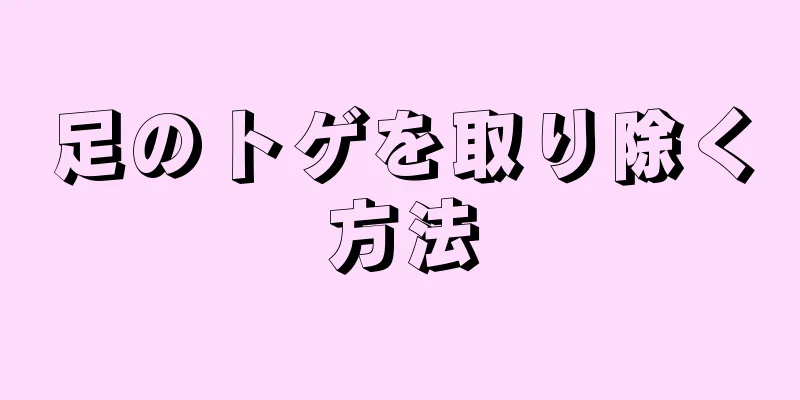
|
角膜は摩擦と圧力によって引き起こされる皮膚の問題です。足に魚の目があると、痛みや不快感を感じるだけでなく、正常な歩行機能にも影響を及ぼし、人々に多くの不便をもたらします。足に骨棘がある場合は、外用剤を使用して骨棘を取り除いたり、理学療法や外科手術で除去したりすることができます。ここでは足の魚の目の原因、症状、治療法などを紹介します。
1. とげはどのようにして形成されるのでしょうか? 長時間立ったり歩いたりする人に起こりやすく、摩擦と圧力が主な原因です。 きつい靴や変形した足の骨により、摩擦や圧力を受ける足の部分の角質層が厚くなり、内側に押し込まれ、上部が内側を向いた円錐形の角質物質が形成されることがあります。 2. 魚の目(たこ)の症状と兆候 皮膚病変は円形または楕円形の局所的な角質増殖です。 ピンの頭から豆の大きさ、淡黄色または濃黄色。 表面は滑らかで皮膚表面と同じ高さかわずかに盛り上がっており、境界は明瞭で、中央に逆円錐形があり、角質栓が真皮に埋め込まれています。 角質栓の先端が真皮乳頭の神経終末を刺激し、立ったり歩いたりするときに痛みを引き起こします。 魚の目は、足底の前部と中央部にある第 3 中足骨頭、中足骨の脛骨縁、小指と第二指の背側、または指の間、その他の突出して摩擦が生じやすい部位に発生することが多いです。 3. トゲを取り除く方法 1. 外用腐食剤:外用としてトウモロコシ膏またはトウモロコシ軟膏を塗布します。10% サリチル酸氷酢酸、30% サリチル酸コロジオン、クリスタルクリームも使用できます。 局所腐食剤は周囲の皮膚を保護する必要があります。亜鉛華テープの中央に皮膚病変と同じ大きさの小さな穴を開け、皮膚病変に貼り付けて病変を露出させます。テープの細い帯をロープ状に巻いて穴を囲み、ダムを形成します。次に薬を塗り、大きなテープで覆います。テープを密封し、剥がれるまで3〜7日ごとに包帯を交換します。 2. 理学療法:電気焼灼術、炭酸ガスレーザー焼灼術、接触型X線照射。 3. 外科的切除。 IV. 注意事項 魚の目が生える原因は様々ですが、特に季節の変化が原因となることがあります。秋以降は気温が下がり、湿度が下がります。肌は適応する必要があります。この時期は水分補給に重点を置き、水をたくさん飲む必要があります。喉が渇くまで飲まないでください。 患者の体にビタミンが不足すると、指に魚の目ができることもありますので、日常生活でビタミンを補給することが重要です。ビタミントローチを飲んだり、ビタミンが豊富な果物や野菜を食べたりしてください。油分や塩分の多い食べ物を食べすぎないようにしてください。 一般的に、魚の目は見た目に悪影響を与えるだけでなく、感染症や炎症を起こしやすいです。そのため、手で強く引っ張ってはいけません。皮膚が裂けて大きな痛みを引き起こす可能性があります。専用のハサミを使用して、きれいに切り取ってください。手のケアに気を配り、ハンドクリームを多めに塗ってください。 魚の目がひどくて感染症を引き起こしている場合は、早めに病院に行って治療を受けることをお勧めします。毎日の食事は軽めにし、ビタミンが豊富な新鮮な果物や野菜をもっと食べるようにしましょう。普段からハンドケアに気を付けましょう。 |
推薦する
汗をかくと体重が減りますか?
ダイエットを計画している女の子は、信頼できる方法を見つける必要があります。一般的なダイエット方法は絶...
授乳中の下痢にはどんな薬を飲めばいいですか?
授乳期間中は薬を服用するのは適切ではなく、薬が赤ちゃんに多かれ少なかれ影響を与えるため、女性は授乳期...
尿に血が混じったらどうすればいい?中国の老医師は食生活の調整を勧める
男性の中には、尿に血が混じっていることに気づく人もいます。これを血尿といいます。男性は火事が多すぎて...
うつ病に対する中医学の治療法は何ですか?
うつ病といえば、多くの友人はこれを精神疾患だと考えています。治療したいなら、心理学者を見つけて薬を飲...
ゴナドトロピンの副作用
尿性ゴナドトロピンは注射薬です。絨毛性ゴナドトロピンと併用すると、性腺ホルモンの分泌を促進する効果が...
ああ、どうして私はいつもこんなに眠いのでしょうか?自分の体をチェックしに行ってください。
冬眠状態に入ってしまったせいで一日中眠いと感じていませんか?いいえ、甲状腺に問題がある場合は、眠気や...
タンポポの草を水に溶かして飲むとどんな効果があるのでしょうか?
青空の下、白いタンポポが舞う光景を夢想したことがある女の子は多いのではないでしょうか。実際、タンポポ...
当帰柳黄煎じ薬の禁忌
漢方薬煎じ薬は、漢方薬の伝統的な解決策であり、煎じ薬の品質は臨床治療効果に直接関係しています。当帰六...
子宮頸管脱の治療方法
毎日コンピューターの前に座っているため、頸椎が突出してしまい、非常に憂鬱になっていると訴える人がよく...
陥没乳首の原因は何ですか?
女性の陥没乳頭も比較的よく見られる症状です。主な原因は遺伝的なものです。もちろん、二次的な陥没乳頭に...
赤ちゃんがひどい下痢を起こした
赤ちゃんの胃腸は比較的弱いので、親は特に食事に気を付けなければなりません。問題が発生すると、赤ちゃん...
ナマコと冬虫夏草の効果とは
ナマコにしろ冬虫夏草にしろ、どちらも非常に貴重な漢方薬であり、また比較的貴重な滋養強壮剤でもあります...
脂肪肝に効くお灸のツボ
脂肪肝は主に中高年に発症する病気です。発症した場合は治療を強く求め、再発しないようにする必要がありま...
肺風邪の治療法は何ですか?
昨今の高齢者は皆とても体が弱く、その多くが冷肺疾患を患っています。冷肺疾患に悩まされることは、高齢者...
色黒? 6つの顔色から病気を予測、中医学でその見分け方を教える
伝統的な中国医学では、観察、聴取、問診、触診を重視します。顔色を観察することで、人の健康状態がわかり...