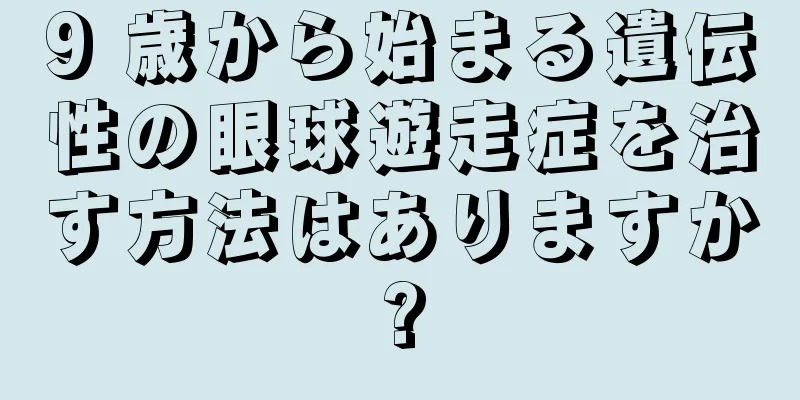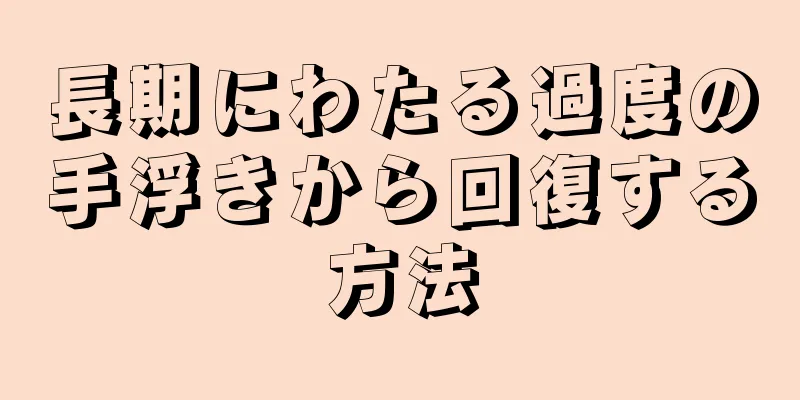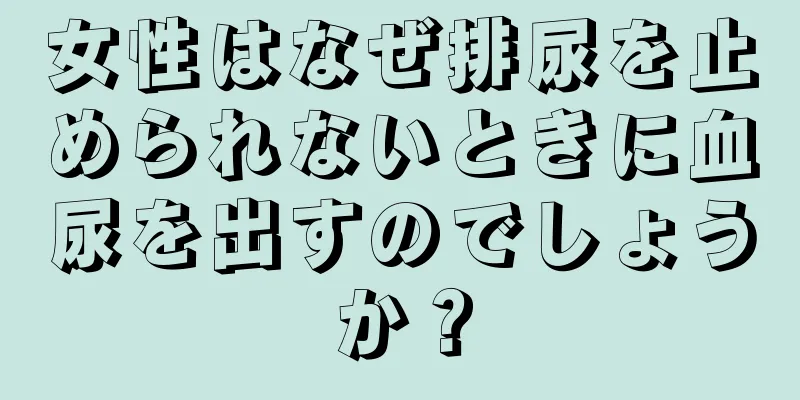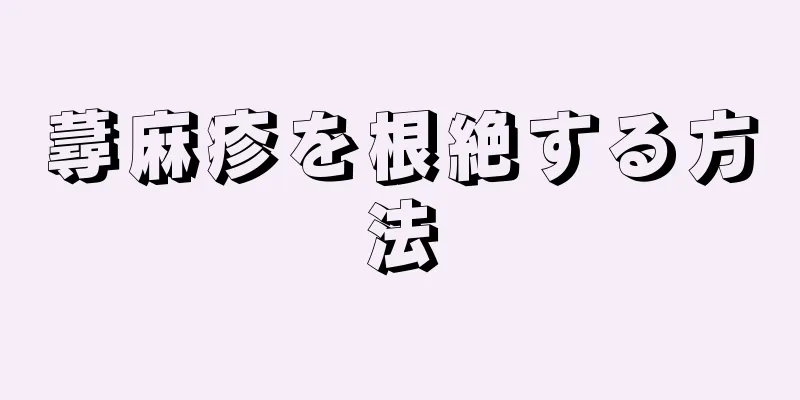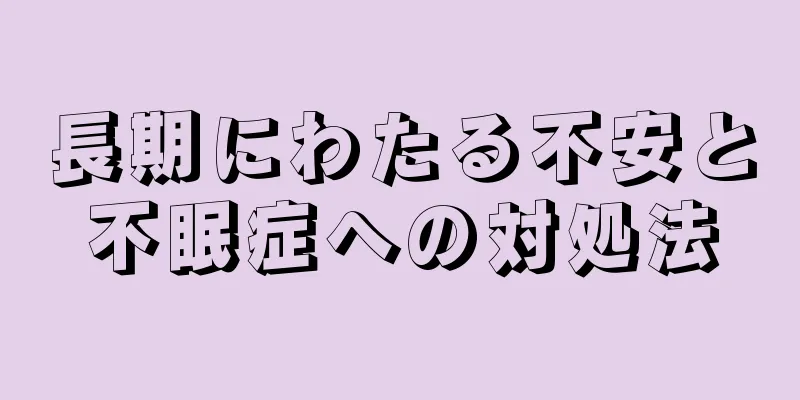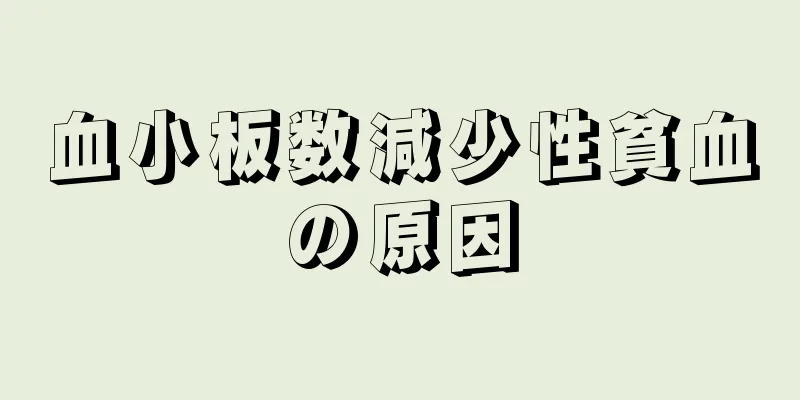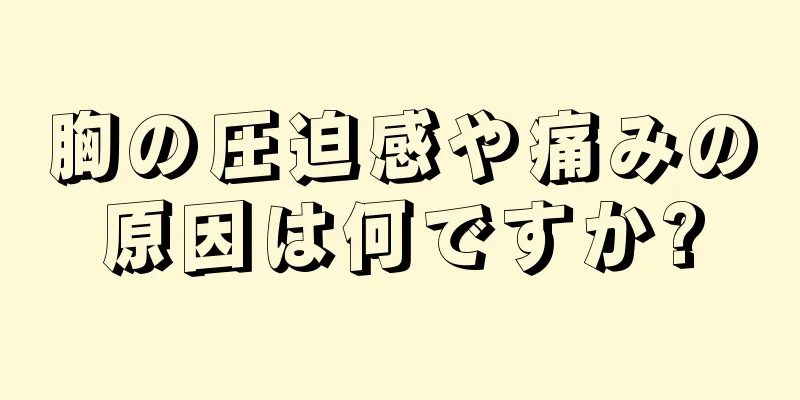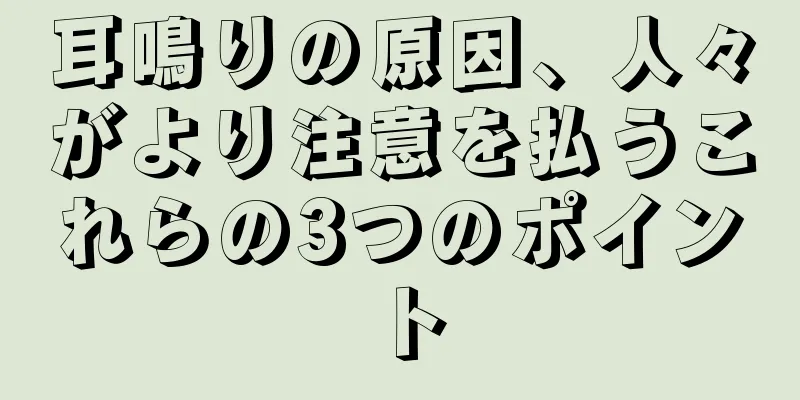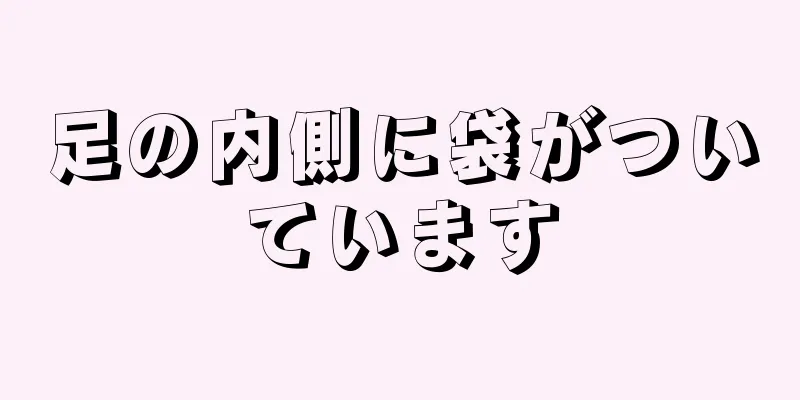中医学脈診入門
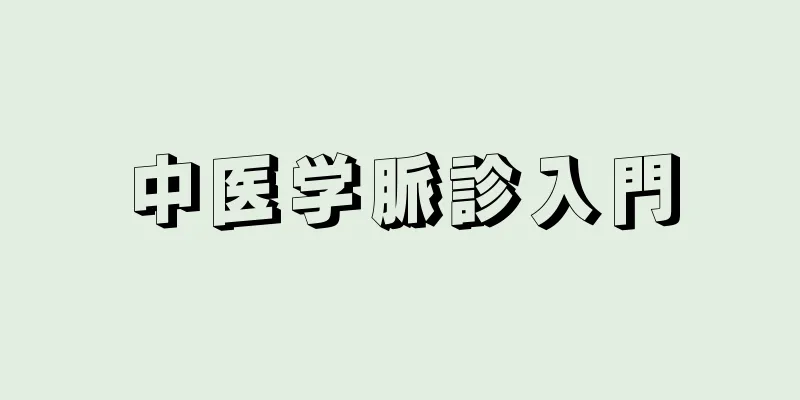
|
伝統的な中国医学では、観察、聴診、問診、触診を重視します。触診とは、脈を測ること、または脈を診断することを意味します。現在、多くの人が中医学について誤解しています。しかし、何千年も受け継がれてきた中医学は、一部の人が言うように全く役に立たないということはありません。中医学を学びたいなら、中医学の脈診から始めなければなりません。脈を測るだけに目を向けてはいけません。すべての身体の病気は脈に反映されます。それをよく学ぶには、本当に努力が必要です。次に、中医学の脈診について紹介します。 伝統的な中国医学によれば、左手と右手の「寸・関・気」の意味は異なります。左手の「寸・関・気」は「心臓、肝臓、腎臓」を表し、右手の「寸・関・気」は「肺、脾臓、腎臓(生命門)」を表すため、伝統的な中国医学では両手を使って脈を測る必要があります。これらを理解したら、脈の状態を分析する方法を学び始めることができます。伝統的な中国医学では、脈を20〜30種類に分類しています。普通の人は、それらすべてを理解する必要はありません。ここでは、脈の上昇と下降、強さ、厚さ、速さ、停止と拍動など、一般的な脈の状態をいくつか紹介します。1. 上昇と下降の2つの状況があります。一つは、脈に手を軽く当てる方法です。少し力を入れるだけで、はっきりとした脈を感じることができます。これを浮脈といいます。まったく感じられない場合、骨にほぼ触れるまで圧力を強めていくと、はっきりとした脈が感じられるようになり、これを沈下といいます。力を使わなければ感じられない場合、少し力を入れて押しても底まで届かない場合は、沈まず浮かずの状態といいます。また、力の入れ具合によって沈む(力が強い)、浮く(力が弱い)とも呼ばれ、総じて中といいます。もう一つは、脈を測るときに、脈の部位である兪脈だけが感じられ、関と気の部位ははるかにわかりにくいため、浮脈とも呼ばれます。また、類推的に、兪脈と気の部位はわかりにくいが気の部位は明らかな場合、沈脈とも呼ばれます。また、脈の部位と気の部位はわかりにくいが、関の部位は明らかな場合、中脈とも呼ばれます。 なぜ脈に浮沈の差があるのでしょうか?一般的に言えば、身体の防御機能が外邪と戦うとき、まず「表面」から問題を解決しようとします。体液、気、血はすべてここに集まって戦います。そのため、ここには気と血が十分あり、脈は浮兆を示します。ここで問題が解決できない場合、邪気は内側に進み、正気は内側に後退し、気、血、体液は中間部(半分は表面、半分は内部)に集中し、脈は中兆を示します。邪気が再び勝利して内側に進むと、正気は再び敗北して内側に後退し、すべて内部に後退し、そこで邪気との必死の戦いを戦う力を蓄え、脈は沈兆を示します。つまり、陽のエネルギー(体液、血、気血)が集まるところは、脈の対応する部分に反映されるので、これを念頭に置いておけば、脈を観察することは難しくありません。2. 力を入れて脈を探した後、ただじっと押すだけでは十分ではありません。医師はいくつかの「ちょっとしたトリック」を使います。ゆっくりと力を入れて押し下げ、少し力を弱めて指を元の位置に戻します。これを数回繰り返します。なぜそうするのでしょうか? それは、指を使って脈の力を指で感じることができるからです。押すと脈が硬く、しっかりしていて、強い反発力を感じる場合は脈が強い証拠です。 「どこを押しても抵抗しないよ!」と指が触れてもあまり抵抗がなかったり、少し力を入れると脈が消えてしまうような場合は、弱い脈です。医師はこれをもとに脈が弱いか強いかを判断します。 では、強い、または弱いというのはどういう意味でしょうか?強いというのは陽気が強いということですが、邪気と陽気が同じであれば、漢方医は常に邪気が強く陽気が大丈夫だと言い、邪気のレベルに応じて治療します。力が足りないということは、気力が不足しているということです。治療では、まず気を補い、支えなければなりません。気力が十分であれば、自然に邪気と戦うことができるようになります!治療法の観点から見ると、強い脈に対して、漢方では攻排の方法をとります。例えば、麻黄煎じ薬の場合は脈が締まっている必要があり、成気煎じ薬の場合は脈がしっかりしている必要があります。この締まってしっかりしているということは、強くなければならないということです。脈が弱い場合、これらの処方を使用すると、患者は倒れて失神してしまいます!弱い脈に対して、漢方では補う方法をよく使います。例えば、桂枝煎じ薬の脈は遅く、紫丹煎じ薬の脈は弱いです。これらは攻撃できず、養うことしかできない弱い脈です。どのくらいの量を使うか、攻めの部分に滋養成分を加えるか、強めの部分に攻めの成分を加えるか、またどのくらい加えるかは脈の強さによって決まります。 3. 脈の強さを知るだけでは十分ではありません。ちょっとしたコツもあります。指を使って、親指側から小指側、小指側から親指側など、水平に繰り返しマッサージまたはこすって、血管の広さを感じてみましょう。平たく言えば、脈の太さや細さを見るということです。生命エネルギー、体液、血液は十分あるので、それらを移動させて外に輸送する必要があります。これには大きな力が必要なだけでなく、輸送経路(血管)のスペースも大きくなければなりません。そうでなければ、生命エネルギーは十分であってもスペースが不足し、リアルタイムで輸送することができません。そのため、中景は「陽明脈は大きい」と言いました。陽明には血と気が多く、それを運ぶためには血管が大きくなければなりません。同様に、「薄い」ということは、もちろん気と血が豊富でないことを意味します。しかし、珍しい状況もあります。臨床診療では、脈は大きいが弱い、あるいは脈は小さいが強いという例がよくあります。なぜでしょうか?これには気血の過剰または不足の問題が関係します。気と血は陰陽の二つの道具です。気は血液を体中に輸送し、注入する役割を担っているため、陽であり、自動的で、膨張します。一方、血は陰であり、滋養を与え、非常に現実的な形(液体)を持ち、見たり触れたりすることができます。脈の強さや太さは気と血の共通の成果ですが、血は脈の強さに焦点を当て、気は血管の太さに焦点を当てています。両者が強いときは脈は太く力強く、両者が弱いときは脈は細く弱く、気が弱く血が強いときは脈は細く力強く、気が強く血が弱いときは脈は太く弱く。なので、厚さや細かさは最後まで見届ける力があるかどうかにも左右されるんです! 中医学では、これに基づいて気を司る薬を使うか、血を司る(陰を司る)薬を使うかを判断します。例えば、現代人は陰虚で陰を養う必要があるとよく言い、ロバ皮ゼラチンや寿烏汁などの陰を養う薬を服用しますが、脈が細いと、これらを服用した後にニキビができやすくなります。また、人参や黄耆などの気を補う薬を好んで服用する人もいますが、脈が太いと、これらを服用した後に怒りっぽくなったり、不眠症になったり、不安になったりします。もちろん、これは単なる一般的なルールです。漢方薬を使用する際に考慮すべき細かい点はたくさんありますが、ここでは説明しません。 4. 正常な脈拍の速さはどのくらいですか? 「蘇文・常人の気と形相について」には、「人が息を吐くとき、脈拍は2回打ち、息を吸うとき、呼吸が安定しているときは脈拍は5回打ち、呼吸を速めるために1回余分に打ちます」とあります。これは、正常な人の場合、呼吸のリズムは固定されており、1回の吸入と1回の呼気の間に脈拍は4回打つべきであることを意味します。シンプルで実用的に聞こえますが、実際には理解するのが非常に困難です。人の呼吸は速かったり遅かったりしますが、誰の呼吸が標準なのでしょうか? この分野における西洋医学の研究は、伝統的な中国医学に大きな助けとなっています。 西洋医学の研究結果によると、正常な成人の脈拍数は1分間に約75回です。高齢者の脈拍数は比較的遅く、若者の脈拍数は比較的速く、乳児の脈拍数はさらに速くなります。この基準により、速いか遅いかを簡単に判断できます。基準回数に達しない人は遅いと呼ばれ、基準回数を超える人は速いと呼ばれます。速度を判断することの意味は何でしょうか?「南京」には「速いは熱、遅いは寒」とあります。これは、速いということは、身体の病気と闘う自己防衛システムが比較的活発で自動的な状態にあることを意味し、遅いということは、病気と闘う機能がすでにかなり消耗しており、消極的、受動的、または諦めた状態に入っていることを意味します。伝統的な中国医学は、脈の速さに基づいて治療戦略を選択します。脈が速い場合は、積極的に協力して邪気を排除し、身体に十分な食料と弾薬を提供します。脈が遅い場合は、まず欠乏を評価して身体を強化し、邪気を攻撃しようと急がないようにしています。戦う気もないのに、無理やり食料や飼料、弾薬を与えて前線に行かせれば、敵に降伏するか、脱走兵になるかのどちらかだ。まずは思想活動で闘志を奮い立たせる必要がある。 s |
推薦する
新生児が母乳を飲みたがらない場合の対処法
一般的に、新生児は母乳で育てられた方が健康であり、いかなる粉ミルクも母乳の栄養にはかないません。しか...
小陰唇の縁に長い肉片がある
小陰唇の縁に長い肉片が現れる現象は、臨床的には外陰炎として知られています。外陰炎は単一の病気ではあり...
ヤムイモアレルギーによるかゆみを和らげる方法
ヤムイモは、陰と腎臓を養い、体を強くし、新陳代謝を促進する植物です。ヤムイモは美味しくて栄養価が高い...
水に浸した黄連を飲むことの効果と効能
オウレンは漢方薬の一種で、多くの人が服用しており、補助的な医療効果を得ることができます。まず、熱を清...
硫黄クリームの役割
硫黄軟膏は独特の硫黄臭のある黄色の軟膏です。疥癬、細菌、真菌を殺す効果があり、油分を除去し、表皮を柔...
低度脂肪肝の治療方法
低度脂肪肝も比較的軽度の脂肪肝であり、適切な治療とコンディショニングのみが必要です。一般的に、症状は...
歯茎が腫れている場合、食べられないものは何ですか?
日常生活で、誰もが歯茎の腫れや痛みに悩まされたことがあります。この病気は本当に痛いのですが、ほとんど...
滑膜炎の原因は何ですか?その理由は次のとおりです
滑膜炎の原因は様々で、種類も様々です。若者の場合、滑膜炎は風邪の感染によって引き起こされる場合があり...
腰椎脱臼を治療するには?
腰椎脱臼は比較的よく見られる症状ですが、より深刻な腰椎の問題でもあります。厳密に言えば、腰椎脱臼は治...
ネズミは狂犬病に感染しますか?
すべての犬が狂犬病に感染するわけではありませんが、狂犬病に感染した犬に噛まれたり、ウイルスに感染した...
視神経萎縮を効果的に治療する方法
視神経萎縮症は、当然ながら科学的で効果的な治療が必要です。治療に関しては、あまり神経質になったり不安...
肺気腫はどのように治療されますか?
肺気腫は日常生活でよく見られる症状でもあり、同様の状況は家庭でも屋外でも発生する可能性があります。い...
副鼻腔炎の治療方法
副鼻腔炎は、通常副鼻腔炎と呼ばれます。日常生活で非常に一般的な病気であり、主に急性と慢性の2種類に分...
生白芍薬根の効能、効果、禁忌
生白牡丹の効能と効能:生白牡丹はキンポウゲ科の緑植物牡丹の花の根です。生白牡丹の効能は、気血を養い、...
顔の骨を噛むと音がします。
噛んだときに顔の骨が音を立てる場合、顎関節症が原因の場合もあれば、炎症性関節疾患が原因の場合もあり、...