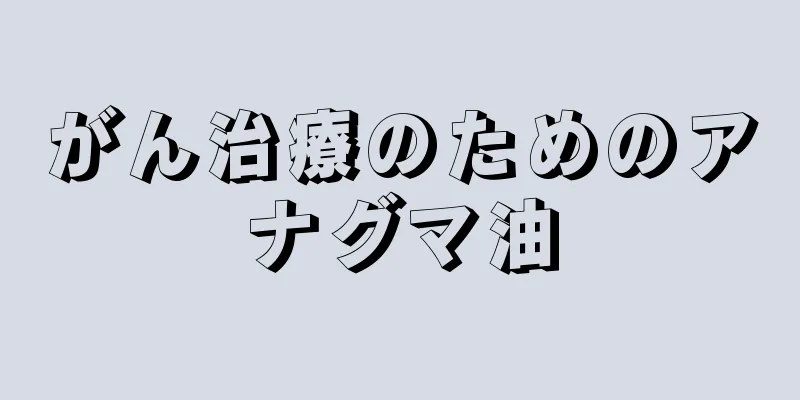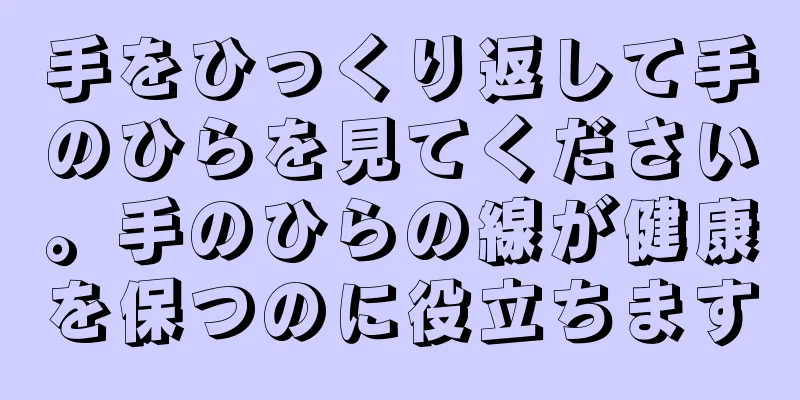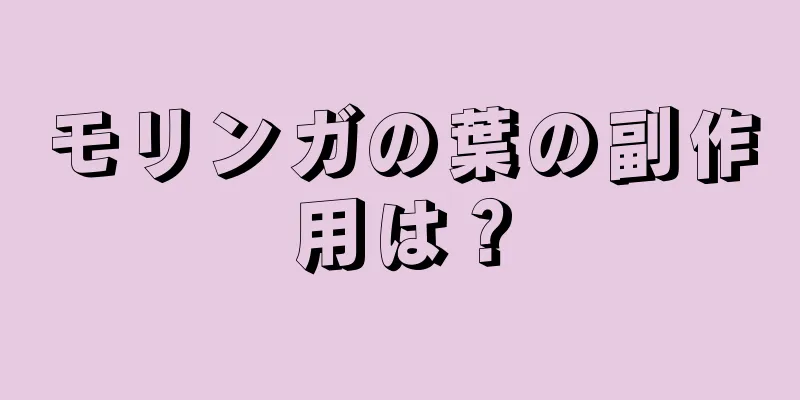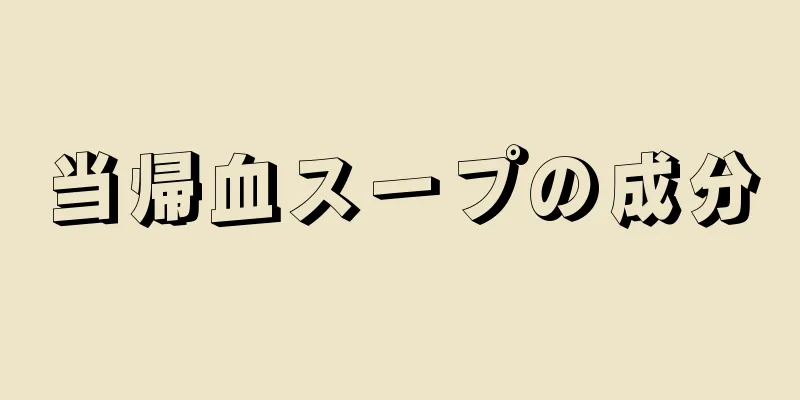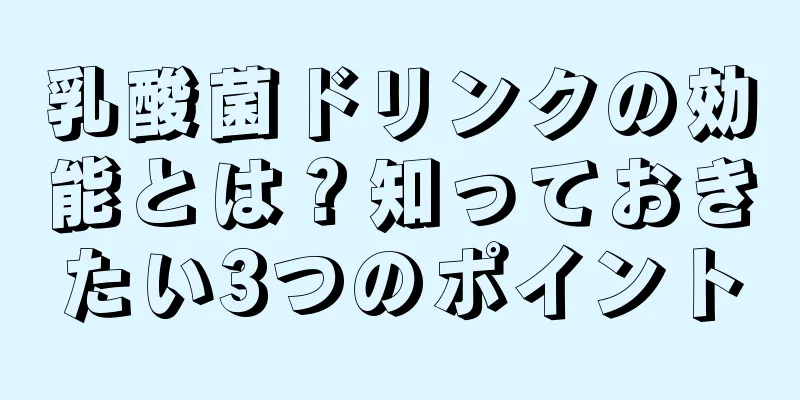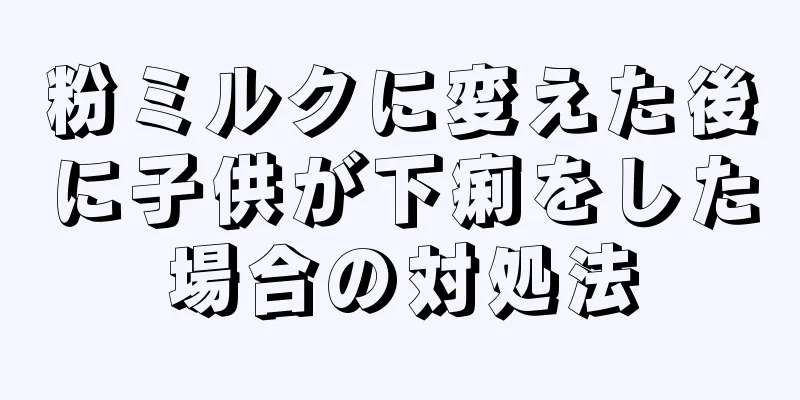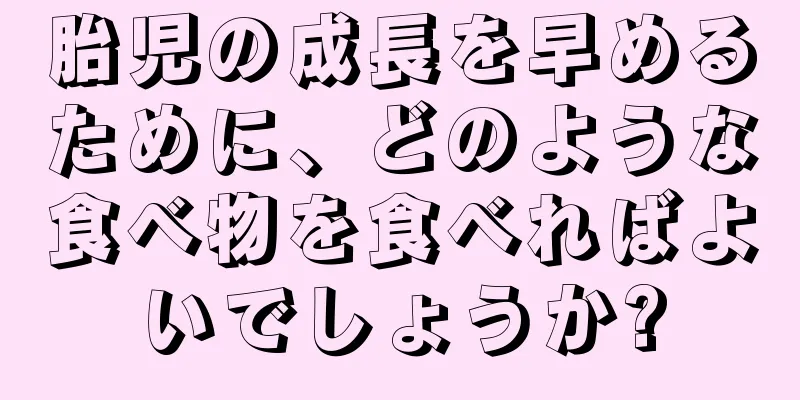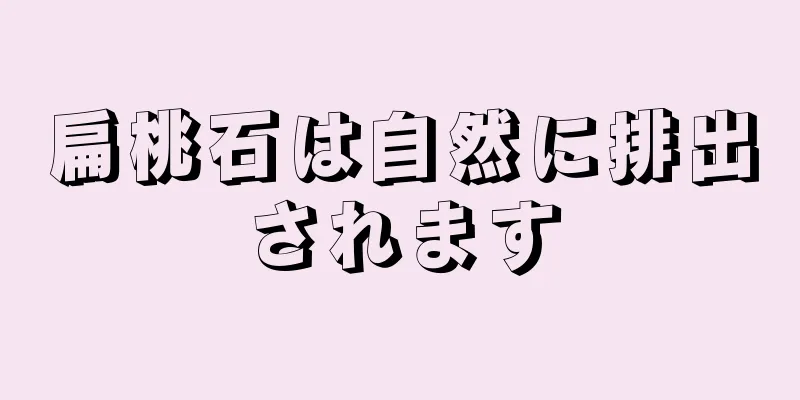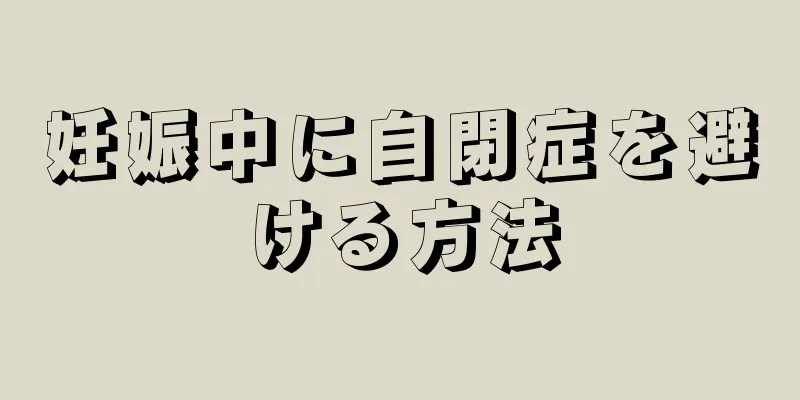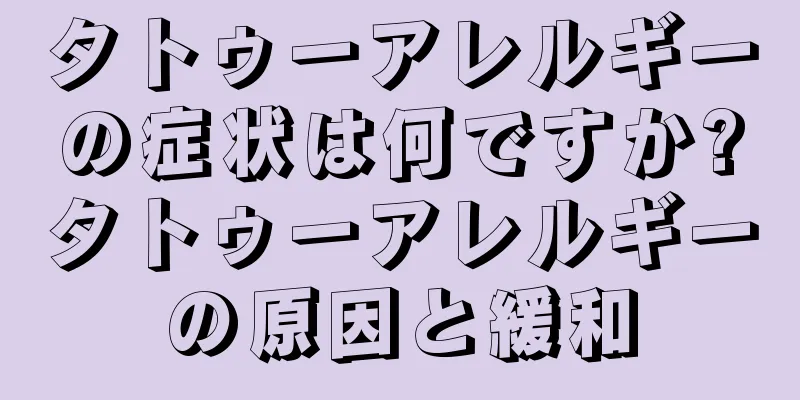中等度の僧帽弁狭窄症の場合の対処法
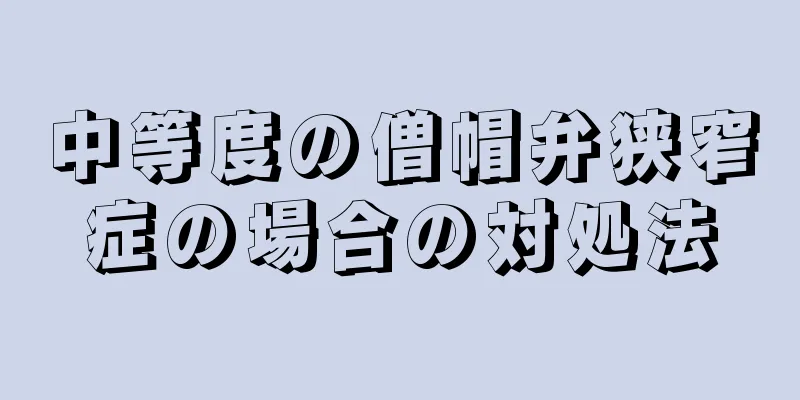
|
中等度の僧帽弁狭窄症がどのような病気なのか、またその症状や原因を知らない人は多いと思います。そのため、中等度の僧帽弁狭窄症を適切なタイミングで治療することができません。実際、中程度の僧帽弁狭窄症は、心不全や心房細動などの心臓病を指します。これらの病気は心臓の機能に深刻な影響を及ぼす可能性があり、適切な時期に治療しないと死に至ることもあります。 治療 1.薬物治療には、リウマチ熱の再発防止、感染予防、合併症の治療が含まれます。 (1)心不全は、利尿、強心、血管拡張治療を含む心不全治療の一般原則に従うべきである。急性肺水腫では、主に細動脈を拡張する血管拡張薬の使用を避けてください。 (2)心房細動の治療の原則は、心室拍動数をコントロールし、洞調律を回復し、血栓塞栓症を予防することです。 ①心室拍動数の速い急性発作:血行動態が安定している患者の場合、ジゴキシンの静脈内注射により心室拍動数を100回/分以下にコントロールすることができます。効果がない場合、静脈内アミオダロン、プロパフェノン、ベータ遮断薬(メトプロロール、エスモロール)またはカルシウムチャネル遮断薬(ベラパミル、ジルチアゼム)を使用できます。肺水腫、ショック、狭心症または失神を伴う急性発作の場合は、直ちに電気的除細動を行う必要があります。 ②慢性心房細動:罹病期間が1年未満、左房径が60mm未満、洞不全症候群や高度房室ブロックがない患者では、洞調律に戻すための薬物治療(一般的な転換薬にはキニジンやアミオダロンなど)や電気的除細動が考慮されることがあります。心房内壁血栓を除外するために、除細動の前に超音波検査を実施する必要があります。除細動が成功した後、洞調律を維持するためにアミオダロンまたはキニジンが使用されました。除細動が適さない患者の場合、経口ジゴキシン、またはジルチアゼム、ビソプロロール、アテノロールの併用により、安静時の心室拍動数を約 70 回/分にコントロールできます。 (3)抗凝固療法の適応 ①左房血栓。 ②塞栓症の既往歴がある。 ③人工機械弁。 ④心房細動。禁忌がない場合は、血漿プロトロンビン時間(PT)の1.5~2倍の延長と国際標準化比(INR)の2.0~3.0の延長を抑制するためにワルファリンが第一選択薬となります。ワルファリン抗凝固療法は、除細動の 3 週間前と除細動の 4 週間後に必要です。 2.外科的治療の選択肢: 僧帽弁狭窄症の手術には、僧帽弁形成術と弁置換術の 2 つのカテゴリがあります。一般的に、血管形成術が第一選択です。病変が血管形成術で治療困難な場合、または血管形成術が失敗した場合は、弁置換術を検討する必要があります。 (1)経皮経中隔僧帽弁形成術(PBMV)の適応: ①症状がある場合、心機能レベルIIまたはIII。 ②症状はないが、肺動脈圧が上昇している(安静時の肺動脈収縮期圧>50mmHg、運動時の肺動脈収縮期圧>60mmHg)。 ③中等度狭窄、僧帽弁面積0.8cm2≤MVA≤1.5cm2。 ④僧帽弁は柔らかく、前尖の可動性は良好で、超音波検査や画像検査で重度の肥厚や弁下病変はなく、重度の石灰化は認められない。 ⑤左房内に壁内血栓は認められない。 ⑥中等度または重度の僧帽弁逆流がない。 ⑦最近のリウマチ活動がない(抗O型および赤血球沈降速度正常)。 (2)閉鎖交連剥離術の適応は経皮的バルーン血管形成術と同じであるが、現在ではバルーン血管形成術と直視血管形成術に置き換えられている。 (3)直視下僧帽弁形成術 適応症:心機能レベルIII~IV、中等度~重度の狭窄、弁尖の重度の石灰化、腱索および乳頭筋の病変、経皮的バルーン血管形成術が適さない左房血栓症または再狭窄など。術後の症状緩和期間は8~12年で、弁置換術の2度目の手術が必要になることも少なくありません。 (4)弁形成術 僧帽弁の変形を矯正することが困難な場合は、弁置換手術が選択肢となります。 適応症: ①明らかな心不全(NYHAグレードIIIまたはIV)または生命を脅かす可能性のある合併症。 ②石灰化、変形、非弾性漏斗状僧帽弁狭窄、分離手術後の再狭窄などの重度の弁病変。 ③重度の僧帽弁逆流症を合併している。 |
推薦する
頭蓋内腫瘍の発生部位
脳は人体の中で非常に神秘的な場所です。人間は脳を頼りに考え、体のさまざまな器官の働きを指揮しているの...
脳卒中の治療
生活水準の向上に伴い、人々の食生活はますます洗練され、高カロリー、高たんぱく質の食品をますます多く摂...
妊娠6週目に出血があったらどうするか
妊娠6週目は妊娠初期です。この時期、受精卵はちょうど胎嚢に成長し、女性の子宮に着床したばかりかもしれ...
初期の痔の症状
痔は現代社会で罹患率の高い病気です。この病気の害は比較的深刻で、一度発症すると、人々は不安に陥ります...
脱毛の原因は何ですか?
抜け毛は、一般の人が脱毛と呼んでいるものです。髪をとかすと、抜け毛が発生します。毎朝髪をとかすときに...
妊娠中に胎動を感じるまでどのくらいかかりますか?
胎動は胎児の発育と妊婦の体調によって決まります。妊婦によって感じ方は異なります。通常、胎児は発育後2...
赤褐色の便の原因は何ですか?
便の色が人間の健康に直接関係していることは誰もが知っています。便の色は体の健康状態を物語ります。多く...
突然の嘔吐やめまいの原因は?注意すべき5つの理由
人生において、突然のめまいや嘔吐などの症状を経験する人もいます。一般的に、この症状に効果的に対処する...
子供の血球数が高いとどうなるのでしょうか?
赤ちゃんの血球数は、多くの場合、体の健康に密接に関係しています。血球数が高いということは、主に体内の...
月経調節種子ピル
月経は女性にとってとても大切なものです。月経が不規則だと、妊娠力に深刻な影響を及ぼします。月経不順の...
川崎病の回復期にまた熱が出た
川崎病は、臨床的には小児粘膜皮膚リンパ節症候群と呼ばれ、5歳未満の乳児に発症することが多い病気です。...
口臭の原因は何ですか?
口臭は非常に一般的です。口臭は人間の健康に大きな脅威を与えるものではありませんが、多くの患者、特に口...
漢方医は一生のうちにこれらの 10 のことを決して行いません。あなたはまだそれを行なっていますか?
清代の養生医、徐文奇は著書『手士真珍』の中で「十大禁忌」を提唱した。彼は、健康維持はまず日常生活から...
月経後の性交中の出血
人生において、女性の月経期間中に性行為をしてはいけないことは誰もが知っています。さもないと深刻な結果...
副作用の少ない抗てんかん薬
てんかんとは、再発しやすい脳機能障害の一種で、神経疾患です。てんかんの発症は年齢と密接に関係していま...