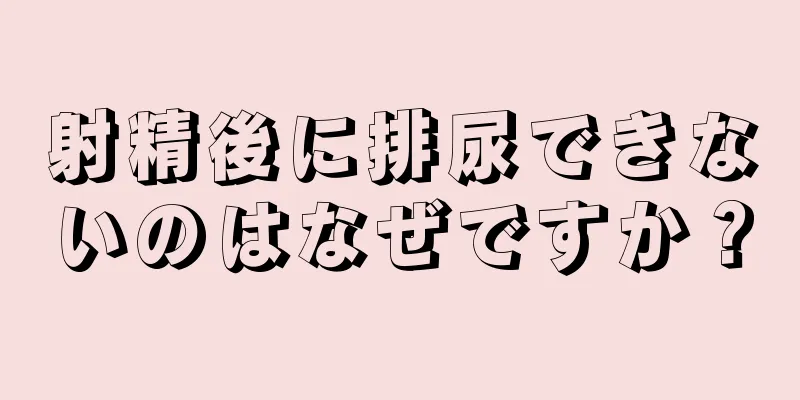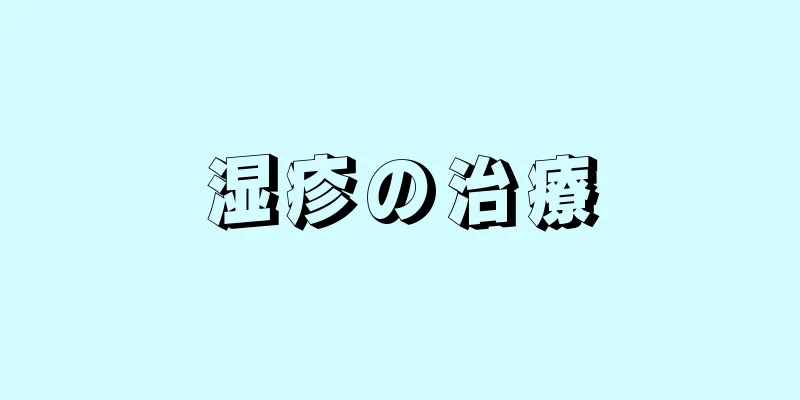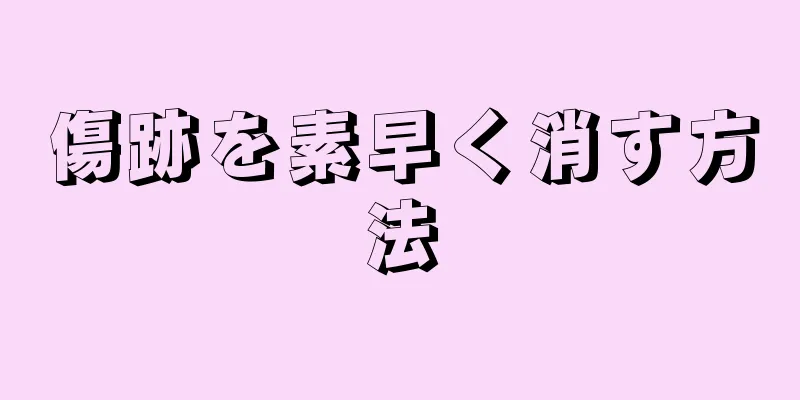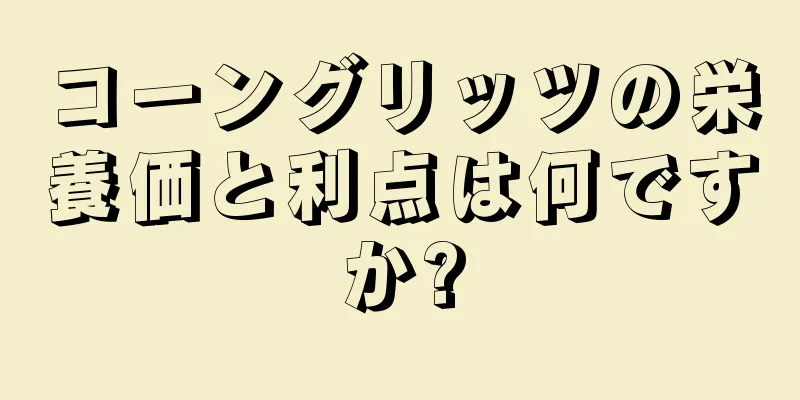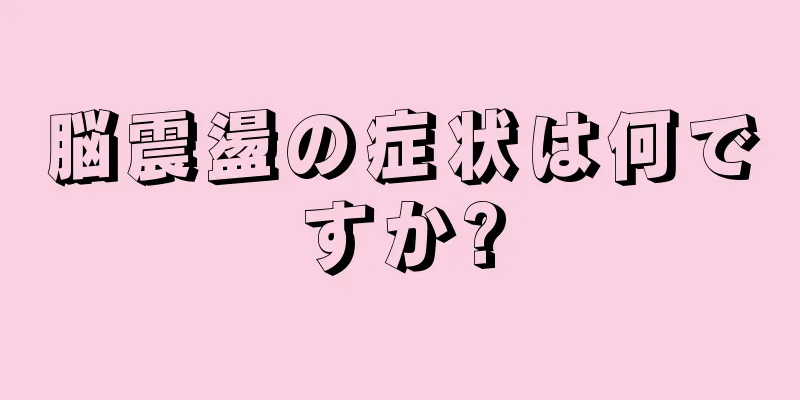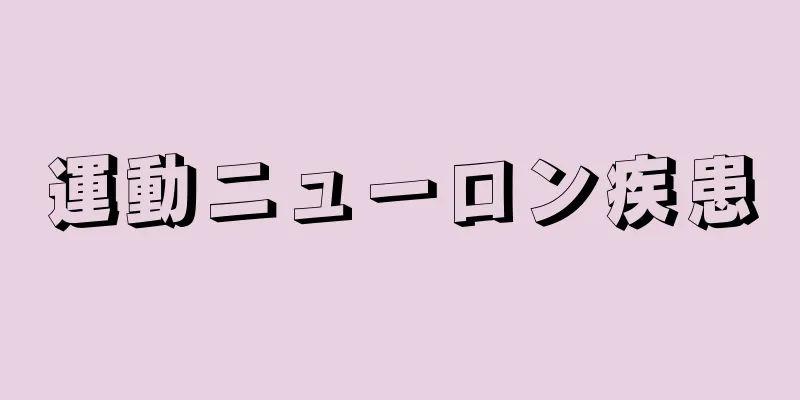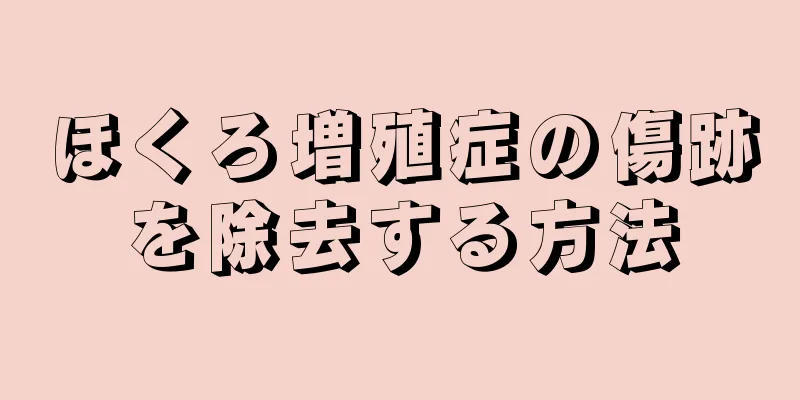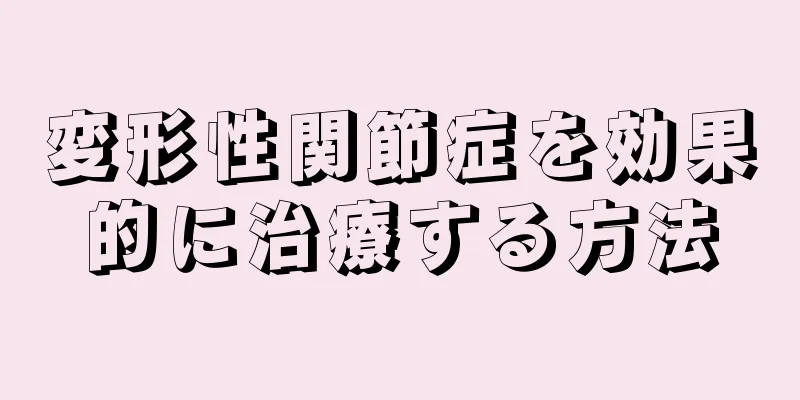漢方薬は食前と食後のどちらで飲んだ方が良いですか?
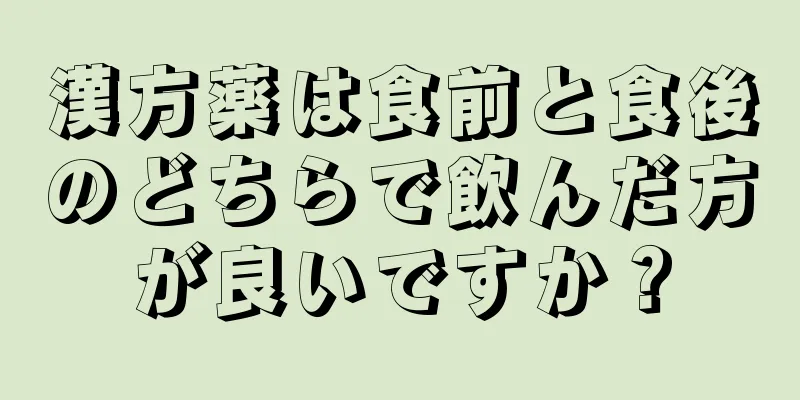
|
漢方薬の副作用は西洋薬よりも少ないため、現在では多くの人が苦い漢方薬を飲んで病気を治療しています。漢方薬の効能を最大限に引き出すには、煎じ方に注意するだけでなく、薬を飲む時間にも注意する必要があります。しかし、漢方薬を飲む時間について混乱している人が多く、食前と食後のどちらに飲めばいいのかわかりません。実際、漢方薬を飲むのに最適な時間は一般化できません。では、漢方薬は食前と食後のどちらに服用すべきでしょうか? 漢方薬は食前と食後のどちらに服用すべきでしょうか? 空腹時に服用する 暁に薬を飲むとも言われ、朝、食事の前に薬を飲むことを意味します。強壮効果のある煎じ薬は、完全に吸収されるように朝の空腹時に服用する必要があります。駆虫薬や四肢血管疾患の治療薬も空腹時に服用する必要があります。薬が腸に素早く入り、高濃度を維持して効果を素早く発揮できるようにするためです。効能を高めるための下剤効果のある煎じ薬も同様です。 食前に服用してください 通常、食事の30〜60分前に薬を服用してください。肝腎虚や腰から下の病気など、病気が体の下部にある場合は、薬効成分が体の下部に届きやすいように食前に服用する必要があります。腸の病気の治療には、食前に薬を服用することもお勧めします。なぜなら、胃が空であれば、薬液は胃腸粘膜に直接接触し、より速く胃を通過して腸に入ることができるため、胃の中で食物によって薄められて薬効が影響を受けることなく、より多くの薬液が吸収されて効果を発揮できるからです。 食後に服用 通常、食後15〜30分後に薬を服用してください。病気が体の上部にある場合は、食後に薬を服用する必要があります。心臓、肺、胸部、横隔膜、胃に関連する病気を治療する場合は、薬効成分が上方に移動できるように食後に薬を服用する必要があります。胃腸管を刺激する薬を食後に服用すると、胃腸粘膜へのダメージを軽減することができます。 就寝前に服用 通常、就寝の15〜30分前に服用します。心臓や脾臓を養い、心を落ち着かせ、睡眠を誘発する薬をこの時に服用することができます。さらに、睡眠薬、駆虫薬、抗アレルギー薬などの一部の西洋薬は、一般的に夜寝る30分前に服用する必要があります。 最後にもう一度おさらいしましょう: 漢方薬を服用するのに最適な温度は何度ですか? 「熱いうちに飲む」というのは、煎じ薬を飲むときのほとんどの人の習慣です。実は、暑いときに薬を飲む必要はありません。 一般的に、漢方薬の煎じ薬は「温かい」状態で服用します。つまり、煎じ薬を沸騰させた後、すぐに濾し、室温で30℃~40℃に冷ましてから飲みます。特に、胃腸に刺激のある薬、例えば、カラスウリや乳香などは、温めて服用すると、胃や脾臓の刺激を和らげ、刺激を軽減することができます。 錠剤や粉末の形の漢方薬は温水で服用する必要があり、これも温服用法の一種です。風寒を払う漢方薬である麻黄、桂枝、芍薬、芍薬などは、温めて服用する必要があり、服用後には温かいお粥や白湯を飲むと薬効が高まります。 甘茂清冷顆粒などの顆粒状の清熱漢方薬には、通常、熱を取り除いて病気の症状を緩和する成分が含まれています。また、熱すぎるお湯は薬の効能に影響を与えます。したがって、このタイプの顆粒状の漢方薬は、60℃〜70℃の水に溶かし、水温が40℃程度に下がったときに服用する必要があります。 最後に、編集者は皆さんにまとめたいのですが、漢方薬を食前か食後に服用するかは、病気や薬によって服用時間が異なり、一般化することはできません。医師の指導のもと、的を絞った選択を行い、自分の病気に合った処方を組み合わせ、時間通りに服用する必要があります。すべての薬にはある程度の毒性があるため、むやみに服用しないでください。 |
推薦する
正常出産後の排尿のヒント
まず第一に、女性にとって、妊娠は非常に困難なことではなく、非常に幸せなことです。妊娠中は多くの痛みを...
Citrus aurantium と Citrus aurantium の違い
オレンジの実の殻は比較的硬いので、そのまま食べることはできません。煮込みスープや飲み物に使用でき、気...
頭にお灸をしても大丈夫ですか?
実は灸は伝統的な中国医学では非常に一般的な治療法であり、多くの友人もそれを認識しています。頭にお灸を...
9歳の子供の唇は青白く血色がない
私たちの日常生活では、唇の正常な色はピンク色ですが、多くの子どもたちの唇は青白く血色がありません。年...
距骨壊死の対処法
私たちの骨は強くて固いように見えますが、実際はそうではありません。注意しないと骨壊死を引き起こす可能...
気管支喘息の治療
気管支喘息には多くの治療法があり、それは現在の医学でも同様です。気管支喘息は人間によく見られる病気で...
高尿酸血症の危険性は何ですか?
高尿酸血症が引き起こす害は比較的大きく、痛風患者は検査で尿酸値が高いことがほとんどです。また、関節の...
生理中の膣のかゆみにどう対処するか?原因を見つけることが鍵
女性の中には、月経中に外陰部のかゆみの症状を経験する人もいますが、これは主に月経中の膣衛生の問題に関...
坐骨神経痛のマッサージ方法
坐骨神経痛の患者は、正しいマッサージ方法に注意すれば、痛みをかなり和らげることができます。マッサージ...
まぶたが赤くなったり、腫れたり、かゆみがあったり、皮が剥けたりしたらどうすればいいですか?
まぶたが赤く腫れ、かゆみ、皮がむける場合は、アレルギー性皮膚炎が原因である可能性があります。症状が重...
足首を捻挫しました。腫れはひきましたが、まだ痛いです。
人間の足首は非常に脆弱な部分であり、可動範囲が広く活動頻度が高い関節でもあるからです。そのため、日常...
痛風の危険性
痛風は人類の病気であり、現代社会においても痛風の発症率は依然として比較的高い水準にあります。痛風はよ...
アナフィラキシーショックへの対処法
アレルギーとは、体が外部からの刺激に対して過剰に反応することで起こる症状です。アレルギーの原因や症状...
皮膚アレルギーがある場合でも喫煙できますか?
皮膚アレルギーは日常生活でよく見られます。皮膚アレルギーが発生すると、皮膚疾患の発症につながることが...
ポリアパウダーの保存期間を維持する方法
ヤシ科の植物は、ほとんどの人が聞いたことがないかもしれません。ヤシ科の植物は、松の木の下に生える腐生...