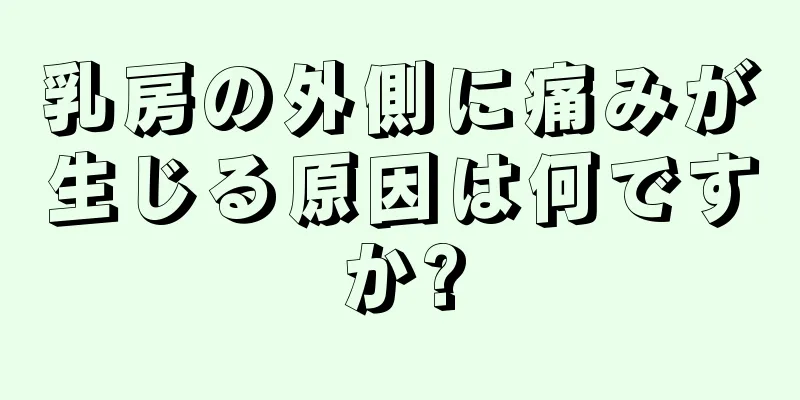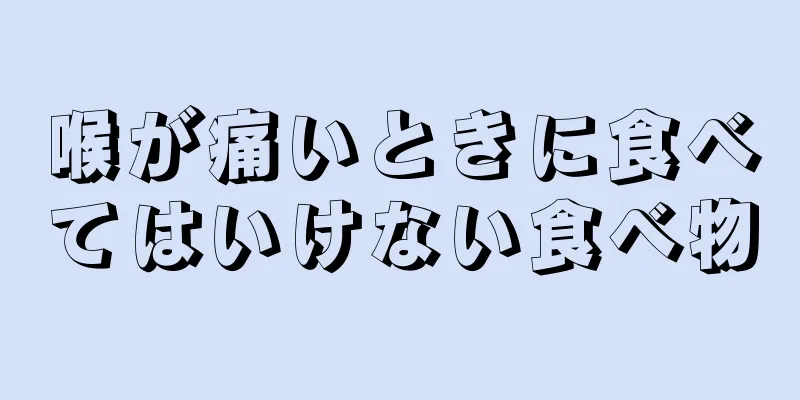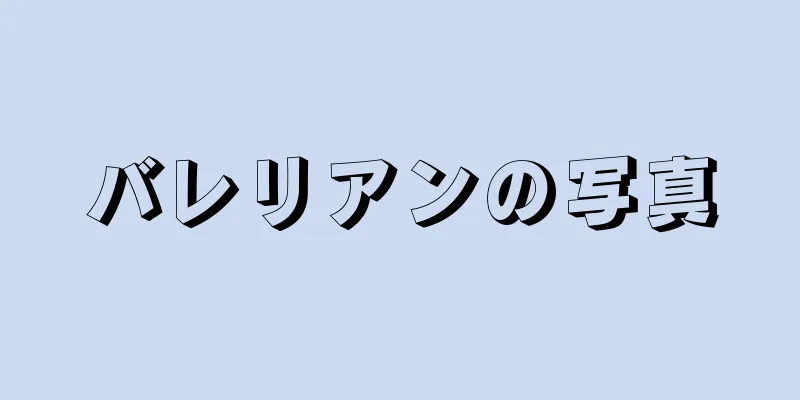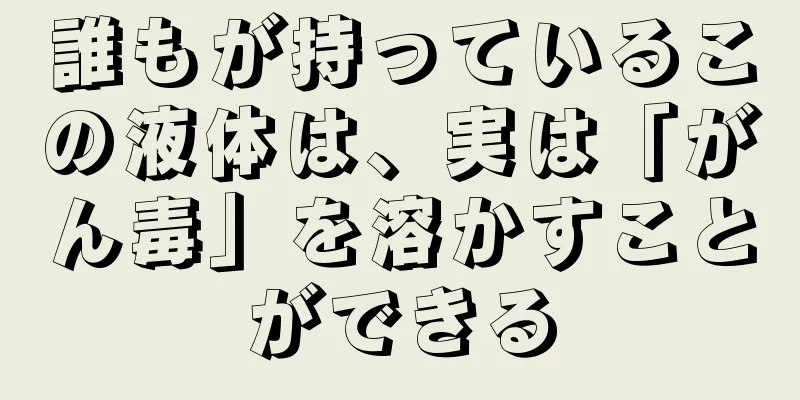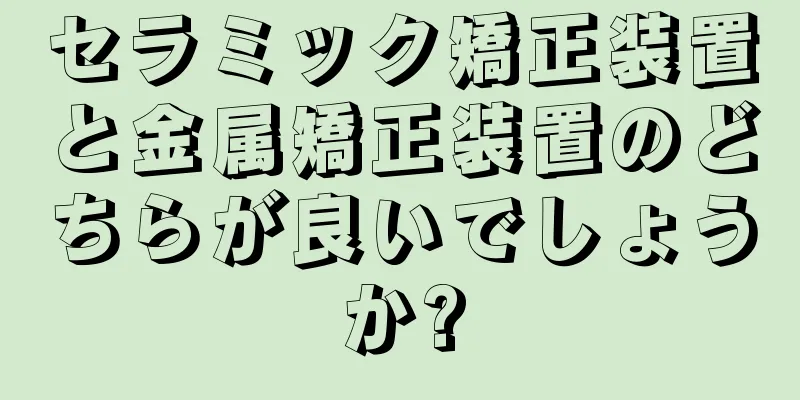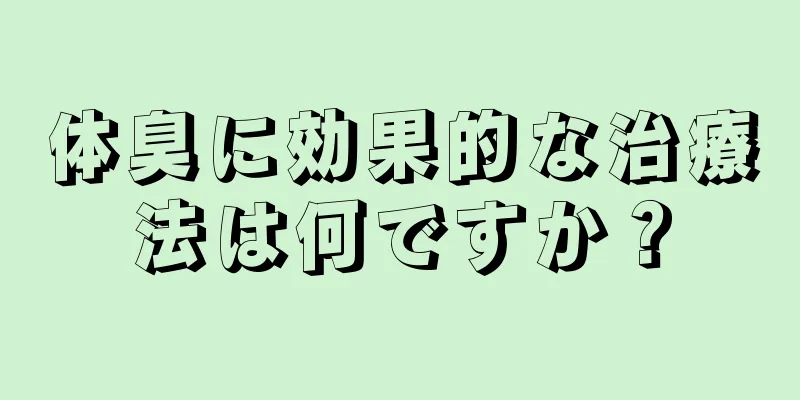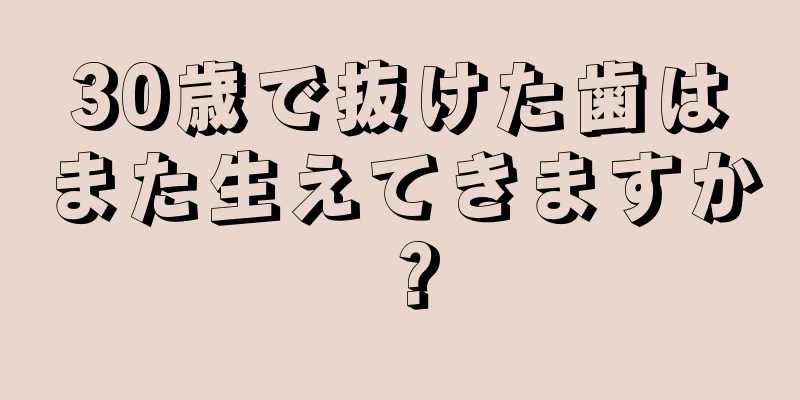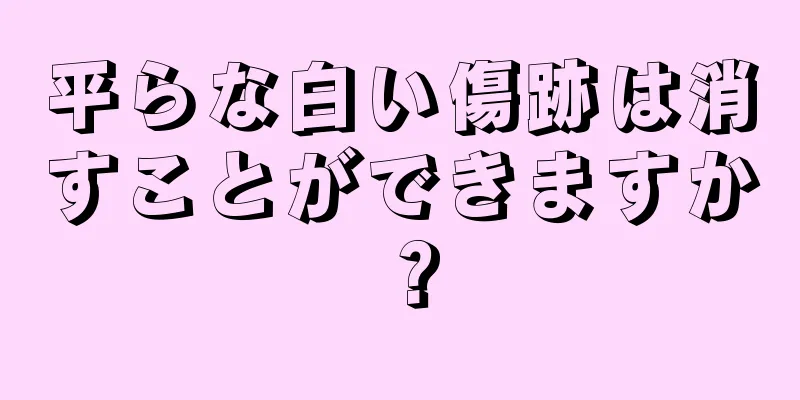デンドロビウム・カンディダムは自然界では寒いですか?
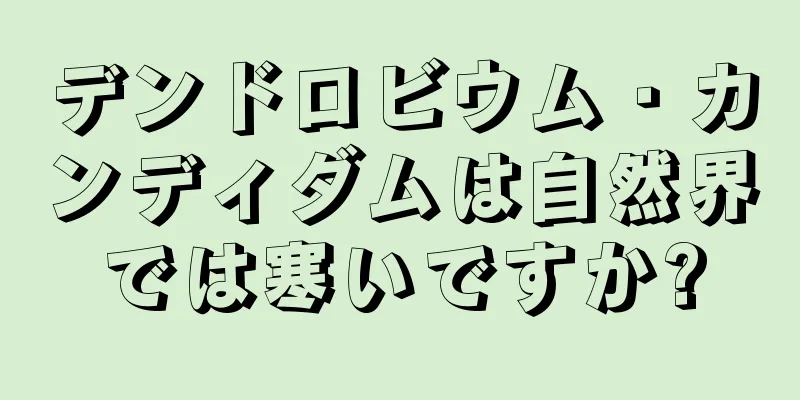
|
デンドロビウム・カンディダムも漢方薬の一種ですが、この漢方薬は使用前に一定期間日光に当てる必要があります。性質は冷たいですが、少し冷たいです。そのため、胃腸が弱い患者でも、この薬を服用する際にあまり心配する必要はありません。少量を服用する限り、胃腸に影響を与えることはなく、肺の保湿効果も良好です。 性質、風味、効果:甘く、わずかに冷たい。 水分を生成して胃を養い、陰を養って熱を取り除き、肺を潤して腎臓に効き、視力を改善して腰を強くします。 薬理作用 身体刺激作用:デンドロビウム・オフィシナールには身体刺激作用があり、主に腺分泌と臓器運動を促進します。 低血糖効果:デンドロビウム・カンディダムは、ストレプトゾトシンによって引き起こされる糖尿病の血糖値を下げることができます。 体の免疫力を高める:デンドロビウム・オフィシナール顆粒(TPSH)は、腫瘍を持つ動物のマクロファージの貪食機能を促進し、Tリンパ球の増殖と分化、NK細胞の活性を高め、腫瘍を持つ動物の血清溶血素値を大幅に増加させることができるため、TPSHは非特異的免疫機能、特異的細胞免疫、体液性免疫機能の改善に一定の効果があることが示されています。 デンドロビウムの生育適温は15~28℃です。そのため、生育に適した温度環境を作るために、夏季の気温が高い場合には、温室内の換気と放熱を強化し、日よけ小屋、噴霧冷却、通風冷却などにより温室内の温度を適切な範囲に制御する必要があります。また、冬季の気温が低い場合には、温室内をしっかりと密閉し、必要に応じてさまざまな加熱方法を使用して施設内の温度を上昇させ、植物の凍傷を防止します。 デンドロビウムは日陰を好むので、光を減らすための遮光対策を講じる必要があります。成長期には、デンドロビウムの遮光度は約60%にする必要があります。苗を植えたばかりのときは、強い日光によって苗が枯れて生存率に影響が出ないように、温室を遮光度70%以上の遮光ネットで覆う必要があります。夏と秋の気温が高く、光の強度が強いときには、温室の遮光ネットをしっかりと覆う必要があります。強度の高い光によって植物が早期に枯れてしまい、背丈が伸びず、収穫量に影響が出てしまうからです。冬には、光の透過を促進し、生育期間を延ばすために、日よけ小屋を適切に開ける必要があります。樹木に付ける栽培(主植物に付ける)の場合は、毎年冬と春に、付けた植物の密生した枝を適切に剪定する必要があります。 (2)水分と湿度の管理 水管理は、デンドロビウムの栽培プロセスにおける重要な要素の 1 つです。移植したばかりのデンドロビウムの苗は水に最も敏感です。このとき、基質の水分含有量は一般的に 60% ~ 70% に制御する必要があります。具体的な操作中は、手で基質をつかんで、湿っているが滴っていないと感じるのが最適です。移植後7日以内(苗木にまだ新しい根が生えていない状態)は、空気湿度を約90%に維持する必要があります。7日後、植物は新しい根を成長させ始め、空気湿度を70%〜80%に維持する必要があります。 |
<<: 妊婦のストレッチマークを治療する最善の方法は何ですか?
推薦する
おたふく風邪で熱が出たらどうするか
おたふく風邪の熱はおたふく風邪の合併症です。私たちの生活では、まず熱を治療し、次におたふく風邪を治療...
血液が心臓に栄養を与えていないと、どのような症状が現れますか?
血が心を養わないというのは、伝統的な中医学の学術用語です。主に患者によく見られる不眠症の症状を指し、...
色素性母斑
理解するうちに、体に発生する異物も種類に分かれており、すべての異物が同じ種類ではないことに気づきまし...
足外反とは?親は直面すべき
医学の分野では、外反足はより専門的な名前で「外反足」と呼ばれ、両足または片足に影響を及ぼすことがあり...
飲酒翌日の関節痛
飲酒の翌日に関節に激しい痛みを感じる人もいます。痛みはかなり激しいです。この場合は、病院に行って詳細...
「三焦の詰まり」が病気につながることを知らない人が多いです。
三焦は全身の気を調節し、人体の五臓六腑のリーダーです。現代医学の研究によると、三焦は人体の内分泌系や...
舌肥大と歯の跡を治療する中国の特許薬
古代の書物の中には、腫れた舌とともに脂肪舌についても論じているものがあります。実際、舌が太くなるのは...
コショウと生姜の湯に足を浸すとどんな効果があるのでしょうか?
花椒と生姜は私たちの生活の中で最もよく使われる調味料です。これらのおかげで私たちが食べる料理はとても...
尿毒症の透析治療はどのように行うのですか?
尿毒症は人体の腎臓病です。尿毒症は適時に治療しないと、生命を脅かす可能性があります。尿毒症は体内の老...
伝統的な中国医学の健康知識、風、暑さ、湿気、乾燥、寒さに対する治療戦略
健康のために、現代人は当然ながら健康維持にますます注意を払っています。効果的な健康維持法は、体と心を...
粗塩温湿布の婦人科疾患に対する効果と分類
粗塩は未加工の大粒塩で、主成分は塩化ナトリウムですが、塩化マグネシウムなどの不純物を含むため、空気中...
しこりのない脇の下の痛み
しこりを感じないのに脇の下が痛いというのはよくあることです。何が起こっているのか分からない人が多いで...
傷口に錆が入るとどうなるのでしょうか?
仕事中に怪我をすることは避けられません。傷口を適時に洗浄しないと、サビが傷口に入り込み、感染症を引き...
湿疹性口唇炎の治療
口唇炎は季節の変わり目や敏感な体質の人によく起こる病気です。発症後は特に注意が必要です。基本的に治る...
肺の質感の向上
医療技術の継続的な進歩により、多くの新しい機器が登場しました。これらの機器は、人体のさまざまな臓器を...